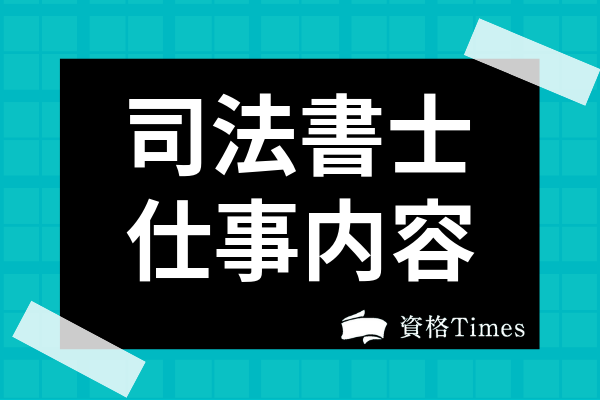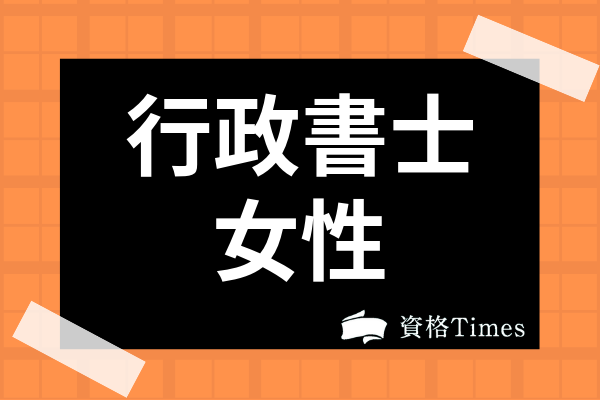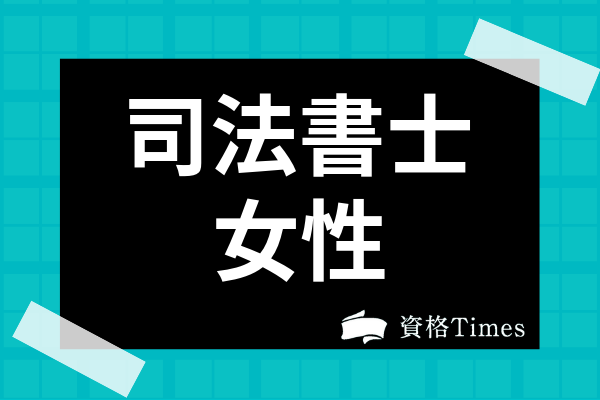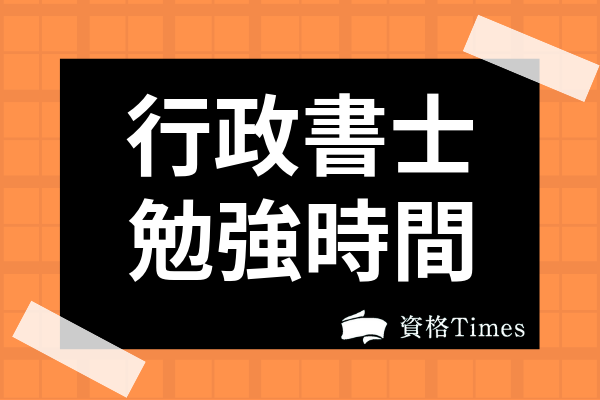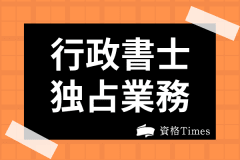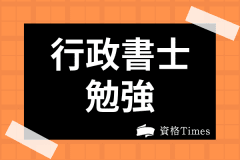行政書士と司法書士の仕事はどう違う?業務内容や年収・難易度まで徹底比較!
「行政書士と司法書士って何が違うの?」
「行政書士か司法書士か、どっちの取得を目指すべきか知りたい!」
こうした疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
行政書士と司法書士の名前は知っていても、その業務の違いについてはあまり知られていません。
そこでここでは行政書士と司法書士の違いについて、仕事内容や年収、資格試験の難易度まで気になる点を徹底比較します!
また、ダブルライセンスのしやすさやメリットについても解説します!
これを読めば2つの資格の違いやそれぞれの魅力はバッチリです!
行政書士と司法書士の違いをざっくり説明すると
- 行政書士と司法書士の業務範囲は近いが、司法書士の方がより高度な専門性が求められる
- 司法書士は一般企業に勤務しながらも活躍することができる
- 行政書士と司法書士では司法書士の方が年収が高い
- 司法書士試験の方が行政書士試験よりも圧倒的に難しい
- 司法書士の方が将来性は高いが、行政書士の方がコスパが良い
このページにはプロモーションが含まれています
行政書士と司法書士の主な違い

行政書士と司法書士の仕事の違い
行政書士と司法書士の一番の違いは、行政の管轄の違いでしょう。
- 行政書士は総務省
- 司法書士は法務省
と、監督官庁(管轄)が違います。
以下、行政書士と司法書士の業務の違いを「できること・できないこと」で分けたものを表にしました。
- 〇=可
- ×=不可
| 主な業務 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 |
| 遺言書作成 | 〇 | 〇 |
| 相続人の調査・確定 | 〇 | 〇 |
| 相続登記 | 〇 | × |
| 相続放棄の手続 | 〇 | × |
| 家庭裁判所への申請書 | 〇 | × |
| 定款作成、公証人役場認証手続 | 〇 | 〇 |
| 会社設立登記 | 〇 | × |
| 市区町村への認可書類 | × | 〇 |
| ビザ申請 | × | 〇 |
| 自動車登録・車庫証明 | × | 〇 |
一見すると司法書士の方が扱う業務が多いと思ってしまいますが、司法書士は法的専門性が高い業務が多く、行政書士は行政手続が多い業務なのです。
行政書士が取り扱うことが出来る書類は、およそ1万種類と言われています。
一方、司法書士は弁護士に近い業務を行うことができ、140万以下の簡易裁判所事件では代理人権限が与えられています。
ただし、司法書士が裁判の代理人になるためには、法務大臣から認可された認定司法書士の資格を保有している必要があります。
行政書士の仕事
行政書士は、「官公署に提出する書類作成・提出代理・代理作成・作成に関する相談」「その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成・提出代理・代理作成・作成に関する相談」を独占業務として行うことが可能な資格です。
行政書士の仕事の特徴は都道府県や市区町村などの官公署への許認可書類の作成や代理提出です。
登記は出来ませんが、会社設立のための書類や飲食店の開業書類などの他、契約書や遺言書の作成などです。
具体的な仕事内容としてみると、故人名義の預貯金口座の相続手続きが業務の1つとして挙げられます。
故人名義の預金口座は死亡が確認された段階で、口座が凍結されるため、その金額を相続人で分配・引継ぎする必要があるのです。
このために、相関関係説明図や遺産分割協議書等を銀行で提出する必要があり、それらの書類作成業務を行政書士が請け負います。
このように、行政書類の作成の専門家というのが行政書士と言えるでしょう。
行政書士の仕事内容は以下の記事を詳しくご覧ください。
司法書士の仕事
司法書士の仕事も書類作成や申請手続きがメインになるので、行政書士とごっちゃになりやすいところではあります。
ただし、司法書士の方がそれぞれの手続きでより顧客と深く関わることができるという特徴があります。
例えば、法人の登記をお手伝いする際には、行政書士は定款の作成・認証手続きまでしかできませんが、司法書士はその後の登記手続きまで行えます。
具体的な司法書士の業務としては、商業登記(会社名、代表者名、株主、本社の所在地などの明記)を法務局に提出する手続き業務や、破産や成年後見人の手続きの際の公的書類の作成業務などが挙げられます
司法書士と行政書士の一番の違いと言えるのは、やはり簡易裁判所事件の代理権が与えられていることでしょう。
例えば、司法書士であればお金の貸し借りでトラブルが起きた時に裁判を行ったりすることが出来ます。
司法書士の仕事内容は以下の記事を詳しくご覧ください。
どちらも対応可能な仕事も!
表を見てわかるように、司法書士と行政書士の業務は被っているものも多いです。
司法書士でも行政書士でも対応可能な業務の代表的な仕事は、「帰化申請」です。
インターネットで検索すると、行政書士事務所が多く表示されますので、行政書士の独占業務と思ってしまいます。
しかし、帰化申請は司法書士でも対応が可能です。このようにどちらでも対応できる業務の場合、どちらを選べばいいか迷ってしまう方も多いようです。
行政書士と司法書士の年収を比較
行政書士になるか司法書士になるか迷った時、一番気になるのは年収ではないでしょうか。
どちらも法人勤務型(行政書士は殆どない)と独立型がありますが、ここでは独立した場合の年収を表で確認してみましょう。※
| 年齢 | 司法書士(万円) | 行政書士(万円) |
|---|---|---|
| 20~24歳 | 559 | 481 |
| 25~29歳 | 647 | 495 |
| 30~34歳 | 691 | 517 |
| 35~39歳 | 760 | 535 |
| 40~44歳 | 830 | 599 |
| 45~49歳 | 955 | 678 |
| 50~54歳 | 1006 | 737 |
| 55~59歳 | 999 | 730 |
| 60~65歳 | 710 | 610 |
| 一般的平均年収 | 877 | 600 |
※あくまで平均年収から推定および作成した目安の年収推移です。
どちらも45歳∼59歳代の年収が高くなっています。法律を扱う専門的な業務ですので、ある程度の経験・年数が年収に表れるということでしょう。
司法書士の平均年収は「877万円」、行政書士は「600万円」と、やはり取得難易度に比例する形で司法書士の方が高くなっています。
各資格の詳しい年収事情については以下の記事をそれぞれ参照にしてください。
年収が安定しているのはどっち?
司法書士の場合、独立開業の道の他に、一般企業に勤めながら司法書士として業務を行う「勤務司法書士」としての働き方もあります。
一方で行政書士は「勤務行政書士」に相当する働き方が認められておらず、行政書士として仕事を行う際は独立するか、行政書士事務所などの士業事務所に勤めることになります。
つまり司法書士は行政書士よりも働き方の選択肢が広いというメリットがあります。
そのため年収の安定性という点でも、一般企業に勤務ができる司法書士が高いと言えるでしょう。
将来性が高いのはどっち?
近年大きな注目を集めているAIですが、士業である行政書士や司法書士の仕事にはどの程度影響してくるのでしょうか。
行政書士と司法書士だと、行政書士の方がAIによって仕事の一部が代替されてしまう可能性が高いです。
行政書士の独占業務である「自動車登録」や「会社設立」など、書類を作るだけの仕事は機械やAIによって比較的代替されやすい部類に入ります。
一方で司法書士は行う業務の種類によって代替可能性が大きく変わります。
司法書士の仕事を大きく分けると以下の3つに分類されます。
- 不動産・商業登記
- 裁判・法務局に提出する書類作成
- 裁判業務
1の登記に関しては書類作成がメインですので、これもAIに取って変わられる業務になる可能性があります。
2についても同様です。
しかし3だけは、司法書士が代理人となって、相手方との交渉を行います。また、上述しましたが司法書士は140万以下の簡易裁判事件では代理権を得ることができます。
こうした人とのコミュニケーションが深く関わってくる業務は、技術が進歩したとしてもAIが行うことは難しいでしょう。
このように、行政書士に比べ司法書士の方が、扱う業務の法律的専門性が高く、AIの普及という点では行政書士よりも将来性があると言えます。
とはいえ行政書士も扱える書類の数は極めて膨大である上に、業務の幅はかなり広いので、その全てがAIによって失われる可能性は実際のところかなり低いでしょう。
各資格の将来性については、下記の記事を詳しくご覧になってください。
行政書士と司法書士の人数の違い
行政書士と司法書士の登録者数にも両資格の違いが大きく表れています。
以下は行政書士と司法書士の登録者数を表にしたものです。
| 年度 | 行政書士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 令和5年度4月1日現在 | 51,041人 | 23,059人 |
| 令和元年度 | 48,768人 | 22,632人 |
| 平成元年度 | 34,515人 | 15,908人 |
データ出典:日本行政書士会連合会 単位会所在地・会員数等
この表から、行政書士の方の登録者数は司法書士の2倍以上あることがわかるでしょう。
また、平成から令和にかけての31年の大きな動きを見ると、増え方も行政書士の方が2倍近い速いスピードで増加しています。
この大きな要因は、各試験の受験者数の違いや合格率の違いが、登録者数の大きな差となって表れているとみられます。
男女比の違いはある?
行政所と司法書士共に、男女比は8:2で圧倒的に男性の多い資格となっています。
ただ、肉体労働と異なり女性が行うのが難しい仕事があるわけではないので、今後の女性の社会進出がさらに進むにつれて、この比率も矯正されることでしょう。
女性の行政書士・司法書士の実情については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもご覧ください。
行政書士と司法書士の難易度を比較

行政書士・司法書士両試験の試験概要をまとめた表が以下の通りとなります。
| 項目 | 行政書士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 試験日 | 11月第2週 | 7月(筆記)、10月(口述) |
| 試験形式 | 5肢択一式、多肢択一式、記述式 | 多肢択一式、記述式、口述式 |
| 合格ライン | 得点率60% | 得点率70~80% |
| 合格率 | 6~13% | 3~5% |
| 受験者数 | 47,850人(令和4年) | 12,727人(令和4年) |
| 合格者数 | 5,802人(令和4年) | 660人(令和4年) |
データ出典
これらの表を基に両試験の難易度で比べると、司法書士の方が圧倒的に難関です。
試験の合格率も司法書士は行政書士の半分以下であり、合格までに必要な勉強時間も司法書士の方が圧倒的に長いです。
また、試験の合格基準にも違いがあります。
司法書士は「相対評価」、行政書士は「絶対評価」の試験となっており、行政書士は他の受験生の得点によらず自分の得点だけで合格が決まります。
対して、司法書士では上位から何人(600人~800人)まで合格と決まっているのです。司法書士試験の合格者が毎年4%と、ほぼ一定なのもこのためです。
各試験の詳しい難易度の詳細は以下の記事をチェックしてください。
資格試験の合格率
試験の難易度は圧倒的に司法書士試験の方が高いとお話ししましたが、実際の過去14年間のデータを確認してみましょう。
データ出典
グラフをみて分かるように、近年では司法書士試験の合格率が4%前後、行政書士は10%∼15%程度となっています。
このことからも、司法書士試験の方が極めて難易度が高いと言えるでしょう。
合格までに必要な勉強時間
司法書士・行政書士を始めて受けるという人が、どのくらい勉強すれば合格できるようになるでしょうか。
大学などで法律を学んだ人ならともかく、全くの初学者となるとかなりの時間がかかるはずです。
大手の資格取得専門学校の調査では、行政書士が平均で500時間~800時間、司法書士が2000時間~3000時間」というデータが出ています。
このように、勉強時間という面から考えても司法書士の方がかなり高難易度な試験であることは明白です。
受験者層の違い
行政書士も司法書士も受験するにあたっての制限、「受験資格」はありません。どちらも学歴、年齢、性別に関係なく受験することが出来ます。
試験を受ける年齢層を見てみると、司法書士も行政書士も共に30代から50代が多く、働きながら学習する方が多いようです。
大手資格取得の通信教育企業の調べでは、行政書士はこれまで法律に関わったことがない人の受験者も多いというデータも出ています。
一方、司法書士試験の受験者は大学や他の資格の勉強を通じて法律を学んだという人が多い傾向にあります。司法試験に不合格されて司法書士試験に移ったという方も多いようです。
受験資格に差はないとはいえ、受験生のレベルも司法書士試験の方が高いことが分かります。
行政書士と司法書士のダブルライセンス

行政書士と司法書士はダブルライセンスの相性が非常に良いです。
資格Timesでは実際に司法書士と行政書士のダブルライセンスを活かしてご活躍されている、現役司法書士の林先生へインタビューを行い、この2資格のダブルライセンスの実態を調査しました。
インタビューの全文は以下よりご確認いただけます。
2つの試験科目には共通点が多い
ここでは行政書士試験と司法書士試験で学ぶ内容について整理して見ていきましょう。
行政書士試験の科目
- 憲法
- 行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法)
- 民法
- 商法・会社法
- 基礎法学
- 一般知識
司法書士試験の科目
- 憲法
- 民法
- 刑法
- 商法
- 不動産登記方
- 商業登記法
- 司法書士法
- 民事訴訟法
- 民事執行法
- 民事保全法
- 供託法
行政書士と司法書士では憲法や民法など広い範囲で試験範囲が被っていることが分かります。
具体的には「憲法」「民法」「商法」の3科目です。
このように試験範囲はかなり被っているので、ダブルライセンスを目指す際は他の受験生よりも有利に勉強を進めることができるでしょう。
司法書士のほうが試験範囲が広い
一方でやはり裁判や登記にも携わることのある司法書士では刑法や登記法も学ぶことになるので、行政書士よりも試験範囲がかなり広くなっています。
さらに行政書士試験は全て筆記ですが、司法書士試験では筆記試験に加えて口述試験も存在する点も大変なポイントです。
口述試験は面接形式で行われます。面接官ふたりと受験者が向かい合い、面接官から質問を受けます。質問に対して口頭で回答をします。
聞かれる質問は筆記試験の科目と同じ内容ですが、例年、「不動産登記法」「商業登記法」「司法書士法」の3分野から出題されます。
口述試験は毎年ほぼ全員が合格するものなので、特別時間をかけて対策する必要はないでしょう。
ダブルライセンスのメリット
行政書士や司法書士として独立開業した場合は、当然同業者の方々と集客を争うことになります。その際、他の事務所とどのように差別化を図っていくかということがポイントとなるでしょう。
そこで、行政書士と司法書士のダブルライセンスにより大きく差別化を図ろうという考えも生まれるのです。
司法書士と行政書士のダブルライセンスのメリットは、単純に対応可能な業務の幅が広がるだけではありません。
司法書士と行政書士の扱う業務範囲は近しいので、様々な手続きを他の行政書士・司法書士に任せることなく自分一人で行えるようになるというメリットがあります。
顧客の側からしても一回の契約で必要な手続き全てが終えられるので、このようなワンストップサービスは非常に魅力的です。
実際、行政書士と司法書士のダブルライセンスは人気が高く、需要の高い存在であるのです。
結局どっちの資格を取得すべき?

難易度の比較の際にも確認したように、法律初学者の方がいきなり司法書士の資格を目指すのは非常に難しいです。
試験勉強の途中で挫折してしまう可能性も高くなりますし、たとえ無事に合格できたとしても時間がかかってしまうので司法書士としての活動のスタートが遅れてしまいます。
そこで片方の取得を目指すのであれば、行政書士の資格から取得を目指すのがおすすめです。
行政書士も簡単な資格ではないものの、しっかりと勉強すれば1年以内に取得も十分狙えます。また、将来的に司法書士の資格を目指す場合も勉強を有利に進められます。
もちろん行政書士の資格だけでも非常に多くのメリットがあるので、必ずしも司法書士を目指す必要はないでしょう。
また、行政書士は司法書士だけでなく宅建や社労士といった資格とも相性が良い柔軟性の高い資格です。
ひとまず行政書士を取得しておけば、その後のキャリアの展開がしやすくなるのでおすすめです。
行政書士に関連するそのほかの資格

司法書士以外で、行政書士資格との関連性がある資格は以下のとおりとなります。
ダブルライセンスとして取得を検討している人も多い資格たちなので、行政書士の資格を取った後に取得を検討してみるのもおすすめです。
- 中小企業診断士
- 社労士
- 宅建
- FP(ファイナンシャルプランナー)
- 税理士
- 弁理士
- 土地家屋調査士
- 簿記
特に社労士や弁理士、税理士などは、行政書士よりも難易度の高い試験となるので、ダブルライセンスの際にはさらなる勉強が必要となります。
自分がどの分野で強みを作りたいかを理解したうえで、これらの資格とのダブルライセンスを検討することをおすすめします。
行政書士と司法書士の違いまとめ
行政書士と司法書士の違いまとめ
- 行政書士と司法書士は業務範囲が一部被っているが、司法書士の方がより法律知識を活かした専門的な仕事ができる
- 平均年収は司法書士の方が高い
- 司法書士試験の方が試験科目が多く合格率も低い
- 行政書士は将来性の面で司法書士に多少劣る
- 行政書士と司法書士のダブルライセンスには非常に大きなメリットがある
- 片方を取得するならまずは行政書士からがおすすめ
行政書士と司法書士の違いを解説しました!
試験の難易度では断然司法書士の方が難しいですが、行政書士も簡単に取れる資格ではありません。
取得を目指す場合は予備校や通信講座なども活用して、十分な対策をしてから試験に臨みましょう。
どちらも難関資格ですが、社会的なステータスも上がり、平均年収も高い魅力的な仕事です。
ぜひとも取得を検討してみてはいかがでしょうか?