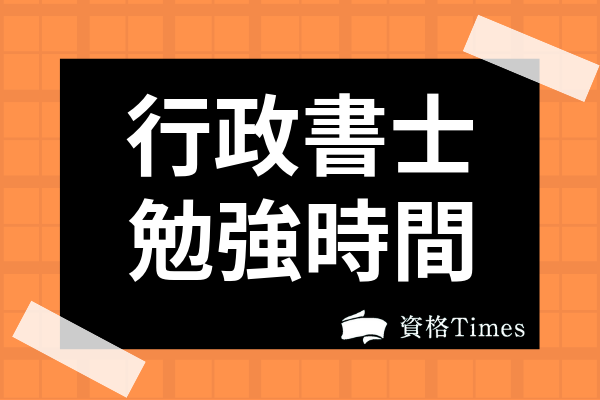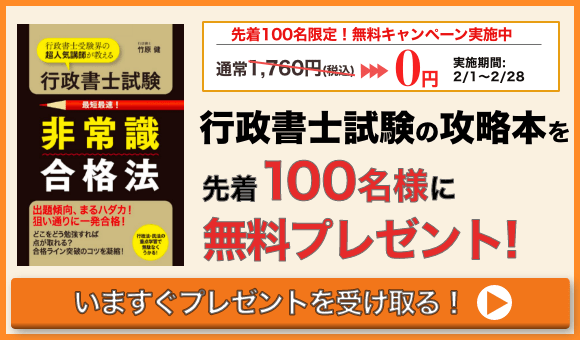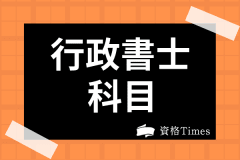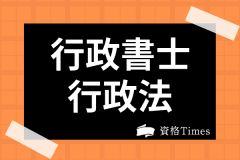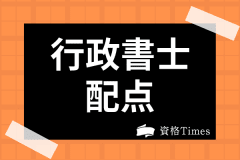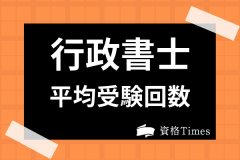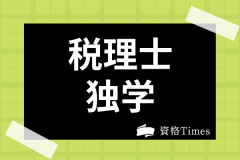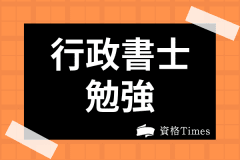行政書士に最短合格するための勉強法のコツ|独学での勉強時間やスケジュール管理の裏技を紹介!
「行政書士を取りたいけれど忙しくて勉強時間が…」
「少ない勉強時間でも受かる方法ってないかな」
なんていう悩みをお持ちのあなた!行政書士に最短合格するためのコツがあることをご存知ですか?
この記事では忙しい日々の中で独学して行政書士合格を目指そうという方に向けて、効率の良い勉強法や学習スケジュールの組み立て方を解説していきます。
もちろん、時間に余裕のある方、資格予備校などを利用される方にとっても役立つ情報が満載ですので、最後までご覧ください!
行政書士最短合格のための勉強法のコツについてざっくり説明すると
- 過去問の活用は必須
- 頻出の基本問題を重点的に対策しよう
- 法改正の情報は要チェック
- 暗記ものは徹底した反復学習を!
このページにはプロモーションが含まれています
そもそも行政書士の独学合格は可能か
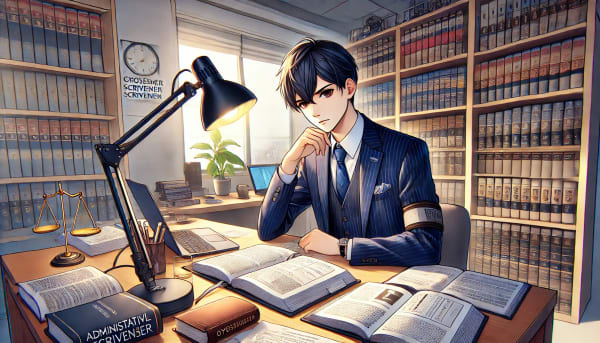
独学で最短合格を達成する方法について紹介する前に、「そもそも行政書士の独学合格は可能なのか」という点について解説をします。
結論から言うと、行政書士の独学合格は可能です。もちろん簡単ではありませんが、他の難関資格の独学合格よりも実現しやすいと言えるでしょう。
司法試験や公認会計士、司法書士などの試験よりは、ずっと独学合格の可能性が高いです。
ただし、最短合格を達成するとなると、話は別です。普通の独学と違って、正しいやり方で効率よく学習を行う必要があります。
効率的な学習方法を取り入れれば、行政書士の独学合格は十分実現可能ですので、まずはこの学習方法を学ぶところから始めましょう。
行政書士の最短合格を目指した勉強法でよくある失敗
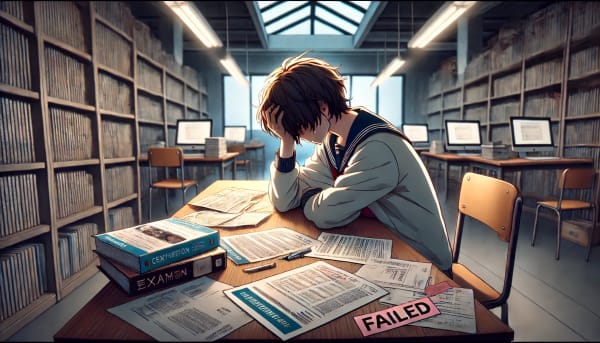
効率的な勉強法のコツを知る前に、独学で勉強している場合に陥りやすい失敗のパターンを見ていきましょう。代表的なものとして
- 過去問重視で勉強をしていない
- 基本の理解を固めていない
- 試験範囲全てを理解しようとする
- 記述式の対策が甘い
- 一般知識を軽視している
の4つを取り上げます。この4つを意識的に回避するだけで合格がグッと近づくのでぜひしっかりと目を通してくださいね!
過去問重視の勉強をしていない
一つ目の失敗パターンが過去問を疎かにしてしまうことです。行政書士試験の対策をする上で、過去問は絶対に欠かせないものなんです。
負けられない戦いをする上で敵をよく知ることは大切ですよね。資格試験において「敵をよく知る」とは、試験についてよく知ること、特にどんな問題がよく出題されるのかを把握するということです。
行政書士試験は大学入試などと違って選抜のための試験ではありません。他の受験者との競争というよりも、行政書士として仕事をする上で必要な知識・能力を身につけているかの確認の試験です。つまり、受験者間で差がつくような難しい問題よりも必要最低限の知識や考え方を問う問題が主に出題されるということです。
このため、過去問を分析して頻出問題などを見極める&過去問を解いて頻出問題をバッチリ対策するというのが合格に欠かせないプロセスとなっているのです。
基本の理解を固めていない
二つ目の失敗パターンは基礎固めをしないことです。一つ目のところでも説明したように行政書士試験では難しい問題よりも基本的な問題を大事にしなくてはなりません。
そもそも法律というのはある共通する考え方に沿って作られています。
ですから、そういった基礎となる考え方、どの法律にも共通する概念などを学んだ方が具体的な法律や個別の事例などが効率よく理解できるのです。
法改正対策をしない
法律の条文についての基礎知識を固める上で盲点となりやすいのが法律は改正されるという事実です。社会の動向や政策を反映して、毎年のように法律が改正されます。法改正は社会のニーズやトレンドを反映しているので試験で問われることも多いのがポイントです。
過去問だけでは対応しきれない部分ですし、独学での対策がしづらいところでもあります。以下の記事などを参考にして対策を講じていきましょう。社労士試験向けの記事ですが行政書士でもほぼ同様の対策が有効です!
試験範囲全てを理解しようとする
単なる合格ではなくて最短合格を目指す場合、試験範囲の隅から隅まで理解しようとするのは却って合格から遠ざかる原因となります。
行政書士で出題される法令は 基礎法学 憲法 民法 行政法 商法・会社法と非常に多岐にわたります。
それに加えて一般知識への対策が求められるため、 全てを理解しようとしては合格から遠ざかってしまいます
時間が有り余っているならともかく、限られた時間で行政書士試験に合格しようと思ったら満点ではなく合格点をとるための学習スケジュールを意識しましょう。
これまでも説明しているとおり、行政書士試験というのは他の受験者が誰も解けないような難問を解かなければいけない試験ではありません。それよりも、合格のために必要な知識・能力をつけることが最優先だと理解して、重要なポイントに絞って勉強しましょう!
記述式の対策が甘い
行政書士試験には択一式の問題の他に記述式の問題があります。
記述式の問題は3問出題されますが、その配点がなんと択一式15問分とかなりのウェイトを占めます。
記述式をバッチリ対策していればかなり大きな得点が期待できますが、逆にいうとここの対策が甘いと大きな得点源を捨ててしまうことになります。
択一式で地道に点を稼げば記述式ができなくても合格することは可能ですが、択一式の細かい知識が必要な問題で点を上積みするよりも記述式の答案作成のコツを掴む方がより効率よく得点を得ることができます。
記述式で必要な知識は基本的な(=頻出の)条文、判例の知識のみです。知識に関しては択一式と全く同じように対策できます。
個別の対策が必要なのは、答案作成の定跡とも言える部分です。問いの形式と答案の形式は決まり切ったいくつかのパターンがありますので、それをしっかり習得するというのが記述式攻略の鍵なんですね。
定跡さえ身につければ簡単に得点がアップするのが記述式の良いところです。ぜひ得意分野にして点数をがっつり稼いでしまいましょう!
一般知識を軽視している
行政書士試験は問題数60問で300点満点の試験ですが、そのうち一般知識には14問で56点分が配分されています。
つまり、おおよそ1/4が一般知識の問題です。
過去問から頻出の分野などを割り出し、日頃のニュースなどを見ることによって対策していきましょう。
行政書士の最短合格におすすめな勉強法のポイント5つ

避けるべき失敗のパターンを学んだところで次は行政書士試験に向けた勉強のコツを見ていきましょう。
行政書士試験という国家試験の特性を理解する
行政書士の資格は行政書士法に定められた国家資格です。行政書士のみが行える業務というのは「行政(役所、官公庁)に提出する書類や申請書類」に関わる幅広い分野にわたっています。行政書士になることで扱えるようになる書類は実に10,000種類以上です。
たくさんの書類を扱えるということは、それに関連する幅広い法律知識が必要になってくるということです。行政書士試験では業務に関連する法律の基本的な知識・運用能力があるかを判定されます。
暗記科目は最低3周は反復学習する
「行政書士試験という国家資格の特性を理解する」の項目でも触れたとおり、行政書士が扱う書類というのは実に多岐に渡ります。多くの種類の書類を扱うということは、それだけ幅広い法律の知識が要求されるということです。
効率の良い勉強法とは、暗記を全くしないことではありません。むしろ、覚えるべきところをしっかり覚えて選択式にも記述式にも知識を広く応用していくことが重要です。基礎となる知識を定着させることが真の効率化に繋がるのです。
必要な知識をあやふやにしないために、これから紹介する暗記科目については最低3周は反復学習をするようにしてください。適切なタイミングで反復学習をすることで最大限記憶に定着させるのが狙いです。
行政書士試験の暗記科目
行政書士試験においては暗記が重要な科目がいくつかあります。そのなかでも特に暗記が重要なもの、ほぼ暗記で乗り切れるものは以下の4科目です。
- 行政法(行政不服審査法)
- 行政法(地方自治法)
- 基礎法学
- 一般知識(個人情報保護)
行政不服審査法は行政手続法と対比しながらの暗記が有効な科目ですし、地方自治法は実際に出題される内容がかなり限定されています。
基礎法学については基本的なことを暗記すればあとは現代文の読解のような内容で、個人情報保護にいたってはほとんど条文そのままでしか出題されません。
また、上の4科目ほどではないですが暗記がそこそこ有効な科目として
- 行政法(行政手続法)
- 商法
があります。これらは一部応用的な論点が出題されることがありますが、基本的には暗記科目と言えます。
繰り返し学習のコツ
暗記科目を勉強する上で何よりも重要なのが、何度も繰り返し学習するということです。反復学習の回数を重ねるごとに暗記ものは定着していきます。
しかし、最短合格を目指すとなるとただ闇雲に繰り返していては効率が悪いですよね。
記憶に定着しやすいタイミングで暗記を繰り返すのが効率良い勉強のポイントです。
具体的には、暗記科目を3周する際に
- まず1回目をしっかり取り組む
- 1回目をやり終えてから1週間以内に2回目をやる
- 2回目をやってから1週間以上空けて3回目をやる
というように初めは短いスパンで、そしてだんだん長く期間を空けて復習するようなスケジュールを立てましょう。
この時重要なのが、1回目はスピードを重視して素早く終えてしまうことです。初めて学ぶ知識も多いために時間をかけてじっくり勉強してしまう気持ちもわかります。
しかし、勉強しなければいけない総量の全体感も掴めないまま、一つ一つを厳密に理解しようとすると効率が悪くなります
また、この段階に時間をかけていると全体の学習の計画も遅れてしまいます。
短いスパンで繰り返し学習することを心がけましょう
横断的な科目学習を心がける
行政書士が学ばなければならない法律というのは、互いに似通ったものも多くあります。
そのため、勉強する際は似た法律同士を対比させながら共通点と相違点を整理していくような学習法が適切です!
例えば、暗記科目の説明でも言ったように、行政不服審査法は行政手続法と対比しながらの暗記が有効です。あるいは、ある科目で通用する考え方は他の科目でも似たような適用ができることが多くります。
一つの科目を完璧にしてから別の科目に移った方が良いのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、
-
最初に見たように、完璧にする(=細かい知識まで全部覚えて難問も解けるようにする)ことを目指すのは効率が悪く避けるべき
-
比較しつつ知識を整理していかないと似た分野で混乱を起こす原因になる
といった理由から科目横断的な学習をおすすめします。
行政書士試験では基礎基本を押さえることがとても重要です。
一つの科目にこだわるのではなく、各科目の基礎を押さえつつ全体を俯瞰しながら勉強を進めていくようにしましょう!
モチベーション維持の方法を考える
独学で勉強される方が最も苦心するのがモチベーションの維持の仕方です。
数ヶ月から1年弱もの長期間勉強時間を捻出し続けるには、モチベーション維持の方法が欠かせません。
家族や職場の同僚に資格試験の勉強をしていることを宣言したり、理解を持ってもらうことも一つのモチベーションの維持の方法となるでしょう。
そのほかにも、ブログを始めるなどさまざまな方法で、周囲の人を巻き込むことでモチベーションを維持することができます。
過去問で頻出事項を掴む
これまで最短合格を目指すための勉強法のコツを紹介してきましたた。最後となる4つ目のポイントは「過去問を分析して頻出事項を掴む」です。
行政書士試験に最短合格するためには、この過去問の活用が最も大事と言っても過言ではないでしょう。
過去問を分析して頻出問題の傾向をつかみ、対策するのが行政書士試験の正攻法です。
具体的に、何に注意しながら過去問を用いた対策をすれば良いかは、これから説明します。独学する上では、予備校などで傾向と対策を教えてもらえないぶん過去問をよく分析するのが重要ですよ!
過去問の焼き増し問題に注目する
一つ目のポイントで確認したように、行政書士試験というのは行政書士としての知識や能力が十分あるかというのを測るための試験です。
受験者の間に差をつけて選抜するテストではありません。
そのため、差がつくような難しい問題を出すよりむしろ、行政書士になってから必要な知識や能力を問う問題が多く出題されます。
必要な能力を問う試験なので、そのための問題を「以前出題したから今年は出題しない」と考えて出題をやめたりはしませんよね?
多くの資格試験に共通することですが、重要な問題というのは過去何度も出題されているものです。そして、そういった問題はこれからも出題されることが予想されます。
つまり、過去問の焼き増し問題が出題される可能性がとても高いということです。
過去に出題された問題とほぼ同じものがあなたの受験の時にも出ると期待して良いのです。過去問を分析して試験の傾向を掴む意義の多くはここにあります。
頻出問題はみなさんが受験する時にも出題される確率が高いですし、頻出事項はそれだけ実際の業務でも重要になってくる知識・能力だと考えられるので、ぜひ身につけておくべきでしょう。
基本事項の完全理解が最短合格の近道
過去問を解いていると、基本的な問題やなんども出くわす頻出問題だけではなく、なかなか解けない難問・一度しか見かけないような奇問に遭遇することもあるかもしれません。もちろんそういった問題が解ければそれは素晴らしことですが、最短合格を目指すみなさんは「徹底的に基礎」だということを忘れないでください。
これまで何度も書いているように、基礎基本の力がしっかりしていれば十分合格できるのが行政書士試験です。逆に、基礎ができていなくて頻出問題を落とすようでは合格はかなり厳しくなってきます。
基礎ができた上で難問を解けるようにするのは時間が有り余っている人にのみ許される高尚な遊びです。
もちろん、科目によっては応用力を問われるものもあります。例えば、行政法のうち行政事件訴訟法などはほぼ毎年応用力を試す問題が出題されています。
ですが、こういった応用問題を解こうとする時にも基礎力が物を言ってきます。応用力というのは、基本的な事項を組み合わせて少し進んだ結論を出す力のことですよね?
基礎的な知識、基本的な考え方が身についていない状態ではそもそ応用するものが無いので応用力も何もありませんね。
基本事項を完全に理解して基礎知識を徹底的に身に付けるのが最短合格の最も基本的な戦略です。 そのために過去問を活用して、なんども反復学習をしましょう!
行政書士の独学に必要な勉強時間

一般的には800〜1,000時間程度
行政書士を独学で合格する場合、一般的な勉強時間は平均して800〜1,000時間程度です。
1日平均3時間勉強できたとしても、9〜11ヶ月と比較的長めの学習期間が必要となります。
ただし、このように長い勉強時間がかかってしまう人の中には、効率的な勉強方法を実践できていない人も多くいます。
最短でも500時間程度は必要
効率的に勉強を行い、行政書士最短合格を目指す場合は、この500時間が一つの目安となります。
当然、法律知識や職務経験が多くある人なら、より短い時間で合格することも可能でしょう。
逆に、事前知識が多くない人の場合、最短合格だとしても500時間の勉強が必要である、と言い換えることもできます。
1日3時間勉強したとしても、5ヶ月から半年の勉強期間を設ける必要があるのです。
よって、より短い期間で合格しようとする場合は、隙間時間の活用などを行なって毎日の勉強時間を増やす努力をする必要があるでしょう。
他の法律系資格と勉強時間を比較
他の法律系科目の一般的な勉強時間(独学の場合)は、概ね以下の通りです。
- 行政書士:1,000時間
- 司法書士:3,000時間
- 弁理士:3,000時間
- 社労士:1,000時間
なお、司法試験はそもそも独学合格が不可能と呼んで差し支えないレベルですので、ここには掲載しておりません。
最難関法律系資格ほどではないにせよ、やはり長い勉強時間が必要な資格だと言うことができます。
いつから勉強を始めるべき
行政書士試験は、例年11月の上旬ごろに実施されます。
当然ですが、試験までしっかりとした勉強の時間が取れる人は、なるべく早く試験勉強を始めましょう。
最短合格を達成することは可能であるものの、やはりより長い時間を設けた方が安心して合格を目指すことができます。
年明けすぐから始める必要はないですが、時間がある人は2月下旬から3月までには学習を開始しておくと安心です。
一方で、時間がなく最短合格を達成する必要がある人は、5月・6月までには学習を開始しましょう。
また、こういった人は毎日の勉強時間を捻出する努力をし、できる限り多くの量の勉強をするように意識してください。
なお、行政書士の勉強時間については、こちらの記事でより詳細に解説をしていますので、参考にしてください。
行政書士試験の勉強ノウハウを知る裏技

ここまで行政書士試験に最短合格するための勉強法の基本をチェックしました。
一方で、例えば出題形式別の対策法といったもっと踏み込んだ勉強法については、まだ不明瞭なところもあるかと思います。
そこでおすすめなのが、行政書士試験のプロである予備校講師の方が持つ行政書士試験の勉強ノウハウそのものを学ぶことです。
大手資格学校のクレアールでは、カリスマ講師である竹原先生がご執筆された行政書士試験の攻略本「非常識合格法」を作成してます。
この本では行政書士試験のプロの目線から出題傾向や科目ごとの具体的な勉強法が記されており、行政書士を目指される方であれば必見の内容となっています。
クレアールでは現在、この「行政書士試験の攻略本」を先着100名様限定で無料プレゼントしています。
行政書士試験の最短合格のノウハウを無料で手に入れる絶好の機会です。受験生の方であれば必ず手に入れておきましょう!
行政書士試験に最短合格するための勉強法まとめ
この記事では、行政書士試験にできるだけ短い期間・少ない勉強時間で合格(=最短合格)するための勉強のコツを解説してきました。このやり方を実践すればかなり合格に近づきますよ!
今回紹介した勉強のコツを振り返っていきましょう。端的にまとめると、ポイントは以下のようになります。
行政書士に最短合格するための勉強のコツ
- 過去問を分析して頻出問題をチェック!
- 頻出の基本問題を重点的に対策しよう
- 法改正の情報は要チェック
- 暗記ものは徹底した反復学習を!
これらのコツを掴んで、行政書士の最短合格を目指しましょう!