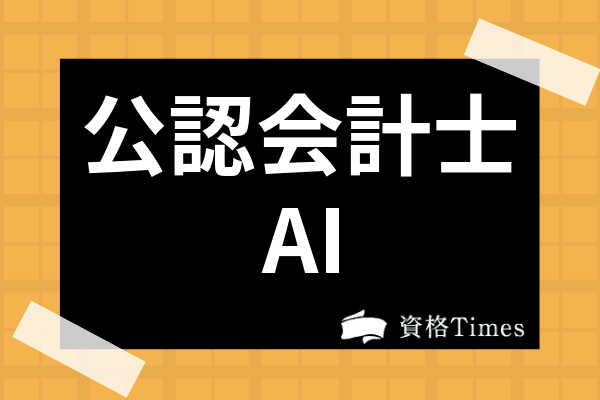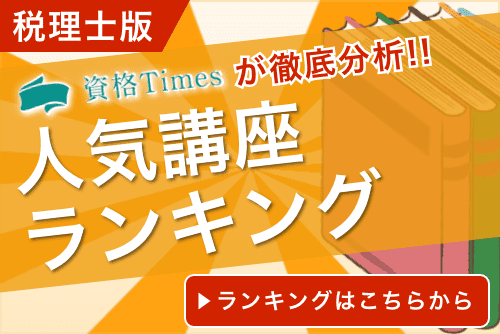税理士と公認会計士の違いは?試験難易度から仕事内容・年収まで徹底比較
「税理士と公認会計士ってどのような違いがあるの?」
「税理士か公認会計士の取得を考えてるんだけど、どっちがおすすめ?」
このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
税理士と公認会計士は共に難関資格であり、取得までにはかなりの勉強量が必要となります。
どちらも会計系の資格として知られていますが、税理士と公認会計士を比較したときに、具体的にどのような違いがあるのかについてはあまり知られていません。
そこでここでは税理士と公認会計士について、資格の難易度差や仕事内容の違い、就職先や年収まで徹底比較していきます!
これを読めば税理士と公認会計士の違いについてはバッチリです!
税理士と公認会計士の違いをざっくり説明すると
- 試験の難易度はほぼ同じだが、公認会計士は短期集中で勉強できる環境が必要
- 仕事内容は一部かぶっているものの、それぞれ専門とする業務は異なり、仕事の向き不向きも分かれる
- 公認会計士は大手企業や監査法人への就職・転職が多く、税理士は独立開業をして中小企業の顧問等をする人が多い
- 税理士も公認会計士も共に高収入が狙える資格である
※この記事は税理士の脇田弥輝様ご監修のもと作成しております。
税理士と公認会計士の業務の違いを比較

簿記の上位資格であり、合格率の低い難関国家資格である「税理士」と「公認会計士」は、どちらも会社の会計や税金関連の業務を行っています。
共通点が多く混同されがちな2つですが、両者には大きな違いがあります。
税理士の業務範囲
法律で決められている税理士の独占業務は税務代理・税務相談・税務書類の作成といった納税に関わる仕事全般となります。
具体的な業務内容としては、会社から資料としてもらった財務諸表を元に、会社に対する節税のアドバイスや納税の際の書類の作成・提出などが挙げられます。
また、法人以外でも個人相手に確定申告の際の手続きをサポートしたり、相続税の相談などを受けるケースもあります。
このように税金に関する全般的な相談や提出が税理士の主な仕事です。
公認会計士の業務範囲
公認会計士の独占業務としては、会社の財務などの監査業務があります。
具体的な業務としては、企業が作ったその年度の財務諸表をチェックすることが挙げられます。
この業務は金融商品取引法193条2項・会社法328条の規定により、資本金5億円以上の大企業や東証一部に上場している企業は公認会計士(監査法人)による監査を受ける義務が定められているため、公認会計士は様々な法人から頼られる存在といえます。
顧客の違い
税理士と公認会計士では、顧客となる層に違いがあります。
公認会計士は、会計監査を受けなければならないのが大企業だけであるため、顧客となるのは大企業や上場企業のみです。
一方、税理士の顧客に関しては、税金は国民の義務であるため税理士は大企業から個人に至るまで顧客が幅広く存在します。
また税金の種類は多様なため、税理士は様々なシチュエーションで活躍できるのです。
就職先や給料の違い
では、税理士と公認会計士で年収や就職先にどのような差があるのでしょうか?
公認会計士は「監査法人」という大企業の会計監査を専門に行う会社に就職するのが一般的です。
公認会計士の年収の平均は概ね1000万円程度となっており、一般的なサラリーマンと比較すると相当高収入といえるでしょう。
一方、税理士は大手の税理士事務所に就職したり、あるいは個人事務所で修行する傍ら独立開業する人が多いです。
勤務の場合は年収にして700万円程度ですが、独立すれば3000万円を超えるような、かなりの高年収も狙えるようになります。
総合すると税理士全体の平均年収は1000万円程度と言われており、公認会計士と同じ水準となります。
このように、どちらも平均して1000万円ほどの年収が見込めます。
大きな違いとして、公認会計士は就職が一般的で年収が安定している一方、税理士は独立する人が8割であり、年収は税理士としての実力によるところが大きいことが挙げられます。
税理士と公認会計士はどっちが難しい?

共に超難関資格として広く知られている税理士と公認会計士ですが、比較するとどっちが難しいのでしょうか?
税理士になるためには?
税理士になるためには、「税理士試験に合格」「租税・会計の実務経験を2年行う」という2ステップを行う必要があります。
また受験資格も設けられているため、まずは受験資格をクリアしなければなりません。
税理士試験の受験資格
税理士試験の受験資格を列挙すると、
- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、法律学及び経済学に属する科目を一科目以上取得した者
- 大学3年次以上で、法律学及び経済学に属する科目を一定数取得した者
- 司法試験合格者
- 公認会計士試験短答式試験合格者
- 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者
などがあります。
これらの内どれか1つでも満たせば受験することができます。
税理士試験の難易度
税理士試験は全部で11科目ある内、5科目を選択して合格する必要があります。
簿記論・財務諸表論といった必修科目に加え、所得税法・法人税法・相続税法・消費税法・事業税・国税徴収法・酒税法・住民法・固定資産税などから勉強する科目を選んで受験するシステムになっています。
各科目の合格は一生有効であるため1年に1科目の合格を目指し5年かけて税理士試験に合格することも可能です。
このように働きながらでも合格を目指しやすい試験であるため、ほぼ一発合格が求められる公認会計士よりも合格は容易であるといえるでしょう。
税理士試験の難易度については、以下の記事で詳しく解説しています。
公認会計士になるには?
それでは、公認会計士になるにはどのようなプロセスが必要になるでしょうか?
「公認会計士試験に合格」「2年以上業務補助を行う」「一定期間の実務補修を受ける」「修了考査に合格」と4つのステップを踏む必要があり、税理士よりも手間と時間がかかります。
受験資格はあるの?
税理士と違い、公認会計士試験には受験資格が設けられていません。
そのため、誰でも受験することができます。
一方で公認会計士に合格するためにはまとまった学習時間が取れる必要があるので、実際には学生が受験者の大多数を占めています。
公認会計士の難易度
公認会計士の試験は、短答式試験と論文式試験で構成されています。
短答式試験は年2回、論文式試験は年1回行われ「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」「租税法」の必須5科目の合格に加えて「経営学」「経済学」「民法」「統計学」の選択科目の中から1科目の合格が必要です。
短答式試験は基本的に一発合格が求められますが、論文試験は不合格であっても税理士の様に「合格した」という実績が残ります。
ただしその実績は2年間しか有効期間がないため、速やかに論文試験に合格する必要があります。
資格Timesでは実際の会計士の先生に、会計士試験のリアルな受験事情を取材しています。より詳細な受験生活について知りたい方は、ぜひご確認ください。
どっちの方が難しいの?
一般的に公認会計士の合格に必要な勉強量が2500~3000時間と言われており、一方税理士の合格に必要な勉強時間が3000時間以上と言われています。
また、合格率を比較すると、公認会計士は11%程度、税理士は15%程度です。
公認会計士は複数科目を同時に勉強して一発合格を狙わなければならず、会社員の方や家事・育児に忙しい方には合格を目指すのが難しのが実情で、そのため合格のハードルも高いと言えます。
一方、税理士の方は科目合格制度があるため、受験が長期化しやすいデメリットはありますが、時間をかければ合格しやすい資格といえます。
そのため、社会人の方が仕事をしながら勉強して取得を目指す場合は、税理士試験の方が合格しやすいといえます。
反対に学生などで短期間で集中的に勉強できる環境が整っている人にとっては、公認会計士の方が目指しやすいでしょう。
このように試験の性質が異なるので一概にどちらが簡単か・難しいかは判断しにくいのですが、公認会計士は手続きをすれば税理士登録をすることができることを考えれば、公認会計士の方が資格のランクは上ということになるでしょう。(税理士は公認会計士として登録できない)
公認会計士の勉強時間については、以下の記事で詳しく解説しています。
合格率を比較
税理士試験と公認会計士試験の合格率について具体的に見ていきます。
税理士試験の合格率(全体)
| 年度 | 受験者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 2015年度 | 38,175名 | 18.1% |
| 2016年度 | 35,589名 | 15.8% |
| 2017年度 | 32,974名 | 20.1% |
| 2018年度 | 30,850名 | 15.3% |
| 2019年度 | 29,779名 | 18.1% |
| 2020年度 | 26,673名 | 20.3% |
| 2021年度 | 27,299名 | 18.8% |
| 2022年度 | 28,853名 | 19.5% |
公認会計士試験の合格率
| 年度 | 願書提出者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 2015年度 | 10180名 | 10.3% |
| 2016年度 | 10256名 | 10.8% |
| 2017年度 | 11032名 | 11.2% |
| 2018年度 | 11742名 | 11.1% |
| 2019年度 | 12532名 | 10.7% |
| 2020年度 | 11598名 | 10.1% |
| 2021年度 | 14192名 | 9.6% |
| 2022年度 | 18789名 | 7.7% |
合格率で見ると、公認会計士の方が10~1桁%を推移しており、試験の難易度は高いと言えます。
ただ、税理士試験も1科目1科目のボリュームが非常に大きい点や、合格までに短くても3年以上を要する点などを考慮すると、長期戦の試験ならではの別の難しさがあります。
税理士や公認会計士は独学で目指せるか?
ここで気になるのが、税理士と公認会計士は独学で取得を目指せるかどうかです。
実際の試験難易度を考慮すれば、独学での取得はとても困難であり、正直なところ不可能に近いです。
取得の難しさを比較すると大差はありませんが、共に難関資格であることは変わりません。
また、膨大な勉強時間が必要であり、勉強する期間も長期間に渡るため、独学だとモチベーションの維持も難しく挫折しやすいのが実情です。
実際に税理士や公認会計士に独学合格したという人は極少数しかいないので、余程学業に秀でている方でなければ予備校や通信講座を利用するのが無難でしょう。
税理士に向いている人、公認会計士に向いてる人

しばしば混同される税理士と公認会計士ですが、当然ながら両者の業務内容は大きく異なるので、それぞれ向いている人も異なります。
税理士に向いているひと
税理士に向いている人は、中小企業や個人事業主と一緒に仕事をしたい方や自ら独立開業を目指したい方、顧客視点のビジネスを設計するのが好きな方などです。
したがって自分の営業力に自信があり、独立開業を目指している人は税理士の方が向いていると言えるでしょう。
また、前述の通り試験の特性から、社会人の場合は公認会計士よりも税理士の方が合格しやすいです。
公認会計士に向いている人
一方、公認会計士に向いている人は、大企業を相手にしたい方で「監査法人」という成果主義・実力主義の環境で切磋琢磨したい人、公共のために監査を行いたいという志に溢れた人が向いています。
また、会社の財務を適正に監査する必要があるため、正義感が強い人も公認会計士に向いています。
税理士と違い独立開業する道は一般的ではないので、組織の中で自分の能力を生かせる人も適性があると言えます。
学生の場合は公認会計士試験の方が長期化しにくく挑戦しやすため、目指してみる価値は大いにあります。
税理士・公認会計士の関連業務

記帳代行や決算業務
記帳代行や決算業務は公認会計士と税理士のどちらも行うことができます。
記帳代行とは、会社から送られてくる領収書などの資料を勘定別に分けてデータ管理していく仕事です。
これらの日々の資料集計の積み重ねが決算につながっていくため、地味ですがとても重要な仕事なのです。
決算業務に関しては、その会社の決算時期に資料の作成や納付すべき法人税の案内などを行います。
IPOやM&A
株式公開やM&A、それに付随する財務デューデリジェンスは企業会計に関する専門的な知識が必要なため、税理士ではなく公認会計士が行います。
IPOなどでは税に関する知識はあまり求められないため、これら業務に関しては公認会計士が専門的に扱う分野になります。
また、上場審査基準をクリアするためには、企業会計に精通しておりIPOの実現のための的確かつ客観的にアドバイスをしてくれる公認会計士が不可欠なのです。
保佐人業務は税理士
税理士は顧客が税務について疑いを掛けられて起訴されてしまった場合、補佐人として代理人である弁護士とともに裁判所で被告人のために意見陳述などを行うことができます。
弁護士は、税理士のように日常的に税理士業務を行っていないため、税法に精通しているわけではありません。
そこで、訴訟の専門家である弁護士と税務の専門家である税理士が協力し、租税訴訟を遂行していく必要があるのです。
税理士は仕事がない?公認会計士への転職も

公認会計士は上位互換?
先ほども触れましたが、公認会計士試験に合格すれば、公認会計士の資格だけでなく税理士や行政書士の登録が可能です。
一方、税理士試験の合格では公認会計士の登録はできないので、最近では公認会計士を目指す税理士が増えてきています。
公認会計士を取得することで一気に3つの資格を取得できるため、とても効率が良いのです。
なぜいま会計士?二極化する税理士業界
税理士が会計士を目指す背景に、税理士業界が2001年に複雑化する財務処理に対して、柔軟な対応を行えるようにするために税理士法が改正したことが挙げられます。
これにより、税理士法人制度が創設され、100人以上の税理士を有する大きな税理士事務所が圧倒的な資本力を背景にした低価格戦略で税理士業界の仕事を安価で請け負うようになりました。
廉価なサービスを受けられる大手事務所に顧客が流れ、税理士の中でも二極化と競争の激化が進行してしまうと、個人事務所を開いてもうまくいかない税理士が増えると懸念されていました。
そのため、「仕事ない」状態になることを避けようと、スキルアップや自身の価値を上げるために税理士も公認会計士を目指す動きが生まれました。
AIへの不安から会計士を受験
近年ではITの発達が目覚ましく、AI(人工知能)に税理士としての仕事が奪われるという調査結果もあります。
こうした機械化による業務の減少と更なる競争の激化を見越して、よりスキルアップを目指す人が増えているという背景もあります。
公認会計士とAIの関係については、以下の記事で考察しています。
税理士よりも公認会計士の方が将来性が高い?

上記のように、税理士の将来に不安を感じ公認会計士を目指す人が出てきていますが、実際に税理士に将来性は無いのでしょうか?
結論からいってしまえば全くそんなことはなく、税理士は今後も幅広く活躍することのできる将来性のある資格です。
最近の報道などでは、簡単な仕事がAIなどの機械に任せられ、AIに税理士の仕事は失われてしまうのではないかと話題になっています。
しかし、実はこうした話題は噂に尾鰭がついたものにすぎず、一般に言われているほど税理士の立場は危うくはないのです。
確かに、税理士の仕事の中で簡単な計算作業や書類作成については、AIに取って代わられるものはあるでしょう。
しかし一方で、税理士の仕事はこうした単純なものばかりではなく、専門知識に基づいた人の手による解釈や判断が必要な業務も非常に多いため、仕事の全てが人工知能に奪われるわけではないのです。
また、きめ細かい心配りやサービスは人工知能には提供できないため、やはり税理士としての価値の高さは不変です。
これは税理士に限った話ではなく、公認会計士の仕事でも全く同じことが言えるため、税理士も公認会計士のどちらも世間が騒ぐような危機的状況に陥っているわけではないことに留意してください。
では、税理士と公認会計士だと、どちらの方が将来性が高いのでしょうか?
これについてはそれぞれ別の市場で需要があるため甲乙つけがたいですが、強いて言えば税理士資格も持てる公認会計士の方がキャリア的には有利であるといえます。
税理士と公認会計士に関するまとめ
税理士と公認会計士に関するまとめ
- 税理士試験は数年かけて合格を目指すのが一般的
- 公認会計士は1~2年のうちに一気に勉強時間を積む必要があるので、社会人よりは学生向きの資格である
- 公認会計士と税理士の平均年収はどちらも1000万円前後だが、独立する人の多い税理士の方が個人差が大きい
- どちらも高い専門性を持っており、今後の需要も高い
税理士と公認会計士は共に難易度が非常に高い資格です。そのため取得を躊躇してしまう人もいるかと思いますが、難易度が高い分取得した際のメリットも非常に大きくなっています。
税理士と公認会計士はそれぞれ得意とする分野や合格の目指し方が異なるため、自分の適性を考慮して勉強を進めていきましょう!