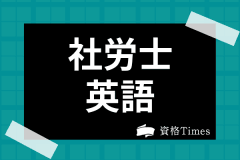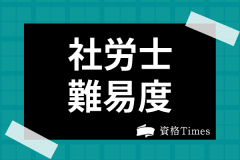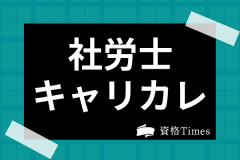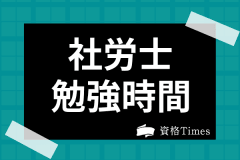社労士の年収は低い?平均年収や開業と勤務の収入差まで解説!
この記事は専門家に監修されています
社労士
のんびり社労士いけい
「社労士の仕事に興味があるけど、実際社労士の年収はどれくらいなの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、社労士の年収やその将来性について、様々なデータに基づいて具体的に解説します。
この記事を読んで社労士の年収について正しい知識を身につけ、社労士の仕事の魅力を再確認しましょう!
社労士の年収についてざっくり説明すると
- 社労士の平均年収は600万円以上
- 業務形態による年収の差が大きい
- 様々な副業で年収アップが狙える
このページにはプロモーションが含まれています
社労士の平均年収は640万円!

厚生労働省が行なった調査によれば、社労士の平均年収は642万円です(過去15年平均)。現在、日本国民の平均年収は2019年時点で436万円となっていますので、社労士の年収は平均よりも200万円以上高いことが分かります。
| 社労士 | 日本国民の平均 | |
|---|---|---|
| 平均年収 | 642万円 | 436万円 |
| 平均月給 | 41.7万円 | 30.3万円 |
| 平均賞与 | 142万円 | 68.3万円 |
上記の社労士の平均月給・平均賞与は、2020年賃金構造基本統計調査のデータを参考に算出しています。
社労士の年収に関する調査は毎年行われていますが、いずれのデータをみても社労士の平均年収は一般のサラリーマンと比較して高い水準にあると言えます。
社労士の平均年収の推移
上のグラフは年度別の勤務社労士の平均年収を表しています。グラフは厚生労働省の実施した賃金構造基本統計調査に基づき作成しています。
年によって平均年収の差がかなり大きいですが、2005年から2020年までの平均値は642万円となっています。
年度ごとの年収差が大きい理由として、主に以下の3点が挙げられます。
- 社労士の年収の個人差が大きい
- 調査の対象となる社労士が毎年同じ人ではない
- 調査の対象となる母集団が少ない
また、厚生労働省の調査は雇用されている社労士のデータを集めたものであり、独立開業した社労士の年収はほぼ含まれていないことに注意が必要です。
一般に、企業に勤務している社労士よりも独立開業した社労士の方が高収入を得ているので、このデータは実際の社労士全体の平均年収より低い可能性が高いということを覚えておきましょう。
社労士の年齢階層別年収
上のグラフは社労士の年齢階層別の年収の推移例を表しています。 グラフより20代の社労士の年収は約350~400万円、年収のピークは50代の約800万円ということが分かります。
グラフはあくまで国税庁及び厚生労働省の統計データに基づいて作成した一例です。参考程度にご活用ください。
社労士の年収には個人差が大きい
社労士の年収は、働き方の違いや勤務地域などによって大きく変動します。
社労士の働き方には大きく分けて、雇用され企業内で活躍する「勤務社労士」と、独立して自ら事務所を立ち上げる「開業社労士」の2つが存在します。
一般に、開業社労士の方が年収の個人差が大きく、勤務社労士の収入は高い水準で安定していることが多いです。
また、勤務社労士の場合は給料が勤め先によって異なるので、もともと給与水準の高い都会では収入も高くなる傾向があります。都道府県別でいうと、東京・愛知・大阪といった大都市では特にその影響が大きいです。
開業した社労士の年収
一般に開業社労士の年収は300万~1000万円以上だと言われており、個人差が大きいのが特徴です。
開業には当然リスクが伴いますが、高収入を狙えるほか自分の裁量で仕事ができる魅力が大きく、現在でも社労士の過半数が資格取得後に開業しています。
ここではそんな開業社労士の年収の実態を見ていきましょう。
独立直後の収入は少ない
多くの開業社労士が独立直後の資金繰りに苦労しています。開業直後は顧客獲得もままならず、年収が200万円程度しか得られないことも珍しくありません。
独立の前には十分に貯金をしておき、開業後2~3年は年収が低くても大丈夫な準備をしておく必要があります。
年収1000万を超える開業社労士も
開業社労士が収入を得る方法は主に以下の2つです。
- 顧客と単発の契約を結び即時的な収入を得る
- 企業と顧問契約を結び継続的な収入を得る
開業社労士が年収を安定して高めていくためには、いかに多くの企業と顧問契約を結べるかにかかっています。
顧問契約は月額制または年額制であり、顧問先企業の従業員数によって金額が変わるのが一般的です。
価格は自分で設定することが可能ですが、以前は社労士会によって都道府県別に報酬価格が決められており、現在もその価格が相場となっています。
以下に旧東京都社会保険労務士会会則による報酬基準を一部ご紹介します。キャッシュフローの予測や価格設定の参考にしてください。
また継続的な契約が取れない場合は、顧客との単発契約を結んで臨時の収入を得ることも一つの手です。
具体的には就業規則を作成したり、各種社会保険や労働保険の提出書類の作成・代行、またはコンサル業務を行うことが挙げられます。
特に最初の段階など、コネのない段階ではこれらの方法を通して地道にお金を稼いでいくのがおすすめでしょう。
開業社労士の年収については以下の記事でも考察しています。
開業社労士が稼ぐための心構え
開業社労士が稼ぐためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
ここでは大事な3つのポイントについて簡潔に紹介していきます。
顧客目線での対応を第一にする
社労士は顧客を第一に考えた対応が求められます。
専門家としてのスタンスを崩さずに法律の範囲内での対応を行いながら、時には顧客の要望に応じて柔軟に対応していく姿勢も必要になるでしょう。
このスタンスを貫くことで、顧客からの信頼を勝ち取ることにもつながり収入も増えていくでしょう。
得意分野を1つ見つける
開業した際には、事務所の看板業務となるものを必ず見つけるようにしましょう。
それを行うことで、事務所の特徴がはっきりと伝わり集客にもつながりやすくなります。
ポイントとしては、他の事務所と差別化できるような業務を見つけられるようにしましょう。顧客の目線に立ってそれらがアピールポイントになるかを考えていく必要があります。
具体的な分野としては、人事労務のコンサルタントや、給与・賞与計算の代行などの分野を考えていくとよいでしょう。
ネットに強くなることも必須
現在はネット社会となっていることから、ホームページによる集客が必須となってきています。
自分たちの特徴をホームページにわかりやすく掲載しておくことで、集客の効果もアップするでしょう。
また、集客面以外でも給与計算や労務管理のデータをクラウドなどで共有することも一般化してきています。
よって、顧客獲得からその後の業務までネットに関する知見は必須となっているので、より多くの顧客との接点を持ちたい場合はこれらの知識は必須といえるでしょう。
企業勤務の社労士の年収

社労士の求人の検索結果から、勤務社労士の平均年収は450~650万円であることが分かります(※一般企業の求人200件の想定年収より算出)。
企業に勤務する社労士は人事部・総務部において活躍するのが一般的です。社労士としての特別枠で採用されるケースは少なく、あくまで1社員として勤務することが多いです。
ただし会社によっては基本給の他に資格手当が貰えるほか、社労士の有資格者ということで昇格のチャンスも広がるので、全くほかの社員と同一というわけではないでしょう。
就職先ごとの年収の違い
企業勤務の社労士の年収パターンとして、今回は一般企業で勤めるパターンと、社労士事務所で勤めるパターンの2つを紹介していきます。
一般企業
一般企業での業務は、自社内での労働問題を未然に防ぐ役割が期待されています。
企業内での活躍の幅は広いといえますが、それだけで年収の大幅アップは期待できません。
資格手当はありますが、月に5,000円~10,000円ほどとなっているので、資格の力だけで評価はあまり上がりません。
企業の利益を第一に考えて、臨機応変に行動して評価を高めていくことが年収アップの秘訣といえるでしょう。
社労士事務所
社労士事務所に雇われた場合は、一般従業員のパターンとパートナー社員として雇われるかで大きく年収は異なります。
一般従業員の場合は、独立前の未成熟な状態の人も多いことから、簡単な業務を任されることが多く、あまり高額な年収は期待できないでしょう。
一方執行役員などのパートナー社員となる場合は、スキル的に成熟している場合も多く、報酬は高くなる傾向にあります。
その分担される仕事の責任も重くなり、企業の相談業務から事務所内の一般従業員のマネジメントなどが挙げられます。
勤務社労士が高収入を得るには
企業に勤務する社労士の場合、勤務先の会社の規模による影響よりもむしろ任される仕事内容によって年収が大きく変動します。
税務会計や各種保険の手続きといった基本的な業務が中心の場合、年収は500万円前後の求人が多く、高収入は望めません。
給与水準が600万円を超えるのは人事統括といったマネジメント業務や大手クライアントに対するコンサルティング業務が中心となっています。これらの業務を担当するためには、資格取得だけでなく実務経験も必要になるケースが多いです。
また、社労士の仕事に対する理解が深い企業を選ぶことも極めて重要なポイントです。
社労士の専門性の高さを正当に評価してくれる企業であれば、企業の重要な立ち位置を任せてくれることが多いので、給与水準もかなり高いです。
高年収の社労士求人を探すなら
勤務社労士にとって、企業が社労士の仕事を正当に評価してくれるかどうかは年収の高低に直結します。
努力して手に入れた社労士の資格、せっかくならしっかりと認めてくれる職場で働きたいですよね。
有資格者向けの求人は探すのに苦労するものですが、10万件以上の非公開求人を抱えるリクルートエージェントであれば、社労士向けのハイレベルな求人をたくさん見つけることができます。年収1000万を超える社労士求人も珍しくありません。
「転職支援実績No.1」という非常に高い評価を得ている信頼できるサービスなので、この機会に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
社労士は女性でも高収入が狙える!

社労士は他の仕業と比較しても女性の割合が非常に高く、年収にも男女差がほとんどないのが特徴です。
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| 社労士の男女比 | 65.5% | 34.5% |
| 平均年収 | 507万円 | 555万円 |
平成28年に実施された厚生労働省の調査結果によると、この年の勤務社労士の平均年収は527万円となっています。このうち、男女別の勤務社労士の平均年収は男性が507万円、女性が555万円です。
他の士業を見てみると、税理士は女性の割合が14.4%、中小企業診断士は女性はなんと全体の6.3%と非常に少ないです。社労士は士業の中でも特に女性の活躍の場が広いことが分かります。
副業で年収をあげることも
資格を生かした副業が豊富なのも社労士の特徴の1つです。
以下では具体的な副業とその収入について紹介します。
予備校や通信講座の講師
週に2日程度、予備校等での講義を行うことで収入を得ます。社労士を目指すのは社会人の方がほとんどなので、講義も平日の夜や休日に行われる点も魅力的です。
自身が努力して身につけた知識を生かせる上に時給も8000円程度と高いことが多いので、非常に魅力的な副業だと言えます。
公的機関の業務補助
行政がハローワーク等を通じて社会保険労務士会に依頼して行われる無料相談会に参加したり、ハローワークで就職相談に乗ることで収入を得ることができます。
相談会は日給2万円程度、就職相談は時給制であることが多いです。
その他保険に関連したアルバイト
他にも社労士資格が生きるアルバイトは多数存在します。例えば保険代理店ではアルバイトとして社労士資格をもつ人を募集していることがあります。
総じて時給は高くはありませんが、副業程度の収入は得られるはずです。
社労士の副業についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
社労士の主な仕事内容は?
先にも述べたように、社労士は扱う業務内容によって年収が大きく変わります。手続き代行や書類作成業務は報酬が低く、クライアントに対する相談業務は高収入につながりやすいです。
それでは、社労士の具体的な仕事内容について見ていきましょう。
独占業務の内容と給与
多くの場合、社労士に求められるのは独占業務と呼ばれる社労士にしかできない仕事です。その内容は主に保険や年金に関する事務手続き代行であり、1号・2号業務と呼ばれます。
1号業務は、具体的には申請書類を作成したり、それらの書類の手続き代行・事務の代理などを行う業務となっています。
2号業務は就業規則などの帳簿書類の作成のことを指します。会社に必ず備え付けておかなければいけない書類となっているので、この業務は大事であるといえるでしょう。
近年では自動書類作成ツールやAI技術の進歩により徐々に失われつつある業務でもあります。そのため、給与相場は低くなる傾向にあります。
相談業務の内容と給与
企業には様々な雇用状況の人がいるため、それぞれの労務管理や保険の手続きについて企業内では判断しかねることも多いです。
そんな企業に対して労務のプロとしてコンサルティングを行うのが社労士の相談業務であり、3号業務とも呼ばれます。
また、近年では個人を対象にした年金相談業務も急増しています。いずれも機械やAIに代替されにくい業務であり、個人が独自の価値を見出すことのできる仕事なので、やりがいが大きく給与相場も高いです。
社労士の仕事内容についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
社労士の年収の将来性は?
社労士に限らず多くの士業はAIによって仕事の大部分が代替されてしまうと言われています。そんな中代替されずに残り続ける仕事は、事務的な手続き業務ではなくコンサルティングなどの個人にしかできない仕事です。
この影響を受け、社労士の1号・2号業務は徐々に失われていくのは間違いありません。
一方で、近年はITインフラの整備やAI技術の進歩により個人の働き方が多様化し、労務のプロフェッショナルである社労士の知識がより一層求められています。さらに国民の高齢化に伴って個人の年金相談もますます増加しています。
したがって社労士の需要は3号業務を中心として今後も大きくなっていき、この先も高い給与水準が維持されるでしょう。
社労士の将来性の詳しい情報は以下の記事も併せて参照してください。
社労士試験の難易度
収入面で魅力の大きい社労士でしたが、資格の難易度は高く取得するのは簡単ではありません。資格取得の難易度が高い理由は主に以下の2つです。
- 受験資格が存在する
- 試験の合格率が低い
受験資格は大卒の学歴があれば問題ありませんが、学歴がない場合には実務経験が必要です。資格取得を考える際には受験資格も必ずチェックしておきましょう。
また社労士試験の合格率は6%前後とかなり低く、また合格ラインが各科目に設けられていることから、合格は容易でないことがわかります。
社労士の難易度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
社労士の年収まとめ
社労士の年収についてまとめ
- 社労士の平均年収は665万円
- 勤務社労士は収入が安定している
- 開業社労士の収入には幅があり年収1000万円を超えることも
- 3号業務は将来も安定した収入源となる
社労士の年収について説明してきました!
皆さんもぜひ社労士の資格を手にして、高収入を目指してみてはいかがでしょうか。