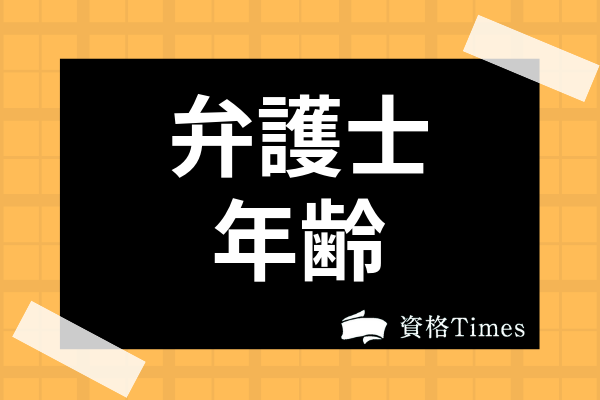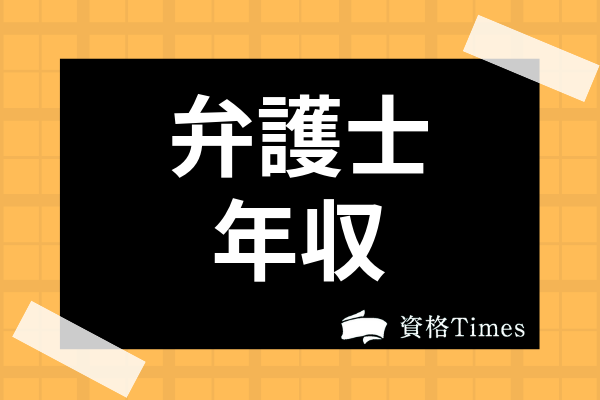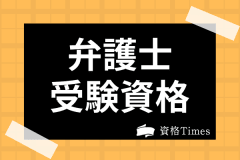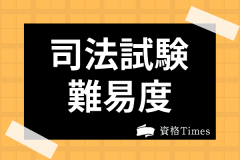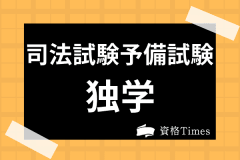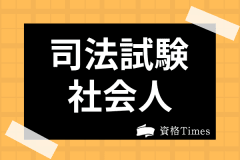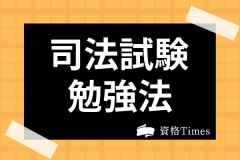弁護士になる難易度はどれくらい?予備試験攻略法や司法試験易化の実態まで徹底検証!
「司法試験の難易度ってどれくらいなの?」
「弁護士って苦労してまでなる価値はあるの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
弁護士になるには司法試験に合格しなければなりませんが、司法試験は難しいというイメージがありますよね。
また、最近は難易度が落ちて簡単になったという話も聞きますが、本当なのでしょうか?
そこで資格Timesでは司法試験の難易度について、合格率から予備試験の難しさなど様々な観点から分かりやすく解説していきます!
これを読めば司法試験の難易度についてはバッチリです!
弁護士になるまでの難易度についてざっくり説明すると
- 司法試験の難易度レベルは最高峰
- 合格ラインは高くなく、以前よりは簡単になりつつある
- 試験範囲が非常に広いため長期の勉強が必要
- 厄介な足切り基準がある
このページにはプロモーションが含まれています
弁護士になる難易度はどれくらい?

弁護士になるには司法試験に合格する必要があります。
司法試験は他の資格試験と比べても難易度は圧倒的に高く、1年や半年で結果を出せる試験ではありません。
しかし、近年の合格率は30~40%程度で推移しており、かつての旧司法試験に比べて10倍以上もの合格率の試験となったことから、「司法試験は簡単になった」という意見も散見されるようになってきました。
そのため、2年~5年ほどの時間をかけて、きちんと対策をして試験に臨めば、十分合格を狙える難易度だと言えるでしょう。
弁護士になる難易度は司法試験の難易度と直結
弁護士になるまでの最大の難関は、やはり最高クラスの難易度を誇る司法試験に合格することです。
また、合格後は1年間の研修である司法修習に移行し、最後には「二回試験」と呼ばれる試験に合格しなければ弁護士として登録することができません。
ただし、この二回試験の合格率は90%以上であり、司法試験合格者であれば特段問題がない限りほぼ確実に合格できる試験となっています。
この高い合格率の理由は、ただでさえ難易度が高い司法試験に合格している人間を改めてふるい落とす必要はないためです。
そのため、弁護士になる難易度は司法試験の合格率とほぼ同じであると言えるでしょう。
まずは司法試験の合格を最大の目標として設定し、そこに向かって勉強することに集中するべきです。
司法試験は簡単になっているのか?

政府は、近年法曹人口を増加させる政策をとっています。
それにより新司法試験の実施が開始され、合格率・合格者数はともに上昇しています。
しかし、いまだ当初の計画通りに法曹人口は増加していないのが実情です。
司法試験の合格率は約30%
ここで、司法試験の過去9年間の合格率を見てみましょう。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 平成27年度 | 23.1% |
| 平成28年度 | 22.9% |
| 平成29年度 | 25.9% |
| 平成30年度 | 29.1% |
| 令和元年度 | 33.6% |
| 令和2年度 | 39.2% |
| 令和3年度 | 41.5% |
| 令和4年度 | 45.5% |
| 令和5年度 | 45.3% |
なお、2023年度の受験者数は3,928人、合格者は1,781人でした。
合格率は近年上昇しており、40%中盤まで上昇していることがわかります。
そもそも、司法試験の受験資格を得るまでに厳しい要件があるため、合格率自体は他の資格試験よりも高くなっています。
厳しい受験要件を考慮すると、実質的な合格率は2~3%程度でしょう。
なお、類似する法律関係の士業としては、行政書士試験の合格率は8~15%、司法書士試験の合格率は3~5%となっています。
司法試験の合格基準点は意外に低い
司法試験の合格ラインは短答式試験・論文式トータルの点数で50%前後となっています。
2023年度の合格ラインを見てみると、770点以上が総合点の合格ラインとなっています。
この合格ラインを見ると、意外とハードルが低く重点箇所を中心にしっかりと対策をすれば合格できるということがわかります。
ただし、1問1問の難易度は高いため油断すると不合格になってしまうことに留意する必要があります。
このように、一般的なイメージが先行して「司法試験は超難関試験だからほぼ完璧な法律知識がないと合格できない」と考えられがちですが、決して100%の完成度は要求されないのです。
つまり、しっかりと得点するべき問題を押さえ、それに加えて分からない問題を少しずつ減らしていけば十分に合格ラインに達することができるのです。
弁護士になるまでには最短で3年必要
司法試験の難易度は落ちているとはいえ、試験を受けるために厳しい受験資格が設けられているため、受験資格を得るまでも大変な道のりです。
司法試験を受けるためには、合格率約4%という難関試験であるである司法試験予備試験に合格するか、あるいは法科大学院を卒業するのいずれかのコースをとる必要があります。
合格までに必要な勉強時間は、予備試験合格若しくは法科大学院入試に向けた勉強を開始する時から起算すると、3000時間~8000時間程度といわれています。
つまり、ゴールである司法試験に合格するためには、数年の勉強期間を要する試験なのです。
このような必要勉強時間から、弁護士になるには勉強開始から少なくとも3年以上の時間がかかると言われています。
もちろん、進捗具合や元々の法律知識の有無などによって3年で合格できる人もいるため、一概には言えない部分もありますが、長丁場になることは間違い無いでしょう。
この長期に及ぶ勉強時間を見ると及び腰になってしまうかもしれませんが、弁護士資格はこの時間をかける価値のある一生ものの高給資格です。
社会的地位も高く、その後のキャリアにいい影響を及ぼしてくれる可能性が高いため、苦労してでも取得を目指す価値はあると言えるでしょう。
司法試験の試験制度と科目の概要
司法試験は一次の短答式試験と二次の論述試験で構成されています。
短答試験では憲法・民法・刑法の3科目の知識が択一問題形式で問われ、論述試験は公法系科目と民事系科目、刑事系科目、選択科目の4科目の知識が問われます。
試験科目は、公法系では憲法・行政法、民事系科目では民法・商法・民事訴訟法、刑事系科目では刑法・刑事訴訟法、選択科目では知的財産法・労働法・租税法・倒産法・経済法・国際関係法(公法系)・国際関係法(私法系)・環境法の中から1科目を選択し、計4科目です。
この中では特に民法の負担が重くなりがちです。条文が1000条以上あり、また各論点もかなり複雑なので重点的に勉強する必要があります、
民法以外も試験科目は膨大で、それぞれの法律の知識もかなり深く要求されます。
そのため、どの法律もメリハリをつけて勉強し、また過去問で多く見かけるような重要論点を落とさずに対策をすることが大切になります。
司法試験がやはり難しいと言われている理由
試験範囲の膨大さ
司法試験が難しい最大の理由は、学ぶ法律科目数の多さと膨大な出題範囲です。
また、短答試験では足切り基準が設けられているため、極端に苦手科目があると総合点が良くても不合格になってしまう危険があるのです。
そのため、できるだけ苦手を作らないように満遍なく勉強をしなければならないことが非常に手間で厄介なのです。
足切りさえクリアできれば、合格ラインは近年では合格点は1500満点中約54%の810~805点ほどであるため、全体的なハードルは低いと言えるでしょう。
実際に、基本書の内容や短答試験・論文試験対策を全て完璧にする前に合格できたという合格者も多いのです。
つまり、メリハリをつけた効率的な勉強をすれば十分に合格できる学力を身に着けることができるわけです。
司法試験の試験科目の詳細は下記の記事をチェック!
膨大な勉強時間と体力の確保
司法試験の総勉強時間は数千時間となるため、社会人生活や学生生活の合間から数年間にわたり時間を確保しなければなりません。
スケジュール管理に加え、勉強以外の様々な誘惑に耐える精神力や健康管理能力も問われるのです。
数年間にわたって定期的な運動や質の高い睡眠、健康な食事などの体調面にも気を付けながら勉強をし続ける生活は、なかなか簡単ではありません。
論文式の対策が難しい
論文式の試験では、白紙の用紙にその場で作成した回答を書き提出します。これが最も難解なポイントになります。
択一式の試験ではないため、知識はもちろん問題の慣れがなければまず得点を得られないためです。
合格点を得るには問題を見た時に 「どのようなポイントに絞って、何を、何文字程度書けばよいのか」を判断できるまで試験に慣れておかなければいけません。
さらに、解答を採点者に一発で理解してもらえるわかりやすい文章を作成する必要があります。
この試験が難しいと言われている理由の一つは、試験対策は自分一人ではなく予備校講師などのプロや司法試験経験者に回答を見てもらい添削をしてもらう必要があるためと言われています。
司法試験の受験資格取得は2パターン
司法試験の受験資格をクリアするためには、「司法試験予備試験に合格する」または「法科大学院を卒業」しなければなりません。
なお、法科大学院の受験資格は「大学を卒業していること」または「大学に3年以上在籍し勝つ優秀な成績を収めていること」などの要件があります。
最難関試験の司法試験予備試験に合格する
司法試験予備試験の合格率は4%程で、とても難易度が高い試験です。
ただし、司法試験とは違い予備試験は受験資格を問わず誰でも受験することができます。
また、予備試験合格者の司法試験合格率は他の有名法科大学院を圧倒しており、予備試験合格者の司法試験合格率は80~90%ほどの非常に優秀な数字となっています。
以下の表が実際の数値です。
| 年度 | 予備試験合格者の司法試験合格率 |
|---|---|
| 2023年 | 92.6% |
| 2022年 | 97.5% |
| 2021年 | 93.5% |
| 2020年 | 89.4% |
| 2019年 | 81.8% |
| 2018年 | 77.6% |
法務省の発表によると2023年の予備試験合格者の司法試験合格率は92.6%となりました。
直近3年では、予備試験合格者の司法試験合格率は90%を超えているのです。
また、予備試験ルートであれば法科大学院の授業料のような大きな出費を抑えることができるため、費用の面でも優れていると言えます。
よって、試験の難易度とご自身の金銭事情を比較衡量した上で、予備試験に進まれるか法科大学院に進まれるかを決定するのがおすすめです。
なお、予備試験合格者は難関試験に合格した証明になります。
「法律知識が豊富な優秀な人材」という評価をしてもらえるため、弁護士事務所への就職・転職活動の際にも有利となるでしょう。
法科大学院で学ぶ
次に、法科大学院を卒業し司法試験を受けるルートを見てみましょう。
法科大学院には、法学部卒業者などの法律既修者を対象にした2年間のコースと、法律未修者を念頭のおいた3年間のコースがあります。
自分の法律知識のレベルに応じてコースを選べるため、学校の資料請求などを行ってカリキュラムを実際に調べるようにしてください。
司法試験合格者のうち、約80%が法科大学院ルートで司法試験に合格しているため、合格者の大半が法科大学院を経由して合格を掴み取っていることがわかります。
学校で実務上のスキルなども学べ、法律の本質も併せて学ぶことができるため、予備試験と異なるメリットを兼ね備えた魅力的な選択肢であると言えます。
弁護士になるチャンスの時代
政府は法曹人口の増加を目指して新司法試験を開始しました。
しかし、合格者人数は政府の計画通りには増加しておらず、今後の司法試験で合格基準が緩くなる可能性が指摘されています。
近年の合格率は上昇を続けており、30%程の人が合格しています。
以前行われていた旧司法試験の合格率は約3%であるため、現在の試験の合格率はその10倍にあたる数字なのです。
そのため、今は合格しやすいチャンスの時代であり、以前と比べて弁護士になりやすい時代だと言えるでしょう。
また、合格しやすくなったとはいえ弁護士の評価や一般的な信頼度は相変わらず高いものとなっており、様々な場面で頼られています。
つまり、なるべく早く勉強を開始して司法試験の合格を目指すのがおすすめとなっているのです。
弁護士の偏差値は75?
司法試験の取得難易度は、偏差値で換算すると75程度だと言われています。
難易度が落ちたと言われているものの、推定偏差値は依然として極めて高く、間違いなく最難関レベルの国家試験です。
弁護士の希少価値や対外的な評価を考慮すれば、この偏差値75という数字は妥当であると言えるでしょう。
なお、他の資格と偏差値を比較すると以下の表のようになります。
| 資格 | 偏差値 |
|---|---|
| 弁護士 | 75 |
| 医師 | 74 |
| 司法書士 | 72 |
| 税理士 | 72 |
| 中小企業診断士 | 63 |
| 社会保険労務士 | 62 |
| 行政書士 | 60 |
| FP1級 | 58 |
| 宅建士 | 56 |
法律系の資格はもちろん、あらゆる国家資格と比較した場合でもトップの難易度を誇ることがこちらの偏差値表から窺い知ることができます。
よって、難易度は非常に高いもの、その難易度の高さに見合ったリターンを得られる資格であることも間違いないため、ぜひ法曹を目指したい方は積極的にチャレンジされると良いでしょう。
弁護士は難易度ランキング第一位の資格
では、合格までに必要な勉強時間を、他の資格と比較してみましょう。
| 資格 | 必要な勉強時間 |
|---|---|
| 司法試験 | 8000時間 |
| 税理士 | 5000時間 |
| 司法書士 | 4000時間 |
| 社会保険労務士 | 1000時間 |
| 行政書士 | 600時間 |
こうして見ても、司法試験は非常に難易度が高い資格であることがわかります。
司法書士の倍近くの勉強時間が必要とされることからも、難易度の高さがうかがえます。
弁護士は他の士業四資格よりどれくらい難しいのか
弁護士は仕事の需要や専門性の高さ、給料の高さでも最高ランクの資格です。
同じ法律系士業である行政書士と司法書士と比較してみましょう。
司法書士
司法書士は登記に関する専門家で、法人登記や不動産登記などの独占業務を持っています。
司法書士試験の試験科目は司法試験と重複するものが多く、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法などがあります。
司法書士試験合格には3000〜4000時間ほどの勉強時間が必要であると言われており、司法書士も十分難しい資格であることがわかります。
なお、司法試験も2〜3年ほどかけて合格を目指す人が多く、根気強く勉強していかなければなりません。
ただし、司法試験に合格するためには司法書士の2倍以上の勉強時間が必要と言われているため、司法書士の勉強でつまずいてしまうと司法試験の合格は難しいでしょう。
司法書士の難易度の詳細は下記の記事も併せてご覧ください。
行政書士
行政書士は許認可に関する専門家です。
1万以上の公的な書類を扱うことができるため、幅広い業務を行うことができます。
行政書士試験の試験科目には憲法・民法・商法など司法試験の試験内容との重複もあるため、行政書士の勉強をしたことがある人は司法試験の勉強に抵抗なく取り組めるでしょう。
とはいえ、司法試験の方が出題難易度が圧倒的に高く、行政書士よりも遥かにレベルが高い問題が出てきます。
行政書士試験の合格には600時間ほどの勉強時間が必要であると言われているため、司法試験に合格するには行政書士の5倍〜12倍ほどの勉強時間が必要ということになります。
行政書士の詳しい難易度は下記の記事をチェックしてみてください。
弁護士志望の司法試験受験者層を分析
弁護士になる層は、司法試験受験者層とほぼ一致しています。
ただし、司法試験に合格した若手法律家の中には弁護士ではなく検察官や裁判官などの国家公務員としてのキャリアを志望する人もいます。
そのため、弁護士になる司法試験合格者の年代層は若干年齢が高めと言えるでしょう。
司法試験合格者の年齢層
司法試験合格者の2023年度試験の平均年齢は26.6歳でした。
近年の平均受験合格者の平均年齢は26~29歳で推移しており、20代後半で受験する人が多いことが分かります。
ちなみに、類似する法律資格である司法書士試験の平均合格者年齢は37~38歳です。
司法試験の平均合格者の年齢が低い理由は、試験の難易度をあらかじめ想定し、大学在学中から勉強を開始するなど対策を早めにとる人が多いことが挙げられます。
大学在学中であれば、法律系科目の講義を受講することで試験科目に直結する知識を得ることができるため、効果的な学習ができるのです。
しかし、社会経験を積んだ上で司法試験合格をする人もいるため、必ずしも若い人が有利というわけではありません。
また、社会人経験を積んだうえで弁護士資格という強力な資格を手にすることで、30代以降からでも法曹として十分に活躍できるのです。
むしろ、社会人経験が浅いか、もしくはほとんど無い若年層と比べると即戦力として見てもらえる強みがあります。
ちなみに、2023年の司法試験最小年合格者はなんと19歳、最高齢合格者は66歳でした。
年齢問わずしっかりと勉強をしていけば合格することができる試験であることが分かります。
司法試験合格者の年齢層や弁護士の平均年齢については下記の記事をチェック!
司法試験合格者の男女比
2023年度司法試験合格者の男女比は表の通りでした。
| 項目 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 司法試験合格者数 | 1257人 | 524人 |
| 合格者に占める割合 | 70.58% | 29.42% |
前年の2022年度も男性72.27%、女性27.73%と、ほぼ同じ男女比となっています。この比率を見てみると、男性比率が大きく女性がかなり少ないことが分かります。
しかし、司法試験に限らず士業は男性の割合が大きいのが特徴なので、特段珍しいことではありません。
男性が試験上有利ということではなく、むしろ司法試験合格者のうちの女性の合格率と合格者数は年々増加しています。
今は女性の活躍や社会進出が求められている時代なので、性別を問わず司法試験に合格し、弁護士になりやすい時代であると言えるでしょう。
離婚案件や家族でのトラブルなど、問題の性質上女性弁護士の活躍が求められる場面も増えているため、今後活躍する女性は増えていくでしょう。
今弁護士資格取得がおすすめのわけ
司法試験の受験者数は近年はやや減少傾向にあるものの、合格率は上昇を続けています。
つまり、弁護士の世間的な評価は高いままであるにも関わらず試験には合格しやすくなっているため、弁護士になるには今が狙い目なのです。
業務範囲が広く就職・転職でも最強
弁護士は法律系資格の中では最高ランクです。
そのため、司法試験に合格することで司法書士・行政書士・社労士・弁理士・税理士の業務もカバーできるようになります。
これにより業務の幅がとてつもなく広がることになるので、自然と様々な方面から頼られることになるのです。
また、一般的に司法試験合格者の優秀さと法律分野での専門性の高さは高く評価されており、全国に高額な弁護士の求人があります。
弁護士資格を活かしてキャリアアップや収入増を目指して転職をする人も多く、転職市場でも多くの企業から高評価をしてもらえるでしょう。
法律事務所などで実務経験を積んでから独立開業を目指す人も多く、非常に使い勝手の良い資格と言えるでしょう。
弁護士の年収は高く昇給・昇進面でも有望
2018年に実施された賃金構造基本統計調査によると、弁護士の平均年収は賞与込みの数値で男性1595.2万円、女性が733.2万円という結果でした。
このように弁護士の平均年収は約1,000万円となっており、一般的なサラリーマンの水準よりも遥かに高いことがわかります。
毎年の年収ランキングでも上位の常連なのが弁護士であり、イメージ通り弁護士は高級取りであることがわかります。
また、弁護士事務所や法律事務所だけでなく、最近は一般企業でもインハウスローヤーとして企業内弁護士を募集する動きがあります。
一般企業で働く場合でも、弁護士資格を生かして省庁や役所で働く場合でも、弁護士資格取得者は周囲から一目置かれる存在であるため、無資格者よりも昇進や昇格のスピードが早い傾向にあります。
また、企業によっては資格手当なども付くことが多いため、金銭面のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
弁護士の年収事情についてはこちらの記事も併せてご覧ください。
弁護士には独立・開業の道も
司法試験に合格した後は、弁護士事務所を独立・開業して自分で商売をするという選択肢もあります。
独立開業した場合、定年退職という概念がなくなるため、年齢に関係なく元気である限り働くことができます。
また、弁護士はただでさえ高収入であることに加えて、自分の弁護士としての能力の高さや事務所の運営の手腕次第で、いくらでも収入増が見込めるという魅力もあります。
60歳以上でも弁護士として活躍している人も多くいるため、年齢に関係なく自分の能力やスキルさえあればいつまでも働くことができることがわかります。
独学で弁護士になるのは極めて困難
司法試験合格までには膨大な量の勉強をしなければなりません。
そのため、他の資格試験以上に、独学で弁護士を目指すことは困難であると言えます。
独学だとモチベーションを保つことが難しいだけでなく、手間がかかるスケジュール管理も自分で行わなければなりません。
また、プロの目線からの口述試験のフィードバックを受けたり、論文試験の添削指導を受けられない点も大きなデメリットです。
フィードバックや添削を受けられないことで、自分の論文の質を高めていくことができないため、周囲と差をつけられてしまうリスクが大きいのです。
弁護士になるまでの勉強法
司法試験の内容はかなり難易度が高いため、全てが理解できなくとも基本書などをまずは読み進めることが重要です。
長く辛い勉強を続けていくためには、目標を共有できる勉強仲間をつくり、予備校や通信講座の講義のペースにあわせていくことが有効です。
また、独学だと分からない問題があっても質問できなかったり、自分の間違えた問題は他の人も間違えているのかという見極めもできません。
有益な情報を交換していくという意味でも、予備校・通信講座の利用は非常に有意義なのです。
対策講座の活用が弁護士への最短ルート
司法試験の合格を目指すのであれば、予備校や通信講座の活用が一般的です。
もちろん、現在大学生の方であれば、法律の講義を受けることである程度は司法試験対策をすることができるでしょう。
しかし、大学の講義は教授の個人的な思想を反映しているだけで、司法試験合格に必要な有名な論点や学説、判例を学ぶことはできません。
このような講義を受けるだけでなく、司法試験対策に最適化された予備校や通信講座の講義やテキストを中心に勉強をしなければ合格は難しいでしょう。
つまり、弁護士を目指すなら対策講座を上手に活用し、最短距離で司法試験合格を目指すことが必要なのです。
長丁場の試験勉強ではスケジュール管理が大切
司法試験の勉強は長丁場になるため、スケジュール管理が重要です。
予備校や通信講座では、合格のノウハウを詰め込んだ勉強スケジュールを立ててくれるため、そのスケジュールにしたがって学習を進めると効果的です。
合格するためには、継続的な勉強が何よりも大切であり、綿密な学習スケジュールを立てることで合格までの道筋が見えてきます。
また、スケジュールをこなしていくことでモチベーションを維持しやすくなり、勉強も継続しやすくなるメリットもあります。
勝負は論文試験対策
短答試験の対策をすることで、論文試験を解くために必要な知識も自然と定着していきます。
論文練習する中で、一人で論文答案の評価をしていても論文はブラッシュアップされず、次に生かせる反省が得られません。
そこで予備校や通信講座を利用すると、プロである講師に論文問題の添削指導をしてもらえるため非常に便利です。
論文試験の対策は、弁護士になった後の仕事にも直結することが多いため、実務対策にもなるのです。
司法試験対策の鉄板の予備校は?
司法試験対策の講座を選ぶ際に、まず検討したいのがアガルートの講座です。
アガルートは高い合格実績を誇りながら、既存の大手予備校の講座と比較して40万円近く安いリーズナブルな価格設定を両立させています。そのためアガルートの講座はコスパ抜群の司法試験対策講座として受講生から非常に高い評判を得ています。
アガルートの講座はオンラインで自分の都合のつく場所や時間で受講することができ、テキストもフルカラーで理解しやすいよう工夫されています。
司法試験・予備試験合格を目指す方は、ぜひ一度アガルートの講座をチェックしてみてください。
弁護士になるまでの難易度のまとめ
弁護士になるまでの難易度のまとめ
- 2〜5年の長期的なスパンで勉強を進めていく必要がある
- 近年は易化傾向にあるため、今が狙い目!
- 試験の合格ラインはそこまで高くないため、メリハリをつけた勉強が重要
- 独学で合格を目指すのは非常に困難なので、予備校や通信講座を利用するべき
「司法試験は簡単になりつつある」という噂はあながち嘘ではありません。
とはいえ、相変わらず超難関資格であることには変わりないので、長きに渡る努力は欠かせないでしょう。
しかし、その分取得できたときのメリットは極めて大きく、キャリアに良い影響を及ぼしてくれることは間違いありません。
取得は簡単ではありませんが、ぜひ合格を掴み取って貴重な人材になってください!