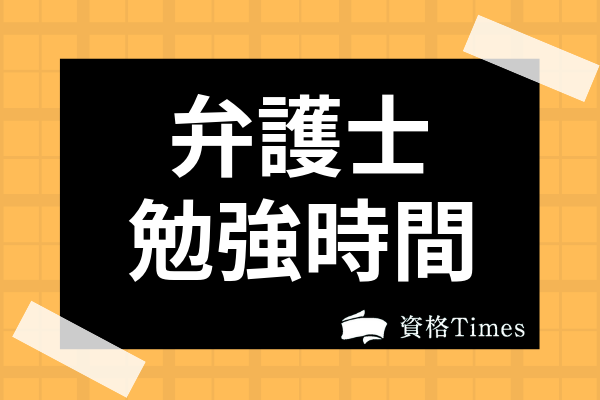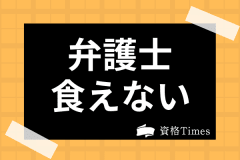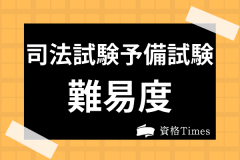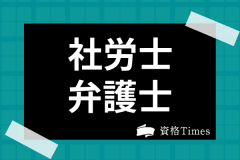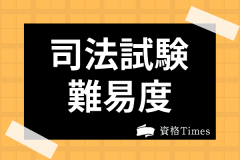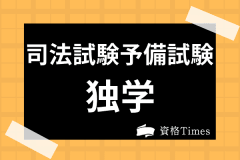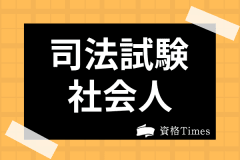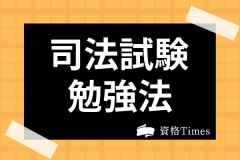司法試験予備試験の独学合格は難しい?弁護士になるための参考書・テキストまで解説!
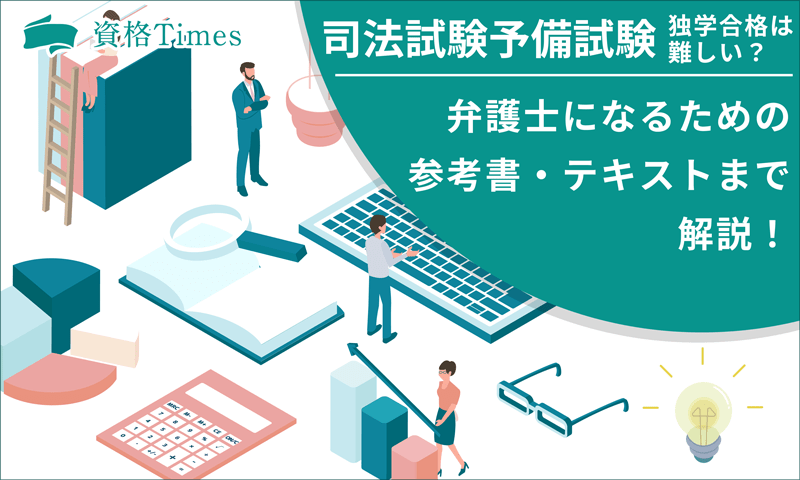
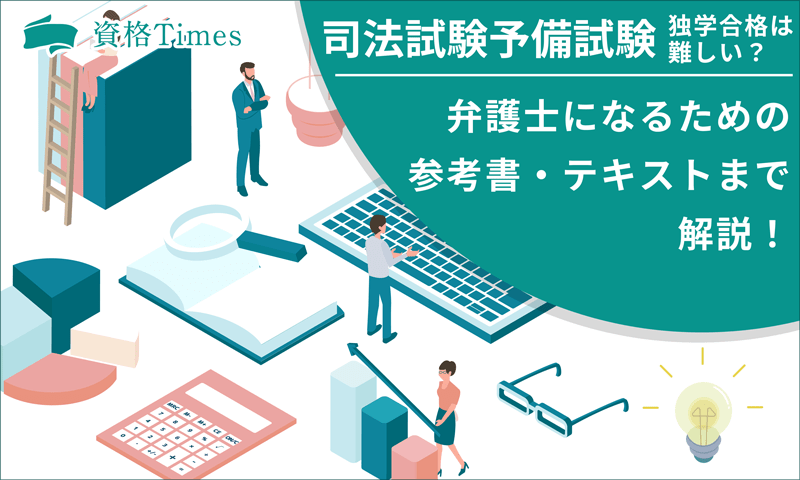
「司法試験予備試験の難易度はどれくらいなの?」
「司法試験予備試験は独学で合格を目指せるの?」
このような疑問をお持ちの方も多いかと思います。
司法試験予備試験の合格率は例年4%程度であり、非常に難易度が高い試験です。
そのため、独学で挑む人は稀であり、予備校や通信講座などを利用することが一般的です。
ここでは司法試験予備試験の具体的な難易度、使うべきテキストや参考書について解説していきます!
司法試験予備試験の独学についてざっくり説明すると
- 最高クラスの難易度なので、独学はほぼ不可能
- 数年に及ぶ勉強が必要になるため、計画性が大事
- 自分に合ったテキストを選び、スマホアプリなども活用すると良い
- インプットとアウトプットを計画的にやらなければならない
このページにはプロモーションが含まれています
そもそも司法試験予備試験とは?

予備試験(司法試験予備試験)とは、司法試験の受験資格を得るための試験のことを指します。
法科大学院を卒業していなくとも受験資格を得ることができ、さらに予備試験自体には受験資格が存在しません。
そのため、高校生や高卒の方など、必要な学歴を満たしていないものの司法試験合格を目指している方々が幅広く受験をする試験となっています。
ただし、司法試験の受験資格は、予備試験合格後の翌年から5年間のみ有効というルールがある点には注意が必要です。
法曹への多様な人材登用のために生まれたこの予備試験という制度ですが、近年予備試験合格者の司法試験合格率が高まっていることから受験者数が増加しています。
以下は、それぞれの令和5年度司法試験合格者数、及び合格率です。
| 区分 | 司法試験受験者数 | 司法試験合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 法科大学院修了者 | 3,575人 | 1,454人 | 40.67% |
| 予備試験合格者 | 353人 | 327人 | 92.63% |
予備試験と司法試験は必要とされる能力が本質的に同じであることから、予備試験の勉強をすることがそのまま司法試験合格の可能性を高めることにつながります。
そのため、司法試験合格のために、予備試験の勉強を行うことは非常に効率が良いと言えるのです。
独学でも予備試験には合格できるのか

まず、司法試験予備試験に独学で合格している人はいるのでしょうか?
実際には、無理に独学で進めるのではなく各予備校・通信講座・法科大学院に通い予備試験対策をする人が多いです。
やはり予備校や通信講座・法科大学院が公表している司法試験予備試験の合格実績は非常に優れており、こうしたデータを見ても独学で挑むより合格できる可能性が高いのは明らかです。
過去の司法試験予備試験合格者は、予備校や通信講座・法科大学院を利用した人がほとんどであるため、よほど自信がない限りは独学は控えるべきだと言えるでしょう。
もちろん、予備校などを利用せずに独学で司法試験予備試験に合格する人もごく少数ながらいます。ただし、少なくとも筆者の周りには一人もいませんし、毎年1人いるかどうかというレベルでしょう。
このように、予備試験・司法試験はともに最難関レベルの国家試験なので、独学で進める場合は相当な覚悟を持って勉強しなければならず、他の人よりも高いリスクを背負って学習を進める覚悟が必要となります。
予備試験の合格率は例年4%ほど
以下は直近5年間の司法試験予備試験の合格率です。※最終合格率
| 年度 | 最終合格率 |
|---|---|
| 2019年 | 4.04% |
| 2020年 | 4.17% |
| 2021年 | 3.99% |
| 2022年 | 3.63% |
| 2023年 | 3.58% |
上記のようにほとんどの受験生が予備試験や通信講座を使って万全の対策をもって試験に臨むにも関わらず、予備試験の最終合格率は4%前後となっています。
こうした状況の中、予備試験に独学合格するのは極めて困難であることがわかるでしょう。
予備試験ルートなら司法試験の完全独学合格が可能
司法試験には受験資格が設けられております、司法試験予備試験に合格するか、法科大学院を卒業するかの2ルートがあります。
このうち、法科大学院ルートを選ばずに司法試験予備試験に合格するルートを選べば、完全に独学で司法試験の受験資格を得ることができます。
予備試験合格者の司法試験合格率は90%以上と非常に高く、予備試験である程度の法律知識が完成することが分かります。
なお、予備試験には受験資格が設けられていないため、年齢や性別・実務経験などによる受験資格制限はなく、基本的には誰でも受験することができます。
そのため、若い内から法律の勉強に励んでいる高校生や大学生から、社会人で働きながら司法試験に合格することを目指している人など、様々な人が受験しているのです。
予備試験は短答試験・論文試験・口述試験の三段階で行われ、そのすべてに合格しなければなりません。
予備試験の合格率は3~4%と低く、科目が司法試験よりも多いため「難易度は司法試験以上に高い」という声もあるくらいです。
しかし、法科大学院を卒業するには2~3年がかかりますし、お金もかなり必要になります。時間的余裕や金銭的な余裕が無く、独学で司法試験合格を目指す場合には、この予備試験を突破するしか手はありません。
予備試験の短答試験
短答試験は憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・一般教養の8科目をマークシート形式で解いていきます。
試験時間は4コマに別れており、令和元年度は以下のようなスケジュールで行われました。
| 試験時間 | 試験科目 |
|---|---|
| 90分 | 民法・刑法・民事訴訟法 |
| 60分 | 憲法・行政法 |
| 60分 | 刑法・刑事訴訟法 |
| 90分 | 一般教養 |
合計270満点で、合格点は160点以上となっています。
予備試験の論文試験
論文試験は、憲法・行政法・刑法・刑事訴訟法・一般教養 (人文化学・社会科学・自然科学)・法律実務基礎科目(民事・刑事)・民法・商法・民事訴訟法の10科目が問われます。
一科目あたり50分の試験時間で、10科目で500点満点の試験になっています。
合格点は240点以上とハードルは低いのが特徴です。
予備試験の口述試験
口述試験で問われる内容は、法律実務基礎科目の民事と刑事についてです。
口述試験であるため、弁論能力が評価の対象です。
面接のような形式で行われるため、これまでの筆記と違って緊張しますが、合格率は90%以上なので滅多に落ちません。
口述試験で問われる弁論内容は、論文試験の知識で十分対応できるため、しっかりと忘れないようにしておけば問題無いでしょう。
1000~5000時間の勉強時間が必要
初学者の場合、司法試験予備試験に合格するまでに1000~5000時間程の勉強が最低でも必要であると言われています。
非常に勉強するべき量が多いため、早くても1年、一般的には2年〜5年の勉強が必要となるでしょう。
社会人が働きながら勉強する場合であれば、一日あたり平日は3時間、休日は10時間ほどの勉強時間を確保できれば、2〜5年程度で合格を狙えます。
つまり、できれば週に30~40時間の勉強時間を確保し、それを継続するようにしましょう。
これだけの長い期間に渡って独学で勉強することができて、法律の勉強に自信があり中断してしまうことがなければ、独学でも合格は狙えます。
これまでに行政書士や司法書士の試験に受かっていて、法律の勉強が苦にならない人であれば挑戦する価値はあるでしょう。
予備試験・司法試験の学習時間の詳細は下記の記事をチェックしてください。
不合格になった時の損失を軽視しない
司法試験予備試験の難易度を考慮すると、上述の勉強時間を無事に達成できたとしても、独学合格できる可能性は限りなく低いというのが現実です。
そして不合格になってしまった場合、当然ながら一年後の試験まで再び勉強し続けなければいけません。
その時間を無駄にしてしまうリスクまで考えると、無理に独学で頑張るのはおすすめできません。
また、独学だと下記のようなデメリットを被る可能性が極めて高く、学習を予備校に通われている方と比べて効果的に進めるのは難しいのが現状です。
- 学習の方向性を誤っても訂正するのが難しい
- 分からない学習内容を質問できない
- モチベーションが上がらない
- 参考書を網羅的に揃えるのが難しい
どうしても独学で挑戦してみたいのであれば、最初の1年間だけ独学してみて、行き詰まりを感じたら予備校や通信講座に切り替えるのもアリでしょう。
ただし、予備校などを利用した方が最適化された教材や講義・添削指導などを通じて効率よく勉強できるため、飛躍的に合格できる可能性が高まります。
年に1度しかない難関試験に確実に合格したいのであれば、無理に独学にこだわり続けるよりも最初から予備校や通信講座を受講する方が、結果的に費用対効果的が優れた選択といえる場合が多いのです。
神童と呼ばれた人でも独学は避けている
予備試験を受験する方の中には、東大法学部などの超エリート層も少なくありません。
筆者の周囲にも、灘高校出身の「神童」で東大法学部在籍中に予備試験に合格した人がいますが、そういった日本トップクラスの頭脳を持つ神童ですら、独学を避け予備試験講座を受講して勉強していました。
こうした事例からも、独学で予備試験を目指すことが如何に厳しいかが分かるでしょう。
予備試験の独学合格が難しい理由

法律という分野がそもそも難しい
独学合格のための一つ目の壁として、「専門用語が非常に難解である」という点が挙げられます。
丁寧に解説がなされている本やテキストは一定数存在しますが、やはり独力で完全に理解することは非常に難しいです。
また、法律の世界では「行間を読む」ということも必要になります。なんとなく内容が理解できる程度では、不十分です。
行間を読むためには、これまで蓄積されてきた議論や何十何百という論文を読み解く必要がありますが、市販のテキストや基本書ではこちらの点がかなり端折って記述されています。
そのため、A説とB説がなぜ対立しているのか、という議論の背景を把握をすることが困難であり、見解の対立点がわからなくなってしまうのです。
加えて、テキストによって言っていることが違う場合も少なくありません。
「通説」であるのか「有力説」であるのか、学習を進めていく中で相場が肌感覚でわかってくるものですが、学習を初めて間もない時期は戸惑ってしまうことが多いです。
試験範囲に対応した学習ができない場合も
予備校が出版している基本書では、司法試験対策のために書かれているのではなく、著者の研究成果を掲載している場合も少なくありません。
当然こういった本では、司法試験対策として的確な学習を行うことはできないでしょう。
また、独学では過去問の分析を行うのにも非常に手間がかかるため、出題されそうな分野の見極めがうまくできないという点も問題です。
優先的に勉強をすべき分野の見極めができないため、膨大な量の判例集、論文、法学雑誌などを読む必要が出てきまし。
そのため、合格に向けた効率の良い学習をすることができなくなってしまうのです。
論文形式の試験が攻略できない
論文形式の採点は「条文や判例と同様だから正解」というようには採点されません。
最高裁判所の判例が出された事件と似たような事例が出題されることもありますが、大抵実際の事件とは微妙に問題をずらして出題がなされます。
そのため、判例に述べられていることをそのまま書いたとして正解にはならないのです。
目の前の問題に対して、論理でストーリーを作る必要がありますが、これは誰かに見てもらわなければ中々上手に書けるようにはなりません。
このように、論文問題は知識だけで解けるものではなく、思考や書き方のテクニックが必要であることから、合格点のハードルは低いものの攻略が難しいのです。
口述試験対策も極めて困難
予備試験には実務基礎科目の口述試験も課されるため、口述対策も欠かせません。
この試験は面接官からの圧迫感がある面接なので、独学では対策ができません。
論文形式の問題と同様、独学合格を目指す場合には鬼門となるでしょう。
独学だと練習相手の面接官役をやってもらう人を見つけるのも非常に苦労します。
また、練習相手を見つけられたとしても建設的なアドバイスがもらえるかどうかは怪しく、==練習の成果を得られるかどうかも不安があります。
予備試験を受ける際には口述試験対策は欠かせないため、独学合格が非常に難しくなってしまいます。
情報収集をこまめに行う必要がある
法律は毎年一定の改正が実施され、判例も新たに追加されていきます。
予備校の場合は、都度講義やテキストでその情報を把握することができますが、独学の場合は自分で積極的に情報を集めに行かないとこの事実に気づくことができません。
改正箇所から一定程度問題が出題されることから、独学の方は抜け目なく改正ポイントの情報も集めていく必要があるのです。
予備試験に独学で臨むメリットは?
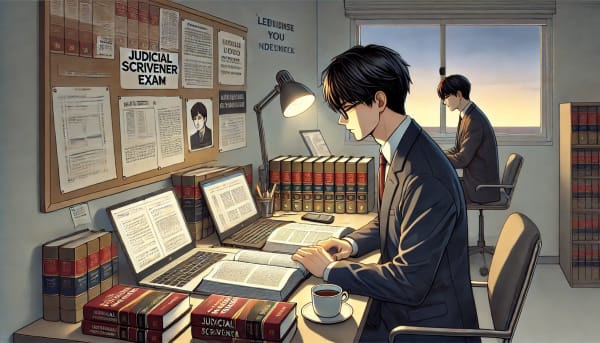
黙々と我が道を行ける
独学で学ぶメリットは、やはり自分のペースで勉強を進めることができる点です。
勉強慣れしていて、地頭が良い人は無理に予備校のカリキュラムに合わせるよりも自分のペースでどんどん進めたほうが効率的になるケースもあります。
また、苦手な範囲を重点的に勉強したり、得意な科目や既に他の法律系の資格試験や法学部での勉強など、事前知識がある分野を手短に済ますなど、柔軟性に勉強のスケジュールを調整できる点もメリットとなります。
予備校などに通っていると、仕事などで急な予定が入ったりした場合に欠席してしまうことになります。
予備校や法科大学院のように通う時間が決まっていると、欠席したときに結果的に受講費用が無駄になってしまうケースがあるため注意が必要です。
コストを抑えて一生ものの資格を得られる
予備校や通信講座を利用すると、かなり高額な受講料がかかってしまうため、費用が抑えられることは独学の最大のメリットと言えるでしょう。
独学の場合、必要な出費は予備校の出版する基本テキストや基本書・問題集など、必要な本を買うことや受験料、模試の受験料などだけで済みます。
そのため、予備校などを利用する場合の10分の1程度で済むでしょう。
一般的に難易度が高く学習期間が長い資格の講座ほど受講費用は高くなるため、独学で進められる自信がある人は挑戦してみる価値はあります。
ただし、何度も不合格を繰り返してしまうと新しいテキストをまた買い揃えなければならないため、結果的に高くついてしまうことがある点には注意が必要です。
予備試験独学のデメリット
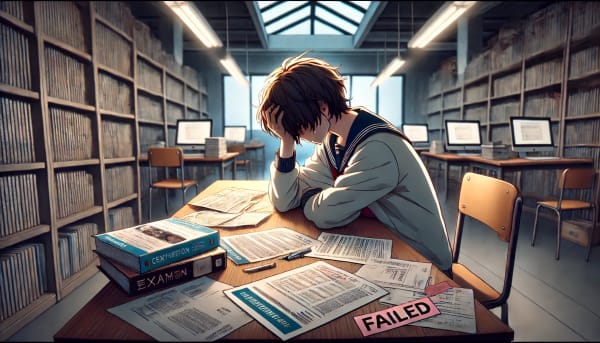
勉強が進まない
一般に、司法試験合格には3000~8000時間以上の勉強が必要と言われているため、3年〜5年以上の長い時間に渡って勉強しなければなりません。
法律の勉強をするときに障害となるのが難解な用語や複雑な判例などの読解です。
法律系の勉強をしたことが無い人の場合は、独学では簡単には理解できない分野が多々出てくるでしょう。
これらの難しい用語や判例を勉強する際には、いちいち用語を調べたりする必要があるため手間がかかり、挫折してしまう危険があります。
また、独学の場合は予備校などと違って一緒に目標を共有できる仲間がいません。
仲間がいないことで、情報の共有ができず周囲の勉強の進捗具合もわからないため、モチベーションや学習ペースの維持が難しいというデメリットがあります。
スケジュール管理が予想以上に難しい
勉強のスケジュールを管理するのは、案外手間がかかります。
周囲のアドバイスが無い中で自分でスケジュールを立てると、試験までに必要な範囲を全てカバーできなかったり、無理があるスケジュールを立てて途中で挫折してしまうことがあります。
また、論文の添削指導が受けられずに、質の高い論文が書けないまま試験本番を迎えてしまうこともあります。
高い評価をされる論文の書き方を知らないまま闇雲に論文演習をしても、建設的なアドバイスが得られないため良い論文を書くことはできません。
そのため、試験を受ける前から絶望的な状況になってしまうことが少なくありません。
特に、予備試験は合格率が低く非常に難易度が高いためスケジュールをしっかり立てないといけません。
予備校・通信講座や法科大学院を利用して勉強をしているライバルは多いため、間違った方法で勉強をしていると残念ながら合格は難しいでしょう。
独学仲間はほとんどいない
残酷な事実として、予備試験に独学合格している人は毎年1人いるかいないかであり、独学合格は不可能と言っても過言ではありません。
そのため共に独学する仲間を見つけることは極めて困難ですし、独学で合格した先輩を見つけることもできません。
そういった状況の中で、それでも独学で勉強し続けるというのは、正直あまり良い選択とは言い難いでしょう。
非効率な勉強スタイルを修正しづらい
司法試験に限らず、その他の資格試験や受験勉強でも独学の方に陥りやすいのが「自分の勉強スタイルが非効率であることになかなか気が付かない」ことです。
自分でテキストや学習スケジュールを管理する必要がある故におこる課題です。
よくある事例が、テキストも複数冊に手を出してしまい「浅く広く」で学習がとどまってしまうケースや、得意な暗記や試験範囲ばかり勉強してしまい苦手範囲の学習がおろそかになってしまうケースです。
長期間にわたる試験勉強管理には修正がつきものです。
第三者に自分の学習スタイルを見てもらい、適宜修正しつつ、学習量を増やしたり減らしたりするなどができない試験勉強はどうしても非効率になってしまいがちになってしまいます。
独学で挑めそうな人の特徴

孤独な戦いになれている人
司法試験対策を独学で進めるのは長く孤独な戦いになるため、過去に難関資格を独学で取得したことがある人など、いわゆる勉強慣れしている人でなければ独学はオススメできません。
このように独学で成果を上げた経験のある人は、「どのくらいのペースでインプットをこなして、どれくらいの時期にアウトプットとして過去問演習をすれば良いか」といった勉強の進め方が既に身に着いています。
また、勉強に対するモチベーションの維持の仕方や、試験直前期の焦りなどの気持ちの面での整理の仕方も経験しているため、独学のハードルが下がっていると言えるでしょう。
また難関資格試験でなくとも、大学受験などの場面で予備校などに通わずに自分の力だけで勉強をこなして合格を掴み取った経験がある人も、独学に向いていると言えます。
また、独学は長い間勉強だけでなく孤独との戦いになるため、一人で黙々と作業することが好きな人や、淡々と努力を重ねることが得意な人は独学に向いていると言えるでしょう。
法律の素養のある勉強家
在学中の方で、法律科目の授業を履修していてすんなりと理解できる人は法律を学ぶ素質があります。
また、すでに行政書士や司法書士などの法律関連の資格を取得している場合は、基礎となる憲法や民法・行政法・商法などの法律知識が身に着いているため初学者よりも有利に勉強を進めることができます。
そのため、司法試験予備試験に必要な法律の理解が早く、独学でもある程度は対応できるでしょう。
また、法律用語などの難解なフレーズをすぐに理解でき、小難しい文章である判例文などもスラスラと読める人は法律を学ぶ上で大きな強みとなるため、独学で挑戦する価値はあるでしょう。
独学の挑戦を助けるテキスト
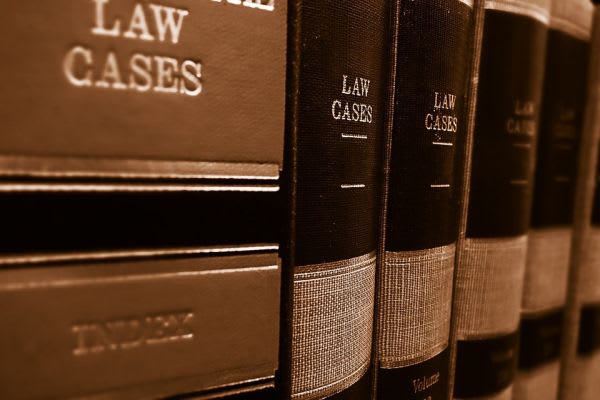
大学教授が研究の成果として発表している基本書を用いて勉強することで、スムーズに勉強が進む可能性があります。
確かに大学教授のような専門的に研究している人が出している書籍は弁護士の実務にも活用できるものが多く、非常に参考になります。
しかし、基本書は内容が専門的で初学者には向かず、必ずしも予備試験・司法試験予備試験向けに書かれているわけではありません。
そのため、初学者が独学で司法試験予備試験に挑むには司法試験予備試験対策専用に予備校が出版している予備校本を使用することがおすすめです。
無理にレベルが高いテキストや弁護士向けの書籍を使うよりも、初学者でもわかりやすいテキストを使った方が学習効率も良いのです。
テキスト選び方
テキストを選ぶ際には、自分の事前知識や法律知識のレベルに合ったものを選ぶ必要があります。
初学者の人であれば、最初は初心者用の参考書などを使い、慣れてきたら徐々に難しい教材を揃えると良いでしょう。
初学者の場合、いきなり法律を勉強したことがある人向けの難しいテキストを使うと、勉強の基礎となる専門用語のニュアンスを間違えて覚えてしまう危険性があります。
また、論証や判例を整理できなくなったりする恐れもあるため、自信が無ければ無理をせずに簡単な参考書を使うべきなのです。
また、司法書士などの他の法律系の資格を取得済みで、法律に関する勉強をしたことがある人であれば、自分が理解しやすいレイアウトのものや、通学・通勤時間中にも読みやすい者ものを選ぶなど、自分にとって勉強しやすいものを選べば問題ありません。
持ち運びしやすく勉強がはかどるようなものを選び、寸暇を惜しんで勉強していきましょう。
改正法に対応した参考書で勉強する
法律は順次改正されるため、法改正に対応した最新版のテキストを使って勉強しないと、せっかく覚えた内容が無駄になりかねません。
特に、最近では民法の大規模な改正が行われました。
これにより、2020年以降の試験では改正後の民法が出題されるため、新民法に対応した最新のテキストを使う必要があります。
問題集を選ぶ際にも、新しい民法の解説がされているかはよく確認する必要があると言えるでしょう。
民法以外にも法律の改正は頻繁に行われるため、時事にも注意を払いつつ勉強を進めていく必要があります。
同一系列のテキストが良い
勉強をする際には、できるだけ同じシリーズの教材で統一すると効率的な勉強ができます。
同一シリーズの基本所と問題集はリンクしていることが多く、問題集の解説において「基本書の○ページ参照」などと親切に書いてあるものが多いです。
また、テキストは何冊も準備する必要はありません。
一度買ったテキストが理解できないからといって、他のテキストを購入しても、つまずくボイントは一緒なのであまり意味がないのです。
そのため、同じシリーズのテキストを購入し、できるだけその一冊で勉強を済ませるようにしましょう。
一冊の内容をしっかりと理解することで、基本的な知識は概ね身に着くため、改めて教材を買う必要はありません。
無駄に多くの教材を買っても、内容が重複したり、漏れが生まれる恐れもあります。
また、それぞれの教材で説明の切り口が違うと、一度理解した内容であっても混乱してしまう恐れもあるため、教材は一つに絞るべきなのです。
伊藤塾の「伊藤真の○○法入門」がおすすめ
司法試験の勉強をするにあたって、「伊藤真シリーズ」は非常にオススメです。
これは、司法試験予備試験対策予備校で最大手である伊藤塾のカリスマ塾長伊藤真の記したテキストです。
「伊藤真の○○法入門」シリーズは難しいイメージがある法律に関して、具体例を交えながら解説しています。
初学者の方でもわかりやすく書いてあるため、法律の勉強経験がない人や自信がない人にもオススメの教材です。
また、憲法、民法、刑法、民事訴訟法・刑事訴訟法・商法、行政法、法学入門と科目ごとにテキストが出ています。
つまり、試験科目がこのシリーズですべてカバーできるので、買い揃えれば予備試験・司法試験予備試験の基礎が網羅できることになります。
長年に渡って司法試験予備試験対策指導に携わってきた伊藤真の基礎テキストは、独学者が使用してもスムーズに勉強できる構成になっているため、大きく道を誤ることはありません。
このシリーズを徹底的に使いこなしていけば、確実に合格に近付けるでしょう。
スマホアプリも使える
現在では、受験生向けのスマートフォンアプリも多く存在しているため、有効活用すると良いでしょう。
これらを用いると、スマートフォンさえあれば勉強できるようになるあめ、通勤中の電車・バスの中でもちょっとした時間を利用して勉強ができるようになります。
そのため、隙間時間で勉強する際にわざわざ大きく重い六法等の参考書を持ち運ぶ必要がなくなるため、非常に楽になるでしょう。
電車内などでついついゲームやSNSを見てしまう人は、今後それらに費やしていた時間をすべて勉強につぎこんでみましょう。
一回の勉強は短い時間でも、コツコツとした積み重ねで驚くべき成果に繋がるため、ぜひ有効に活用してください。
司法試験予備試験短答問題練習アプリや論文試験合格に必要な論証を確認できるアプリ、さらに持ち運ぶには重い判例六法を見られるアプリもあるため、必要に応じてインストールしておくと良いでしょう。
通信講座を使うのも手
完全独学で勉強を続ける自信のない方は、通信講座(オンライン予備校)の受講を検討するのも良いでしょう。
通信講座であれば独学に近い形式で隙間時間を生かしながら勉強可能ですし、予備校と比べて費用も安く済むのでおすすめです。
特にアガルートの司法試験予備試験講座は司法試験・予備試験の合格者を641名も輩出している大人気講座なので、この機会に是非チェックしてみると良いでしょう(令和5年度時点実績)。
アガルートの予備試験・司法試験講座の詳細は以下の記事も併せてご覧ください。
独学を続けるには

長期スケジュールを覚悟する
予備試験合格には少なくても1年、通常は2年〜4年以上の勉強期間が必要になるため、長期に渡り勉強する覚悟が必要です。
そのため、毎年5月に実施される予備試験まで、勉強できる期間があと数カ月しかないといった場合は、その年の試験での合格はほとんど不可能に近いでしょう。
本番の雰囲気を体感するという目的で、試しに受験してみるのは大いにアリですが、このようにあまり勉強期間がとれない場合は、来年以降の試験に照準を合わせるべきです。
その際に、どのように合格を目指すのか綿密に計画を立てるべきなのは言うまでもありません。
また、スケジュールを立てる際は、できるだけ時間にはゆとりを持った日程を組むように心掛けましょう。
日程にゆとりがあることで、突発的な用事が入って当初の予定通りできなくなってもリカバリーできるため、精神的な安心に繋がります。
ただし、期間だけ長く取っておいて、勉強のモチベーションが持続していないと意味がありません。
計画を立てるのと同じく、うまくモチベーションを維持することにも注意を払う必要があるでしょう。
最初は基礎知識を頭に入れる
人によってやりやすい勉強方法は様々です。
そのため、以下の内容はあくまで参考にし、自分の都合に沿った勉強法でぜひ進めていってください。
まず最初は、基本テキストとなる予備校本や基本書を使って、基本情報のインプットをしていきましょう。
当然一度では理解できない内容もあるため、まず1周目は全体像を把握し、2周目以降で細かい理解をすれば問題ありません。
インプットが終わったら、問題集などを使ってアウトプットをこなしていきましょう。
アウトプットをしっかりと行わないと、自分の理解が甘い箇所や苦手分野が浮き彫りにならないため、丁寧に行うことを心掛けましょう。
独学の場合、使うべき一冊を決めたら、その一冊を何度も繰り返し読み込んで完成度を高めていくことが重要です。
もし、選んだ一冊が予備試験・司法試験予備試験レベルの内容を完全に網羅していない場合は、より応用の利いた発展的なテキストを準備すると良いでしょう。
基本テキストは3周以上繰り返し読む
基本テキストを初めて読む段階では、前述したとおり分からない論点が出てきてもあまり気にせず、どんどん読み進めていくべきです。
全体像を体系的に理解すれば、2周目以降の読み込みで細かな部分の理解も自然と追いついてるため、1周目でわからない場所があっても深く気にする必要はありません。
テキストは、少なくとも3周は読み返して、目立った疑問点が無くなったらアウトプットに着手すれば良いでしょう。
また、基本テキストを読み込みと同時進行で予備試験や司法試験予備試験の短答問題を解くことで、インプットした内容の理解を深めることもできます。
インプットだけでなく、しっかりとアウトプットも行うように心掛けましょう。
10年分以上の過去問を解く
十分にインプットをこなして実際に問題を解いてみると、自分の知識に抜けがあったり、判例の解釈が間違っていたというケースが出てきます。
そのような問題に出くわしたときは、しっかりと復習してインプットをし直して正確な知識を定着させなければなりません。
間違いが多いと精神的にへこむこともありますが、ここでしっかりと見直しておかないと合格はできません。
このようなケースを通じてどんどん記憶の質が高まっていくため、アウトプットは非常に重要なのです。
過去問は本番レベルの問題を体感できるものであり、内容・レベルともに最良な練習材料です。
つまり、過去問演習をしっかり時間をかけて取り組むことができるかどうかが、合否を分けると言えるでしょう。
合格者の多くは10~15年分の過去問をこなしていることから、過去問は少なくとも10年分は解くようにしてください。
ここで重要なのは自分の間違いにしっかりと気づくことです。
間違っていた範囲に関しては、何度も解説とテキストを読み直し、似た問題では絶対に間違えないように反省することが合格を目指すうえで何よりも重要なのです。
予備試験ルートのメリット
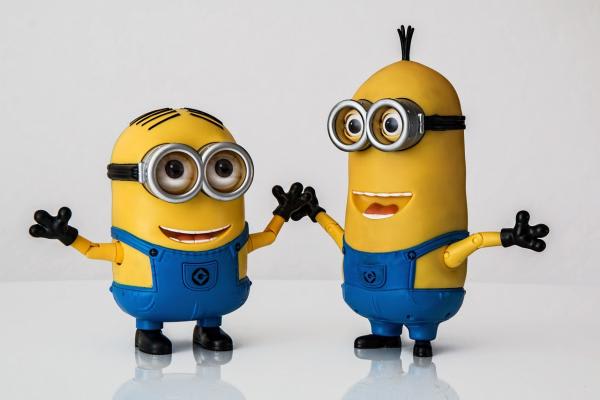
司法試験の易化した今がチャンス
試験科目の膨大さや合格に必要な勉強時間等を総合的に勘案すると、今なお司法試験予備試験は最難関の国家試験です。
しかし、「司法試験は簡単になった」という巷の声もある通り、旧司法試験予備試験に比べると試験難易度は低下しており合格率は高まっています。
つまり、取得しやすくなっているにも関わらず司法試験合格者や弁護士の世間的な評価は非常に高いため、取得を目指すのであれば今が狙い目と言えるのです。
今後もこの易化傾向が続けば、数年後は弁護士の数が増えすぎて飽和状態になってしまうことも考えられるため、できるだけ早く取得して実務経験をこなすことが重要となります。
司法試験の難易度変化については下記の記事をご覧ください。
周りから一目置かれる
司法試験予備試験に受かることで、司法試験への挑戦権を得たことになるので周囲から一目置かれるのは間違いありません。
予備試験ルートでの司法試験合格者は、検察官・裁判官となるにあたっても優秀な人材と見なされるため、昇格のスピードが速い傾向にあります。
また、司法試験に合格すれば、行政書士や司法書士・税理士・弁理士・社労士の業務範囲もカバーできるようになるため、自分の業務の幅が大きく広がり自分の市場価値を高めることに繋がります。
司法試験予備試験合格者の優秀さ、法律分野での専門性の高さは高く評価されているので、一般企業や法律事務所からの引く手は多いでしょう。
「司法試験予備試験合格」のステータスで求人サイトに登録すると、実際に多くの企業からスカウトメールが来るため、需要は非常に高いと言えます。
法科大学院の学費が浮く
司法試験へのもう一つのルートである法科大学院の学費は、年間100万円近くかかります。
予備試験に合格することで、その学費を節約することができるため総費用はかなり安く済む他、弁護士になるまでの期間も短縮できるため予備試験ルートは非常にコスパが良いと言えます。
予備試験の準備に充てっても予備校へ支払う受講料などは発生するものの、法科大学院ほどの費用はかかりません。
つまり、予備試験は「安く早く」合格を目指せるためおすすめなのです。
予備試験対策は独学と予備校どっちがおすすめ?

ここまで確認してきたように、予備試験に独学合格することは「制度上は」不可能ではありません。
しかし、不可能ではないことと、現実的であるかどうかは全く別の話です。
ライバルとなるほとんどの受験生が学習環境の整った予備校に通っている状況で、独学で彼らを出し抜くのは困難を極めるでしょう。
予備試験の難易度を考えれば、予備校や通信講座を利用して出来る限りの対策の上で試験に臨むのが賢明です。
予備校・通信講座のメリットは大きい
独学ではなく、予備校・通信講座を選んで学習をされる場合、特に下記のようなメリットを享受することができます。
頻出知識に的を絞って対策できる
予備校・通信講座の講師は過去問を徹底研究し、頻出箇所とそうでない箇所を熟知しています。
そのノウハウは、講義やテキスト作りに生かされており、受講生は膨大な範囲の中から試験の点数アップに直結する頻出論点に効率よく当たることができるのです。
独学では、そもそも頻出箇所を把握するために多大な時間を要することを加味すると、ストレートで合格直結の知識にあたれることは大きなメリットであると言えるのです。
法律用語をわかりやすく解説してくれる
法律用語は、概念が抽象的で理解が進みづらかったり、一般的な使い回しとは異なる意味を持つものが多く存在します。
講師陣は、このような受験生が躓きやすい箇所を長年の指導経験から熟知しており、具体例も交えながらお粥レベルに噛み砕いて講義を進めてくれます。
よって、抽象的な文言が並ぶテキストを必死に理解しようとして多大な時間を浪費してしまう独学での学習と比べて、インプットがスムーズに進み、アウトプットなど他にやるべき大切な勉強に時間を割けるようになるのです。
予備試験対策の予備校は?
予備試験対策、及び司法試験の合格を目指されている方であれば、まず検討されるのは伊藤塾でしょう。
伊藤塾はあらゆる司法試験予備校の中でも他の追随を許さぬ実績を誇っており、知名度・信頼度共に非常に優れています。
一方で伊藤塾の講座費用は100万円以上とかなり高く、入塾するのは現実的に難しいという方も多いです。
そこでおすすめなのが、アガルートの予備試験対策講座です。
アガルートであれば伊藤塾よりも30万円近く支出を抑えることができる上に、641名もの司法試験・予備試験合格者を輩出している(令和5年度実績)など、確固たる実績も併せ持っています。
さらにアガルートはオンライン講座ということで、なかなか勉強時間が確保できないという方でもスマホ1つでいつでもどこでも学習を進められます。
予備試験合格を目指される方は、是非この機会にアガルートをチェックされてみてはいかがでしょうか。
司法試験予備試験は独学できるのかまとめ
司法試験予備試験の独学まとめ
- 独学での合格は不可能ではないが、非常に難しいことは覚悟するべき
- 非常に膨大な範囲を勉強するため、根気が必要
- 独学のメリットとデメリットを理解し、自分に向くかどうかを見極める
- 隙間時間も有効活用し、努力を継続することが大事
司法試験予備試験に独学で臨むのは難しく、仮に独学で頑張るのであれば相当な覚悟が必要です。
確実に合格を目指すのであれば、通信講座や予備校の利用が安定でしょう。
また、これまでに法律の勉強をしたことがない人や自信がない人は、迷わず予備校などの利用を検討してください。
難しい分、取得メリットが大きい資格なので、ぜひ頑張って自分の可能性を広げていってください!