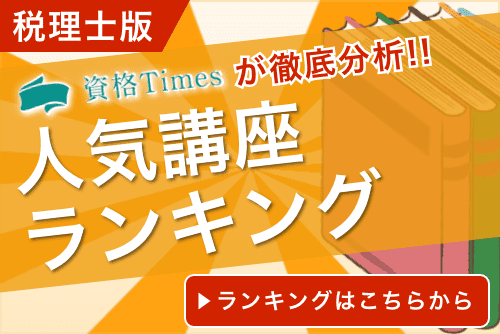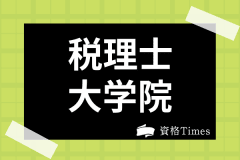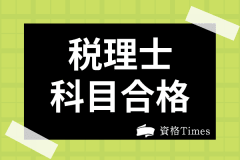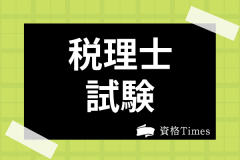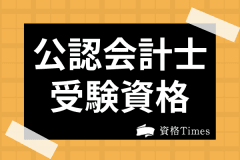税理士試験の科目免除とは?条件や活用方法・利用時の注意点まで徹底解説!
「税理士試験の科目免除制度ってどんなものだろうか?」
「自分も制度を利用できるのだろうか?」
そんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
科目免除制度は上手に活用することで税理士合格までの負担を減らすことができますが、一方で制度を利用するための負担や利用することによる影響も見逃せません。
ここでは税理士試験の科目免除制度について、その特徴や利用時の注意点について解説します。
税理士試験の科目免除についてざっくり説明すると
- 資格や学位、勤務年数により免除できる制度がある
- 免除制度そのものは決して税理士への近道ではない
- 税理士として活動できるだけの知識・経験を身に付けておくべき
税理士試験の免除制度とは?
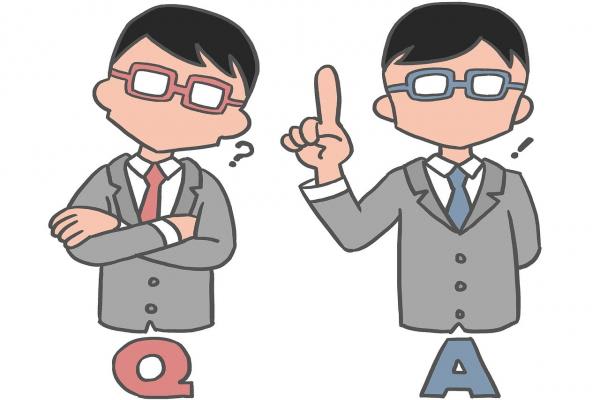 税理士は国家資格の中でも特に難関であることが知られていますが、それゆえに途中で資格習得を諦めてしまう人も多いです。
税理士は国家資格の中でも特に難関であることが知られていますが、それゆえに途中で資格習得を諦めてしまう人も多いです。
しかし、実は税理士試験には免除制度が存在することをご存知でしょうか?
免除制度には、以下の3種類があります。
-
資格による免除
-
大学院の学位による免除
-
国税専門官など、税務署勤務による免除
世の中には、このような様々な免除制度を利用して資格習得をする人も多いのです。
資格による免除
弁護士、公認会計士の資格を持っている人は、そもそも試験を受けずに税理士の資格が取得でき、税理士として登録ができます。つまり、全科目が免除されることになります。
しかし、公認会計士に関しては平成29年4月1日以降に合格した場合、税法に関する研修を受けることが必須となりました。
理由は、公認会計士試験の租税法が税理士試験での税法よりも範囲が狭いため、公認会計士試験に合格しただけでは税法に関して十分な知識が得られないことが懸念されるためです。
実際、細かい税務の現場では公認会計士ではなく税理士が頼られることが多いので、この制度変更は実態に即したものであると言えるでしょう。
大学院の学位による免除
大学院の学位によって試験を免除することも可能です。
ただし、取得した時期によって免除の内容が異なっていますので、注意が必要です。
また、特定の科目の大学院で学位を取得することで免除が可能となっており、その免除科目も選ぶことができます。
なお、免除科目を会計科目にするか税法にするかということを選ぶことができるのは、このケースだけとなっています。
平成14年3月31日以前に大学院に進学した場合
商学系の学位を取得していれば、会計科目2科目が免除となります。
また、法学、財政、経済系のいずれかの学位を取得していれば、税法科目3科目が免除となります。
平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合
このケースでは、取得した学位が修士なのか、それとも博士なのかによって免除の内容が異なっています。
まず、博士の場合には、会計系あるいは税法系の博士論文を書いて学位を習得することで、試験免除となることが可能です。つまり、平成14年3月以前の制度と同じ制度となっています。
一方で、修士の場合には、会計系あるいは税法系の修士論文を書き学位を習得し、かつ、それぞれの科目で1科目以上の合格が必要となってきます。この点が、法改正で変わった点となっています。
税務署勤務による免除
国税専門官などとして税務署に一定期間勤務していた人を対象とした免除制度も存在します。
この税務署勤務による免除では、「勤務内容」と「勤務年数」が免除の内容に大きく関わっています。
このあたりの条件は少しややこしくなっているので、注意することが必要となってきます。
10年または15年以上税務署に勤務した場合
| 法的根拠 | 該当者 | 免除科目 |
|---|---|---|
| 法8条4号 | 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上 | 税法-国税 |
| 法8条5号 | 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上 | 税法-国税 |
| 法8条6号 | 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上 | 税法-地方税 |
| 法8条7号 | 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上 | 税法-地方税 |
| 法8条8号 | 第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上 | 税法 |
| 法8条9号 | 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上 | 税法 |
まず、国税については、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税のいずれかに従事している場合には10年となり、それ以外の場合には15年となります。
また、地方税については、道府県民税(含:都民税)、市町村民税(含:特別区民税)、事業税、固定資産税のいずれかに従事している場合には10年となり、それ以外の場合には15年となります。
23年または28年以上税務署に勤務した場合
| 法的根拠 | 該当者 | 免除科目 |
|---|---|---|
| 法8条10号イ | 第4号から第6号(上記表)までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上 | 会計学 |
| 法8条10号ロ | 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上 | 会計学 |
| 法8条10号ハ | 8条10号イに規定する期間を通算した年数の23分の28(約82.14%)に相当する年数と8条10号ロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上 | 会計学 |
23年または28年以上税務署で勤務し、かつ、指定研修を修了した人は、会計学に属する科目となります。免除される科目については、23年または28年いずれも違いがありません。
23年に該当するケースは、国税、もしくは地方税のうち、道府県民税(含:都民税)、市町村民税(含:特別区民税)、事業税、固定資産税に従事している場合です。先の10年または15年以上の表における、第4号から第6号がこれに該当します。
28年以上税務署に勤務すれば自動的に税理士になれる?
実際23年または28年以上税務署に勤務している場合には、税法と会計科目の全てが免除されているということもありうるため、試験を受けることなく税理士になってしまうケースが存在します。
これは、5科目合格者からすると好まれないこともあり、一部では批判されていたりもしています。
免除申請に必要な書類は?
免除申請を行うにあたっては、所定の書類が必要となりますが、免除の種類(資格、学位、税務署勤務)によって必要な書類が異なってきます。
資格の場合
公認会計士などの資格取得者が免除申請を行う場合には、その資格の合格証明書などを提出する必要があります。
学位の場合
博士、修士などの学位取得者が免除申請を行う場合には、学位取得証明書 (「修士(法学)」、「修士(商学)」等の学位名が記載されたもの)や成績証明書、学位論文の概要などを提出する必要があります。
税務署勤務
国税専門官などの税務署勤務の要件を満たす者が免除申請を行う場合には、任命権者による職歴証明書を提出する必要があります。
免除制度は一般的になりつつある
 2022年3月時点の資格別税理士登録者数は以下のとおりとなっています。
2022年3月時点の資格別税理士登録者数は以下のとおりとなっています。
| 資格別 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 国家試験合格者 | 35,010 | 43.67 |
| 試験免除者 | 31,340 | 39.10 |
| 税務署等出身特別試験合格者 | 2,348 | 2.93 |
| 公認会計士 | 10,759 | 13.42 |
| 弁護士 | 703 | 0.88 |
| 税務代理士 | 2 | 0.00 |
| 資格認定者 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 80,163 | 100.00 |
表でも確認できるとおり、免除制度利用者の割合は40%に迫っており、科目免除利用者は一般的になりつつあることが読み取れます。
科目免除者の人数は?
税理士登録者の試験組・免除者数の推移は以下のとおりとなっています。
| 年度 | 免除者 | 5科目合格者 |
|---|---|---|
| H24 | 1,423人 | 1,017人 |
| H25 | 1,468人 | 876人 |
| H26 | 1,329人 | 867人 |
| H27 | 1,326人 | 892人 |
| H28 | 1,452人 | 850人 |
近年の税理士登録者数の状況を見てみると、5科目合格者よりも免除者の方が多くなっていることが読み取れます。
また、免除者の割合は年々増加していることから、今後が免除者の方がより一般的になるのではとも推測できます。
これまで、免除ルートは「わき道」などと揶揄されることもありましたが、本筋の5科目合格ルートがいつの間にか「わき道」になり、免除ルートが「本筋」に変わっていると言えます。
科目免除が人気の理由
税理士試験において、5科目全てに合格しようとするならば、何年も時間を費やしてしまうケースが存在し、相当な労力が必要となってしまいます。
そのため、この労力を惜しむ人が多くなっており、科目免除の制度を利用する人が増えている傾向にあります。
科目免除の制度を利用すれば、①短時間で合格できる可能性もあること、 ②少ない科目数を集中して勉強すれば良いため、勉強の効率が上がることなどのメリットがあります。
以上が、科目免除の制度が人気の理由と言えるでしょう。
免除制度を利用する際の注意点

免除するための労力は小さくない
免除制度という言葉だけ見ると、一見して楽に資格が取れそうな気がするかもしれません。
しかしながら、実際には免除制度を利用するための条件に関してはどれも厳しいものとなっており、長い年数がかかるものや、税理士試験の勉強とはまた違った勉強が必要となると言えるでしょう。
そのため、「免除制度=楽」という方程式は、税理士試験においては当てはまらないと言えます。
お金や時間がかかる場合が多い
例えば、大学院の学位による免除を利用する場合には、通学に200万円近くの費用を要することになります。
また、大学院の入学試験に合格する必要があることはもちろんですが、免除制度の恩恵を受けるためには教授に論文が認められる必要があるため、大学院に行ったからといって必ずしも試験科目が免除されるわけではありません。
そういった点からも、ただ単に税理士試験に合格するために免除制度の条件を満たそうとするならば、かえって膨大な時間とお金を要してしまうと言えるでしょう。
5科目合格者に見下される?
一昔前までは、免除制度を利用した人については、5科目全て受験して合格した人からするとどうしても甘えて合格したという風に見られてしまう傾向にありました。
また、そうした見方は試験合格後も続いて、同業者の中で免除制度利用者が肩身の狭い思いをするというケースもあったようです。
しかしながら、これまで述べてきたとおり、科目免除自体は今や一般的になっているので、その心配は無くなってきていると言えるでしょう。
知識・実務経験不足を不安視されることも
ただし、免除制度を利用して合格した人は、5科目受験して合格した人と比べて、税理士として必要な専門知識が足りないのではないか?という風に考える人も少なくありません。
この知識・実務経験不足が不安視されていることが、先の免除制度利用者に対する見方を構成する一因かもしれません。
一方で、税理士として実務を行う上では、試験で学んだこと以上に経験が大切になってくるという考えが浸透してきています。
そのため、この点についても基本的には心配する必要はないと言えるでしょう。
免除する科目の選び方
 それでは、どの科目を免除科目として選択することがおすすめなのでしょうか。
それでは、どの科目を免除科目として選択することがおすすめなのでしょうか。
前提条件として、免除制度の各要件のうち免除する科目を選択できるのは、大学院の学位による免除の場合のみとなっています。
大学院による免除を利用する場合には、2科目の免除が可能な「税法の免除」がおすすめと言えるでしょう。
合格のしやすさだけという観点で見るのであれば、選択必須科目である「法人税法」と「所得税法」、あるいは「相続税法」の難易度が高いですので、免除にはおすすめな科目と言えるでしょう。
ただし、税理士としては「法人税法」の知識については実務で頻繁に使いますし、持っておいた方が就職や転職の際に有利となります。
そのため、免除科目として選択するかどうかはよく考えるべきでしょう。
税理士試験の免除まとめ
税理士試験の免除まとめ
- 免除制度は資格、学位、勤務経験の3種類
- いずれも要件は厳しく、税理士の近道と呼べるものではない
- 5科目受験、免除制度のいずれでも、税理士になったあとの力を身に付けるべき
今回は、税理士試験の免除制度について、様々な観点から紹介してきました。
これまで見てきたとおり、免除制度そのものは非常に魅力的なものですが、税理士としての実力を備えずに免除制度を利用して税理士になってしまうと、その後の活動で苦労するかもしれません。
そのようなリスクも考慮した上で、税理士として働けるだけの実力をしっかりと養成する必要があると言えるでしょう。
税理士を目指す人たちにとって、参考情報の1つになれば幸いです。