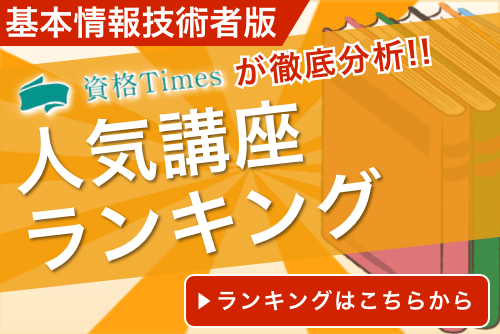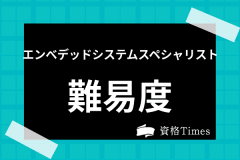基本情報技術者試験の表計算とは?対策のコツ・問題の解き方を徹底解説!
「基本情報技術者試験の表計算って何をするの?」
と疑問をお持ちの方もいるでしょう。
基本情報技術者試験の表計算は、プログラミング問題の1種です。初心者でも勉強しやすい分野ですが、馴染みのない方も多いはずです。
今回は、基本情報技術者試験の表計算について、対策のコツや問題の解き方などを詳しく解説します。
これを読めば、表計算問題への取り組み方がよく分かるはずです。
基本情報技術者試験の表計算をざっくり説明すると
- 表計算はExcelに似ている
- 演算子や関数を使いこなせるように練習が必要
- ミスが多発する科目なので、メモを取ることが重要
基本情報技術者試験とは
 表計算の説明の前に、まずは基本情報技術者試験の概要を解説しましょう。
表計算の説明の前に、まずは基本情報技術者試験の概要を解説しましょう。
ITエンジニアの登竜門
基本情報技術者試験は、新人エンジニアの登竜門と言われる国家試験です。IT関連の業務に必要である、基本的な知識や技能の習得を目的とします。
経済産業省にとって認定される、情報処理技術者試験の一つです。
IT企業によっては、新人社員に受験を義務付けているところもあり、就職や転職には有用な資格となります。
新人の場合、基本情報技術者試験の知識や技能を持っていることで、仕事に早く順応することが可能です。先輩エンジニアとの、業務上の意思疎通もスムーズにいくでしょう。
また一般企業からの転職でも、この資格は役に立ちます。基本情報技術者の資格は、IT業務に必須となる、基本知識や技能の証明となるからです。
この資格を所有していることで、経験の浅さをカバーすることができます。
基本情報技術者試験の難易度
基本情報技術者試験の合格率は、例年20〜30%の間を推移しています。また、近年は20%台前半が多いです。そのため、合格率でいうと、難易度はやや高いと言えます。
基本情報技術者試験は、情報処理技術者試験の中で、レベル2に分類されます。レベル区分でいうと、レベル1のITパスポート試験と、レベル3の応用情報技術者試験の中間に位置する試験です。
よって、IT初心者や新人エンジニアレベルでは苦労することもあるでしょうが、一番難しいというほどではありません。
基本情報技術者試験の表計算ってどんな科目?
 基本情報技術者試験では、午後試験の選択科目の一つとして、表計算が出題されます。
基本情報技術者試験では、午後試験の選択科目の一つとして、表計算が出題されます。
以下では、表計算の詳細を、午後試験の概要説明を交えながら詳しく解説します。
午後試験には何が出題される?
午後試験の出題は、長文形式の問題です。一つの大問の中には、複数の設問が含まれています。
試験内容ですが、「情報セキュリティに関すること」(第1問)と「データ構造及びアルゴリズムに関すること」(第6問)は必須問題です。
問2〜5からは2問を選択して解答します。ソフトウェア・データベースからシステム戦略まで、幅の広い出題からの選択です。
問7〜11に関しては、Java・c言語・Python・アセンブラ・表計算というソフトウェア開発に関連した分野の選択問題から、1つを選んで回答します。
午後試験の配点は以下の通りです。
| 問い番号 | 回答数 | 配点割合 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 20点 |
| 2〜5 | 2 | 各15点 |
| 6 | 1 | 25点 |
| 7〜11 | 1 | 25点 |
表計算を含むプログラミング言語の配点は25点です。これは全体の4分の1にあたり、この部分の出来が大きく合否に影響すると考えられます。
午後試験の概要は以下の記事で確認してください。
表計算の主な特徴・出題内容
表計算は、プログラミングに馴染みがなくても、勉強を始めやすい科目だと言えます。
Javaなど他のプログラミング言語は、覚えることが多いため、未経験者がいきなり取り組むのは困難です。ある程度習得するには、かなりの時間がかかります。
一方で表計算は、一般にも馴染み深いExcelとよく似ていることで知られています。そのため、始めるハードルは比較的低い科目と言えるでしょう。
表計算では、足し算や引き算に用いる演算子が使われます。出題内容としては、関数を用いた計算や、表計算シートを自動化するプログラム作成などです。
表計算はミスしやすい科目
表計算は比較的易しいと言われる科目である一方、ミスを多発しやすい科目でもあります。そのため、表計算を選ぶ場合は注意が必要です。
例えば、関数や演算子を組み合わせる際には、式の長さを意識しなければなりません。また、表のマス目1つ1つを表すセルの記述の際には、順番などに気を配る必要があります。
このように、表計算で注意しなければいけない箇所は多いです。ミスしやすい部分を把握し、その点に意識を配りながら解き進めていくことが重要になります。
時間を食いやすい科目
表計算は、ミスが起こりやすい科目のため、注意すべき箇所が多数あります。また、読み取る情報量も多いため、解答に時間を要する科目です。
そのため表計算の勉強では、問題演習の量をこなすことが重要になります。演習をたくさんこなし、式やプログラミングの読解に慣れましょう。解答速度を上げることで、時間がかかりやすい問題にも順応できます。
問題演習の際は、早い段階から試験時間を意識して行うようにしましょう。実際の試験時間よりも、設定時間を短くして練習することも有効です。
表計算の対策で押さえるべき箇所
 表計算の対策には、出題内容の特徴を押さえた上で、それを意識しながら問題演習に取り組む必要があります。その方法によって、実力は向上していくでしょう。
表計算の対策には、出題内容の特徴を押さえた上で、それを意識しながら問題演習に取り組む必要があります。その方法によって、実力は向上していくでしょう。
そのため、まずはこれから解説する内容を頭に入れることが大切です。
Excelと試験に出てくる表計算ソフトの違いを理解
基本情報技術者試験の表計算ソフトはExcelと類似しています。しかし、あくまで試験用に作られた架空のソフトであるため、Excelの知識をそのまま活かすことはできません。
以下では、その違いをいくつか具体的に紹介します。
関数が日本語表記になっている
Excelの場合、足し算の関数は「SUM」という記号で表されます。一方で、基本情報技術者試験の表計算では、足し算を表す記号は「合計」です。
Excelを使い慣れた人にとっては、混同しやすい部分の一つなので、注意が必要です。
「=」を計算式につけない
Excelでは、計算式に「=」を付けないと計算結果が出力されません。
しかし、基本情報技術者試験の表計算ソフトでは、「=」を入力する必要はないため、注意しましょう。
必要ない「=」を入力して消すだけでも、時間を無駄にしてしまいます。
相対参照と絶対参照の違いは必ず理解
表計算ソフトでは、セルの場所を「セルの番地」と呼びます。ただし、「セルの番地」には2通りの意味があるので注意しましょう。
具体的には、「相対参照」と「絶対参照」があります。これらはセルを参照する際に用いられる言葉です。
「相対参照」では、参照する数式をコピーすると、コピー先のセル番地に合わせて代入されるセル番号は変化します。これは通常のコピーで使用される参照方法です。
一方で「絶対参照」においては、参照されるセルは固定されます。そのため、コピー先のセルによって参照した結果が変化することはありません。
つまり、コピー元と違うセルを参照する時には「相対参照」を、コピー元と同じセルを参照する時には「絶対参照」を使用するということです。
基本的な演算子を理解
演算子は、学校で習う四則演算に加え、不等号や式の区別に使用するカッコなどが用いられます。演算子の種類は以下の通りです。
| 演算子の種類 | 演算子 |
|---|---|
| 足し算・引き算 | +、- |
| 掛け算 | * |
| 割り算 | / |
| 不等号 | >、< |
| カッコ | ( ) |
表計算ソフトの使い方ですが、例えば、5足す3は「5+3」、5かける3は「5*3」と入力します。先述したように「=」は必要ありません。
これら演算子の使い方は、演習を通して暗記しましょう。使いこなせるようになることで、本番の時間短縮にも繋がります。
関数は理解することで使いこなせる
表計算ソフトやExcelにおける関数とは、複雑な計算処理を一定の条件を与えることによって、簡単に処理できるようにしたものです。
基本情報技術者試験における関数は、出題されるものがある程度決まっています。そのため、頻出の関数に関してはきちんと理解しておくことが重要です。
例えば、複数セルの合計値を求める場合には、合計を用います。A1〜A10までの合計なら「合計(A1: A10)」と入力することで計算が可能です。
また条件が正しいか間違っているかで、セルの返す値を変えることもできます。その場合は「IF関数」を使います。
具体的には、{primary}(「IF(A1>A2,’東京’,A3)」)と入力したとしましょう。この場合、A1の値がA2よりも大きければ「東京」という文字が返されます。それ以外の場合は「A3」です。
複数セルの平均値を求めたい場合は「平均」を使います。使い方は「平均(セル範囲)」です。A1〜A10までの平均を求めたい場合は、「平均(A1: A10)」と入力します。
さらに「条件付合計」という関数も存在します。使い方は「条件付合計(検索範囲, 検索条件, 合計範囲)です。
例えば、「条件付合計(A1~:A10, =25, C1~:C10)」であれば、A1〜A10のうち、25のセルが検出されます。ここでは、A2とA6、A7が選ばれたとしましょう。
この場合、C1〜C10のうち、A2とA6、A7に対応するセルの合計が返されます。
問題を解く際はメモを取る
表計算の問題は情報量が多いため、出題内容や解法がすぐには分からないこともあります。
その場合は、問題の要点をメモするようにしましょう。頭の中が整理され、スムーズに解答が導き出せます。
具体的には、問題文の重要箇所に線を引いたり、関係を図でまとめるのが有効でしょう。
メモを取ることで解答の能率が上がり、時間短縮にも繋がります。思考コストを節約し、集中力の持続にも効果があるでしょう。そのため、ミスの削減にも有効です。
マクロの範囲は要対策
表計算は、プログラミング言語の中では、対策しやすい科目だと言われています。しかし表計算においても、「マクロ」の範囲は、難易度の高い箇所です。
マクロはプログラミング言語の一つで、表計算においては、試験の後半部で出題されます。
難易度は高いマクロですが、ワークシートへのデータ入力・出力の確認が自動化できるため、作成すると便利です。
仮にマクロを捨ててしまうと、プログラミングでは、半分近くの点数を失うことになるでしょう。
そのため、対策は必須の範囲になります。
マクロを理解すれば、アルゴリズムも同時に理解できるため、試験対策においては重要視すべきでしょう。
実際の試験でどのようにして解くか
 ここからは、本番での具体的な解答方法のコツについて説明します。
ここからは、本番での具体的な解答方法のコツについて説明します。
セル番地への計算式は必ずメモ
表計算問題の前半部分は、ワークシートを作り上げる問題です。空欄のセル番地に計算式を入力していく作業になります。
設問になっているセル番地と入力する計算式の役割は、必ずメモするようにしましょう。要点を押さえることで、問題の全体像が把握できます。
特に混乱しやすいのは、セル番地が計算式で表されている場合です。この場合、何を計算しているのか分からなくなってしまうこともあります。
そのため、各セル番地の役割をメモすることは重要です。メモを見ながら、計算式の役割を正しく認識するように心がけましょう。
選択肢はグループ分けするとわかりやすい
選択肢は文言や数字など、性質ごとに分類することがおすすめです。例えば、5つの選択肢があれば、3つと2つなどに分けましょう。
グループ分けを行うことで、絶対に該当しない選択肢を効率よく排除することができます。無駄な検討時間が削減できるため、解答時間の短縮が可能です。
特に表計算の問題では、選択肢を多数持つ出題も多いため、グループ分けが大いに有効になります。問題演習のうちから、グループ分けして解く練習をしておきましょう。
マクロを作る際は目的を把握しておく
マクロは、ワークシートを自動化するためのプログラムです。このプログラムは、ある一定の目的を元に設計されます。そのため、まずはこの目的を正しく把握しましょう。
この目的をきちんと押さえないまま設計に取り掛かると、出題意図にそぐわないプログラムになってしまいます。
目的を最初に確認したら、問題の横にメモをしておきましょう。そして、常にそれを意識しながら進めることがおすすめです。
マクロのプログラムは、目的に対応した設計を行うことが大切になります。
表計算を勉強する際におすすめ参考書
 表計算の勉強には、テキスト選びも重要です。良いテキストを使う方が、知識が定着しやすくなります。習得した知識をどれだけ試験で活かせるかも、使うテキストによって異なるでしょう。
表計算の勉強には、テキスト選びも重要です。良いテキストを使う方が、知識が定着しやすくなります。習得した知識をどれだけ試験で活かせるかも、使うテキストによって異なるでしょう。
今回おすすめしたいテキストは、「基本情報技術者 表計算 とっておきの解法」です。
ワークシートの図が豊富に掲載されているため、初心者にも理解しやすい内容となっています。ページ内の説明に「ポイント」や「注意」のアイコンを用いるなど、丁寧な作りに定評のあるテキストです。
また、表計算に必要な関数やマクロの知識を、基本から応用まで詳しく解説しています。過去問を元にした問題や、オリジナル問題も収録されており、表計算対策はこれ一冊あれば十分と言えるほど、充実した内容です。
基本情報技術者試験の勉強法
 表計算は、あくまで基本情報技術者試験の一部です。資格取得には、他の分野でも十分に得点する必要があります。
表計算は、あくまで基本情報技術者試験の一部です。資格取得には、他の分野でも十分に得点する必要があります。
基本情報技術者試験の出題形式・出題範囲
基本情報技術者試験は、午前試験と午後試験に分けて実施されます。ちなみに表計算は午後試験の一部です。
午前試験は、多肢選択式(四肢択一)で80問が出題されます。試験時間は、9時30分〜12時の150分間です。
午後試験に関しては先述した通りになります。試験時間は、13時〜15時30分までの150分間です。
以下、出題範囲の詳細をまとめました。
【午前試験】
- テクノロジ系
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| 基礎理論 | 基礎理論 |
| アルゴリズムとプログラミング | |
| コンピュータシステム | コンピュータ構成要素 |
| システム構成要素 | |
| ソフトウェア | |
| ハードウェア | |
| 技術要素 | ヒューマンインタフェース |
| マルチメディア | |
| データベース | |
| ネットワーク | |
| セキュリティ | |
| 開発技術 | システム開発技術 |
| ソフトウェア開発管理技術 |
- マネジメント系
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント |
| サービスマネジメント | サービスマネジメント |
| システム監査 |
- ストラテジ系
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| システム戦略 | システム戦略 |
| システム企画 | |
| 経営戦略 | 経営戦略マネジメント |
| 技術戦略マネジメント | |
| ビジネスインダストリ | |
| 企業と法務 | 企業活動 |
| 法務 |
【午後試験】
| 出題範囲 | 内容 |
|---|---|
| コンピュータシステムに関すること | ハードウェア、ソフトウェア、データベース、ネットワーク |
| 情報セキュリティに関すること | 情報セキュリティポリシ、情報セキュリティマネジメントなど |
| データ構造及びアルゴリズムに関すること | 配列、リスト構造、木構造など |
| ソフトウェア設計に関すること | ソフトウェア要件定義、ソフトウェア方式設計など |
| ソフトウェア開発に関すること | プログラミング(C、COBOL、Java、アセンブラ言語、表計算ソフト)など |
| マネジメントに関すること | プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント |
| ストラテジに関すること | システム戦略、経営戦略・企業と法務 |
基本情報技術者試験の勉強は独学が基本
基本情報技術者試験の難易度はやや高めですが、独学でも十分合格できる試験です。
独学の際は、インプットとアウトプットのバランスを意識しましょう。比率の目安は7:3です。
ちなみにインプットとは、テキストを読み込んで知識を蓄えること、アウトプットとは、問題集や過去問で演習を行うことを指します。
まずは試験範囲を大まかにインプットしましょう。IT関連の基本的な用語に関しては、きちんと理解することが重要です。
試験内容を大まかに把握したら、アウトプットに移行します。分からない問題はテキストで復習し、着実に弱点を克服していきましょう。
インプットからアウトプット、そして再びインプット(復習)のサイクルが、独学で合格するための必勝法です。
過去問を有効活用する
基本情報技術者試験においても、他の資格試験同様、過去問演習が有効です。
過去問を解くことで、頻出範囲や出題傾向を把握できます。また弱点を発見し、克服するきっかけにもなるでしょう。
過去問演習をする際は、過去問題集を購入することがおすすめです。問題と解答だけでなく、解説がついている方が、独学での勉強は捗ります。
基本情報技術者講座を利用するのも良い
独学での合格に自信のない人や、多忙で勉強時間が満足に取れない人は、予備校や通信講座を活用するのも良いでしょう。
特にスタディングの基本情報技術者講座は、表計算にも対応しており、スマホ学習でスキマ時間を有効活用できるおすすめ講座となっています。
講義・教材もスマホ学習でも実力がアップするハイクオリティなものへと仕上がっていることから、スキマ時間でも高い学習効果を発揮すること間違いなしです。
基本情報技術者試験の表計算まとめ
基本情報技術者試験の表計算まとめ
- プログラミング初心者でも勉強しやすい科目
- 難易度の高いマクロはしっかり押さえる
- メモをしっかり取って、ミスを防ぐことが大切
基本情報技術者試験の表計算について、対策のコツや問題の解き方を解説しました。
表計算は、プログラミング初心者でも対策しやすい科目です。演算子や関数、マクロなどをしっかり対策し、本番ではメモを取ることを大切にしましょう。