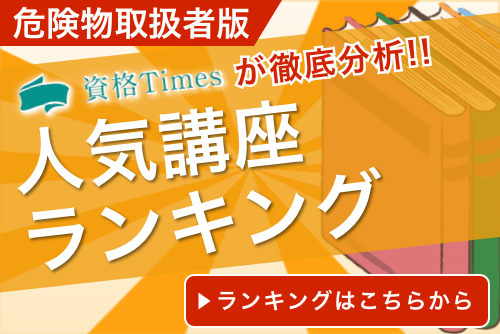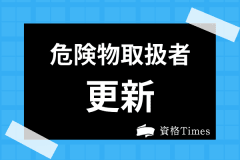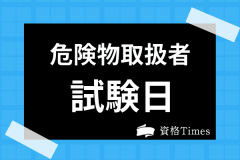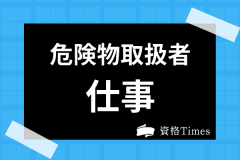危険物取扱者の試験問題はどんなもの?乙4や甲種・丙種の過去問についてまで解説!
「危険物取扱者の甲種・乙種・丙種の試験問題は?」
「過去問は入手できるの?」
そんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
危険物取扱者の甲種・乙種・丙種の各種の問題がどのようになっているのか気になるという人は多いです。
この記事では、危険物取扱者の甲種・乙種・丙種の試験問題や過去問について紹介していきます。
試験の問題や過去問について把握することで、効率的に試験勉強ができるでしょう。
危険物取扱者試験をざっくり説明すると
- 各種の試験問題のマークシート形式
- 甲種・乙種は5択、丙種は4択
- 試験科目は3種類
危険物取扱者の試験問題について

危険物取扱者試験は3つに分かれており、甲種・乙種・丙種から選ぶようになります。試験の各種によって、問題数や試験時間が異なっているのです。当然、各種で難易度も大きく変わってきます。
ここでは危険物取扱者試験の問題について、甲種・乙種・丙種ごとに分けて解説していきます。また、試験の科目・時間など詳しい情報も伝えていきましょう。危険物取扱者試験の科目は、どのようなことが出題されるのか気になるはずです。
試験を受けようとする方は自分が受ける試験の種をしっかりと理解して、把握すると良いです。試験勉強をする前にしっかりと試験の情報を知っておくべきです。
乙種
危険物取扱者試験の中でも乙種を受験する方は特に多いです。乙種は6つに分かれており、その中でも乙4種が一番人気です。しかし、乙種で最も難しい試験になっているので、しっかりと勉強をする必要があります。
乙種の出題方法は、マークシート形式で5つの選択肢から1つの答えを選ぶようになっています。
試験科目は、「危険物に関する法令」・「基礎的な物理学及び基礎的な化学」・「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」の3種類です。ちなみに試験時間は120分となっています。
各科目の問題数は「危険物に関する法令」15問、「基礎的な物理学及び基礎的な化学」10問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」10問の計35問です。
試験時間が120分のため、1問3分ぐらいで解くと時間が少し余るようになります。残った時間は最終確認などミスがないか、確認するようにしましょう。
甲種
甲種は危険物取扱者試験の中で、最も難しいです。試験の出題方法は、乙種と同じでマークシート形式で5つの選択肢から1つの答えを選びます。
試験科目は、「危険物に関する法令」・「物理学及び化学」・「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」の3種類です。試験時間は150分と、乙種より30分ほど長くなっています。
各科目の問題数は「危険物に関する法令」15問、「物理学及び化学」10問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」20問の計45問です。
試験時間・問題数は危険物取扱者試験の中でも最も長く、多くなっています。1問3分ぐらいで解くと、最後に確認する時間ができるでしょう。
丙種
丙種は危険物取扱者試験の中で最も合格しやすいです。試験の出題方法は甲種・乙種と違い、4つの選択肢から1つを選ぶマークシート形式になっています。試験時間は75分と、3種の中で一番短いのです。
試験科目は、「危険物に関する法令」・「燃焼及び消火に関する基礎知識」・「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」の3種類になっています。
各科目の問題数は、「危険物に関する法令」10問、「燃焼及び消火に関する基礎知識」5問、「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」10問の計25問です。
危険物取扱者試験の丙種は合格しやすくなっていますので、最初に受けても良いでしょう。問題を解くスピードは1問3分で、ちょうど試験時間の75分かかります。受験者は解くスピードを速くして、最後に確認する時間を確保しましょう。
頻出問題を押さえよう
以下に、乙4種で頻出する項目を挙げています。
| 法令 | 基礎物理学・基礎化学 | 性質・火災予防・消火 |
|---|---|---|
| 指定数量の計算 | 物質三態 | 物質三態 |
| 保安講習 | 静電気 | 静電気 |
| 予防規程 | 物理変化および化学変化 | 物理変化および化学変化 |
| 定期点検 | 有機化合物 | 有機化合物 |
| 保安距離 | 燃焼原理(燃焼三要素) | 燃焼原理(燃焼三要素) |
| 給油取扱所基準 | 消火三要素 | 消火三要素 |
| 消火設備 | 消火設備 | 消火設備 |
| 運搬基準 | ||
| 移送基準 | ||
| 義務違反への措置 |
項目は細かく分かれており、幅広く勉強する必要があります。
試験対策のためのツール

上記では、乙4種で頻出する問題を項目に分けて紹介しました。項目が細かく分かれているので、理解するには時間がかかります。試験勉強をし始める時は、時間に余裕を持つ必要があるでしょう。
続いて、試験対策に有効なツールについて伝えていきます。効率的に勉強を進めていく上で、役に立つ情報があるはずです。試験勉強をする際に試してみても良いでしょう。
危険物取扱者の受験者によって苦手なジャンルが異なってきますが、自分に合ったツールを使ってみても良いです。試験勉強でメインに使用するのではなく、サブの要素として使うことを考えてみましょう。
過去問サイトで学習
過去問を取り扱っているサイトで学習する方法だと、全て無料で使うことができます。1問でも多くの問題を解きたいと考えている方には良いでしょう。
しかし、過去問を取り扱っているサイトは記載されている情報が必ずしも正しいとは限りません。サイトの中には間違っている内容も含まれている可能性もあるため、注意が必要です。
勉強方法としては、テキストや講座をメインにすることをおすすめします。
消防試験研究センター
一般財団法人消防試験研究センターは、試験を実施している公式機関です。ここでは、「甲種」・「乙種第4種試験」・「乙種第1.2.3.5.6試験」・「丙種試験」の4つに分けて、過去の問題の一部がPDF形式で見ることが可能です。
受験者は、過去の問題を解くことができるだけでなく、解答を確認することもできます。しかし、解説が載っていないので、やはり自分で解答に至る理由を考えたり調べたりする必要があります。
ぜんせきweb 乙4模擬試験お試し版
「 ぜんせきweb 乙4模擬試験お試し版」は、乙4種の試験を本番と同じ形式で受験が可能です。模擬試験は、過去3年分の問題からランダムで出題されます。
試験の結果については採点されて、解説も付いてきます。もし、問題に間違った場合は解説があるので、理解を深めやすいです。本番の試験を意識して、一度受験しても良いでしょう。
消防設備士・危険物取扱者の過去問、想定問題サイト
消防設備士・危険物取扱者の過去問・想定問題サイトを使用すると、区分ごとに問題を解くことができます。
また、1問答えるごとに解答・解説が表示されるようになっているため、焦らずに1つずつ理解ができるでしょう。1問ずつ問題を解きながら、その都度理解を深めたい方にはおすすめです。
問題を解く際には経過時間が表示されますので、本番を意識して解くことができるでしょう。
通信講座で過去問以外にも触れよう
危険物取扱者試験には一定の出題傾向があるため、過去問に当たるということはある程度までは有効な試験対策方法です。しかし、試験に過去問と全く問題が出題されることはないため、過去問を解くだけでは試験対策の質に限界があります。
通信講座なら、過去の出題傾向を踏まえて講座を設計しているため、闇雲に過去問に当たるよりも要点を押さえて過去問の傾向を把握しやすくなります。また、通信講座で提供される予想問題は試験本番でも通用する質の高いものが多く、一度は解いてみるべきというものが多いです。
特にユーキャンの危険物取扱者講座は過去の出題傾向を踏まえた質の高い講義やテキストに加え、全5回の予想模擬問題がついています。こうした充実の講座を利用すると、独学で闇雲に市販のテキストや過去問に当たるよりも効率的な試験対策が可能になるため、ユーキャンの危険物取扱者講座は受講することが非常におすすめできます。
おすすめ参考書
危険物取扱者試験の勉強をする際におすすめ参考書を2つ紹介していきます。 1つ目は「わかりやすい!甲種危険物取扱者試験 (国家・資格シリーズ 103) 」で、 価格が3080円です。
本の作者の名前から「工藤本」とも呼ばれており、見やすく語呂合わせで暗記の手助けてくれる参考書です。
2つ目は「甲種危険物取扱者試験 令和5年版 」で、価格が2,970円になっています。この参考書は過去問をベースに作成されているので、試験にそのまま出ると評判です。時間が限られている方や効率的に勉強したい方には、おすすめでしょう。
過去問の例題

ここでは、危険物取扱者試験の例題と答えについて挙げていきましょう。
- 1つ目の問題
法令上、予防規定に関する説明として、最も適切なものは、次のうちどれか。
-
製造所等における危険物保安監督者および危険物取扱者の責務を定めた規定をいう。
-
製造所等の点検について定めた規定をいう。
-
製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めた規定をいう。
-
製造所等における危険物保安統括管理者のせキムを定めた規定をいう。
-
危険性をまとめた規定をいう。
解答は「3」になります。製造所について問われる問題ですが、迷ってしまいそうな内容になっているでしょう。試験の際は、勉強した内容を整理しながら解くようにしましょう。
- 2つ目の問題
アセトンの性状について、次のうち誤っているものはどれか。
-
無色無臭の液体である。
-
水と任意の割合で混ざり合う。
-
引火点は常温(20℃)より低い。
-
水よりも軽い。
-
アルコール、エーテルに解ける。
解答は「1」になります。5つの選択肢の中で4つが合っているので、混乱しそうです。選択肢の中で誤っているものを見つけ出すためには、単語や言葉を正確に覚えておきましょう。
例として挙げた2問は過去に出題された問題で、本番の試験のイメージが多少できたでしょう。
危険物取扱者本試験について

上記では、危険物取扱者試験の過去も一部を紹介しました。乙4種を受験する方は上記のような問題を解くようになるので、覚えておきましょう。出題される問題は、正しいものを選ぶだけではないです。
本番で出題される問題のイメージがついたところで本試験について、詳しく触れていきます。危険物取扱者の本試験のレベルは過去問を解くいた時の感覚以上に高いと言われています。
そのため、受験者は本試験の試験時間中にいきなり問題の難しさに圧倒されて、気持ち的に落ち込みかねません。だからこそ、危険物取扱者の本試験の現状を把握する一方で、通信講座等も上手に利用して、過去問に頼り切りでない試験対策をしっかりと行う必要があります。
本試験の方が難しい
危険物取扱者試験の本番では、今まで見たことない問題が出題されるでしょう。これは過去問を多く解いたとしても、あり得ることです。
試験勉強で見たことない問題が出題された時には、慌てずに気持ちを一度落ち着けましょう。そして、問題がちゃんと解けるのか冷静に判断します。もし、解けそうでなければ確実に解ける問題から取り組んで合格に近づけましょう。
難問に注意を
本試験では過去問題を多く解いた受験者でも、解くことができない難問が出題されることがあります。この問題が出題された時の対策として、1つの方法があります。それは問題を飛ばすことで、試験の最後に残しておくことです。
難しい問題の例として、「消火設備」・「屋内タンク貯蔵所」・「アセトアルデヒド」・「アセトン」などが挙げられます。解けない問題をどうにか解こうとしても、限られた試験時間を無駄にしかねません。
基本問題を確実に得点しよう
受験者が試験に注意する点は、基本的な問題を落とさないようにすることです。解ける問題を落としてしまうと、合格からかなり遠ざかってしまいます。
試験対策としては、基本的な問題を確実に解けるような能力を身につけるようにしましょう。難しい問題が解ける対策をするよりも、合格する可能性は高くなるはずです。
本試験の第5問・第6問以外は、基本的な問題が出題されることが多くなっています。基本的な問題を解けるようにして、得点を合格基準に到達できるようにしましょう。
危険物取扱者試験の勉強で大事なこと

ここまで、危険物取扱者試験について項目ごとに解説してきました。甲種・乙種・丙種の各種に分かれていますが、受験する種によって試験勉強する時間や労力は大きく変わりそうです。
特に甲種の受験を考えている方は、本試験日を確認してから計画を立てていきましょう。社会人や忙しい方は1日できる勉強時間が限られているため、長期間で計画を立てた方が良いです。
危険物取扱者試験の勉強を進めていく上で大事になるのは、高いモチベーションを保ち続けることです。試験勉強をしていくと、難しい単語や表現が出てくるでしょう。
ほとんど知識がない方は、整理できずに途中で諦めてしまう可能性もあります。時間に余裕を持って、高いモチベーションで試験勉強を進めていきましょう。日々の努力を積み重ねることで、合格に近づくはずです。
本試験では解ける問題から1つずつ取り組んで、1度で合格できるようにしましょう。
危険物取扱者試験の問題まとめ
危険物取扱者試験の問題まとめ
- 基本問題は確実に解く
- 本試験は難しい
- 難問が出題される可能性大
危険物取扱者の甲種・乙種・丙種の問題について解説してきました。
本試験では難しい問題も出題されますが、基本的な問題を落とさないことが大事です。
試験勉強をしっかりと行って、合格できるようにしていきましょう。