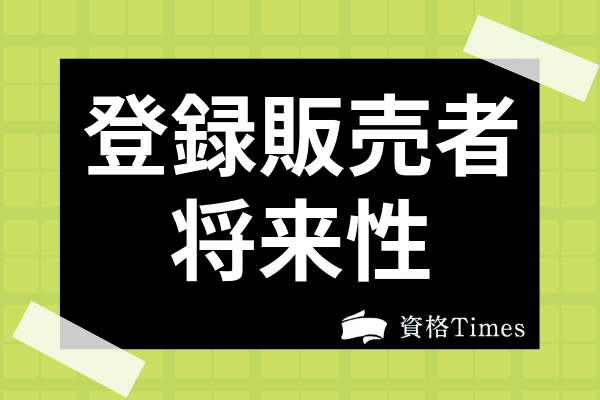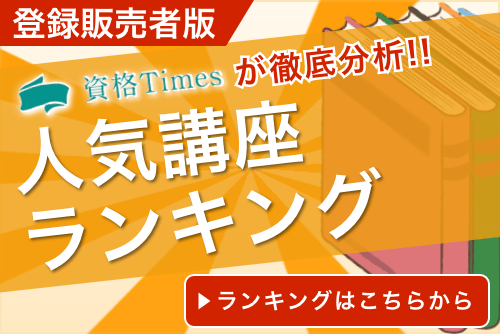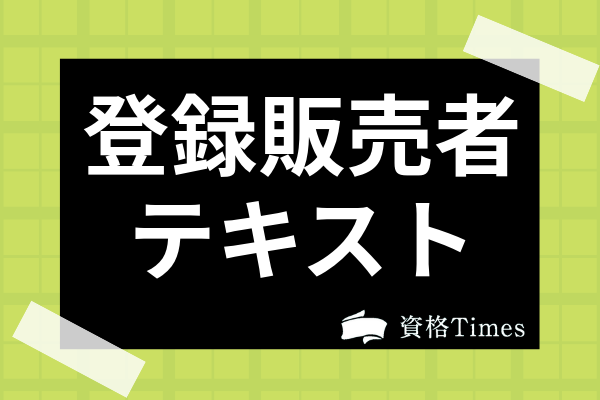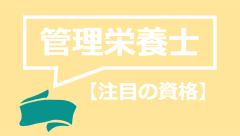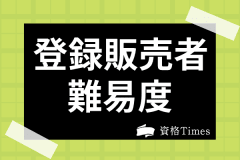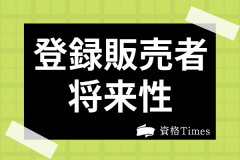登録販売者試験の難易度はどれくらい?合格率や勉強時間を徹底考察
一般用医薬品の販売や医薬品に関するカウンセリング・コンサルティングを行う店舗や施設は、急激な増加を続けています。
そうした環境のなかで、薬剤師に代わって注目を浴びているのが「登録販売者」です。
この記事では、登録販売者試験の難易度を中心に合格率や合格基準、勉強時間や試験対策などについて徹底的に考察していきます。
登録販売者試験の難易度をざっくり説明すると
- 受験制限がなく、だれでも受験が可能
- 150~200時間程度の勉強時間が必要
- 合格率は毎年40%台前半で偏差値は45
- 2つの合格基準があり、両方の基準を同時に満たせば合格
このページにはプロモーションが含まれています
登録販売者試験の難易度はどれくらい?

登録販売者試験とは、かぜ薬や鎮痛剤などの一般用医薬品を販売できる人を認定する資格試験で、各都道府県が実施する登録販売者試験に合格すれば取得できます。
試験の合格率は40%前半ですから、しっかりした準備をすれば独学合格も可能な資格試験と言えるでしょう。
ここでは、登録販売者資格に興味のある人のために、受験登録販売者試験の難易度や試験対策にかかわるさまざまな情報を提供します。
登録販売者の試験範囲
登録販売者は国家資格ですが、登録販売者試験は国家試験ではなく各都道府県が実施する試験です。
そのことで問題は都道府県で異なりますが、難易度に格差が生じないよう「厚生労働省のガイドライン」にもとづいて作成されます。
次に、試験範囲・問題数・試験時間を、一覧表で紹介しておきます。
| 試験範囲(出題項目) | 出題数(問) | 時間(分) |
|---|---|---|
| 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 20 | 40 |
| 人体の働きと医薬品 | 20 | 40 |
| 主な医薬品とその作用 | 40 | 80 |
| 薬事関係法規・制度 | 20 | 40 |
| 医薬品の適正使用・安全対策 | 20 | 40 |
| 合計 | 120 | 240 |
医薬品に共通する特性と基本的な知識
ここでは「医薬品の効き目・医薬品の安全性に影響を与える要因・薬害の歴史」など、医薬品を適切に販売するための基本的な知識が問われます。
非常に簡単な分野なので、最初に取り掛かる方が多いと言われています。
問題数は20問で試験時間は40分です。
人体の働きと医薬品
ここでは「人体の構造」「薬が働く仕組み」「医薬品を使用したことで起こる主な副作用」など、購入者への情報提供・相談対応に必要な知識が問われます。
臓器の働きなどを扱うため、中学の理科や高校の生物などで習った知識が生きてくるような分野になっています。
問題数は20問で、試験時間は40分です。
主な医薬品とその作用
ここでは「主な医薬品とその作用」に関し、市販の医薬品に関する情報提供や相談対応のための実践的な知識や理解度が問われます。
登録販売者試験で最も難しい分野と言われており、成分名や薬の名前をひたすら暗記することになります。
問題数は40問で試験時間は80分です。
薬事関係法規・制度
ここでは医薬品の取扱者に最も重要な薬機法と呼ばれる「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の理解度が問われます。
聞かれていることは簡単ですが、試験では問題がひっかけ問題になっていることが多いため、十分な対策が必要になります。
問題数は20問で試験時間は40分です。
医薬品の適正使用・安全対策
ここでは「製品表示への理解」「副作用報告制度・副作用被害救済制度」について問われますが、ある程度は一般教養でも答えられます。
問題としては非常に簡単で、他の分野との関連も多いため、最後の手を付けるのが良いとされています。
問題数は20問で試験時間は40分です。
登録販売者士試験の難易度は変わっていない
資格試験の難易度を示す指標の1つは、当該試験の「合格率」です。
登録販売者士の場合、試験の開始年度は約65%でしたが、その後は40%台前半で推移しています。
もっとも、受験者数や問題の難易度などが異なる各都道府県での試験結果の平均値ですから、国家試験ほどの納得性はないと言えるでしょう。
その証拠として各都道府県の合格率には、大きな差が発生しています。
全体の合格率は40%台前半での推移で、難易度に変化はありません。
しかし、都道府県間には大きな格差があることは押さえておくことが必要です。
登録販売者の難易度を偏差値で表すと?
登録販売者試験は、「第2類・第3類の一般用医薬品の販売を行える資格者認定の試験」です。
国家資格に偏差値をつけてランキング設定しているサイトによれば、この登録販売者試験の偏差値は45と判定されています。
偏差値45にランクされる他の資格は「日商簿記検定3級」や「販売士2級」などです。
偏差値45の試験の難易度は「普通よりもやや易しいレベル」と言えます。
登録販売者試験の合格率
ここでは、合格率とともに都道府県別合格率・合格基準・勉強時間などの視点から、登録販売者試験を考察します。
登録販売者の合格率は約40%
登録販売者の過去6年間の合格率は、下表のとおり40%前半での推移です。
| 実施(年) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 55,606 | 24,707 | 44.4 |
| 2021 | 61,070 | 30,082 | 49.3 |
| 2020 | 52,959 | 21,953 | 41.5 |
| 2019 | 65,288 | 28,328 | 43.4 |
| 2018 | 65,436 | 26,996 | 41.3 |
| 2017 | 61,126 | 26,606 | 43.5 |
直近の数字を見ると、2021年度だけ数字が大きく伸びているものの、全体的には4割前半の数字で合格率が推移しています。
ただ、以下で詳述する通り、合格率は受験する都道府県によって大きく変化するため、こちらの数値はあくまでも全国平均の参考値という認識を保つことが大切です。
登録販売者の都道府県別の合格率
登録販売者試験は各都道府県が独自に実施(関西地域連合は6府県)されることから、合格率も全体と都道府県別のデータが公表されます。
この合格率を見て驚くのは、都道府県間の大きな格差です。
年度によって異なるものの、毎年下記のように都道府県によって大きな格差が生まれていることがわかります。
| 実施時期 | ベスト3 | ワースト3 |
|---|---|---|
| 2021 | 1位 山口県:68.8% 2位 広島県:66.7% 3位 岡山県:64.9% |
47位 秋田県:32.5% 47位 宮城県:32.5% 45位 佐賀県:34.2% |
| 2020 | 1位 広島県:58.1% 2位 愛知県:56.0% 3位 山口県:54.0% |
47位 埼玉県:30.1% 46位 長野県:31.8% 45位 山梨県:32.1% |
| 2019 | 1位 北海道:64.3% 2位 宮城県:61.9% 3位 青森県:61.0% |
47位 埼玉県:23.3% 46位 千葉県:24.8% 45位 高知県:25.0% |
| 2018 | 1位 北海道:58.6% 2位 熊本県:57.0% 3位 宮城県:56.6% |
47位 福井県:19.5% 46位 岡山県:28.4% 45位 鳥取県:28.5% |
| 2017 | 1位 北海道:62.4% 2位 宮城県:62.1% 3位 秋田県:60.5% |
47位 沖縄県:26.7% 46位 鳥取県:27.1% 45位 山口県:27.1% |
だからといって、登録販売者士試験の場合は受験者数や問題にも違いがあることから、合格率がそのまま難易度を表わしているわけではありません。
下に、2021年の「登録販売者試験の都道府県別合格率一覧」を示しておきます。
| 都道府県名 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,236 | 948 | 42.4 |
| 青森 | 808 | 318 | 39.4 |
| 岩手 | 954 | 394 | 41.3 |
| 宮城 | 1,749 | 759 | 43.4 |
| 秋田 | 560 | 183 | 32.7 |
| 山形 | 533 | 205 | 38.5 |
| 福島 | 932 | 330 | 35.4 |
| 奈良 | 657 | 321 | 48.9 |
| 福井 | 578 | 282 | 48.8 |
| 関西地域連合 | 9,402 | 5,295 | 56.3 |
| 埼玉 | 2,886 | 1,178 | 40.8 |
| 千葉 | 3,025 | 1,251 | 41.4 |
| 東京 | 4,888 | 2,112 | 43.2 |
| 神奈川 | 3,311 | 1,615 | 48.8 |
| 茨城 | 1,344 | 642 | 47.8 |
| 栃木 | 981 | 420 | 42.8 |
| 群馬 | 1,405 | 715 | 50.9 |
| 新潟 | 956 | 442 | 46.2 |
| 山梨 | 346 | 154 | 44.5 |
| 長野 | 1,372 | 632 | 46.1 |
| 富山 | 718 | 383 | 53.3 |
| 石川 | 926 | 481 | 51.9 |
| 岐阜 | 1,287 | 682 | 53.0 |
| 静岡 | 1,607 | 916 | 57.0 |
| 愛知 | 3,519 | 2,078 | 59.1 |
| 三重 | 759 | 396 | 52.2 |
| 香川 | 624 | 397 | 63.6 |
| 愛媛 | 840 | 543 | 64.6 |
| 高知 | 441 | 231 | 52.4 |
| 鳥取 | 285 | 172 | 60.4 |
| 島根 | 338 | 194 | 57.4 |
| 岡山 | 1,064 | 691 | 64.9 |
| 広島 | 1,333 | 889 | 66.7 |
| 山口 | 666 | 458 | 68.8 |
| 福岡 | 2,891 | 1,405 | 48.6 |
| 佐賀 | 378 | 149 | 39.4 |
| 長崎 | 705 | 310 | 44.0 |
| 熊本 | 924 | 406 | 40.9 |
| 大分 | 647 | 281 | 43.4 |
| 宮崎 | 503 | 216 | 42.9 |
| 鹿児島 | 929 | 326 | 35.1 |
| 沖縄 | 763 | 282 | 37.0 |
上表の「関西地域連合」含まれるのは、滋賀・京都・兵庫・和歌山・大阪・徳島の6府県です。
登録販売者試験の合格基準
登録販売者試験には次の2つの合格基準があり、この両基準を同時に満たせば合格です。
- 総出題数に対する正答率が70%以上
- 各試験項目の正答率が35~40%以上
1つ目は、全部で120問のうちの7割以上、つまり84問以上正解する必要があります。
2つ目は、5つある項目のそれぞれで3.5割以上または4割以上正解する必要があります。なお、3.5割以上か4割以上かは、都道府県によって異なるので注意してください。
登録販売者合格までに必要な勉強時間
登録販売者試験に合格するまでに必要な勉強時間は、一部には400時間前後と言われます。
しかし、試験の難易度や登録販売者試験対策講座が36時間で開講していることなどから判断して、150~200時間・勉強期間3~6カ月と考えていいでしょう。
200時間勉強するためには、毎日2時間の勉強で100日(3カ月半)・毎日3時間で70日(2カ月半)を必要です。
登録販売者試験の勉強の中心は「暗記と記憶」ですから、長時間机の前での勉強にこだわらなくても、すき間時間を利用した効率のいい勉強ができます。
また、カタカナを使った用語・医薬品名・成分名などを暗記しなければならないことから、暗記の得意な人にとっては200時間より短時間で受験準備を完了できるでしょう。
登録販売者試験の勉強時間については下記の記事で詳しく解説されています。
登録販売者試験の受験資格
かつて、登録販売者試験には受験資格が設定されており、医薬品販売の実務経験が1年以上の人だけが受験できました。
しかし、2015年4月からの試験で「受験資格なし」へと制度変更され、誰もが受験できるようになりました。
このことで、受験者の受験時の年齢・性別・職業といった個人情報は集約されていないようで、受験者に関する属性データは開示されていません。
なお、合格者が正式な登録販売者として働くには2年以上の実務経験が必要ですから、あくまでも受験の際にだけ実務経験が問われなくなったということです。
したがって推測の域を出ませんが、登録販売者試験の受験者の多くは、ドラッグストアや薬局で働いている人や過去に勤務経験のある人と言えるでしょう。
登録販売者の難易度を比較

登録販売者の難易度を示すデータは、「合格率は40%台前半・偏差値は45・受験条件の制限なし」です。
ここでは、登録販売者試験と「他の医療系資格試験」「主婦に人気の資格試験」の難易度を比較して解説します。
他の医療系資格と難易度を比較
まず、登録販売者試験と3つの医療系資格試験の難易度を比較します。
なお、比較するデータは、「合格率」「偏差値」「受験資格」の3項目です。
薬剤師試験
薬剤師は、病気の治療や日常生活における健康維持に必要な「薬剤」を取り扱う専門職です。
医薬品全般に関する豊富な知識を活かし、医師の処方にもとづく調剤・服薬指導・医薬品の管理を行います。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 薬剤師試験 |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 平均約70%・新卒約85% |
| 45 | 偏差値 | 62 |
| 制限なし | 受験資格 | 6年制の大学の薬学科卒業 |
偏差値を見れば明らかなとおり、薬剤師試験の方が難易度の高い資格試験です。
調剤事務管理士技能認定試験
調剤事務管理士技能認定試験とは保険調剤薬局の受付や会計、レセプト業務などを担当する事務スタッフのスキルを認定する民間資格試験です。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 調剤事務管理士技能認定試験 |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 約60% |
| 45 | 偏差値 | 42 |
| 制限なし | 受験資格 | 制限なし |
調剤事務管理士技能認定試験は、参考資料を持ち込めるうえに年6回も受験できます。 総合的に見て、登録販売者試験の方が難易度の高い試験です。
調剤薬局事務試験
調剤薬局関連の資格試験は、調剤薬局での報酬事務業務に必要な基礎的な知識および技能のレベルを認定する民間の資格試験です。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 調剤薬局事務試験 |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 90%前後 |
| 45 | 偏差値 | 42 |
| 制限なし | 受験資格 | 原則として制限なし |
この試験は教材の持ち込みが可能なこともあって合格率は90%を超えており、難易度は登録販売者試験の方が高いと言えます。
調剤薬局事務資格の難易度が気になる方は、以下の記事もご覧ください。
主婦に人気の資格と登録販売者の難易度比較
医療系資格との比較に続き、ここでは「主婦に人気の資格」と登録販売者の難易度を比較します。
医療事務
医療事務資格は医療機関で受付、会計、カルテ管理などの仕事ができる資格です。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 医療事務 |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 50~80% |
| 45 | 偏差値 | 43 |
| 制限なし | 受験資格 | 受験資格は問わない |
医療事務資格の試験はさまざまありますが、資料の持ち込みが可能であり比較的難易度の低い試験です。 難易度は登録販売者試験の方が高いと言えます。
歯科助手
医療事務資格は医療機関で受付、会計、カルテ管理などの仕事ができる資格です。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 歯科助手 |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 講習会の受講で合格 |
| 45 | 偏差値 | 不明 歯科衛生士は44 |
| 制限なし | 受験資格 | 特になし |
「歯科助手資格」は都道府県の歯科医師会が開催する講習会を受講するだけで取得できます。
したがって、登録販売者の方が難易度の高い試験です。
介護事務
介護事務資格の中でも有名な介護事務報酬請求事務技能の場合は、書類作成や電話対応に加えて「介護報酬請求業務」を処理できます。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 介護事務(報酬請求事務技能) |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 80%程度 |
| 45 | 偏差値 | 不明 |
| 制限なし | 受験資格 | 講座修了または学校からの申込 |
数多くある介護事務資格のいずれもが、登録販売者よりも低難度の試験です。
保育士
保育士とは、子どもを預かるとともに基本的な生活習慣を身につけさせる仕事をする人です。
| 登録販売者試験 | 比較項目 | 保育士 |
|---|---|---|
| 40%台前半 | 合格率 | 10~20% |
| 45 | 偏差値 | 58 |
| 制限なし | 受験資格 | 複雑なので公式サイトで要確認 |
保育士資格試験は偏差値が高く合格率の低い試験で、登録販売者試験よりも難易度の高い試験といえます。
保育士の難易度については下記の記事をご覧ください。
登録販売者の資格をとるメリットとは?
近年、一般用医薬品のインターネット販売の普及やセルフメディケーション意識の高まりの後押しで、登録販売者の需要が高まっています。
この記事では、登録販売者の資格を取得することのメリットについて解説します。
登録販売者になったら何ができる?
登録販売者に認められている主な仕事は、一般用医薬品の約9割にあたる第2類・第3類医薬品の販売と購入者への情報提供や相談対応です。
しかし近年は、職場によって仕事内容や求められる職務は次のように異なります。
- 製薬会社の営業:営業先での医薬品に関する説明
- 医薬品通販オペレーター:電話の相手に対する健康相談、薬に関する質問・相談、提案業務
- 介護サービス事業:サービス提供職員や利用者の薬に関する相談対応やアドバイス
- エステサロン:体質改善や体の悩みに関するアドバイスや質問対応
幅広く活躍できる
医薬品は薬局やドラッグストア以外にも、スーパーやホームセンターなどでも取り扱っています。
こうしたことから、医薬品の取扱いや販売の専門家として認められている「薬剤師」や「登録販売者」の需要は拡大しているのです。
なかでも、絶対数で不足しているうえに人件費の高い薬剤師よりも、登録販売者を求める傾向にあります。
「登録販売者になったら何ができる?」の記事で紹介しているとおり、登録販売者が活躍できる場は、近頃では薬局やドラッグストアだけではないのです。
キャリアアップに繋がり、収入も上がる
勤務先によって異なりますが、登録販売者の資格取得は、収入やキャリアに関連して次のようなメリットにつながります。
- 非正規社員から正社員への身分変更を認める。
- 店舗管理者への任用の必須資格に設定している。
- 昇給する。
- 資格手当を支給する。
- 祝い金を支給する。
需要が高く就職や転職に有利
薬剤師か登録販売者の存在なしには、医薬品の販売はできません。
とはいえ、薬剤師は不足していて採用難のうえ給与が高いことから、何人も雇っていては人件費が膨らみます。
そこで、薬剤師より登録販売者を積極的に採用する企業などが増えているのです。
しかも、登録販売者を求めている企業などは多種多様化し、登録販売者の需要はますます高まっています。
こうした環境にあるからこそ、登録販売者は就職や転職で有利と言えるのです。
今後も需要が見込まれる
登録販売者の活躍の場は、今では家電量販店や免税店などにも拡大しています。
このような登録販売者の、将来性について考察してみましょう。
次のような理由から、「登録販売者に対する需要は、今後も拡大する」というのが結論です。
-
セルフメディケーションの推進拡充で、今後の一般用医薬品の購入は増加が予想されます。したがって、登録販売者の需要はますます高まるでしょう。
-
医療や介護の需要が激増すると見込まれている2025年以降に備え、「地域包括ケアシステム」が推進されています。このシステムでは、地域に密着した形での活躍を期待されているのが登録販売者なのです。
-
介護や在宅医療に出向いた先では、高齢者に薬の使用法の指導やカウンセリングを行う必要があります。こうした介護や在宅医療の現場における高齢者の健康維持のための活動は、登録販売者に期待されています。
登録販売者の将来性については以下の記事を参考にしてください。
登録販売者は独学で合格できるのか
登録販売者試験の偏差値は普通以下であり、実務経験や学歴などの受験資格もありません。
ですから、誤った勉強方法での準備をしない限り、独学合格が可能な試験です。
独学合格を目指す時の注意点
まず、独学合格を目指す際に注意しなければならない点について列挙しておきます。
- 最新のテキストを準備する。
- 自分に合ったテキストを選ぶ。
- 勉強する環境を整える。
- 無理に暗記しない。
- 過去問題にしっかりと取り組む。
試験日程を確認する
登録販売者の試験日は例年8月下旬~12月中旬、申込期限は各試験日の約2カ月前です。
また、登録販売者の資格試験は都道府県が独自に実施しますから、試験日は都道府県によって異なります。
そこで、受験する都道府県の試験日程を確認しておかないと受験できなくなる可能性があるので、注意が必要なのです。
学習スケジュールを立てて継続的に勉強する
継続的に受験勉強をするうえで何よりも大切なことは、適切な学習スケジュールを立てることです。
1日当たりの勉強時間は可能時間の70~80%で、週1日は遅れを取り戻すためのブランクの日を設定します。
こうしたポイントを押さえ、目指す資格試験に合格するまでの道筋が分かる学習スケジュールを作成するのです。
問題集や過去問を利用する
過去問は、受験者が記憶すべきことを教えてくれる素材です。
過去問を解くことで分かった「知らなかったこと・誤解していたこと」を、テキストに戻って記憶します。これを繰り返すのが過去問のベストな利用法です。
なお、問題集は、厚生労働省が「試験問題作成に関する手引き」を改正した場合、その項目に関する問題を解くことと改正点を記憶するために活用します。
試験時間に注意する
登録販売者試験の試験時間は、どの都道府県でも午前2時間、昼休憩をはさんで午後2時間の4時間です。
試験時間は第3項目だけが80分で他は40分であることから、第3項目を実施する際には他の項目の1つと組み合わせ、2つで120分の試験が行われます。
なお、試験時間は合計240分で120問なので、1問2分で解かなければなりません。
マークシート方式を活かす
登録販売者試験は、マークシート方式で行われますので、マークミスに気を付けながら回答します。
マークシート方式は択一式ですから、細かく暗記をしていなくても正しく理解していれば回答は可能です。
迷った時は、明らかに正答ではない選択肢を外し、残りの選択肢の中から選べば正解率を上げられます。
もちろん、問題によって紛らわしい引っかけ問題も出題される場合がありますので、「正しいもの」を選ぶのか「誤っているもの」を選ぶのか、問題文をしっかりと読み込んでください。
登録販売者試験対策におすすめのテキスト
登録販売者の参考書として資格Timesが一番おすすめするのが、「ユーキャンの登録販売者 速習テキスト&重要過去問題集」です。
この参考書は、全ページカラー印刷されており、初心者の方にありがちな質問などもまとまっているため、暗記や勉強に苦手意識を持つ方でも手を付けやすい内容となっています。
資格Timesでは、これ以外にも登録販売者の勉強をするのにおすすめのテキスト・問題集をピックアップしていますので、もし興味があれば次の記事も参考にしてみてください。
登録販売者試験対策には通信講座がおすすめ
登録販売者試験は、もちろん独学可能な試験ではありますが、「確実に1回で受かりたい」「実務に生かせる知識を勉強したい」という場合には、通信講座を受講するのがおすすめです。
ユーキャンの登録販売者講座では、7回にわたる添削指導を受けられたり隙間時間でも勉強できるデジタルテキストで学べたりするなど、手厚いサポートを受けられることができるため、初心者の方にもおすすめの講座となています。
また、受講生にはもれなく就職活動サポートもあるため、実務に役立てたい方や登録販売者資格を生かした就職につなげたい方は積極的に利用すると良いでしょう。
この機会に是非、ユーキャンの登録販売者講座をチェックしてみてください。
登録販売者試験の難易度まとめ
登録販売者試験の難易度まとめ
- 2015年から受験制限がなくなり、だれもが受験できる試験に変更された。
- 一部では400時間とも言われるが、150~200時間程度の勉強時間で対応できる。
- 合格率は40%台前半、偏差値は45で「日商簿記検定3級」などと同レベルの資格試験である。
- 2つの合格基準があり、両方の基準を同時に満たせば合格できる。
登録販売者試験について、難易度をメインにさまざまな側面から解説・紹介をしてきました。
合格率・偏差値・受験条件のいずれからみても、しっかり記憶中心の勉強をすれば独学合格が可能な試験です。
ぜひ、社会的に期待されていて取得メリットも多い登録販売者を目指してみてはいかがでしょうか。