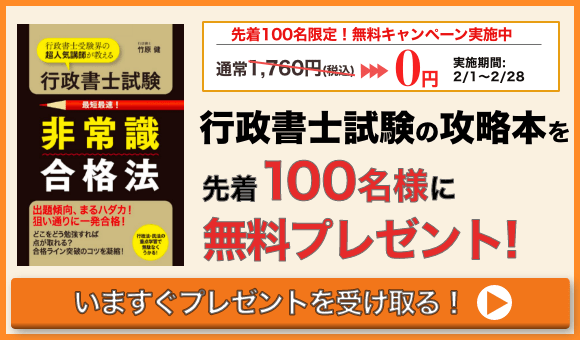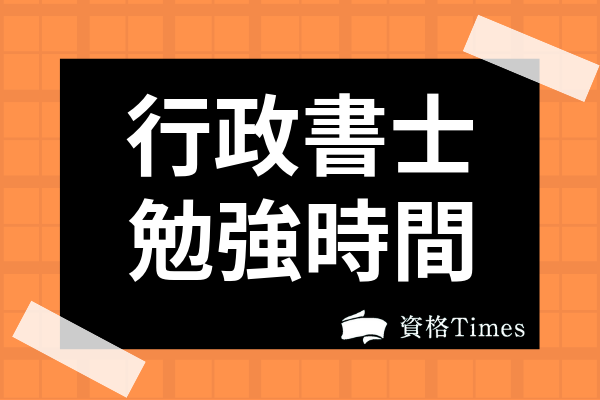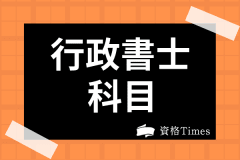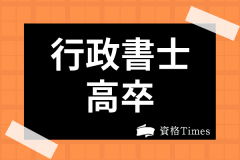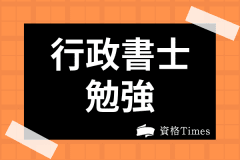行政書士の合格率が低い理由は?数値に現れない本当の難易度を徹底考察!
「行政書士の合格率は相当低いけれど、本当に難しいんだろうか?」
行政書士は人気資格として多くの人が受験する資格であり、試験の難易度を知りたい人も多いはずです。
しかし試験の実際の難しさは合格率だけでは分からない部分もあるので、詳しく知りたい人もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では行政書士の本当の難易度について解説します!
行政書士になって活躍するためにはまずは試験の特徴を理解することが大切です!
合格率という数値に表れない本当の難易度を理解して、行政書士試験合格に向けた第1歩を踏み出して下さい!
行政書士の難易度についてざっくり説明すると
- 合格率は10%前後で推移していて9割の人が落ちる試験である
- 学習範囲の広さや出題形式の多様さなどが理由で合格率が低い
- 受験者層の変化など合格率に表れない点もあるので注意が必要
- 他士業と比べれば易しい試験だが簡単に合格できる訳ではない
このページにはプロモーションが含まれています
行政書士試験の合格率の推移
行政書士は国家資格の1つで、弁護士や司法書士などと並ぶ士業系資格の1つです。毎年5万人近くが申し込む大人気の資格でもあります。
しかし合格率は10%前後で推移していて相当難しい資格です。多くの人が受験しているものの毎年9割近くの人が不合格になっています。
他資格の合格率と比較することで行政書士の難易度や位置付けが分かるので、以下では他士業の合格率との比較を紹介していきます。
他士業試験の合格率との比較
令和4年度実施試験の合格率を比較してみると、社労士5.3%・宅建士17.0%となっています。行政書士は社労士よりは簡単で、宅建士よりは難しい資格です。
そのため士業系資格の取得を目指す人の中には「合格率が1桁の司法書士や社労士は無理でも行政書士は頑張って合格を目指してみよう!」と考えて行政書士試験にチャレンジする人が多くいます。
また法務系資格を取りたい人の場合、難関資格の弁護士や司法書士は無理でも行政書士ならば合格できそうだと考える場合もあります。そのため受験者数は毎年非常に多く、人気資格の1つとなっています。
しかし行政書士の合格率は10%前後と低く、決して簡単ではないことも事実です。合格率がこれほどまでに低いのには理由があるので、その理由や試験の特徴をしっかりと理解しておかなければいけません。
社労士・宅建のそれぞれの難易度詳細は以下の記事をご覧ください。
行政書士試験の合格率が低い理由5選
 仮に合格率が同じでも資格試験ごとに特徴が違うので難易度が同じとは限りません。合格を目指す試験の特徴を理解することが大切です。
仮に合格率が同じでも資格試験ごとに特徴が違うので難易度が同じとは限りません。合格を目指す試験の特徴を理解することが大切です。
以下では行政書士試験の合格率が低い理由のうち、特に理解しておきたい5つの理由について紹介します。
試験の特徴を理解すれば効率的な学習や対策が可能になるので、行政書士試験に向けて勉強する際の参考にしてみて下さい。
合格点の設定が厳しい
行政書士試験には大きく分けて法令科目と一般知識科目があります。
法令科目・一般知識科目・総合のそれぞれで足切り点をクリアする必要があるので、全部で3つの合格基準を満たさなければいけません。
そして配点としては法令科目のほうが大きく、全体の足切り点を超えるためにも法令科目を重点的に勉強することになります。
しかしその結果として一般知識科目の対策が疎かになり、逆に一般知識科目で足切りにあって不合格になる人が多いのも行政書士試験の特徴です。
そもそも一般知識科目は対策しい科目なので、早めに勉強を進めて法令科目に加えて一般知識科目まで時間を割けるかどうかが重要になります。
行政書士の合格点は以下の記事を詳しくご覧ください。
学習範囲が非常に広い
行政書士は試験範囲が非常に広いことも特徴の1つです。
【法令科目】
- 憲法
- 行政法
- 民法
- 商法
- 基礎法学
【一般知識科目】
- 政治・経済・社会
- 情報通信・個人情報保護
- 文章理解
行政書士は仕事で取り扱う業務範囲が広く、豊富な知識量が必要とされるので試験範囲も広くなります。学習すべき量が多く、上記の通り法令科目5科目と一般知識科目3科目の勉強をしなければいけません。
さらに科目ごとに難易度や配点がバラバラで対策が難しいことも特徴です。科目ごとの足切りを超えつつ総合点でも合格点を超すためには、得点計画を立てるなど戦略的に学習をしなければいけません。
科目合格制度などが存在しない
中小企業診断士や税理士のように科目合格制度を採用している試験もありますが、行政書士試験では科目合格制度はありません。
完全に一発勝負の試験であり、法令科目・一般知識科目・総合のいずれかの足切りに掛かるだけで不合格になってしまいます。
科目合格制度がある試験の場合は合格科目の受験は翌年以降不要になるので他科目の勉強に集中できますが、行政書士試験ではそうはいきません。不合格だと翌年も全ての科目を受け直す必要があります。
少しのミスだけで不合格になるパターンを繰り返すと合格までに何年もかかるケースもあり、合格率が低い理由の1つになっています。
勉強不足の受験者も多い
行政書士試験研究センターによれば、受験者のうち過半数は30代と40代が占めていて、50代の受験者も加えると全体の4分の3になります。
行政書士は30~50代の社会人が主に受験している試験であり、日々の仕事や家事で忙しくて十分に勉強できないまま受験する人が一定数いると考えられます。
さらに行政書士は受験資格がない試験です。申込さえすれば誰でも受験できるので、モチベーションが上がらないまま何となく受験してしまう人もいます。
合格がほぼ絶望的な状況で受験をされる方が一定数いるため、合格率が低く出てしまう大きな要因となっています。
出題形式が多様で対策が困難
行政書士試験は択一式がメインですが、それ以外にも多岐選択式問題や記述式問題もあり、出題形式が多様です。
それぞれの出題形式に合わせた対策をしなければならず、合格できる知識レベルに達するまでにどうしても時間が掛かります。
配点が高い択一式対策を重点的に行う必要があるとは言え、多岐選択問題や記述式問題への対策が不十分だと結果的に足切りに掛かる可能性も高くなります。これも行政書士の合格率が低い理由の1つです。
近年は合格率が上がってきている?
 一昔前であれば行政書士の合格率は5%前後で推移していましたが、近年の合格率は10%前後です。以前と比べれば合格率が上がっていて難易度が下がっているようにも感じられます。
一昔前であれば行政書士の合格率は5%前後で推移していましたが、近年の合格率は10%前後です。以前と比べれば合格率が上がっていて難易度が下がっているようにも感じられます。
しかし合格率だけから試験の難易度を判断するのは決して適切ではありません。これは行政書士以外の資格試験でも言えることですが、以下では合格率を参考にする際の注意点について解説していきます。
合格率と難易度の関係に注意
試験の難易度を示す指標の1つとして合格率は確かに役立ちますが、仮に合格率が同じでも難易度が異なる場合があります。
例えば合格率が同じ10%の試験があった場合、法学部出身者だけが受験できる試験と受験資格がなくて誰でも受けられる試験では、前者の試験のほうが当然難しい試験です。難易度は同じではありません。
つまり試験の難易度には受験者層も大きな影響を与えるということです。合格率が上昇していても受験者層が以前と変化している場合があり、合格率で軟化・難化は一概に判断できるものではありません。
試験はむしろ難化傾向にある?
「過去と現在での受験者層の違いによる影響」は行政書士試験でも言えることです。
まず近年の傾向として、ドラマの影響や行政書士会の認知度向上の努力により「街の法律家」としてよく知られるようになりました。
行政書士の知名度が上昇して法律系資格として認識されるようになり、弁護士や司法書士などの超難関法律系資格を目指している人でも行政書士を受験するケースが増えています。
また司法試験に受験回数制限が設けられたことで、司法試験合格を断念した層が受験するケースも多くなってきています。
そのため以前に比べて高度な法律知識を持っている人の受験が増えている状況です。それにも関わらず合格率が極端に上昇していないことを考えると、試験としては寧ろ難化傾向にあると言えるでしょう。
行政書士の本当の難易度
 これまで行政書士試験の合格率が低い理由や合格率を参考にする場合の注意点を解説してきましたが、それらを踏まえた「行政書士の本当の難易度」とは一体どれくらいなのでしょうか?
これまで行政書士試験の合格率が低い理由や合格率を参考にする場合の注意点を解説してきましたが、それらを踏まえた「行政書士の本当の難易度」とは一体どれくらいなのでしょうか?
試験の難易度や特徴を理解した上で適切な勉強法や対策を取ることが大切なので、他資格との比較や必要な勉強時間について解説します。
法律系資格の中では依然として比較的易しい
行政書士は受験資格がなくて誰でも受験できる試験です。勉強が間に合っていない人や単なる記念受験の人も一定数いるので、10%前後という合格率が表すほど難しくはありません。
10人中1人しか合格できない試験と聞くと難しく感じますが、実際にはもう少し合格しやすい試験と考えて良いでしょう。
社労士や弁護士、司法書士に比べれば合格率は高いので、その意味でも行政書士は士業系資格の中では取得しやすい資格と言えます。
十分な勉強時間が必要
ただし上記で紹介したのはあくまで難関資格との比較の話です。行政書士は難しい試験であり、簡単に取得できる資格ではありません。
そもそも行政書士に合格するためには600~800時間の勉強時間が必要と言われていて、これは半年から1年かかる勉強時間です。
軽い気持ちで受験してもまず合格は無理ですし、実際何年も不合格になってしまう人や途中で挫折してしまう人も一定数存在します。
舐めた気持ちで臨むと痛い目に合ってしまうので、そうならないためにも計画を立てて最初から真剣に勉強に取り組むことが大切です。
勉強のモチベーション維持も課題に
合格を勝ち取るためには合格率が低い理由や試験の特徴を踏まえた上で適切な対策と効率的な勉強法を実践することが求められます。
さらに士業系資格では勉強期間が1年以上の長期に及ぶことも多く、モチベーションを継続できるかどうかも大切なポイントです。
時には勉強に疲れてしまったり何のために頑張っているのか分からなくなることもあるでしょう。
勉強を初める前に自分が本当に合格まで頑張り続けることができるかどうかもしっかりと検討することも重要だと言えるでしょう。
行政書士試験の勉強時間については以下の記事も併せて参照してください。
無理して独学合格を目指さない
行政書士は試験科目数が多く、自分の力だけでそれぞれに最適な勉強法を取るのは正直かなり難しいです。
特に法律の勉強にはコツがいるので、独学だと非効率な勉強を延々と続けてしまいいつまでたっても合格できない恐れもあります。
法律の事前知識がある方や普段の生活で多くの勉強時間を確保できる方以外は、プロの指導の元で学習を進めることをおすすめします。
通信講座であれば比較的リーズナブルな価格で受講できる上に、隙間時間を生かせるスマホ学習機能なども活用することができるので、忙しい社会人の方でも効率よく勉強することができるでしょう。
おすすめの行政書士通信講座は?
行政書士の通信講座であれば、業界最多の合格者数と合格者への全額返金特典制度を合わせ持つアガルートの行政書士講座がおすすめです。
2022年度には296名の合格者を輩出し、初受験者の合格者数は205名、合格率は全国平均の4.63倍となる56.17%と非常に高い数字を記録しています。
また、合格した際には受講者への受講料全額返金も併せて実施しており、合格に向けた強力なインセンティブがある点も大きな魅力です。
受講生の方からの評判も大変良い通信講座なので、この機会に是非一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
行政書士の難易度まとめ
行政書士の難易度まとめ
- 合格率は10%と低いものの合格率の低さほど難しい訳ではない
- 合格率が低いのは学習範囲の広さ等対策の難しさが要因である
- 合格率からは判断できない難易度や特徴もあるので注意が必要
- 難しい試験なので十分に勉強して試験に臨むことが大切である
今回は行政書士の難易度について紹介しました!
行政書士は少しの勉強で合格できるような甘い試験ではないものの、合格率の低さほど難しくはないことも理解できたと思います。
業務の幅も広くて様々な形で社会に貢献できる行政書士は魅力に富んだ資格です!行政書士資格の取得に是非チャレンジしてみて下さい!