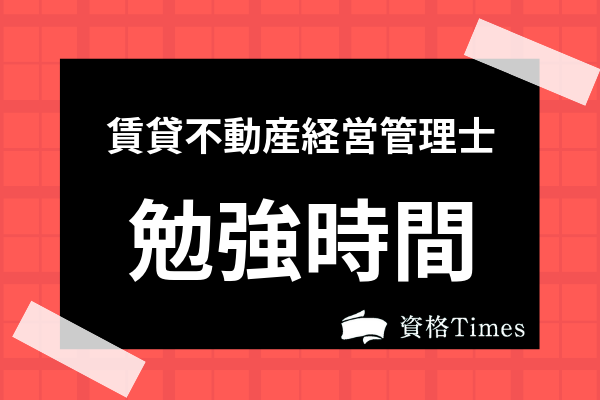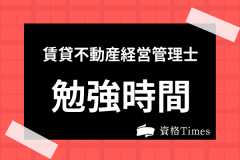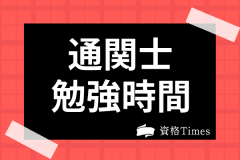賃貸不動産経営管理士の難易度は?合格率や合格点・試験内容の難化の噂まで徹底調査!
更新
「賃貸不動産経営管理士の難易度はどのくらい?」
「賃貸不動産経営管理士試験は難化しているって本当?」
このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
賃貸不動産経営管理士は、その名の通り賃貸不動産に関する専門家であり、貸主と借主に対して様々なサポートを行っています。
この資格の取得を目指している人にとって、難易度や合格率、合格点などの試験データは大いに気になりますよね。
こちらの記事では、賃貸不動産経営管理士試験の難易度や合格率・試験会場などの基本的な情報をお伝えしていきます!
賃貸不動産経営管理士の概要と難易度をざっくり説明すると
- 難易度はそこまで高くない試験だが、近年は難化傾向にある
- 令和5年度試験試験会場は全国35都道府県にある
- 宅建などの不動産資格と非常に相性が良い
- 賃貸不動産の経営管理の専門家であるため、今後の高い需要が見込まれる
賃貸不動産経営管理士の難易度は上昇

賃貸不動産経営管理士は主に賃貸アパートや賃貸マンションなどの管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
不動産の有効活用の重要性が高まっている背景もあり、近年は受験者が増加している注目の資格と言えるでしょう。
人気が高まっている一方で合格率は下がりつつあり、試験は難化傾向にあります。
賃貸不動産経営管理士の資格概要
賃貸不動産経営管理士の資格を取得することで、賃貸不動産の管理や経営のノウハウを身に着けることができ、また入居者の生活をサポートするための知識を習得することができます。
一般人には賃貸不動産の関する専門的な知識を持っている方は少ないため、身に着けた知識や能力を生かして入居者の入居~退去するまでの長期間において様々なサポートを行っています。
また、賃貸不動産経営管理士試験の試験会場は全国の主要都市ですが、各都道府県で行われているわけではありません。
令和5年度の試験会場は北海道、岩手、宮城、福島、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、奈良、京都、大阪、兵庫、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、沖縄の全国35地域となっています。
不動産管理のプロとして必要不可欠
賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅管理業者登録制度において、以下のような業務を行うことができます。
- 貸主に対する管理事務の説明やサブリース方式の契約の説明
- 貸主に対する賃貸住宅管理に係る重要事項の説明や書面への記名・押印
- 貸主に対する賃貸住宅の管理受託契約書の記名・押印
- 住宅宿泊業者の登録
特に、民泊に関する仕事は近年注目が高まりつつあるため、不動産業界全体からも注目されています。
賃貸不動産経営管理士の試験内容
賃貸不動産経営管理士試験は、四肢択一のマークシート形式で行われます。
主な出題内容は以下の通りです。
- (イ)管理受託契約に関する事項
- (ロ)管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
- (ハ)家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
- (ホ)賃貸住宅の賃貸借に関する事項
- (へ)法律に関する事項
- (ト)イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項
このように、賃貸不動産の経営や管理に関する専門的な内容が問われます。
受験資格はなく誰でも受けられる
試験には受験資格が設けられておらず、学歴や実務経験に関係なく誰でも受験がすることができます。
そのため、受験のハードルはとても低く不動産業界で働いている人や不動産業界への就職・転職を目指している人が多く受験しています。
賃貸不動産経営管理士は偏差値50
試験は近年難化傾向にありますが、そこまで難しい試験ではありません。
他の資格試験と比べても難易度は低く、現段階では「やや優しい」レベルの資格試験であると考えられています。
そのため、資格試験の難易度を偏差値で表すと50程度、もしくはそれ以下であると考えられています。
同じ不動産系の資格の代表である宅建やマンション管理士などと比べても取得しやすく、まずは自信をつけるために目指す人も多いです。
合格率は大幅に低下している
前述したように、賃貸不動産経営管理士の試験は難化傾向にありますが、それは合格率の低下を見れば明らかです。
また、他にも試験が難しくなっている要因があるため、それらを解説していきます。
試験結果と合格率から見る難化傾向
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 31,687人 | 8,774人 | 27.7% | 34点 |
| 令和3年度 | 32,459人 | 10,240人 | 31.5% | 40点 |
| 令和2年度 | 27,338人 | 8,146人 | 29.8% | 34点 |
| 令和元年度 | 23,605人 | 8,698人 | 36.8% | 29点 |
| 平成30年度 | 18,488人 | 9,379人 | 50.7% | 29点 |
| 平成29年度 | 16,624人 | 8.033人 | 48.3% | 27点 |
| 平成28年度 | 13,149人 | 7.350人 | 55.9% | 28点 |
| 平成27年度 | 4,908人 | 2.679人 | 54.6% | 25点 |
| 平成26年度 | 4.188人 | 3,219人 | 76.9% | 21点 |
| 平成25年度 | 3,946人 | 3.386人 | 85.8% | 28点 |
※令和2年度から出題数が40→50問に変更
データ出典:賃貸不動産経営管理士試験 統計データ
この表を見て分かるように、合格率が近年低くなっているのに加えて合格点のハードルも上がっています。
令和4年度の試験の合格率は27.7%で、およそ3人に1人以下しか合格できていない計算になるため、かなり難しい試験であることが分かります。
この傾向は今後も続いていくと考えられており、早い段階で受験した方が合格しやすいと言えるでしょう。
以下の記事では賃貸不動産経営管理士試験の合格率を徹底解説しています。
傾向の変化も難化の要因
最近の試験では出題傾向にも変化の兆しが見られ、それらも難化する一因となっています。
令和元年度の賃貸不動産経営管理士の試験では、過去問題で頻出論点だった分野だけでなく、これまでに出題実績が無い問題や対策しようのない難問もいくつか出題されました。
これらのことから、今後の試験でも幅広い知識だけでなく応用力やひらめき・対応力が問われるようになるため、ただ単にテキストの内容を覚えるという勉強法ではなかなか得点が伸びないでしょう。
国家資格化に伴いさらに難化
国土交通省が、賃貸不動産のスペシャリストのニーズの増加に伴い「賃貸不動産経営管理士の社会的な役割を明確化すること」が課題であると明言しました。
このような動きの影響で賃貸不動産経営管理士の国家資格化が目指されており、試験内容も令和2年度から変化されています。
具体的な変化のポイントとしては、「問題数が40問から50問へと変わること」「試験時間も90分から120分になること」が挙げられます。
また、試験内容についてもこれまで以上に専門的な内容になる可能性があり、試験の難易度の上昇は今後も続いていくでしょう。
合格点は年によって変動
賃貸不動産経営管理士試験の合格点は試験回によって違います。
合格点は一律ではなく毎年異なるため、合格ラインぎりぎりを目指すのではなく「例年の合格基準点+5点」くらいを目標にして日頃から勉強すると良いでしょう。
また、毎年各種予備校が発表する予想合格点を参考にしながら目標を定めるのも良いでしょう。
この試験は1点の差で合否を分けることが非常に多いため、ケアレスミスに気を付けるのに加えて「取れるべき問題は確実に取る」という強い意識が必要です。
賃貸不動産経営管理士試験の合格点について以下の記事で詳しく解説しています。
合格ラインは7割以上の正答率
合格点が毎年変化するものの、おおむね7割の正解が合格ラインとなることが多いです。
多くの受験生も「まずは7割の得点」を目標にしているため、近年の合格点は7割以上が当たり前となっています。
そのため、過去問などで学習をする際には7割ではなく8割の正答率を目指す練習をしておくと、本番でも落ち着いて取り組めるでしょう。
また、練習の段階から「確実に正解しないといけない問題」「初見だから後回しにする問題」を見極める訓練をしておきましょう。
賃貸不動産経営管理士の難易度ランキング
他の様々な資格試験と難易度を比較した「難易度ランキング」では、賃貸不動産経営管理士は中央をやや下回る「やや簡単な試験」の部類に入ります。
似たような難易度の資格として、国家資格であれば登録販売者、公的資格であれば簿記3級、民間資格であれば情報処理技能検定などが挙げられます。
他の不動産関連資格と難易度を比較
賃貸不動産経営管理士とよく比較される不動産関連資格である「宅建」と「マンション管理士」と難易度を比較してみましょう。
なお、これらの資格は親和性が高く相性が非常に良いため、ダブルライセンスを取得して不動産業界で活躍している人も多くいます。
宅建
宅建は不動産取引のスペシャリストで、不動産系資格で最も知名度が高い資格とも言えます。
宅建も受験資格は特に設けられておらず、合格率は15%程度で推移しているため難易度が高い資格であると言えるでしょう。
合格ラインの正答率については賃貸不動産経営管理士と同じく7割程度(50点中35点程度)となっていますが、宅建試験の方がより宅地建物取引業・不動産の仕事に必要な実践的な知識が出題されます。
不動産の売買のみならず賃貸に関する専門的な知識も学べるため、不動産業界で働く上では欠かせない資格と言えます。
宅建試験の難易度について別記事で解説しています。ぜひご覧ください。
マンション管理士
マンション管理士はマンションなどの集合住宅の管理に関するプロフェッショナルです。
マンション管理士の合格率は9%程度となっており、宅建よりも難易度が高い資格となっています。
マンション管理士の合格ラインもおおむね7割程度となっていますが、試験問題ではマンション管理に関する法令規則やマンション構造・長期修繕計画など難解な内容を理解していないと解くことができません。
今後の高い需要が見込まれる資格なので、専門性の高い知識が要求されているのです。
これらの内容を総合的に判断すると、不動産関連の資格の中で賃貸不動産管理士は圧倒的に取得しやすく、手始めに合格を目指すのにぴったりの資格なのです。
マンション管理士試験の難易度が気になった方は以下の記事を参照してください。
賃貸不動産経営管理士を目指すべき理由
賃貸不動産経営管理士の資格を取得していると、様々なメリットを享受できるだけでなくビジネスチャンスも広がります。
こちらのトピックで、資格を所有していることのメリットを解説していきます。
不動産業界でキャリアアップ
賃貸不動産経営管理士は、やはり不動産業界で役立てることができます。
賃貸不動産に関する業務の幅が広がり、顧客から信頼を得やすくなったり企業内でキャリアアップできる可能性を高めることができます。
また、賃貸管理のプロとして多くの家主さんと信頼関係を築きやすくなり、他の不動産業者との差別化も図れるようになるでしょう。
自分が家主だったら、無資格者よりも有資格者に仕事を頼みたいと考えますよね。
このように、不動産業界において絶大なメリットを享受できるでしょう。
事務や金融でも役立てられる
賃貸不動産経営管理士は、不動産業務の中でも総務や金融等の分野で活躍できます。
近年は年金不安のニュースなどの影響もあり、不動産投資や大家業の関心が高まっています。
そこで、賃貸不動産経営管理士の資格を生かして不動産担保の融資や資産運用など、金銭的な業務において役立てることができるのです。
当然、仕事以外の自分の実生活でも役立てることができるため、様々な形に落とし込んで自分の知識を高めていってください。
就職・転職で有利な資格
賃貸不動産経営管理士の資格を所有していることで、不動産業界への就職・転職で役立てることができます。
この資格を持っていることで不動産の賃貸経営に関して専門的な知識を持っている証明となるため、選考の場において好印象を持たれやすいです。
また、この資格は宅建やマンション管理士ほど知名度は高くなく成長途中であるため、現在は保有者がそこまで多くありません。
そのため、この資格を取得しておくことで周りに差をつけることができ、自身の評価を上げることにつながるのです。
また、前述したように宅建やマンション管理士などの不動産資格と非常に相性が良いため、ダブルライセンスを実現できればより自分の価値を高めることができます。
賃貸不動産経営管理士は独学で合格できる?
こちらのトピックでは、独学で合格するために必要な学習計画・勉強方法について解説していきます。
勉強時間は150時間あると安心
賃貸不動産管理士の資格試験に合格するためには、100時間程度の勉強が必要とされています。
ただし、前述したように近年は試験が難化傾向にあります。
今後も試験の難易度が上昇したり試験の問題数が増えることなどを考えると、150時間ほどの勉強時間を確保して余裕を持った勉強計画を立てると良いでしょう。
ただし、これはあくまでも独学勉強する場合の話であり、通信講座や予備校で効率よく対策を行っている場合この目安の勉強時間よりも短く済むケースがあります。
また、詳しくは後述しますが、宅建に既に合格している人であれば民法などの基本的な知識がすでに身に着いているため、より短い時間でも合格を目指すことができるでしょう。
賃貸不動産経営管理士試験の勉強時間についてさらに知りたい方は以下の記事をご覧ください。
参考書と問題集の反復で得点アップ
賃貸不動産経営管理士の問題はそこまで難しくないため、インプットとアウトプットという基本的な勉強法を実践すれば問題ありません。
まず最初は、賃貸不動産経営管理士の試験範囲に対応するために、参考書などを読み込んで基本的な知識を詰め込んでいきましょう。
しっかりと基本的な知識をインプットした後に問題集を解くことで、本試験でも対応できる実践的な応用力や対応力を磨くことができます。
インプットとアウトプットをしっかりと行っていれば自然と合格ラインに到達できるレベルに達するため、手を抜かずに丁寧に勉強を進めていきましょう。
この二つの作業を繰り返し反復して行うことで、出題傾向が変わった後の問題にも対応できる学力を身に着けることができます。
過去問は解説までしっかり読み込む
新しい出題傾向の問題もしっかりと対策をしておく必要がありますが、過去に出題された問題も多く出題されます。
そのため、最近の出題傾向ばかりに気を取られるのではなく、過去問のやり込みも重要な勉強プロセスです。
重要論点や頻出論点は出題の切り口が似ていることが多いため、過去問を繰り返す解くことで自然と体で覚えることができます。
過去問を解く組む際には、解説を斜め読みするのではなく内容を熟読して出題者の意図を把握することを心掛けましょう。
単なる答え合わせで終わらせるのではなく丁寧に解説を読み込むことで、問われ方が違う場合でも対応できるようになるのです。
宅建士を先に取得するとスムーズ
実務経験なしで賃貸不動産経営管理士に登録する際には、宅建試験に合格して宅建士証の交付を受ける必要があります。
つまり、実務経験がない人にとっては宅建とのダブルライセンスをクリアすることが登録のために必須となります。
宅建士の方が難易度が高く賃貸不動産経営管理士の試験内容とも重複があるため、先に宅建を取得することがおすすめです。
先に難易度が高い宅建を取得しておくことでスムーズに賃貸不動産経営管理士の勉強ができるようになり、また勉強の全体像もつかみやすくなります。
また、宅建の資格を持っていることで資格手当の対象になりやすい上に将来的に不動産業界でより幅広く活躍できる可能性が広がるため、ダブルライセンスを取得することで様々なメリットを享受できるようになるでしょう。
難化を考えると通信講座もおすすめ
賃貸不動産経営管理士は難化傾向にあるため、通信講座で学習を進めると安心です。
わかりやすく丁寧に説明してくれる講座が多いので、難しい内容でも学習がはかどること間違いなしです。
賃貸不動産経営管理士の通信講座の中でも、特に資格Timesではスタディングの通信講座をおすすめします。
スタディングの講座最大の売りは、圧倒的な低価格の受講料であり、今まで値段に抵抗感を持って踏み出せなかった人も通信講座で学習することが可能です。
また、低価格にもかかわらず教材の質も高くなっており、わかりやすい教材のもと学習を進められるでしょう。
令和4年度には236名もの合格者を輩出するコスパと実績の高さを兼ね備えた講座となっておりますので、試験の合格を目指されている方はぜひこの機会に受講をご検討ください。
賃貸不動産経営管理士まとめ
賃貸不動産経営管理士まとめ
- 合格基準点は毎年変動しているが、8割の得点を目標にしておけば安全圏
- 過去問や近年の出題傾向を押さえておけば、独学でも合格が狙える
- 近年は難化傾向にあるため、早めに取得しておくと良い
- 宅建やマンション管理士とのダブルライセンスを目指そう
賃貸不動産経営管理士は不動産系資格の中では難易度は低く取得しやすい資格なので、不動産業界に興味がある人はぜひ取得を検討してみてください。
勉強のコツや出題傾向押さえつかめれば、自然と合格圏に到達できるでしょう。
試験が難化傾向にあり、今後の需要も増えていくと考えられる資格なので、早めに取得しておくことをおすすめします。