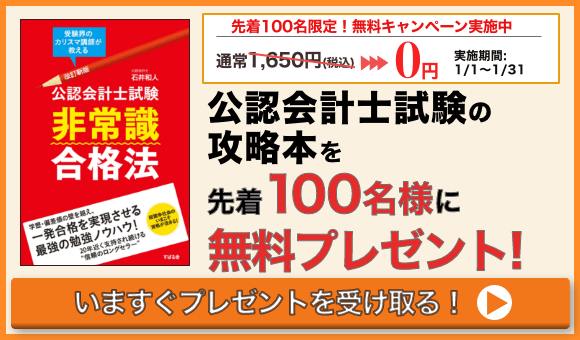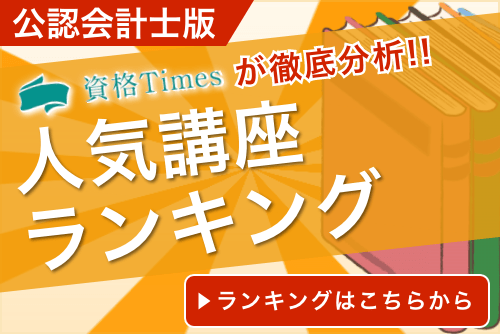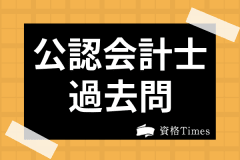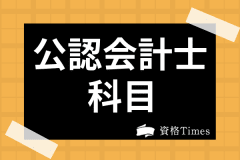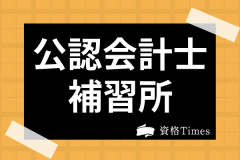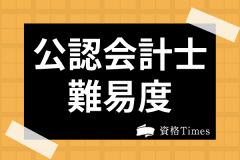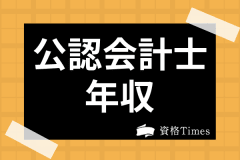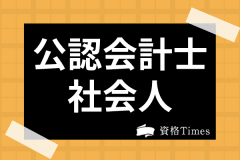公認会計士の独立は儲かるの?年収から失敗した際の対応策まで徹底解説!
この記事は専門家に監修されています
公認会計士
白井敬祐
「公認会計士って独立しても儲かるの?」
「もし独立して失敗したらどうすればいいの?」
このような疑問や不安をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
公認会計士は専門性が高く、独立開業しやすい資格です。
とはいえ、しっかりと準備をして営業をしないと食っていくことはできず、早期に廃業してしまうでしょう。
また、開業したらどの程度稼ぐことができるのか、気になりますよね。
こちらの記事では、公認会計士の資格を生かして独立開業する方法や、もし失敗してしまったときの対応策などについて解説します!
公認会計士の独立についてざっくり説明すると
- 独立後の仕事も、自分の選択次第で多岐に渡る
- 独立することで通勤や人間関係などのストレスから解放される
- ワークライフバランスの実現がしやすくなる
このページにはプロモーションが含まれています
監査法人のあとは独立開業

公認会計士の資格を取得後、監査法人に勤めて経験を積んだ後に独立開業する人が多いです。
独立すると大きな責任を伴うことになりますが、その分やりがいも大きく高収入も狙える選択肢です。
独立してからの仕事
公認会計士として独立してからの仕事は、主に以下のようなものがあります。
- 会計コンサル
- IPO・M&A・資金調達・事業再生等に関わるコンサルティング
- 税務業務
- 監査法人の監査補助
- ベンチャー企業・スタートアップ企業の会計税務業務
- 経営者の資産管理会社の運営サポート
- 個人のタックスプランニングや税務申告のサポート・代理

私の場合特殊かもしれませんが、10年間監査、コンサル、事業会社経理を経験してから独立して、予備校の講師という道もあります。
10年間実務をしたからこそ講師として様々な経験を世の中に伝えたりできるという強みになっていると思います。
主な独立の選択肢は?
公認会計士が独立する際は、主に「監査」「FAS・コンサルティング」「会計アドバイザー」「税務」等の業務が軸となります。
もっとも簡単なのは「監査」での独立であり、まずは監査業務を受託するケースが多いです。
主に中小の監査法人と業務受託契約を結び、コツコツと仕事をこなしていくことになります。
独立したての若手会計士にとっては実務経験が積める上に条件の良い仕事であるため、非常に人気です。
独立によるメリット
当然、公認会計士として独立することには様々なメリットがあります。
ここでは独立の良い点を確認していきましょう。
儲かる選択肢である
開業した公認会計士の平均年収は1000万円以上と言われています。
注意点としては、開業公認会計士の年収は個人の能力次第の競争社会であることです。
営業がうまくいかないと、場合によっては独立前より稼げなくケースも十分にあり得ます。
このように年収の個人差は幅広く、あまり稼げない公認会計士がいる一方で、顧客を集める営業能力・専門性を併せ持つことで2000~3000万円以上の超高年収も可能となっています。
なお、高額の年収を手掛ける公認会計士は、以下のような活動をしている人が多いです。
-
ベンチャー企業の株式を持ちながらIPOを手掛ける
-
M&Aや不動産取引の上流に入って行き、トランザクションの成功報酬等を得られるモデルを築く
-
国際税務等の特殊性の高い分野で独自の地位を作る
-
組織を拡大して経営者になる
私生活の時間を取れる
独立すると、仕事の都合などを自分で決められるため、1日のスケジューリングが楽になります。
自分の時間を取りやすく、ワークライフバランスの実現もしやすいでしょう。
また、通勤の時間を省けて残業の時間なども自分で調節できるため、これまで移動時間などで費やしていた時間を有効活用できるようになります。
また、組織だと上司への気遣いや、組織での立ち位置など人間関係で気を遣わなければならない場面は多いでしょう。
独立すると不安や気遣いから解放され、人間関係のストレスが大きく減るのもメリットと言えます。
どの年齢で独立するべきか
独立するべきタイミングに正解はなく、人によってタイミングは異なります。
ただし、実務経験が不十分な状態で独立するのはやめておくべきで、金銭面・準備が整い、独立するモチベーションが起きたときに独立しましょう。
しかし、独立はリスクが伴うため不安があったりプレッシャーを感じたくない人は無理に独立するのはやめておくべきです。
大手の監査法人で働くことでも貴重な実務経験を得ることができるため、現在の状況と比較した上で慎重に検討することをオススメします。
公認会計士は「知識と経験」を提供する職業であるため、独立前にしっかりと経験を積んでおくことが顧客を獲得する上で何よりも重要なのです。
一方で、年齢が若い内の独立は「経験が少ない」というデメリットはあるものの、「単価を安く仕事を受注できる」「家庭面、キャリア面でリスクテイクしやすい」などのメリットがあります。
独立の際の準備とは?

専門分野を決めて業務を経験しておく
独立する際には、自分が得意とする分野や仕事で扱いたい専門分野をあらかじめ決めておくことが大事です。
専門分野を決めておくことで、その分野の業務に強い企業を選んで入社することができ、貴重な実務経験を積むことができます。
経験を積んで得意分野の実務能力を高めておくことで、独立後の業務に生かすことができます。
公認会計士を取得後のキャリアプランとしては、まずは監査法人に就職するケースがほとんどです。
実際に公認会計士の業務を経験することができるため、監査業務を中心に専門分野を検討するのがオススメです。
なお、監査法人に入社した場合、最低でも3年程度経験を積んでおくと良いでしょう。
あまり短い期間だと十分な実務経験を積めずに、独立するのに十分なスキルが身に着かない恐れがあるため、注意が必要です。
また、様々な公認会計士と人脈を作り、情報網を広げておくのも良いでしょう。
このように、人脈を生かしていつでも助けてもらえる体制を作ることで、いざとなったときに対応できるようになります。
クライアントを増やす
独立の準備にあたり、クライアントを確保することは何よりも大事です。
独立当初は自力で開拓していくことはなかなか難しいので、前職の先輩やパートナーから仕事を紹介してもらいクライアントを作るケースが圧倒的に多いです。
その後の人脈作りは、業務に直結しているクライアントを絞ってアポイントを取り、自分のスキルや事務所の強みをアピールすることで広げていくと良いでしょう。
また、開業当初は幅広い分野の仕事を引き受けることで自分の仕事の幅が広がっていくため、責任感を持ちながら地道に仕事をこなしていくことも大切です。
資金準備もぬかりなく
独立の準備にあたり、業務に必要な資金を準備することも大切です。
開業の際に、資金繰りの方法として借り入れがありますが、借金は金利負担や返済のリスクを考えるとあまりオススメはできません。
自分自身の生活費だけでなく、設備代や人件費などを考えた上で資金を調達することが重要です。
開業当初は顧客獲得に苦労することが予想されるため、余裕を持った資金計画を立てるようにしましょう。
独立にあたり準備するべき資金はどれくらいか
独立しても、儲かるようになるまでには数カ月程度かかってしまうのは覚悟しておく必要があります。
そこで、具体的にはいくらくらいの資金を準備しておくべきか見てみましょう。
テナントを借りて事務所を構えるかどうかによりますが、借りる場合は初期費用がかなり高くつきます。
敷金や礼金・仲介手数料などの諸経費と事務用品のリース代などを含めて、200〜300万円は準備しておくと安心です。
なお、無収入期間でも自分の生活費や家賃などのコストはかかってしまうため、できるだけ多くの貯金をして備えておくと尚良いでしょう。
仕事が徐々に入るようになり、コツコツと信頼を重ねていけば事業を軌道に乗せることができます。
せっかく開業しても、準備資金が少ないと早々に廃業に追い込まれてしまうため注意しましょう。
公認会計士の開業は失敗しやすい?

独立開業するノウハウを持っていない状態や、同業者や他士業の方との人脈がない状態で開業しても事業が失敗する可能性が高いでしょう。
士業全体で見ると、6割にあたる事務所が独立しても最終的に廃業してしまっています。
特に計画性が無い開業をしてしまうと、開業後1~3年で廃業する人の割合が多いです。
逆に、3年以上事務所の運営が続く人たちは、その後も上手くやっているケースが多いのです。
つまり、開業後の3年は事務所がうまく回るかどうか非常に重要な期間と言えるでしょう。
公認会計士の独立が失敗する主な要因
ここでは公認会計士としての独立がうまくいかない主な原因を確認していきましょう。
営業活動に失敗した
公認会計士が非常に高度なスキルを持っていて専門性が高いとはいえ、しっかりと営業活動をしないと顧客を獲得することはできません。
そもそも営業を行わないと自分の存在をアピールすることができず、公認会計士を探している人の目にも留まりません。
多少広告費を出してでも、自分のこれまでの実績や得意分野などをアピールしなければ、独立しても稼いでいくことはできません。
他者との違いを打ち出せなかった
競合他社と違いを作り、うまく顧客を獲得できるような工夫をしていかないと、うまく稼いでいくことはできません。
公認会計士の主な業務は監査業務なので、監査を強みとして売り出しても他社と被ってしまう可能性が非常に高いのです。
公認会計士以外の他の資格を生かした独自のサービスの提供やコンサルティング業務など、他社と違いを作り差をつけていくような工夫は必要不可欠です。
景気の影響を受ける場合も
公認会計士の独立は、景気の変動によって大きく影響を受けます。
例えば、好景気の時だと監査業務の仕事は増えるため仕事を引き受けることは簡単ですが、不景気の時には仕事も減り、仕事を獲得する難易度が高まってしまいます。
このことから、不景気の際に仕事を受注することができず、収支のバランスが崩れてしまうことが廃業に結びついてくるのです。
特に、ある1つの事業や業界などを専門的に業務を引き受けている場合は、その業界の景気状態の変化で収益が簡単に影響を受けます。
そのため、景気が悪くなる兆候がある場合は特に注意が必要と言えるでしょう。
開業に失敗した後は転職できる?
 独立に失敗してしまった場合、再就職を目指すことになります。
独立に失敗してしまった場合、再就職を目指すことになります。
その際には、ポジションや年収にこだわらなければ比較的すぐに再就職できます。
再就職の際に大事なことは、事務所を畳んだ後の事後処理に追われることで、長いブランクを作らないことです。
その理由としては、ブランクがあると法改正などの業界の最新事情についていけなくなり、活躍できなくなる恐れがあるためです。
また、廃業の影響が無い就職先を見つけて、気持ちを新たに再スタートできる環境を整えることも大切です。
一般的な就職先としては監査法人・会計事務所や一般企業などが挙げられます。
公認会計士の転職について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
失敗した後の再就職先
それでは、開業に失敗してしまった場合の再就職先の候補を確認していきましょう。
監査法人・会計事務所
独立に失敗した後でも、監査法人や会計事務所に再就職することは可能です。
廃棄歴があるとネガティブなイメージがありますが、逆に個人事務所の立ち上げを経験していることで、公認会計士としてスキルが高いとみなされて転職の際に高く評価される場合もあります。
また、ビッグ4と呼ばれている大手監査法人でも需要はあるため必ずしも廃棄がマイナスに作用することはありません。
一般企業への就職も可能
一般企業内で会計のポジションを募集している会社があるため、そのような企業への再就職も可能です。
一定以上の規模のある会社であれば、福利厚生も整備されているためワークライフバランスを整えながら再び仕事に打ち込めるようになるでしょう。
転職先を選ぶときには、年齢とキャリアを考慮したうえで給与を決定してくれる会社が特におすすめです。
また、ベンチャー企業など小規模企業のCFOになる選択肢もあるなど、様々な選択肢があります。
転職の時に気を付けるべきこと
独立開業に失敗した場合でも、再就職という選択肢があるのでお先真っ暗とはなりません。
一方で、独立をやめて転職を考える場合には気をつけるべきポイントもいくつか存在します。
失敗の影響の少ないところへ就職
廃業の影響が及ばない就職先を見つけて、心機一転スタートできる環境を整えることも大切です。
事務所を廃業してしまった旨の噂はすぐに広まってしまいます。
また、知り合いなどがいると過去の失敗を引きずってしまい、心新たに生き生きと働きづらくなってしまうこともあるため注意が必要です。
ブランクの期間は最小限に
事務所を畳んだ後に、その対応業務に追われることで長いブランクを作ってはいけません。
理由としては、公認会計士業界の最新事情についていけなくなり、法改正などに対応するのに手間がかかってしまうためです。
再就職を目指す過程で長いブランクがあると、スムーズに仕事に入れなくなるリスクを孕んでいます。
転職求人はどうやって探す?
転職求人は基本的には数ある転職サイトの中から探すことになります。
しかし、転職サイトと一口に言っても求人の質はサイトによって異なる場合も多く場合によっては失敗するリスクもはらんでいます。
特に開業に失敗した後だとこれ以上のリスクを負うことは難しいため、良質な求人を高い確率で見つけていくことが重要になります。
良質な求人を見つけるために、会計士転職に特化した転職サイトで案件を見つけていくことをおすすめします。
数多くの会計士の転職を支援し制約に結び付けていることから、豊富な案件情報やコネクションを擁しており、良質な求人に効率よく当たることができるでしょう。
公認会計士の独立まとめ
公認会計士の独立まとめ
- まずは基本業務である監査に関する業務をマスターして、独自のアイデアを展開すると良い
- 独立するとより高い年収を稼ぐチャンスが生まれる
- 専門分野を作り、強みを持っておくと良い
公認会計士は独立しやすい資格ですが、独立した全員が成功するわけではありません。
独立することで高年収のチャンスが生まれますが、仮に事業がうまくいかなくても再就職して再スタートを切ることは可能です。
公認会計士は多くの魅力がある資格なので、興味がある人はぜひ取得を目指してみてください!