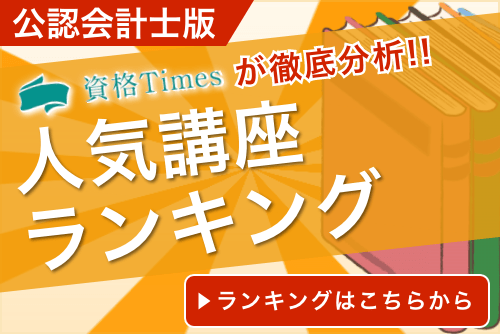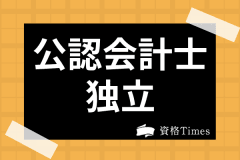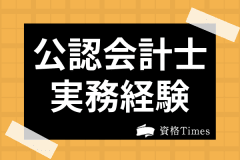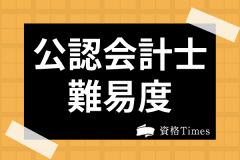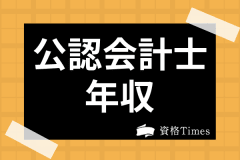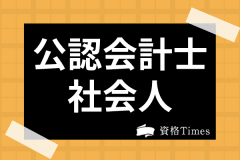公認会計士合格後に通う補習所って何?補習所の役割から修了考査の内容まで徹底解説!
この記事は専門家に監修されています
公認会計士
白井敬祐
「補習所ってどんなところなんだろう?」
「公認会計士になるためには、補習所に通わないといけないの?」
公認会計士を目指している人たちの中には、このような疑問を持っている人も多いかと思います。
そこで、今回の記事では、公認会計士試験合格後に通う補習所について、その役割から学習内容、さらには修了考査の内容まで、徹底的に解説していきます。この記事を読むことで、補習所についての理解を深めることができるでしょう。
公認会計士の補習所についてざっくり説明すると
- 公認会計士合格者が正式に公認会計士と認められるために通うところである
- 授業やeラーニング、合宿や修了考査など、様々なイベントがある
- 補習所を最大限活用するためのポイントがある
このページにはプロモーションが含まれています
補習所ってそもそもどんなところ?
 そもそも、補習所とはどんなところで、どのような役割があるのでしょうか?
そもそも、補習所とはどんなところで、どのような役割があるのでしょうか?
補習所とは略称であり、正式名称は「実務補習所」となっています。
公認会計士の論文式試験を突破すると、試験合格者は「準会員」となります。正式に公認会計士と認められるためにはいくつかの要件があり、その要件の1つとして補習所に通うことが挙げられます。そのため、公認会計士になる予定者は、約3年程度補習所に通う必要があります。
補習所で行うこと
次に、補習所で実際に行われていることについて紹介します。端的に説明するならば、補習所には公認会計士としての標準的な品位と素養を身につけさせるという役割があり、そのために様々な事項を実施しています。
具体的には「ライブ講義(大学の授業形式での講義)」や「eラーニング」、「ゼミによるディスカッション」、さらには「合宿」などを実施し、その中で、「考査(定期テスト)」や「課題研究(レポート)」、「修了考査(卒業試験)」が課されることになります。
受講形態
補習所における主な受講形態としては、補習所に行って直接授業を受けるパターンと、eラーニングで授業を受けるパターンという、2つのパターンが存在しています。
どちらのパターンでも出席が必要なものであり、出席の記録をもとに単位が付与されていくこととなっています。
補習所の主な場所としては、「東京実務補習所」「東海実務補習所」「近畿実務補習所」「九州実務補習所」の4つの場所があります。
また、授業を受けるという形態以外にも、「ゼミ」「ディスカッション」の形態や、「合宿」形式の授業もあります。
「ゼミ」「ディスカッション」は、3年間の間で4~5回行われることとなり、班ごとに様々な議題を議論することになります。
また、合宿は丸2日かけて行われます。合宿の内容としては、「ビジネスゲーム」や「連結財務諸表の作成」などといったラインナップがあり、途中で工場見学なども行われます。
通常講義
通常講義の際の出欠確認については、「補習生カード」を用いて行われています。講義開始前と講義終了後にカードリーダーに補習生カードを通すことで、出欠が記録されます。この記録を基に単位が付与されることになります。
eラーニング講義
一方、eラーニング講義の場合には、システムにログインし、講義を視聴し、確認テスト、アンケート回答を経ることで、当該講義が受講完了となります。そして、その記録を集計することで単位が付与されることになります。
授業スケジュール
授業は、3年間にわたって実施されることとなっていますが、カリキュラムの70%は1年目に実施されることとなっています。
したがって、1年目は週1~2回のペースで授業が行われることとなり、全体の期間の中で1番ハードな時期であると言えるでしょう。
2年目はカリキュラム全体の20%、3年目はわずか10%と、年を重ねるにつれて授業を受ける負担は軽減されていきます。2年目は月1回程度、3年目は1~2回の出席でeラーニングの授業がほとんどとなっています。
短縮申請を出すこともできる
ただし、各年度の1/15までに実務経験が2年以上ある場合であれば、補習所の通学期間を短くできる制度が存在します。
具体的な条件としては、2年短縮するためには、1年目の1/15 までに2年以上の実務経験を積むことが、1年短縮するためには、2年目までの1/15 までに2年以上の実務経験を積むことが、それぞれ必要となってきます。
補習所の場所について
 補習所は、公認会計士会館と呼ばれている建物のほか、それぞれの地区で以下の場所に設けられています。
補習所は、公認会計士会館と呼ばれている建物のほか、それぞれの地区で以下の場所に設けられています。
①東京実務補習所
- 公認会計士会館
- 日本教育会館(一ツ橋ホール)
②東海実務補習所
- 日本公認会計士協会東海会 研修室(名古屋クロスコートタワー11階)
③近畿実務補習所
- 日本公認会計士協会近畿会 研修室(クラボウアネックスビル2階)
- 大阪商工会議所
- 天満研修センター
④九州実務補習所
- 日本公認会計士協会北部九州会 研修室(天神幸ビル5階)
補習所での実際の授業とは?
 ここでは、補習所での実際の授業内容や雰囲気などについて紹介していきます。
ここでは、補習所での実際の授業内容や雰囲気などについて紹介していきます。
授業内容
授業科目の分類としては、監査・会計・税務・経営・法規・コンピュータの理論・および実務が主に行われることとなっています。以下に、それぞれの授業内容についてまとめています。
| 授業科目 | 内容 |
|---|---|
| 監査 | 監査論関係の授業(制度論やリスク評価、各科目の手続についてなど) |
| 会計 | 会計学関係の授業(連結財務諸表作成や財務分析、IFRSなど) |
| 税務 | 租税法関係の授業(法人税、所得税、消費税など) |
| 経営・IT | 経営学やIT関係の授業(デューデリジェンスやリスク管理など) |
| 法規・職業倫理、特別講義 | ビジネススキルや職業的懐疑心などに関する授業 |
なお、講師は監査法人の上の役職の人が多いことから、授業の内容もハイレベルであり、非常にためになる授業ばかりとなっています。
授業の雰囲気
ここでの授業の雰囲気は、まるで学校のような雰囲気となっています。また、同じクラスメイトもレベルの高い人たちばかりであるので、将来一緒に仕事をするかもしれないハイレベルな仲間と知り合ったり、様々なことを話し合ったり議論を深めたりすることができる、とても貴重な機会であるとも言えます。
必要単位数はどれくらい?
補習所では、3年間で合計270単位を取得する必要があります。この単位の取り方の目安としては、1年目は最低180単位必要であり、一般的には200単位以上取ることになるでしょう。
また、2年目は60~70単位程度の取得が、3年目は20単位程度の取得がそれぞれ必要となってきます。「取得単位が足りない」といったことがないように、計画的に取得していくことがおすすめです。
さらに、考査試験というものが全10回開催されており、各試験で最低40%以上、10回の合計で60%という水準を上回る必要があります。この条件を満たさないと、追試を受けなければならないので、要注意と言えるでしょう。
最後に待ち受ける修了考査


最近では修了考査の合格率は5割を切るレベルで合格率は下がってきています。早くて半年前、少なくとも3ヶ月前くらいからは修了考査の勉強は真剣に取り組むことをおすすめしています。
私は予備校で修了考査の会計実務の講師を担当していますが、最近ではIFRSの問題も出題されるなど、問題も相当難しいので覚悟しましょう。
必要単位をすべて取得するだけでは、公認会計士になることはできません。すべての必要単位を取得した後に受験可能となるものが修了考査です。この修了考査を突破することで、正式に公認会計士になることができます。
受験科目は、「会計に関する理論および実務」「監査に関する理論および実務」「税に関する理論および実務」「経営に関する理論および実務」そして、「公認会計士の業務に関する法規および職業倫理」の5科目となっています。
また、合格率に関してみると、以前はおおよそ7割程度と比較的高かったものの、近年は5割ほどまで低下しており、依然と比較して突破することが困難となっています。
そのため、普段仕事で忙しい人についても、有給休暇を取るなどといった対応で、しっかり対策をすることが重要であると言えます。
補習所に通ううえで押さえるべきポイント
 ここでは、補習所に通ううえでの、押さえるべきポイントについて紹介していきます。
ここでは、補習所に通ううえでの、押さえるべきポイントについて紹介していきます。
クラスメイトとの交流
1点目は、クラスメイトとの交流についてです。
ただ一人で黙々と授業を受けているだけでは、補習所での実りある3年間を最大限に生かせないでしょう。
今後、一緒に仕事をするかもしれないクラスメイトとのコミュニケーションを取って仲良くなっておくことで、素晴らしい人脈を築くことができ、いざというときにおいても、とても頼りになる可能性もあるでしょう。
このような観点からも、できるだけ多くの人と交流することをおすすめします。
きちんと単位を取りきる
2点目は、きちんと単位を取りきるということです。
単位に関する注意点としては、単位を目安通りに取ることが大事と言えます。理由としては、1年目での単位取得が少ないと、2~3年目で過年度の単位を取る必要があり、その際にはお金が発生してしまうことが挙げられます。
また、3年目の講義はそもそも数が少ないため、取り逃すとアウトの可能性が高いので、注意する必要があります。
費やした時間やお金が無駄とならないように、計画的に単位を取得するようにしましょう。
節度を持った行動を
3点目は、節度を持った行動を心がけるということです。
上記で、補習所の雰囲気は学校のようなものと紹介しましたが、あくまで社会人としての振る舞いが求められています。学生気分なまま、場をわきまえた行動をとらないと、処分されてしまう可能性もありますので、注意しなければなりません。
服装についても、スーツなど場をわきまえた服装で行くのがベストです。さらに、場を踏まえたふさわしい行動を見極める能力は、就職した後も重要な能力であることから、このような場面で身につけておくことが大事であると言えるでしょう。
公認会計士の補習所についてのまとめ
公認会計士の補習所についてのまとめ
- 公認会計士予定者が正式に公認会計士と認められるため3年通う必要がある
- 定期的な考査のほか、修了考査に合格する必要がある
- 知識を学ぶという観点のほか、将来の人脈づくりという観点からも、積極的に取り組むべきである
今回は、公認会計士の補習所について、様々な観点から解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事が、公認会計士を目指している人たちにとっての参考情報の1つとなれば幸いです。