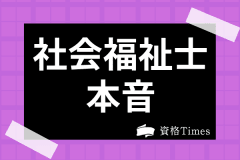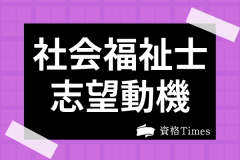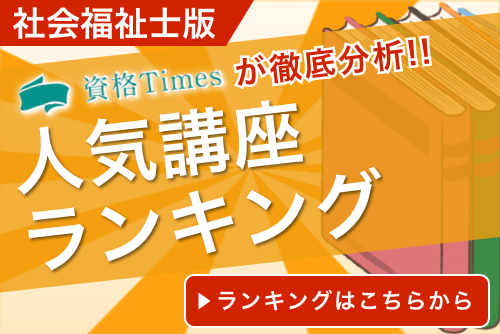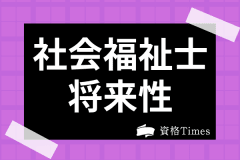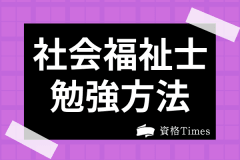社会福祉士の合格率が低い理由は?推移や不合格者の特徴から実際の難易度を考察!
更新
「社会福祉士の合格率はどうして低いの?」
「不合格者の特徴は?実際の難易度はどのくらい?」
などと疑問をお持ちの方もいるでしょう。
社会福祉士試験の合格率は27%前後で、福祉系国家資格の中で最難関の部類に入ります。しかし、国家資格の中では特別難しい試験とは言えません。
今回は社会福祉士の合格率が低い理由について、合格率の推移や不合格者の特徴、実際の難易度を含めて解説します。
これを読めば、社会福祉士の合格率がどうして低いかがよく分かるはずです。
社会福祉士の合格率が低い理由をざっくり説明すると
- 18科目の対策を行わなければいけない
- 合格基準が厳しい
- 勉強時間の確保が難しい方が多い
社会福祉士試験の合格率の推移

社会福祉士は福祉のプロフェッショナルに与えられる国家資格です。
ソーシャルワーカーとも呼ばれ、様々なハンディキャップを持った人たちの相談に乗ったり、日常生活の支援を行います。
特別養護老人ホームや児童相談所、障害者支援施設など、様々職場で資格を活かして働くことができます。
しかし、取得するメリットが大きい国家資格ではありますが、取得するのは困難です。
以下は2018年~2022年の過去7年間で実施された試験の合格率の推移を表したグラフになります。
社会福祉士試験の合格率は例年27%前後であり、福祉系国家資格の中では最も難易度が高いと言われています。
どうしてこれほどまでに合格率が低いのかについては後述の内容を参考にしてください。
他の福祉系国家資格やケアマネと合格率を比較
社会福祉士と他の福祉系国家資格やケアマネージャと比較してみましょう。それぞれの合格率は以下通りです。
| 資格 | 合格率 |
|---|---|
| 社会福祉士 | 27%前後 |
| 介護福祉士 | 70%程度 |
| 精神保健福祉士 | 60%程度 |
| ケアマネージャー | 10%〜20%程度 |
上記を見ると、社会福祉士試験は福祉系国家資格の中では最難関ですが、ケアマネージャーよりは合格しやすいと言えるでしょう。
決して簡単な部類ではありませんが、手がつけられないほど難しくはありません。
社会福祉士試験の合格者層
社会福祉試験合格者の男女比を見ると、男性が約34%、女性が約66%であるため、男女比は1:2程度です。
また福祉系大学等の卒業者が約57%、養成施設の卒業者が約43%なので、福祉系大学出身者の方が割合的には割合的には若干多いでう。
年齢層を見ると、合格者の半数以上が30歳以下ですが、30代や40代で合格している人も4割近く存在します。そのため、あまり年齢は関係ない資格と言えるでしょう。
社会福祉士試験の合格率が低い理由6選

以下では社会福祉士試験の合格率が低い理由を6つ紹介します。
出題範囲が非常に広い
社会福祉士試験では以下の18科目から出題がなされます。
- 人体の構造と機能及び疾病
- 心理学理論と心理的支援
- 社会理論と社会システム
- 現代社会と福祉
- 地域福祉の理論と方法
- 福祉行財政と福祉計画
- 社会保障
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 低所得者に対する支援と生活保護制度
- 保健医療サービス
- 権利擁護と成年後見制度
- 社会調査の基礎
- 相談援助の基盤と専門職
- 相談援助の理論と方法
- 福祉サービスの組織と経営
- 高齢者に対する支援と介護保険制度
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
- 就労支援サービス
- 更生保護制度
上記の中には日常生活では馴染みのない専門用語や制度が登場する科目も多いので、それらを大量に暗記するのは大変です。
合格基準が厳しい
社会福祉士試験に合格するには、以下の2つを同時に満たす必要があります。
- 問題の総得点の60%程度を基準に、問題の難易度で補正した点数以上の得点
- 18科目全てで得点する
1科目でも0点だと不合格になる
社会福祉士試験の合格ラインは、約60%以上の正答率と18科目の全てで1点以上得点することです。
なお、総得点に対する合格ラインは、毎年問題の難易度によって変動します。
全体の60%以上はまだしも、18科目全ての対策を行うのは困難です。得意・不得意に関わらず、満遍なく得点する必要があるので、苦手克服が課題になるでしょう。
一度で全科目に合格する必要がある
社会福祉士試験の合格ラインは全体に対して設けられており、各科目に関する基準はあくまで足切りでしかありません。
つまり、科目ごとに合格が決まるのではないため、一度に全科目の対策が必要であるということです。
例えば保育士試験などでは、科目単位で合格が判定され、再受験の際は合格した科目を受験する必要はありません。よって試験勉強の負担が幾分か軽減されます。
一方で社会福祉士の場合は、一度で18科目全てに合格(1点以上)しなければならないのです。
勉強時間の確保が難しい
社会福祉士試験は科目数が多く、合格基準も厳しいため、合格するには相当の勉強時間が必要です。
受験者の約半数が社会人
以下は社会福祉士試験の合格者数を年齢層別にまとめたものです。
| 年齢 | 合格者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 30以下 | 7,081人 | 43.3% |
| 31~40 | 2,865人 | 17.5% |
| 41~50 | 3,558人 | 21.8% |
| 51以上 | 2,834人 | 17.3% |
上記を見ると、社会福祉士試験の合格者の約半数は31歳以上であることが分かります。つまり働きながら合格を目指す人が多いということです。
また合格者には女性が多いため、家事や介護をこなしながら受験する人も大勢いると考えられます。
そのため、忙しくて十分な試験対策ができないまま受験し、良い結果が出ない受験者も例年一定数存在します。
実務経験との両立が簡単でない
社会福祉士試験の受験資格は以下の3つです。
- 大学等で指定科目を履修
- 短大等で指定科目を履修し、1〜2年の実務経験を積む
- 高卒等で実務経験を積み、養成課程を修了する
上記より、基本的には指定科目の履修と実務経験の両方が必要になることが分かります。
実際には実務経験を積みながら、通信制もしくは定時制の学校で指定科目を履修するというスタイルが多いです。
試験に合格するには実務経験及び指定科目の履修と試験勉強を両立させないといけないので、かなり大変と言えるでしょう。
他の国家資格とダブル受験する
社会福祉士と精神保健福祉士では、出題範囲中11科目が共通しているので、両者をダブル受験することも可能です。
ただし、両方の対策を同時に行うには、勉強時間の確保やスケジュール管理などが課題になります。
ちなみに精神保健福祉士は、精神に障害のある人の訓練や社会復帰の手助けを行うための国家資格です。
勉強のやり方が適切でない
働きながらで余裕がないこともあり、非効率な勉強方法で結果が出ない受験者も大勢います。
非効率な勉強をしている
社会福祉士試験は出題範囲が広いため、効率よく勉強を進める必要があります。
限られた勉強時間内で合格基準点を突破するには、全てを満遍なく対策するのではなく、頻出範囲を中心にメリハリのある勉強をしなければなりません。
働きながらやる気を維持するのは難しいですが、資格取得後の未来を想像するなどの工夫をして、上手くモチベーションを維持することが必要です。
試験当日に実力を発揮できない
社会福祉士試験は1問1点・150点満点のマークシート方式で実施されます。問題数が多いため、マークミスで失点する受験者も多いです。
また試験は冬に実施されるため、体調管理に失敗する受験者も例年一定数存在します。特にインフルエンザには注意が必要です。
さらに仕事や家庭の事情で試験を欠席しなければならないこともあるでしょう。
一つの科目で失敗し、それを次の科目に引きずってしまうという受験者も多いです。社会福祉士試験では18科目から出題されるので、引きずっていては力を発揮できません。
そのため、試験当日は気持ちの切り替えなどメンタル面のコントロールも必要になるでしょう。
本気でない受験者がいる
社会福祉士試験には例年多くの受験者が試験に臨みますが、その中にはあまり意欲的ではないお試しの受験者も存在します。
大学からの指示で渋々受験する福祉系の学生や勉強はしていないが受験資格があるから試しに受けてみる社会人など、一定数の受験者はあまり本気ではありません。
社会福祉士試験は年に1回しか実施されないので、受験資格があればとりあえず受けておこうと考える人は多いです。
そのため、そうしたお試しの受験者の存在が合格率を下げる要因になっているとも考えられます。
本気で勉強して試験に臨む者でも多忙で満足に対策ができない人も多いので、万全な状態で受験する人が少ない試験とも言えるでしょう。
試験の難易度が上がっている?

以下は過去5年間における社会福祉士試験の合格基準点をまとめたものです。
| 合格基準点 | |
|---|---|
| 令和4年度 | 90点 / 150点 |
| 令和3年度 | 105点 / 150点 |
| 令和2年度 | 93点 / 150点 |
| 令和元年度 | 88点 / 150点 |
| 平成30年度 | 89点 / 150点 |
上記を見ると、合格基準点は例年ほぼ一定であることが分かります。合格基準点は試験の難易度に応じて変動するので、難易度自体もあまり変わらないということでしょう。
令和5年度試験でも難しいと感じるような問題が出題される可能性はありますが、極端に試験問題が難化するということはないでしょう。
基本的には試験の難易度を予想するより、どんな問題でも余裕で合格できるように対策しておくのがおすすめです。
試験対策では総得点の60%(90点 / 150点)は最低でも取れるような勉強を行いましょう。
社会福祉士の実際の難易度
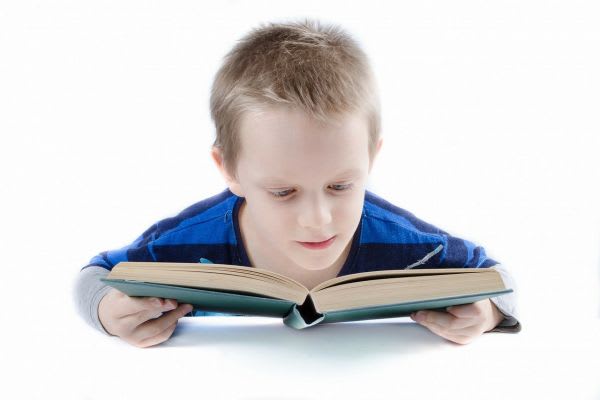
ここからは社会福祉士の難易度を合格率以外の観点からお伝えします。
国家資格の中では難しくない
合格率こそ比較的低いものの、国家試験の中では社会福祉士は難しい部類ではありません。
受験に年齢制限もないので、きちんと勉強すれば誰にでも合格するチャンスがあります。
ちなみに社会福祉士試験の偏差値は57程度で、偏差値で見ると第3種電気主任技術者や宅建士と同程度の水準です。
決して簡単な試験ではありませんが、司法試験や公認会計士試験など超難関の国家試験と比べれば、それほど難しい資格ではありません。
学校選びが重要
受験するには指定科目を履修するための学校に通う必要があります。学校を選ぶ際は以下の内容を参考にしてください。
知名度だけで選ばない
有名な大学なら必ず良い教育が受けられるとは限りません。また合格者数は多くても合格率はあまり高くない可能性もあります。
そのため、知名度だけで何となく学校を選ぶのはやめましょう。
カリキュラムなどを確認して、社会福祉士関連の指導ノウハウがきちんと備わっているかどうかを判断するべきです。
自分に合った学校を選ぶ
WEBで映像授業を何度も見返せる、講師の人柄を含めて教室の雰囲気が良いなど、学校にはそれぞれの特色があります。
そのため、自分の性格や都合に合った学校を選ぶことが大切です。資料請求や学校見学などで、自らに最適な学校を選びましょう。
勉強時間は300時間程度必要
社会福祉士試験に合格するには、300時間程度の勉強が必要と言われています。つまり毎日2時間勉強したとしても、半年程度はかかる計算です。
先述した通り、社会福祉士試験を受験するには実務経験を積みながら、指定科目を履修しなければなりません。毎日2時間も勉強時間を確保するのは難しいと言えます。
そのため、1日にどのくらいの勉強時間が取れるかを考え、試験日から逆算して余裕のある学習スケジュールを立てるのが良いでしょう。
社会福祉士試験に合格するには
社会福祉士試験に合格するには、意欲的に学習に取り組み、そのモチベーションを試験当日まで維持することが重要です。
また勉強に集中できる環境作りにもこだわりましょう。
社会福祉士試験は出題範囲が広いので、特に専門用語や制度内容の暗記は計画的に取り組むべきです。
さらに過去問演習を通して、出題傾向や自分の苦手箇所を把握し、得点能力を高めることも重要になります。
基本的には全体で60%を取れば合格できるので、満点を狙う必要はありません。自分の得意・不得意を把握し、弱点を克服しつつ長所を伸ばす戦略を立てるのがおすすめです。
独学で強行しないことも大事
社会福祉士は合格率は福祉系資格の中でも低いほうであり、試験科目数も豊富で合格点もそれぞれ定められていることから、独学で不十分な学習を進めてしまうと合格から遠のいてしまう可能性が高いです。
よって、まんべんなく学習を進められるか不安を抱えている人は、通信講座を使ってスキのない学習を進めていくことをおすすめします。
合格に近づくための要素をしっかりと網羅していることから、独学よりもはるかに効果的に勉強を進められるでしょう。
特にユーキャンの社会福祉士講座は、2012年から2021年までの10年間で4,130人もの合格者を輩出している実績抜群の講座であることから、対策の際はユーキャンの通信講座を使うことをおすすめします。
教材のわかりやすさはもちろん、サポート内容も充実していることから、初めての人でも安心して学習を進められることから、多くの人にお勧めできる講座であるといえます。
試験当日の注意点
18科目全てで得点すれば合格のチャンスがあるため、出来が良くない科目があっても最後まで諦めずに取り組むことが重要です。
試験時間は240分ですが、150問が出題されるのであまり余裕はありません。分からない問題は飛ばして、スピーディな解答を心がけましょう。
150問中50問程度は間違えても余裕で合格できるので、上手くいかない箇所があっても焦ってはいけません。他の科目で挽回できるチャンスがあるので先に進むべきです。
またマークミスで失点するのはもったいないので、塗り間違いを含めて見直しを十分に行うようにしましょう。
社会福祉士資格を取得するメリット

社会福祉士資格を取得すれば、専門知識の証明になるため、相談者からの信頼を得やすくなります。
就職や転職においても即戦力と見なされるので、採用される確率も上がるでしょう。
社会福祉士の勤務先は福祉施設や医療施設、行政機関など多岐に渡ります。資格を取得すれば、勤務先の選択肢が増えるので自分の希望に沿った働き方が可能です。
また社会福祉士の平均年収は480万円程度と言われており、収入が安定している点も魅力的です。中でも特別養護老人ホームで働く社会福祉士の年収は高いと言われています。
このように社会福祉士を取得するメリットは実に豊富です。そのため、試験の合格率は低いですが、挑戦する価値は十分にあると言えるでしょう。
社会福祉士は名称独占資格
社会福祉士は、医師や看護師のような「業務独占資格」ではなく、いわゆる「名称独占資格」です。
そのため、社会福祉士を名乗って活動することは資格の保有者にしか認められていません。ただし、資格がなくても生活相談員などとして働くことは可能です。
先述した通り、社会福祉士の合格率は低いので、「社会福祉士」という名称には大きな価値があります。
資格を取得すれば、収入面や待遇面などで様々な恩恵が受けられるでしょう。
社会福祉士の合格率が低い理由まとめ
社会福祉士の合格率が低い理由まとめ
- 試験範囲がやたらと広い
- 合格基準が厳しい
- 時間的余裕のない受験生が多い
- 勉強方法が知られていない
- 本番でマークミスする人も
- お試しの受験者も多い
社会福祉士の合格率が低い理由について解説しました。
社会福祉士試験は出題範囲が広く、18科目全てで得点しなければいけないという合格基準の高さもネックになります。
また実務経験と指定科目の履修が必要であり、仕事や家事をしながら合格を目指す人も多いので、勉強時間の確保が難しいという理由もあります。
しかし、お試しの受験者が一定数いることもあり、国家資格の中では特別難しい試験ではありません。年齢制限もないため、きちんと勉強すれば誰でも合格できます。
独学での勉強が不安という場合は、通信講座を活用するのもおすすめです。効率的に勉強し、一発合格を目指しましょう。