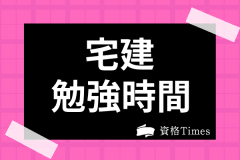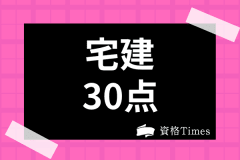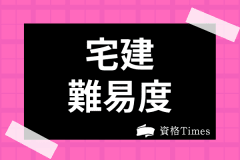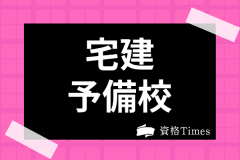【2025年最新版】宅建試験の合格点は?今後の合格ラインの推移を予想!
この記事は専門家に監修されています
宅建士
関口秀人
「宅建の合格点は何点?」
「過去のボーダーラインはどれくらいだった?」
「今後の合格ラインはどうなる?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
宅建の合格点や合格ラインは、受験生にとって最も気になる情報の一つではないでしょうか。
宅建は誰でも簡単に受かるような試験ではありませんが、合格点の背景にあるものを知り、しっかり対策することで十分に合格を狙えます。
ここでは宅建試験の合格点について、今後の合格ラインの推移を予想しながら徹底的に考察していきたいと思います。
この記事を読み終わる頃には、宅建の合格ラインがイメージできるはずです!
宅建の合格点をざっくり説明すると
- 宅建の合格点は年度ごとに変わリ、試験は相対評価に基づく
- 合格ラインはあらかじめ決まっているわけではない
- 過去10年間のボーダーラインは31点~38点である
- 今後、合格基準点が上がり続けることは考えにくい
このページにはプロモーションが含まれています
宅建試験の試験について

宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引の専門家です。土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんをする際に、宅建士は不動産に関する知識の乏しいお客様が不当な契約を結ばないよう重要事項を説明します。
宅地建物取引業を行うには、一定数以上の宅建士を置く必要があります。この宅建士に認定されるためには宅建試験に合格しなければなりません。
宅建試験は年一回、10月の第3日曜日に開催され、50問を2時間で解きます。学籍・国籍・年齢などの受験資格制限は一切ありません。
試験科目は、権利関係・宅建業法・法令上の制限・税金その他の4つに別れており、試験形式はマークシート式です。
宅建士資格試験は、毎年20万人以上が受験しており、非常に人気な国家資格であると言えるでしょう。
宅建の配点・合格点

宅建の合格率は15%から17%の間を推移しており、比較的難しい国家試験であると言えるでしょう。
ここでは宅建の配点・合格率や合格点の推移など、試験の実態についてみて行きたいと思います。
宅建試験は50点満点
宅建士試験の出題数は50問で試験時間は120分です。
出題形式は、4つの選択肢から1つを選ぶマークシート式となっており、配点は1問1点 となっています。
宅建士試験の出題科目と配点は以下の通りです。
| 出題科目 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 権利関係 | 14問 | 14点 |
| 宅建業法 | 20問 | 20点 |
| 法令上の制限 | 8問 | 8点 |
| 税金その他 | 8問 | 8点 |
宅建業法は、4科目のなかでも分かりやすい上に、配点が高く出題数が多いです。したがって、最初に宅建業法から勉強するのがおすすめです。
このように、配点を意識して学習を進めると良いでしょう。
続いて、宅建士試験の合格点についてみていきましょう。
直近12年の宅建の合格点の推移
直近12年の受験者数、合格率、合格点の推移を以下の表に示しました。
| 年度 | 受験者数 | 合格率 | 合格点(一般受験者) |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 195,515人 | 17.9% | 33点 |
| 2010年 | 186,542人 | 15.2% | 36点 |
| 2011年 | 188,572人 | 16.1% | 36点 |
| 2012年 | 191,169人 | 16.7% | 33点 |
| 2013年 | 186,304人 | 15.3% | 33点 |
| 2014年 | 192,029人 | 17.5% | 32点 |
| 2015年 | 194,926人 | 15.4% | 31点 |
| 2016年 | 198,463人 | 15.4% | 35点 |
| 2017年 | 209,354人 | 15.6% | 35点 |
| 2018年 | 213,993人 | 15.6% | 37点 |
| 2019年 | 220,797人 | 17.0% | 35点 |
| 2020年(10月) | 168,989人 | 17.6% | 38点 |
| 2020年(12月) | 35,258人 | 13.1% | 36点 |
| 2021年(10月) | 209,749人 | 17.9% | 34点 |
| 2021年(12月) | 24,695人 | 15.6% | 34点 |
| 2022年 | 226,048人 | 17.0% | 36点 |
上記のデータによると、平成28年度~令和2年度の合格基準点は35点を超えており、ここ数年の合格基準点は高い傾向にあることが分かります。
特に令和2年度(2020年度10月)の試験は合格点が38点という過去最高の記録を更新していることから、合格点の上昇傾向は近年のトレンドであるといえるでしょう。
合格率は10年間で15%から17%の間を維持しており、合格率については変動が小さいといえます。
数値をみても、合格基準点が高くても低くても、合格率にその影響が及ぶわけではなく、合格基準点と合格率には相関がないことが分かります。
2023年試験の合格点はどれくらい?
2016年度以降、合格点が35点前後で推移していることから、2023年試験も7割超の得点率が一つ合格の目安となることが予想されます。
また、コロナの影響で不景気が続くと予想される中、資格試験を検討する人は増加傾向にあります。
受験者全体のレベルは引き上がっているため、これらを加味すると8割の得点獲得を狙って学習を進めることをおすすめします。
2023年度宅建士試験の合格点を本気で予測

ここでは宅建試験の今後の合格点や合格ラインを中心に考えていきたいと思います。
今後の合格基準点はどうなる?
2023年度は民法大改正の余波が収まったことから、試験内容が急激に変わるということはほぼないでしょう。
また、試験は宅建士として必要な専門知識を中心に身につけてほしいという意図があることから、難問が多数続出して合格点を大きく下げてくることも考えにくいでしょう。
よって、今後の合格点は35点前後で推移を続けていくものと思われます。
ただ合格者数は、不動産業界などで宅建士の需要がどのくらい見込まれるか、国が宅建士をどこまで増やそうとしているかによっても、左右されていきます。
合格者数は合格基準点に影響してくるので、不動産業界全体のマクロな状況にも目を光らせておくことも必要です。
2023年度宅建士試験の合格ラインは?
今後の合格ラインはどうなっていくでしょうか?
2021年試験は10月・12月試験どちらも34点が合格点となりました。
ここ数年の傾向を見ると、35点±1〜2点の合格点が続いていることから、来年度の合格点の合格点もこのレンジで収まることが予想されます。
したがってこれまでの傾向から単純に予測すると、2021年度の宅建士試験の合格ラインは34点~37点となります。
なお、問題の作成者は、過去の受験生の正答率など、あらゆるデータから、易しい問題や難しい問題を分析しています。極端な話をすれば、試験は簡単にすることも難しくすることもできるのです。
しかし宅建士のレベルを一定に保つためにも宅建試験の信頼性が損なわれることがあってはなりません。「○%の合格率で△△点の合格基準点」という形で想定をして、それに合わせて問題を作っているようにも考えられます。
結局のところは、実際に試験を見てみないとわからないのが現状であることから、予想だけを鵜呑みにせず、確実に合格できる点数取得を目標に勉強に邁進していく必要があります。
今できる対策方法
合格ラインを突破するために計画的に対策していくことは重要です。
以前は37点を目指す勉強法でも十分合格までたどり着けましたが、2020年度に38点という過去最高得点を記録しました。
これらの結果から、従来通り40点という得点を一つの指標として勉強するのが安全策であるといえるでしょう。
40点以上を得点するには、民法などの難しい科目であっても、ある程度得点する必要があります。試験の配点や合格基準点から考えても、特定の科目だけに偏って勉強するのはおすすめできません。
合格するためには、たとえ苦手科目があっても捨て科目を作らずに、まんべんなく勉強することが肝心です。 各科目の基本問題を確実に解けるようにすることが大切です。
そもそも基礎知識をつけることが、国家試験の意義です。資格を取得することの目的を意識して、宅建士になるために必要な知識を習得していこうとする姿勢が大事だといえるでしょう。
宅建の合格基準点を見る際の注意点
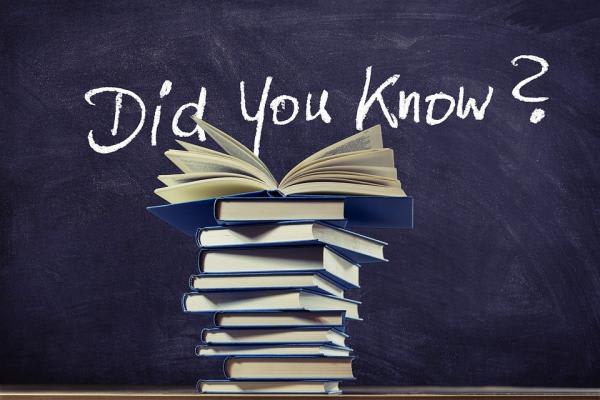
宅建は相対評価の試験です。合格基準が絶対評価の試験とは異なる部分があり、合格基準点を見るときにも注意が必要です。
合格基準点の決まり方
「宅建は何点取れば合格できる?」といった疑問があるかもしれませんが、宅建の合格点は試験前の段階では分かりません。というのも宅建試験は試験終了後に合格基準点が決まるからです。
宅建は相対評価の試験といわれています。スクール関係者や受験生の間では 「合格者数と合格率を一定のラインにするために、合格基準点を調整している」という予測もあるようです。
宅建士試験では合格点が事前に設定されていないので、合格基準点はその年ごとの試験問題の難易度に左右されることになります。具体的には、問題が難しければ合格基準点が低くなり、問題が易しければ高くなります。
相対評価の試験なので、受験生の質が上がって合格点が40点以上に跳ね上がるのではないかと心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、その点は心配しすぎる必要はありません。
問題を作成する側も、過去のデータ等から受験生が簡単に解けそうな問題や難しい問題などを分析して、合格率に対して合格基準点が妥当な範囲内に収まるように意識しているといえるでしょう。
合格基準点と試験難易度の関係を誤解しない
「合格基準点が高いと試験難易度も高い」と勘違いする方もいらっしゃいますが、合格基準点と試験難易度は比例するわけではありません。
では双方の関係性はどのようなものなのでしょうか?
たとえば、受験生が解けないような難問が多く出題されれば、試験の難易度は上がります。そして、試験が難しければ合格基準点は低くなるはずです。
この考え方からすると、むしろ合格基準点が高いということは、多くの受験生が得点しやすかったということであり、試験自体は簡単だったという見方もできます。
しかし、試験の難易度だけでなく、他にも受験生のレベルの高さや受験者数などが、合格基準点に大きく影響します。
したがって、合格基準点だけを見て試験の難易度を判断することはできないと言えるでしょう。
宅建士試験は簡単なのか

宅建の合格率は年によって異なりますが、約15%と低いです。毎年8割以上の受験生が落ちているという事実を鑑みると、決して簡単な試験であるとは言えません。
一方で試験は過去問の類題が多く、合格までに必要な勉強時間は他の有名国家資格よりも短いため、宅建の難易度は「やや低い〜中程度」であると言えるでしょう。
ここでは、宅建試験合格率が低い原因について解説して行きます。
宅建試験の難易度は上がっている?
宅建の受験者数は年々増加しているにもかかわらず、合格率に大きな変化はありません。
したがって、数値上は難易度の変化は読み取れない、つまり難易度は一定であると判断できます。
一方で近年では、宅建の士業化や通信講座の普及などに伴い、レベルの高い受験生が増加しており、以前より合格しにくくなっているのが実態です。
宅建は他の国家資格よりも取得しやすい部類に入りますが、ある程度の勉強時間を確保して計画的に取り組まなければ、合格するのは難しいといえます。
また、宅建士の質を一定に保つためには、それ相応の合格ラインを設定する必要があります。
受験者の上位15%に入るためには、熾烈な競争に勝ち抜くべく試験勉強をする必要があり、必然的に受験生のレベルも上がってきます。
すなわち、合格基準点が上昇するのも、得点率の高い受験生が増えたことが原因だと推測されます。
それでは、なぜ宅建の合格率がこのように低いのかをみていきましょう。
試験範囲が広い
合格率が低い一つの原因として、試験範囲の広さがあげられます。不動産に関する幅広い知識が求められるのです。
それでは各科目について、みていきましょう。
宅建業法
宅建業法では重要事項の説明や37条書面(いわゆる契約書)など、宅建士になってからも特に必要となる内容が聞かれます。
「免許」「宅地建物取引士」「営業保証金」など出題の多い分野が毎年固定されており、比較的得点しやすい科目です。
配点が最も高いため、ここで点数を稼ぐことが大切であると言えるでしょう。
権利関係
この科目の出題範囲は民法、借地借家法、区分所有法及び不動産登記法などです。
民法は理解を問う問題が多く出題される一方で、勉強範囲がとても広いため最も対策に時間がかかります。しかし権利関係の配点も高いため、しっかりと学習することが必要となります。
法令上の制限
この科目では土地計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法について聞かれます。
理解はしやすいですが、様々な事項や数字など一定量の暗記をしておかなけれななりません。論点をおさえて効率的に勉強することで得点しやすくなるといえるでしょう。
税・その他
不動産取得税や登録免許税などの税金や土地・建物などから出題されます。
主に税金についての知識から地価公示法、不動産鑑定評価基準について問われ、最新の統計数値などをおさえておかなければなりません。
範囲が広いため基本をおさえて、過去問などから論点を絞り込み学習しましょう。
受験の機会が一年に一度しか無い
宅建の試験の受験のチャンスが一年に一度しかないため、不合格となってしまったら、次回の受験までモチベーションを保つのが難しいと言えるでしょう。
再挑戦して合格する人が減ってしまうことが、合格率が低い原因であると言えるでしょう。宅建は特に初見の方には難しい試験となっており、一発合格が出来るとは限りません。
不合格になってしまった場合、例えば数ヶ月後に再度受験する機会があるならば勉強のモチベーションも保ちやすいですが、一年後の試験の為に勉強を続けるのには相当な根気が必要です。
宅建に合格するには、諦めずに勉強を続ける強い覚悟が必要であることを覚えておきましょう。
おすすめの勉強法

合格点に届くためには、勉強法を工夫する必要があります。ここでは、おすすめの学習法を紹介していきたいと思います。
過去問をしっかりとやり込む
宅建試験に合格するには過去問をやり込んでおくことがカギとなります。
過去問の問題と解答を暗記するのではなく、条文や判例など、重要論点を理解しておくことが大切です。違った角度から出題されても、論点が分かっていれば対応することができます。
過去10年分は網羅すると良いでしょう。また過去問に取り組む際は、試験時間を想定して時間内に解き切ることを意識しましょう。
暗記が多いため対策は早めに
宅建資格試験は覚えることや理解すべき法律の基本型が多く、対策をするのに時間がかかります。直前期に過去問を何周もできるようにも、早めの時期から対策しておくことが肝心となっています。
試験は10月中旬に実施されるため、独学であれば前年の10月から12月には勉強を開始しておくと良いでしょう。
ネット上では超短期間の合格体験記もありますが、無理に短期間で勉強を終わらせようとすると、知識が定着できず不合格になってしまうので、それらは参考程度に見ておきましょう。
無理に独学せずプロの力も頼ろう
独学での学習にこだわって何年も連続で不合格になってしまうのはあまり賢い選択ではありません。
もしも自分だけの力では合格は難しいと感じたのであれば、通信講座(オンライン講座)等の受講も検討するのが良いでしょう。
通信講座の中には合格率が平均の4倍以上という圧倒的な合格実績を誇るものもあります。きっとあなたの学習を大きく助けてくれるでしょう。
宅建の通信講座については、以下の記事でランキング形式で紹介しています。
宅建の合格点まとめ
宅建の合格点まとめ
- 宅建は相対評価に基づく試験で、合格点は受験者数や受験生のレベルにも影響される
- 数値上では、試験の難易度は一定であるが、近年合格は難しくなってきているのが実態
- 今後の合格ラインは34点~37点(高くても37点)だと推測される
- 合格基準点の上昇を心配しすぎず、今できる勉強をしよう
ここまで宅建の合格点について詳しく考察してきました。試験勉強にぜひ役立てて頂きたいと思います。
合格ラインを突破できるように、しっかりと対策して試験本番に臨んでください。応援しています!