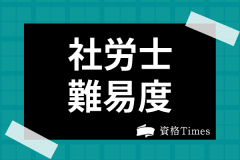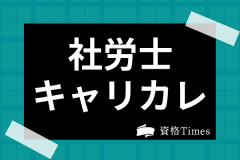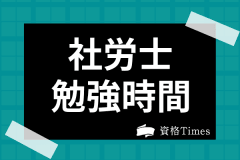社労士の開業は失敗しやすい?廃業する人の割合や特徴を徹底分析!
この記事は専門家に監修されています
社労士
のんびり社労士いけい
「社労士の資格を取って開業するのに興味があるけれど、失敗してしまうリスクはどのくらいあるの?」
そう不安に思う人も多いのではないのでしょうか?
「士業」といわれる仕事の中でも人気の高い「社労士(社会保険労務士)」。毎年3,500人程度の合格者が出ており独立開業する人が多いのが特徴ですが、開業に失敗してしまう人も多いのが実情です。
この記事では、社労士としての開業が失敗してしまう原因と、失敗しない為の注意点について解説していきます!
社労士開業のポイントをざっくり説明すると
- 独立し開業する人は多いが、失敗し廃業する人も多い
- 失敗する人にはいくつかの共通点がある
- 気持ちの持ち方と仕事への向き合い方が成功への鍵
このページにはプロモーションが含まれています
社労士資格取得後の進路は「開業」が多い
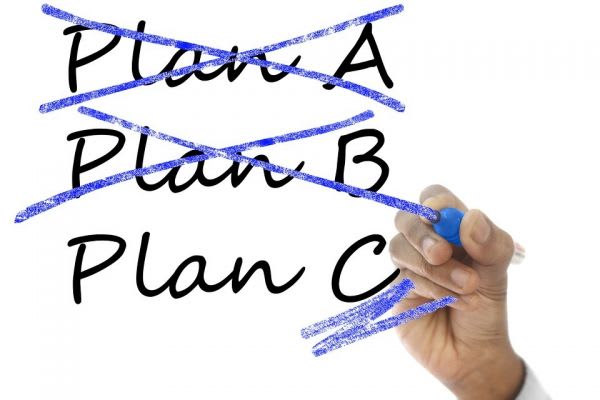
社労士資格取得後の進路としては、「社労士事務所への就職や法人の設立」「一般企業の人事部等への勤務」「開業」の大きく3パターンに分かれます。
しかし、実際には約半数の人が開業を選択すると言われています。
それには社労士事務所の求人が少ないといった事情等もあるでしょうが、何より社労士は他の士業と比べて顧問契約が取りやすく、売り上げが安定して稼ぎやすいといった面があるからです。
社労士資格が人気を博している背景の一つにはそのようなものがあります。
ただし、当然のことながら開業すればとにかく稼げる、というわけでは決してありません。稼げるようになる前に、廃業してしまうパターンも多いのが現状です。
社労士の開業が失敗する割合
実は、社労士に限らず士業の開業というのは、ノウハウや人脈がない中で実行してもなかなか上手くいかないケースが多いのです。
士業全体では6割が開業に失敗していると言われ、特に、開業後1~3年以内での廃業が多くなっています。逆に、それ以上続く人たちというのはその後も上手くやっていくケースが多い様です。
社労士の廃業に関してネットで検索すると「3年以内に70~80%が廃業」「10人中9人は廃業する」といった情報が多くあります。
実際には廃業には「高齢での引退」や「死亡廃業」なども理由としてありますから、全ての廃業が「=開業に失敗」というケースではありません。
正確な数字はわからないものの、開業したが数年で廃業するケースもかなり多いであろうことは容易に推測できるところです。
社労士が開業して失敗する原因

開業したが失敗してしまったという人には、いくつかの共通した特徴が挙げられます。
見栄や自尊心を重視する
プライドが高すぎたり、こだわりが強すぎたりすると、周囲からのアドバイスや意見を素直に受け入れられず、事業の成長を自分自身が妨げてしまうことに繋がります。
独立して少人数でやるからこそ、周囲の同業者との意見交換は貴重な機会ですし、お客様の要望に応えてサービスの形を変えていくという様な柔軟性も必要になります。
プライドが高く、自分が困っているときに素直に助けを求めることができない人はピンチがそのまま失敗に直結してしまうことでしょう。
周囲を頼るのが苦手
業務でもトラブルでも、自分だけで解決しようとするのは危険です。
いくら優れた人間でも、有能な社労士であっても、一人の人間がこなせる量は限られています。
人手が足りないなら従業員を雇って仕事を分散するべきですし、従業員がいれば困ったことは相談するべきです。
社労士同士でも、仕事においてそれぞれに得意不得意の分野があるので、それを考えてお互い助け合ったり交流をしたりすることが大切です。
それが出来なければ、いずれパンクしてしまうでしょう。
小さいことの積み重ねができない
多くの場合、起業してすぐはなかなかコンスタントな仕事もなく、地道に営業をしていくことになります。
中には、最初から運良く大きな仕事を任され、成功を収める人もいるかもしれません。
しかし最初に大きなラッキーがあったとしても、それがこの先も永遠に続くことはないでしょう。
その時に、次もその運を期待するのではなく、また、身近にそういう人がいても自分はそれを期待することなく、地道にコツコツ仕事をこなしていくことが必要です。
ありきたりですが、そうした地道な活動や努力によって周囲からの信頼を得られ、そこから仕事が生まれ、持続的な成功と収入の拡大に繋がっていくのです。
運や勢いだけに頼ってしまい小さいことの積み重ねが出来ないと、どこかで躓くことになるでしょう。
自分に合っている仕事ではない
自分がそれを理解しているかどうかは別として、人には「向き/不向き」というのがあります。
向いていないから出来ない、ということではありません。向いていなくても、それを補う努力をして成功する人もいます。
「頑張っているのになかなか上手くいかない・・・」
もし、自分も周りの人もそのように感じている様であれば、そもそも社労士に合っていなかったのかもしれません。
自分の中に、「絶対に出来る」という自信があるかどうかが判断材料になるでしょう。
不安や心配があっても、心の底では「絶対に成功する」と感じているのかどうか、をしっかり考える事が大事です。
もし、冷静にしっかりと考えて、その自信がないと自分が感じているのであれば、それはこの仕事が合っていなかったということでしょう。
失敗はしなくても大成功しない要因
次に、廃業するほど困ってはないが、独立当初に目指していた目標への到達には遠い・・・、という場合の要因を挙げてみます。
値引きにより集客を狙う
競合他社や、とにかく仕事を受注することを意識するあまり安さ勝負に出てしまうことはどの業界でもあります。
しかし、安さを売りにして顧客を大量に獲得しても、膨大な業務を安い給料ですることで忙しくなるだけであり顧客量や労働量とその対価が合わなくなってしまいます。
将来的に事業を拡大した後に、値段を上げにくくなってしまうこともあるでしょう。
専門家としての責任感が甘い
社労士は、専門知識や情報があること自体が仕事なのではありません。
自分が今持っている知識や情報を人の役に立てて、それに見合った報酬をもらうことで、仕事として成立します。
知識を披露することで満足しているのではプロ意識に欠けます。どのようにすれば自分の知識を人の役に立たせ、見合った報酬を得られるかを考える事が重要なのです。
報酬を得ることは「責任」に繋がります。当たり前のことですが、仕事には責任感を持って臨まなければなりません。
行政協力にハマる
行政協力自体がダメなわけではありません。宣伝にもなりますし、新人社労士なら経験を積む、収入を得る重要な場でもあります。
しかし、あまりにもそれに時間を取られてしまうと、社労士の本業である「顧客と契約して顧問先の業務委託を受ける」ことに時間が割けなくなってしまいます。
その結果、社労士としてビジネスを成功させることは出来ませんし、そもそも独立して開業した意味もなくなってしまうでしょう。
開業して失敗しない為に気をつけること
では、開業して失敗しない為にはどのようなことに気をつければ良いのでしょうか。
気持ちの持ち方
できる方法を考える
どうしてできないのか、と「できない理由」ばかり考えていてもできるようにはなりません。その逆で「できる理由」つまり「どうしたらできるのか」を考えることが大事です。
どのようにすれば顧客を獲得できるのかを考え、実行する。上手く行かなければ新たな方法を考えて実行する。この繰り返しです。
これができなければ、自営業ではやっていけません。
自分で考える
開業してから成功までの道のりについて、型に填められたパターンしかイメージできていない、ということはありませんか?
成功に決まったパターンがあるわけではありません。
今までの自分の経験を活かそうと自ら考えることが大切であり、それによって他の社労士との区別がつけられるのです。
考える事を止めて型にとらわれたやり方しかできなければ、他の多くの競合社労士の間に埋もれてしまうでしょう。
宣伝を恐れない
待っているだけでは顧客は来ません。
名刺を配る、DMを送付する、広告を出す、異業種交流会に参加する等、できることはいくつもあります。地域のボランティア活動を毎回必ず手伝う、なんていうのも良いでしょう。
宣伝はこちらの存在を知ってもらうために行うものです。宣伝に失敗しても、本業で失敗するわけではありません。より効果的な宣伝方法を習得していけば良いだけです。
宣伝を恐れず、とにかく実際に行動を起こさないことには何も始まらないのです。
不安定な収入を恐れない
職安や労基署の相談員など、行政協力をしていれば一定の収入は見込めます。
フルタイムかそれに近い勤務であれば、そこそこの生活をしていくのに足りるくらいの給与を得られるかもしれません。
しかし、それで満足していては、事業所を成功に導くことはできないでしょう。
安定的な仕事を減らしてでも、事業に打ち込むことで初めて社労士としての成功を得られるのです。
収入が不安定になることへの恐怖を克服しなければ、社労士として独立開業した意味も無くなってしまいます。
仕事への向き合い方
顧客のことを考える
社労士事務所の顧客となるのは企業です。そして、企業はそこで働く従業員で成り立っています。
ですから、顧客企業のことを考えるときは従業員の事を考えなければなりません。
従業員の中には、現状維持を第一とし、変化を嫌うタイプの人もいます。また、そういうタイプでなくても、基本的に人間は意図の見えないものには拒否反応を示すものです。
就業規則の変更や会社の構造改変などで従業員にとって「変化」がある時にはしっかりと説明することが大切であり、それを怠ってはいけません。
そうすることで企業が目指す方向を従業員も目指せるようになり、組織としての成長に繋がっていきます。
経営者、従業員のどちらの視点も持つ
企業には経営者と従業員の二つの立場があります。どちらの立場の視点も持っていることが、顧客である企業にとって安心材料になります。
経営者には経営者の悩みが、従業員には従業員の悩みがあります。双方の悩みを理解できそれぞれのニーズに応えられる社労士であれば、企業にとっては心強いパートナーとなるでしょう。
物事を捉えるとき、一方に偏った視点ではなく複数の視点で捉えることは、より正確にその物事を判断することに役立ちます。
そのようにしてどちらの立場でも納得のいく内容を提供することで、顧客の満足度も高くなります。
開業失敗後の転職はどうする?

「できるだけのことはしたけれど、廃業してしまった・・・」
さて、そんな時はどうしたらよいのでしょうか。
再就職をする際にも大切なポイントがあるので、ここからはその点をご紹介していきます。
失敗して廃業した時の再就職先
廃業後の再就職先は「社労士事務所」と「その他一般企業」の2つに大きく分けることができます。
社労士事務所に戻る場合
社労士としての仕事を続けたい、という場合はどこかの社労士事務所への就職が第一の選択肢になるかと思います。
その場合は「ブラック企業の存在によって恩恵を受けているところ」が良いでしょう。
ブラック企業とまではいかなくても、労務に何の問題もない、という企業は一部で、多くの企業が何らかの労務問題を抱えています。
また、コンプライアンスに関しては以前よりかなり言われていますが、未だ整備ができていない企業も多いので社労士の需要は増加の傾向が続いています。
そういった状況を把握し、就業規則の整備を積極的に行っている事務所は、今後もしばらくは仕事がなくなることがないでしょう。
社労士にこだわらない場合
社労士にこだわらないのであれば、中小企業やベンチャー企業の人事部門が狙い目です。
大企業だと人事労務部門も細分化していることが多いですが、規模の小さい事業所だと一人が行う業務の範囲が広く、様々な仕事を任されます。
社労士資格を活かした仕事をしながら、他の業務についての経験も積んでいくことができるでしょう。
転職時に気をつけるべきこと
以前の仕事とのつながりを避ける
独立したチャレンジ精神を評価してくれることもあるかもしれませんが、個人事務所を廃業した、というのはやはりマイナスイメージであり転職においてはプラスにはなりにくいと言えます。
同僚にバレてあることないこと噂を立てられたり、悪い評判を広められたりする可能性もあります。
気持ちを切り替えてゼロから新しい気持ちで始められる環境の方が、再スタートには相応しいでしょう。
経歴に空白期間をつくらない
職務経歴に空白期間が生じると、転職が難しくなります。
ヘッドハンティングなどを除いて、一般的に35歳を過ぎると正社員での転職が難しいと言われる中で、独立開業して廃業したとなると年齢的にもかなりのハンディが生じてきます。
廃業整理を行いながらの転職活動は心身共に堪えるものですが、できるだけ経歴にブランクを作らないよう、計画的に活動していく必要があります。
廃業後に再就職先を探すなら
年齢を重ねた後の転職は基本的には難しいとされていますが、社労士であれば独立開業による「実務経験」は転職において有利に働きます。
独立開業で身につけた社労士のスキルを活かすなら 日本最大級の転職エージェントであるリクルートエージェントを利用するのが一番です。
「転職支援実績No.1」であるリクルートエージェントであれば、社労士の仕事をよく理解し、その専門性の高さを正当に評価してくれます。
リクルートエージェントに相談することで、実務経験を持った社労士を即戦力として高年収で雇いたいという企業にもきっと巡り会うことができるでしょう。
無料相談を通じて超ハイクラスな求人も確認できますので、この機会にぜひ利用してみてください!
社労士開業で失敗する人の割合や特徴まとめ
社労士開業で失敗する人の特徴まとめ
- 独立開業する人は多いが廃業する人も多い
- 廃業する人には共通する特徴が見られる
- 成功には気持ちの持ち方や仕事への向き合い方が重要
この記事では社労士の開業について様々な側面から解説してきました。
開業にはリスクも伴いますが、向き合い方次第で良い方向に進めていくこともできるでしょう。
せっかく取った社労士資格です。自分にとって最高・最適な社労士としての在り方を追求してみてはいかがでしょうか。