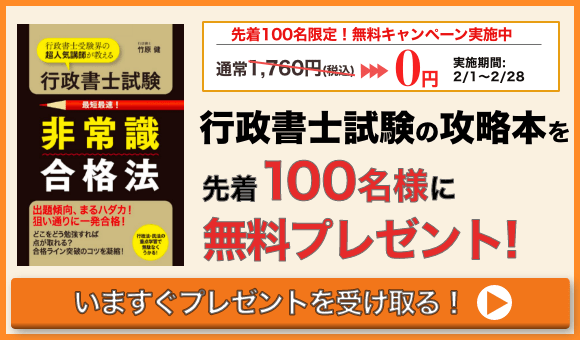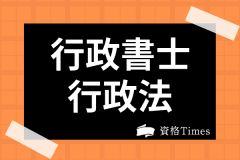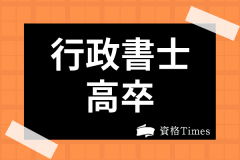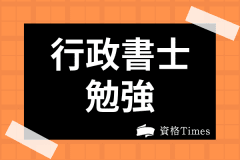行政書士試験の憲法はどんな科目?対策のポイントや目安の勉強時間まで解説!
「行政書士試験の勉強をしているけれど、憲法の効率良い勉強法が知りたい!」
「憲法に苦手意識があってなかなか勉強が進まない・・・」
行政書士試験を受験しようと思っている方の中にはこういった悩みを抱えている人も多いでしょう。
憲法は内容そのものが難しく、苦手意識を持っている人が多い科目です。しかし、他の法律にも関わるのでしっかりと勉強しておく必要があります。
ここでは行政書士試験の憲法について、科目の特徴や出題形式、効果的な勉強方法まで分かりやすく解説します!
正しい勉強法を身に着けて合格を目指しましょう!
行政書士試験の憲法をざっくり説明すると
- 憲法は他の法令を学ぶ上でも重要な科目である。
- 配点も難易度も比較的高いので、時間をかけて勉強する。
- 学習は条文と判例を中心に進める。
このページにはプロモーションが含まれています
行政書士試験の憲法の概要

憲法は日本の最高法規です。その目的は国民ひとりひとりの人権を保障すること。すべての法の基本となる、最も重要な法です。
行政書士試験では「行政書士の業務に関し必要な法令等」の一部として出題されます。行政書士の作成する書類は法に基づいて作られますから、仕事に必要な法の一つということですね。
また、憲法はその他のすべての法の基本となる法です。試験で出題されるその他の法令を学ぶ上でも、この憲法を理解しておくことは重要です。
小学生のころから授業で学ぶので、法学部出身ではない多くの人にとっても馴染み深い憲法ですが、苦手意識を持っている受験生も多いものです。
憲法の出題範囲
日本国憲法は補足を含めると百条以上もあります。国際的には短い方とされていますが、勉強するとなると長いですよね。行政書士試験ではもちろんこのすべてが出題範囲というわけではありませんが、行政の機能を担う上で重要な原則・制度についてはかなり広い範囲が問われます。
行政書士試験で出題される憲法は、「憲法総論」「人権」「統治」の三つに大きく分けられます。
それぞれどのような問題が出題されるのか、みてみましょう。
憲法総論
憲法総論で問われるのは憲法の歴史や基本原理といった基礎事項です。他の二つの項目と比べると、問題数が少なく、難易度の高い問題が出題されやすい傾向にあります。
難しい問題が多いので正解しにくく、出題数が少ないので得点にも結び付きにくいと言われています。それゆえ、勉強の中心にはなりません。
人権
人権は憲法でも定められています。しかし、憲法の条文は決して明確なものではありません。生存権の「健康で文化的な最低限度の~」のように非常に抽象的な表現がされています。
そのため、条文をそのまま覚えることはあまり意味がありません。より重要なのは、裁判所が条文をどのように解釈したのかを理解することです。
統治
統治分野はさらに「国会」「内閣」「司法」の三つに分けられます。人権分野とは異なり、具体的な条文が多いため勉強しやすいでしょう。
統治分野の勉強法は暗記が中心です。条文の細かな定めを正確に覚えることが点数に結びつきます。
憲法の出題形式と配点
行政書士試験は300点満点で行われます。このうち、56点は一般知識という時事問題や文章理解の問題が出題され、残りの244点が法令科目の配点です。
憲法は法令科目の一部で、28点分出題されます。五肢択一式と多肢選択式という2種類の形式で出題されます。それぞれの問題数と配点は次の表の通りです。
| 憲法の出題形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 五肢択一式 | 5問 | 20点 |
| 多肢選択式 | 1問 | 8点 |
五肢択一式が20点分、多肢選択式が8点分です。これは、法令科目の15パーセント、行政書士試験全体でみれば9パーセントに当たります。
数字だけ見ればあまり高くはないかもしれません。しかし、憲法はその他の法の元となる基本です。憲法の科目を捨てて合格するのは難しいでしょう。
憲法は重要度の高い科目
これまで見てきたように、行政書士試験において憲法は出題数が多くはありません。そのうえ、配点も低いです。その一方で出題範囲が広いので、得点効率の低い科目と言えます。
そのため、行政書士試験受験者の中には憲法の勉強を敬遠し、あまり触れたがらない人もいます。この場合、苦手意識をもったまま試験に臨むことになりますね。
しかし、憲法は全ての法の基本です。法律の勉強を進めるうえで憲法の知識が必要になることもあります。
例えば、行政法の勉強には憲法の知識が不可欠です。実際、憲法の勉強をおろそかにしている人は、行政法の勉強だけを行っても点数があまり伸びません。
このように、憲法の理解は他の科目にも影響を及ぼします。配点以上に重要な科目なので、しっかりと対策するのが適切な勉強法と言えます。
行政書士試験における憲法の難易度

難易度は比較的高く対策に時間がかかる
法学部出身の方はご存じかもしれませんが、そもそも憲法という分野は法学の中でも特に難解な科目です。
憲法の知識は義務教育でも習うのでその点では入り込みやすいですが、行政書士試験を突破するためにはより深い理解が必要となります。
また、出題される問題の難易度に差があるという特徴もあります。簡単な問題もありますが、難しい問題もあります。中にはかなりの勉強時間を必要とするなど、ばらつきが大きいのです。
科目としての難解さに加えて、難易度に幅があるという事情が複雑さに拍車をかけています。それゆえ、どの程度勉強すればよいかという線引きが難しく、多くの受験生が苦手意識を抱えたまま試験に臨むことになるのです。
目標点数は18点
行政書士試験には一定以上の点数に満たなければその時点で不合格になる合格基準点、いわゆる足切りがあります。
法令科目は122点、一般知識は24点、総得点は180点の3つをすべて満たすことが合格ラインを突破する条件です。
そのため、確実に合格するためには法令科目だけで166点とることを目標にしたいものです。法令科目で166点取れば、一般知識は合格基準点ちょうどでも総得点に届くことになります。
法令科目の主な得点源は配点の高い民法と行政法ですが、憲法でも60パーセントに当たる18点は取得しておきたいです。
特に、憲法以上に難易度の高い「商法・会社法」といった科目を「捨て科目」にすることを考えると、憲法でもある程度は得点しておくことが望ましいでしょう。
憲法対策におすすめの学習法
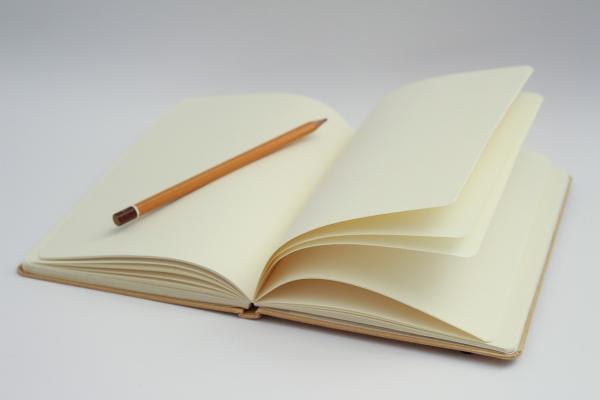
このように憲法は難易度の高い科目ですが、試験に合格することを考えるとある程度の点数を取る必要があります。そのためには正しい勉強法が不可欠です。以下では勉強時間や分野ごとの勉強法を紹介します。
勉強時間の目安
行政書士試験全体に必要な勉強時間はおおよそ600から700時間と言われています。もちろん法学部の方ならもっと短くなるでしょう。
このうち、憲法にかけるのは12パーセントから15パーセントほど。つまり、75時間から85時間が目安です。
配点から考えると少々多すぎるように感じるかもしれません。しかし、これまでも説明してきたように憲法は重要な科目。他の法の理解にも影響するので配点以上に意味をもつのです。
理解度の目標は憲法の基本事項をスラスラと言えるようになること。簡単な問題は一つも落とさずに答えられるようにしておきましょう。
人権分野は理解重視
まず人権分野ですが、理解重視で勉強を進めます。人権関連の条文は抽象的なものが多いので、いわゆる「丸暗記」による学習は問題を解く際にあまり効果を発揮しません。
人権分野のポイントは「判例」です。判例とは裁判所が過去に下した判決のこと。つまり、裁判所が解釈した憲法の意味ですね。
行政書士試験で問われる問題の多くは、裁判所が憲法をどう理解したのかを問うものです。そこを理解していないと解答にたどり着くことが難しくなります。
言い換えれば、判例さえしっかりと理解しておけば大抵の問題はさほど苦労することなく解くことができるとも言えます。
統治分野はまずは暗記してしまう
次に統治分野です。こちらは人権分野とは反対に暗記重視で進めていくことがおすすめです。統治分野の条文は具体的なものが多く、そのまま読んでいても意味が理解できます。
そのため、統治分野は暗記中心で勉強します。試験では暗記量こそがものを言うのです。
試験で出題される内容も、国会等の運営の仕組みのような問題がほとんど。特にひねった問題もなく、知っていれば解ける問題ばかりです。
覚えれば覚えるほど点数が伸びていくので、得点効率が良い分野になります。逆に言えば知らなければ解けない問題ばかりなので、確実に暗記したうえで試験に臨みましょう。
過去問演習は基本中の基本
憲法に限った話ではありませんが、行政書士試験では過去問を活用することがおすすめになります。実際に出た問題だからこそ、試験に役立つ手がかりを見つけられるでしょう。
行政書士試験は試験範囲が非常に広い試験です。あれもこれもと網羅的に勉強すると時間がどれだけあっても足りないため、的を絞って効率よく勉強することが重要になります。
例えば、過去問で繰り返し出題されている問題は自分が受ける際に出題される可能性が高いでしょう。こういった頻出問題は貴重な得点源になります。
また、試験の出題傾向や苦手分野をつかむこともできます。特に行政書士試験では、基準点以下ならただちに不合格になる足切りがあるので、苦手分野への対策は必須と言えます。
このように過去問には試験に役立つヒントがちりばめられているため、必ず活用するようにしましょう。
勉強法をもっと具体的に学ぶ裏技
ここまで勉強法の基礎をお伝えしましたが、まだまだイメージがよく掴めていないという方もいらっしゃるかと思います。
そんな方におすすめなのが、大手資格予備校が講座に取り入れている勉強法を知ることになります。
大手予備校のクレアールでは、カリスマ講師の執筆した行政書士試験の攻略本「非常識合格法」を無料プレゼントしています。
科目ごとの出題傾向や、どこをどう勉強すれば合格ラインを効率よく突破できるかなど、行政書士試験に合格するためのノウハウが凝縮された一冊となっています。
無料プレゼントは先着100名様限定なので、この機会を逃さず手に入れておきましょう!
出題形式別の解答のテクニック

行政書士試験の憲法分野では、五肢択一問題と多肢選択問題という二つの形式で出題されます。形式ごとに解答テクニックが異なるので、分けて解説します。
五肢択一問題
まずは五肢択一式問題です。五肢択一問題とは、五つある選択肢の中から正しいものを一つ選ぶ問題のことです。
このスタイルの問題はシンプルな問題が多く、ひねった問題はほとんどありません。暗記がメインなので、時間をかけて対策すればするほど得点につながります。
条文や判例ごとに論点になる部分は決まっているので、過去問演習でしっかりと体に刷り込んでおくことが大切です。頻出論点さえ押さえておけば「あと二択まで絞れたけど…」といった事態になりにくくなります。
毎年必ずと言ってよいほど、一般的な勉強時間では答えられない難問が出題されます。満点を取らなくても試験には合格できますので、潔く捨てた方がいいでしょう。過去問演習で「捨て問」を見る目を養っておくと本番で慌てずに済みます。
多肢選択問題
多肢選択問題とは、一部が虫食い状になった長文の空欄に当てはまる言葉を選択しから選ぶ問題です。空欄は四つ、選択肢は二十あります。
多肢選択問題は判例を元に出題されます。そのため、重要な判例を覚えておくと答えやすくなります。
対策のポイントは判例の結論よりもなぜそうなったのかという過程を重視して覚えることです。問われるのは必ずしも結論とは限りません。また、このように覚えることで記憶定着率も良くなります。
もし試験本番で答えに詰まったなら、それっぽい選択肢を入れてみて文章に矛盾がないか確認するという方法を試しても良いでしょう。
ただし、この方法は非常に時間がかかってしまいます。問題を一通り解き終わった後の余った時間や見直しのタイミングで行うことを勧めます。
行政書士の憲法勉強法まとめ
行政書士試験の憲法勉強法まとめ
- 配点以上に重要なので80時間程度は必要
- 目標は60パーセントの18点。満点を取る必要はない
- 人権は判例理解、統治は条文暗記
- 過去問はやりこむ
これまで行政書士試験における憲法に関して紹介してきました。記事を読み始める前よりも具体的な勉強法が見えてきたのではないでしょうか。
憲法は時間をかければかけるほど点数の伸びる科目です。じっくりコツコツ、頑張っていきましょう。