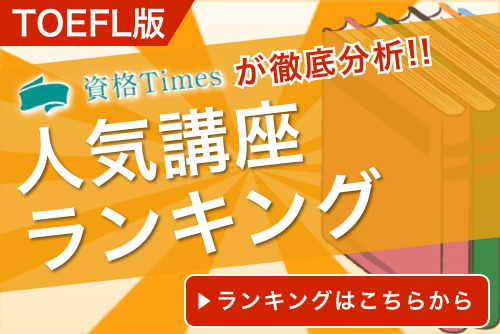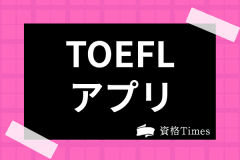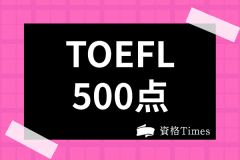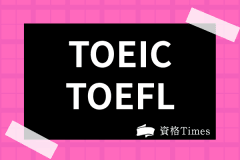TOEFL readingのおすすめ対策法は?出題形式別の解法のコツやダミー問題の噂まで解説
「TOEFLのreadingにはどんな対策をするべき?」
「解き方のコツはある?ダミー問題って?」
などと疑問をお持ちの方もいるでしょう。
TOEFL iBTのリーディングセクションはTOEICよりも難易度が高いので、ハイスコアを目指すならより良い対策法を考えなければいけません。
今回はTOEFL readingのおすすめ対策法について、各出題形式の解き方のコツやダミー問題の存在などを含めて解説します。
これを読んで、TOEFLの対策法を考える上での参考にしてください。
TOEFL readingのおすすめ対策法についてざっくり説明すると
- 速読ではなく正確に読解することを重視するべき
- 問題文を先に読むべき
- プログリットなどのスクールに通うのもおすすめ
このページにはプロモーションが含まれています
TOEFLiBT readingの概要

TOEFLにはいくつかの種類がありますが、今回は最も代表的なTOEFL iBTのreadingについて解説します。
TOEFLのreadingは同じくETSが作成しているTOEICのそれよりもかなり難しいです。
TOEICではビジネスに関連した基礎レベル・標準レベルの英文が出題されますが、TOEFLではアカデミックな内容の文章が出題されるので、馴染みの薄さが難しさの要因となっていると言えるでしょう。
なお、2019年8月1日以降の新形式では、readingの出題パターンは以下の2通りです。
- 54分で3パッセージ
- 72分で4パッセージ
どちらにせよ、1つの文章に対して18分かけることができます。各パッセージの問題数は10問なので、受験者は全部で30問もしくは40問に解答するということです。
ちなみに新形式では問題数(パッセージ数)が減少したため、受験者にとっては負担が軽減されたと言えるでしょう。
得点別レベルの目安
TOEFLのreadingのスコアと英語力のレベル、CEFRの関係は以下の通りです。
| readingのスコア | レベル | CEFR |
|---|---|---|
| 0-3点 | 初級 | A2 |
| 4-17点 | 中級 | B1 |
| 18-23点 | 上中級 | B2 |
| 24-30点 | 上級 | C1 |
ちなみにCEFRとは「The Common European Framework of Reference for Languages」の略語で、英語をはじめとするヨーロッパ言語の運用能力の程度を表す指標のことです。
なお、レベルに関して以下を参考にしてください。
- 初級
簡単な言葉で書かれた文章なら、よく知っているトピックを扱った日常的な事柄についての短い物語を理解することができる。 ’can do’ discriptorより
- 中級
構成がはっきりとした物語の筋を理解することができ、最も重要なエピソードや出来事は何か、それらに関して重要な事は何かを認識することができる。 ’can do’ discriptorより
- 上中級
物語や劇の中の登場人物の行動の動機や筋の展開でその結果がどうなったかを理解することができる。 ’can do’ discriptorより
- 上級
自分の仕事や関心のある分野と関連がなくても、読み返す十分な時間があれば、例えば新しい機器の使用などの長い複雑な説明を理解することができる。 ’can do’ discriptorより
上記の対応表とこれらの説明を見れば、自身のreadingのスコアから英語力の程度を判断することができます。
ダミー問題の存在に注意が必要
TOEFLでは、リーディングセクションとリスニングセクションにダミー問題が混ざっていることがあります。ダミー問題とは正誤がスコアに影響しない問題のことです。
今後の試験問題作成に役立てるための調査として入れられているのですが、受験者にとっては解答するメリットがありません。
なお、ETS公式がダミー問題の存在を公表しているわけではありませんが、解いていない問題があるにもかかわらず満点だったなどの事例があるため、信憑性の高い情報と言えるでしょう。
ちなみにreadingに関してはパッセージが4つの時に登場すると言われています。
TOEFL readingパートを読むうえで押さえたいコツ

ここからはTOEFL readingで各パッセージを読解する上でのコツをいくつか紹介します。
正確に意味を理解しながら読むことが最も大切
TOEFL readingのパッセージはそれぞれ700語程度の長文です。各長文問題に18分ずつ時間を使うことができ、含まれる設問数は10問なので、1問あたり108秒ずつかけることができます。
よって、文章の難易度は高いものの、解答時間には比較的余裕があると言えるでしょう。そのため、速読というよりも意味を正確に理解することを心がけるべきです。
1分あたり100語くらいを読解できれば十分解き切れるので、スピードに関してはそれほど意識しなくて構いません。
ちなみに1分あたり100語というのはかなりゆっくりです。アメリカ人の読解ペースは1分あたり200〜250語程度と言われています。
速読を意識しすぎないことが大事
readingで時間が足りないと速読に活路を求める人もいますが、TOEFLに関してはそれはおすすめできません。
上述したように、TOEFLのreadingは1分100語という比較的ゆったりしたペースでも十分に解き終わる試験です。
そうした試験で時間が足りなくなる原因は、おそらく一回で正確に意味を把握できず、何度も読み返してしまうことでしょう。一回一回のスピードは十分でも読み返すことで1分100語を割ってしまうのです。
単語や熟語の知識が不足していたり、文法構造を把握する能力が低いとこうしたことが起こり得ます。
そうした人が速読を意識すれば、尚更文章読解が不正確になり、さらに何度も読み返す結果になってしまうので本末転倒です。よって時間が足りないなら、正確に読む力を磨くのが良いでしょう。
集中力を維持する
TOEFLのテストは、リーディングだけでも1時間かかりますが、全体で3時間以上と試験時間が長いのが特徴です。
各試験の間の休憩も短いため、いかに集中力を維持するかが点数アップのカギになります。
テンポよく問題を解けるように実力をつけるのはもちろんのこと、本番の緊張感で解く練習をしたり、試験前日の休養や栄養補給なども大切になります。
集中力を最大限維持できるよう対策してから、試験に臨むようにしましょう。
1問あたりの目安時間を決めて演習を行う
TOEFLの文章は難しいので、特に学習の初期段階では1問あたりに長い時間をかけすぎてしまうこともあるでしょう。しかし、それだといくら速読力が要らないTOEFLと言えども時間が足りなくなってしまいます。
先述した通り、1問あたりにかけられる時間は108秒です。よって演習をする際はこの時間を意識して解き進めるのが良いでしょう。
TOEFLのスピード感に体を慣れさせることが、最終的なスコアアップに繋がるはずです。
問題文を読んで必要な情報を把握
本文を読む前に、先に問題文を読んでおくのがおすすめです。問題文を読むことによって本文の内容を少し把握できるので、より理解が捗るでしょう。
また先に問われる内容を知っておけば、答えとなる部分を探しながら本文を読むことになるので、メリハリのある読み方が可能になります。
一方で本文を読んでから問題文を読むという流れだと、問題文を読んで再び本文を読み返すという作業をしなければならなくなる可能性が高いので非効率です。
質問はピンポイントに聞かれることが多い
TOEFLのreadingで出題される問題は、基本的には本文の特定箇所の内容を尋ねるものばかりです。本文全体に関わるような内容を聞くものは少ないので、たいていの場合は一部分を読めば解答することができます。
つまり答えがわからなくて再び本文を読み返すなら、文章全体を再度読み直すのではなく、答えが書かれている部分をピンポイントで探せばそれで事足りるということです。
この点を理解しておけば大きく時間短縮ができるでしょう。
わからない問題は飛ばす勇気が必要
TOEFLの初心者はわからない問題で立ち止まってずっと考えてしまうことが多いです。しかし、結局わからずに勘で答えるなら、時間をかける価値はありません。
よって、初めのうちはわからない問題には適当に解答し、早く次の問題に進むのが良いでしょう。後半に簡単な問題が出題されることもあるので、そうした問題を確実に取っていけば十分に得点は稼げます。
ただし、20点以上のハイスコアを狙うなら全部に正解するつもりで臨んだ方が良いので、ある程度実力がついていきたら方針を切り替えるのが良いでしょう。
長文読解のコツを出題形式別に紹介

ここからはTOEFL readingにおける長文読解のコツは出題形式ごとに解説します。
語彙力の幅を増やすことが必須
長文読解の基礎となるのが語彙力です。TOEFLの英文には日常では用いないようなアカデミックな単語・熟語も数多く登場するので、そうした語彙力も十分に高めておかなければなりません。
語彙力を鍛えれば、読解スピードと理解力が共に向上するため、ハイスコアも狙えるようになります。よって単語・熟語に関しては毎日コツコツ暗記していくのが良いでしょう。
語彙力は長文読解の精度だけでなく、出題形式の一つである語彙問題の点数にも直結するので、解答時間を短縮してスコアを伸ばす上では非常に大切な要素です。
5W1Hの状況を問う問題は見る箇所が肝
5W1H問題とは、why(なぜ)・when(いつ)・where(どこで)・what(何を)・who(誰が)・how(どうやって)に関する問題です。
この問題の解き方は実にシンプルで、たいていの場合、問題文が言及している箇所よりも前を探せば答えが見つかります。
5W1Hで問われるような状況説明は、基本的には文全体や段落の前半でなされることが多いからです。
why(なぜ)に関して言えば「原因→結果」という順序で説明することが多いですし、when(いつ)に関しても年代や季節などを終盤の結論部で述べることはまずないでしょう。
挿入問題は該当文章の内容見極めが大切
挿入問題とは、ある文章を英文のどの箇所に挿入すれば文脈的に適切かを判断する問題のことです。(A)〜(D)のうち、該当文章を挿れるのにふさわしい箇所を選びます。
これに関してもまず本文を読んでから挿入する文章を読むのは非効率なので、最初に挿入する文章の意味を確かめるのが良いでしょう。
該当文章の意味を把握しておけば、あり得ない選択肢を除外することができますし、単語の繋がりから可能性が高い選択肢だけをピックアップすることもできます。
事実正誤は主に2種類のパターンに分かれる
事実正誤の問題は、正しい選択肢を見つけるパターンと誤った選択肢を見つけるパターンの2種類があります。
前者のパターンでは、該当段落の最初と最後をよく読むことが大切です。最初と最後はメイントピックスと関係していることが多いので、正しい答えを見極める上で有益な要素を見つけることができます。
また後者のパターンに関する解き方は、明らかに間違っている選択肢を探すか、正解の文章を消していくかの2通りです。
間違った文章がすぐに見つからない場合は、正しい答えを一つずつ除外していくしかないので、いずれにせよ正しい選択肢を見抜く力が必要になります。
言い換え問題は選択肢の取捨選択が大切
言い換え問題とは、ある文章と同じ意味を持つ選択肢を選ぶという問題ですが、これを攻略するには間違いの選択肢を切ってくことが重要です。
なお、間違いのパターンは大体以下の2通りしかないので把握しておきましょう。
- 文章には書かれていないことに言及している(異なる原因、もしくは結果など)
- 文章と反対の意味になっている
なお、この問題に登場する文章は、選択肢を含めて全て因果関係を表しているため、原因と結果ごとに考察していくと良いでしょう。
推測問題はまず本文の展開に注目
推測問題では文章には明示されていない答えを選ぶわけですが、正解は必ず「暗示」されているので、本文をきちんと読解することが大切です。
本文を読む際は、事実正誤で正しい選択肢を選ぶ時のように、メイントピックに言及している最初と最後の文章をよく読むのが良いでしょう。
それらから本文の意味を的確に捉えられれば、自ずと正解の選択肢は一つに決まるはずです。
最後の要約問題は細かい内容の選択肢を排除
要約問題に関しては、文章全体の内容に言及している選択肢を選ぶということが大切になります。つまり文章の細部にしか言及していない選択肢に関しては、基本的に除外して良いということです。
なお、正しい選択肢を見つけるには、各段落の最初の文章を読むのが良いでしょう。上記で解説した通り、最初と最後の文章はメイントピックに言及していることが多いからです。
よって最初の文章の内容と関連した選択肢なら、メイントピックのことを語る正しい要約である可能性が高いでしょう。
よく出題される分野に精通しておくことが大切
TOEFLではアカデミックな文章を扱いますが、特に以下の7分野は頻出です。
- 生物学
- 地質学
- 考古学
- 歴史学
- 社会学
- 環境学
- 経済学
これらの分野に関連する英文を、全く予備知識がない状態で読解するのは難しいので、問題演習などを通してそれらに慣れておくのが良いでしょう。
また特に苦手な分野に関しては、専門的な単語を重点的に覚えたり、その分野の概要を調べたりするのもおすすめです。
reading対策に必須の参考書を紹介

ここからはreading対策におすすめの参考書をいくつか紹介します。なお、各見出しの最後はそれぞれの書籍の基本情報です。
TOEFL Test iBTリーディングのエッセンス
18題の集中トレーニング問題で、ハイスコアに繋がるリーディングの解答スタイルを身に付けることができます。
各問題に解答時間の目安が明記されているため、TOEFLの解答スピードや時間配分の感覚を覚えたいという人にもおすすめです。
また巻末には模試形式の確認テストが2回分収録されており、実践練習を通して学んだテクニックやコツをより確実に体得することができるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 題名 | TOEFL iBT® TEST リーディングのエッセンス |
| 著者 | Z会編集部 |
| 出版社 | Z会 |
| 価格(税込) | 2,640円 |
| ページ数 | 400ページ |
| 特徴 | TOEFLの難易度と形式を忠実に再現した問題で効率的なリーディング対策ができる |
| 評判 | 時間制限の中で問題を解く練習をするのに非常に役立つ良書 |
TOEFLテスト英単語3800
TOEFL iBT対策に必須の3,800単語を難易度のランクごとに収録した単語帳です。TOEFL対策では売り上げNo.1のシリーズの単語帳なので、クオリティは申し分ないと言えるでしょう。
また付録の「分野別英単語」では、TOEFL特有のアカデミックな専門用語やその背景知識も学ぶことができるので、読解力の向上に役立ちます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 題名 | TOEFLテスト英単語3800 |
| 著者 | 神部 孝 |
| 出版社 | 旺文社 |
| 価格(税込) | 2,530円 |
| ページ数 | 304ページ |
| 特徴 | TOEFL iBTに頻出の3,800単語を厳選して収録・2タイプ(BGMありなし)の音声も収録 |
| 評判 | 本書の単語を一通り覚えたら過去問演習において単語で悩むことがなくなった |
Extensive Reading for Academic Success Advanced A Student’s Book
右にアカデミックな英文、左に設問という見開きの問題が全部80問収録されているというボリューム満点の参考書です。
生物学や社会学、科学、技術などTOEFLでも頻出のテーマを扱っており、問題もTOEFLに似ているため、TOEFL対策として問題演習をするのに良いでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 題名 | Extensive Reading for Academic Success Advanced A Student’s Book |
| 著者 | Jeff Zeter |
| 出版社 | Compass Publishing Japan |
| 価格(税込) | 2,970円 |
| ページ数 | 187ページ |
| 特徴 | TOEFLに似た文章問題を80問収録 |
| 評判 | 出題傾向がTOEFLに似た問題をたくさんこなせるので良い |
本質的な読解力を磨くことも大切

TOEFLのreadingでハイスコアを目指すなら、小手先のテクニックだけはなく、純粋なリーディングスキルを磨くことも大切です。
TOEFL iBTの受験者には、留学や仕事でスコアを活用したいという人が多いはずですが、ハイスコアを取れても実際に英語を使えなければ意味がありませんし、そもそも実践的な英語力がなければハイスコアは取れません。
なお、本質的な英語の読解力を磨くには、洋書をたくさん読むことが一番です。そこで以下ではTOEFLとも関わりがありそうなアカデミックな内容に関するおすすめの洋書をいくつか紹介します。
英語で学ぶ生物学
こちらは純粋な洋書ではありませんが、表題通り「生物学を英語で学ぶ」第一歩としては最適な一冊です。TOEFLでも頻出の生物学の予備知識を学ぶ上でも良いでしょう。続編も出版されています。
本書にはアメリカの大学の教科書などから抜粋された様々な生物学的テーマに関する文章が乗っているので、生物学の各分野を幅広く学ぶことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 題名 | 英語で学ぶ生物学 |
| 著者 | 渡邉 純子・渡邉 和男 |
| 出版社 | コロナ社 |
| 価格(税込) | 2,420円 |
| ページ数 | 151ページ |
| ジャンル | 生物学 |
| 評判 | 専門性が高すぎないので気軽に読めてとても楽しめた |
Silent Spring
環境問題を語る上でレイチェル・カーソンの「沈黙の春」は欠かせません。1962年に執筆された本書は、今でこそ当たり前となった農薬などの化学物質の危険性や生物濃縮などの問題を初めて世界に知らしめました。
生物学や環境問題に関するベストセラーなので、是非一度目を通しておくのが良いでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 題名 | Silent Spring |
| 著者 | Rachel Carson |
| 出版社 | Penguin Classics |
| 価格(税込) | 1,475円 |
| ページ数 | 336ページ |
| ジャンル | 生物学・環境問題 |
| 評判 | 物質の構造式などは登場するものの一般人にもわかりやすいように書かれていて読み応えがあった |
Sociology
世界的に有名な学者による社会学の入門書です。様々な社会学的トピックを写真や図表なども用いながらわかりやすく解説してくれるので、TOEFLに向けて社会学を予習するのには良いでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 題名 | Sociology |
| 著者 | Anthony Giddens |
| 出版社 | Polity Press |
| 価格(税込) | 5,322円 |
| ページ数 | 1152ページ |
| ジャンル | 社会学 |
| 評判 | グローバル化やジェンダーなどの現代的な議論も充実しているので楽しめた |
独学で実力が上がらない場合はスクールを頼るのが最善

独学での対策では、TOEFLのスコアを短期間で上げるのは難しいです。
また先述した通り、TOEFLのreadingの難易度はTOEICのそれよりも高く、全体としても高度なので、自己流の対策ではスコアが全く上がらないということもあり得ます。
さらに今回は解説していませんが、TOEFLではスピーキングやライティングのテストもあるので、特に英語が苦手な場合、独学では対策が捗らないでしょう。
よって短期間で効果的にスコアを上げたいなら、英語学習のコーチングをしてくれるスクールに通うのがおすすめです。
なお、スクールにも様々な雰囲気や形態のところがありますが、折角なら少し厳しめのスクールでガッツリ勉強するのが良いでしょう。
TOEFL初心者は点数が上がる前に諦めてしまうことが多いので、短期集中型で頑張り、最短でのスコアアップを目指すべきです。1回目で結果が出れば、その後も学習を継続できるでしょう。
PROGRITでのマンツーマン指導がおすすめ
TOEFL対策講座の中でも、特にPROGRITは受講生の実力アップを遮る要因を徹底的につぶすことで大幅なスコアアップを強力に後押しするおすすめサービスです。
サポート体制として、主に
- 個人の実力アップに最適化されたカリキュラム
- 学習継続習慣を徹底習得
の2つのサービスを軸として、これまで数々の受講生の英語力向上に貢献してきました。
このメソッドはTOEFL対策にも存分に生かされていることから、確実にスコアを上げていきたい人には特におすすめの講座であるといえるでしょう。
TOEFL readingのおすすめ対策法まとめ
TOEFL readingのおすすめ対策法まとめ
- TOEFLの長文に頻出のアカデミックな単語をきちんと覚えるべき
- 1問あたり108秒以内で解答することを意識
- スコアに影響しないダミー問題が出題されることもある
TOEFL readingのおすすめ対策法について解説しました。
TOEFlのreadingは長文の難易度こそ高いものの、解答時間にはある程度余裕があります。1問108秒以内のペースで解答していけば良いので、速読よりも正確に理解することを重視しましょう。
またTOEFLではアカデミックな内容の文章を扱うため、専門用語を含めて語彙力をきちんと高めておくべきです。
さらに本文を読む前に問題文を先に読むのが良いでしょう。
なお、TOEFLはTOEICよりも難しいため、独学に限界を感じるならプログリットなどのスクールに通うのもおすすめです。
以上を参考に、より良い対策法を考えてみてください。