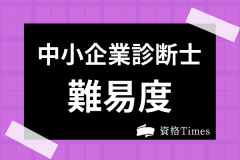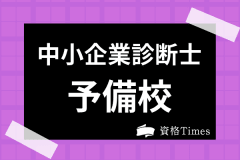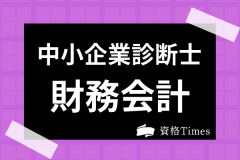中小企業診断士試験は過去問が超重要!解く時期・活用方法も徹底解説
この記事は専門家に監修されています
中小企業診断士
平井東
皆さんの中には、中小企業診断士の試験勉強でどこから手を付けたら良いのか迷っている方もいるのではないでしょうか?
この記事では中小企業診断士の試験を合格する為に欠かせない過去問の重要性、過去問をどう活用していくかを詳しく説明していきます!
中小企業診断士の試験では過去問を制する人が試験を制すると言っても過言ではありません。
今回の記事を読んで、あなたに合った過去問を購入して、中小企業診断士の試験合格へ突き進んでいってください!
中小企業診断士試験をざっくり説明すると
- テキストと過去問のサイクルを積み重ねることが重要
- 捨て問と取り問の取捨選択に慣れる
- 過去問は2種類用意し、用途に合わせて使い分ける
このページにはプロモーションが含まれています
中小企業診断士試験における過去問の優先度
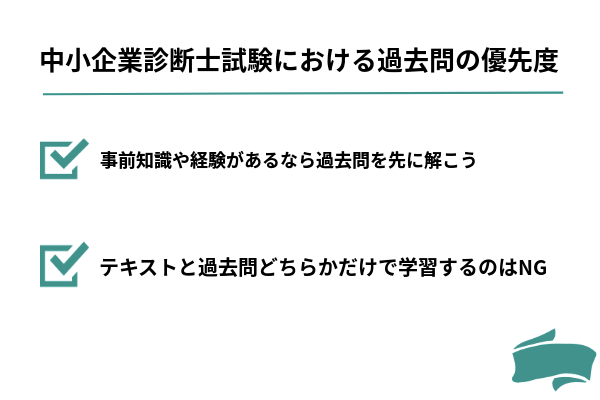
中小企業診断士の試験で合格を目指す際に、過去問が極めて重要であることは間違いないのですが、合格への道のりは1つではないことをまずは紹介していきます。
皆さんの現在の勉強状況や仕事の種類はどのようになっているのでしょうか?
事前知識や経験があるなら過去問を先に解こう
中小企業診断士の試験を受験する際、現在の勉強状況が進んでいる方や、中小企業診断士の試験科目に関する仕事をしている方はいきなり過去問を解き始めるのもオススメです。
テキストを読んでから過去問を解き始めるのが一般的と言えますが、ある程度科目の内容を仕事で知っている方は、過去問を解き自分がどの程度解けるのかを理解することで試験科目の勉強時間を短縮することができます。
逆に事前知識のない科目を勉強する時は、まずテキストを読み、次に過去問を解き始めることでより理解が深まります。
テキストでポイントを理解して、過去問を解く
この繰り返しが知識の定着を図ります。
テキストと過去問どちらかだけで学習するのはNG
中小企業診断士の勉強する時に、テキストだけを読む方や過去問だけを解く方は少ないと思います。
テキストを読んで得たインプットを試験でのアウトプットに変えられるよう過去問を解いていくことが、中小企業診断士の試験合格の近道になります。
前の見出しで書いたように過去問を先に解き始める方法もありますが、大体の方はテキストを読んで、過去問を解いていくことになるでしょう。
中小企業診断士のテキストを読むことは、勉強していることへの満足感から自分のモチベーション維持にも繋がり、勉強時間短縮の為や知識の定着の為にも大変効果的です。
過去問演習中、テキストで一度見た単語などがあればそれを思い出そうとするので脳をたくさん働かせることになり、理想的な学習サイクルが出来上がります。
中小企業診断士試験で過去問が大事な理由
 中小企業診断士の1次試験各科目の問題数と試験時間は以下の通りになっています。
中小企業診断士の1次試験各科目の問題数と試験時間は以下の通りになっています。
| 試験科目 | 問題数 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 経済学・経済政策 | 25問 | 1時間 |
| 財務・会計 | 25問 | 1時間 |
| 企業経営理論 | 40問前後 | 1.5時間 |
| 運営管理 | 40~45問 | 1.5時間 |
| 経営法務 | 20~25問 | 1時間 |
| 経営情報システム | 25問 | 1時間 |
| 中小企業経営・政策 | 40問 | 1.5時間 |
なんと1問解くのに3分程度の時間しか与えられていません。
次に、上記のような中小企業診断士の試験問題にある特徴を何点かの項目に分けて説明していきます。
試験には捨て問が存在する
中小企業診断士の試験は、時間との戦いでもあります。
よってその問題が解くべき問題なのか、捨てるべき問題なのかを見極めていく必要があります。
中小企業診断士の試験には、ほとんどの受験生が解くことができない難問が2割程度出題されます。
その問題に時間をかけすぎると、解かなければならない残り8割の問題を解けないという悪循環に陥ってしまいます。
難問を除く中小企業診断士の8割の問題は、過去に出題された問題の類似の問題になります。
中小企業診断士の試験は、この約8割の問題を時間をかけて解答することに集中することが重要でしょう。
過去問演習が重要な理由
中小企業診断士の試験では過去問と同じ問題が出題されるわけではありませんので、過去問を解いてその選択肢を覚えてしまうような勉強では意味がありません。
しかし中小企業診断士の試験では過去問に類似した問題が多く出題されますので、基本的な事項を理解し過去問演習でアウトプットの訓練をしていけば、合格ラインの6割程度を解答できるようになります。
よって、過去問演習で問題を見極める力や覚えたことをアウトプットする力を養うことが中小企業診断士の試験では重要になります。
出題範囲とどこまで問われるかを把握する
中小企業診断士の試験では7科目もの種類があり、その出題範囲はかなり広いです。各科目ごとの範囲の中に簿記の知識や会社法や民法の知識を必要とする問題も出てきます。
出題範囲が広いと、どこまで勉強するかが掴みきれず不安になってしまいますよね。
しかし出題される問題には傾向があります。その出題範囲や必要な知識の深さを知る為に、過去問を解いて勉強することが重要だと言われています。
独特な出題形式や表現に慣れる
中小企業診断士の試験はマークシート方式の出題です。
マークシート方式の出題では、限られた時間の中で問題文を正確に理解し的確に解答する必要があります。
中小企業診断士の試験では独特の言い回しや出題方法がありますので、それに慣れる為にも過去問を解いておく必要があります。
例としては、解答文の中に誤りを混ぜることが挙げられます。また専門用語を違う用語に置き換えたり用途を置き換えたりするパターンもあります。
過去問を解いてこういった出題形式に慣れておくことで、中小企業診断士の試験を時間内に解き終えることができますし、問題文の読み間違いをするリスクを軽減することができます。
解き方を覚える
中小企業診断士の科目の「財務・会計」「運営管理」「経済学」などで出題される計算問題は、出題される文章は異なっても使う公式や手順は同じものがほとんどです。
その為、過去問を解いて解答方法をしっかりマスターしていくことが中小企業診断士の試験を合格に導く近道となります。
中小企業診断士試験で過去問から学ぶ
 中小企業診断士の試験では過去問が大切ですが、過去問から各科目の全体像を知っていくことも大切です。
中小企業診断士の試験では過去問が大切ですが、過去問から各科目の全体像を知っていくことも大切です。
各科目のテキストを読んで各章終わりに過去問を解くというサイクルが大切だと書いてきました。
中小企業診断士試験は多角的に問題が出るので、そのサイクル後にその科目の全体図や関係性を図にして書いておくことでより理解が深まります。
一度作れば過去問を解く時や直前期の時にどこの問題でどのように繋がっているかを知ることができるので、大変便利です。
過去問の分析結果だけを貰いたい人
資格学校のクレアールでは過去問から解析した全体像を元にした「非常識合格法」という独自の勉強法を学習の基盤としています。
通常このノウハウはクレアールの講義を受けることでしか手に入りませんが、現在クレアールではこの過去問の分析結果を元にした中小企業診断士試験の攻略本「非常識合格法」を無料でプレゼントしています。
自分で過去問を解いて全体像を把握するプロセスは外せませんが、この本を読むことでより鮮明に中小企業診断士試験の合格までの道筋が見えるようになるはずです。
プレゼントは先着100名様限定なので、受験生の方であれば是非とも手に入れておきましょう!
最も効果的な過去問演習法を紹介
 今まで過去問の重要性を書いてきましたが、ここでは効果的な過去問演習法の紹介をしていきます。
今まで過去問の重要性を書いてきましたが、ここでは効果的な過去問演習法の紹介をしていきます。
中小企業診断士の試験は難易度の高い資格試験ではありますが、勉強のやり方を間違えなければ確実に合格に近づきます!
いつから過去問を使い始めるのか
暗記系の科目では、テキストを各章ごとに区切り
- テキストを読む
- 過去問を解く
- テキスト確認
の順で章ごとに早い段階で過去問を解き始めると良いでしょう。
問題の出題方法や傾向に注意しながら、テキスト⇒過去問のサイクルを繰り返しやっていきましょう。
過去問はアウトプットの問題演習ですが、インプットとしても活用できます。
また、計算問題はテキストをしっかり読んである程度内容を理解しないといくら問題を見ても解けませんので、理解を深めた時点で解き始めましょう。
できれば過去問は2回以上解くことをオススメします。
合格を目指してより深く内容を理解するためには2回以上解くようにしましょう。
過去問の周回回数と合格率は相関がある?
筆者の経験上、過去問5年分以上を2~3周している人は明らかに合格率が高いです。
もちろん
「早いうちから過去問に着手できる」=「勉強計画がしっかりしている・要領が良い」
という側面は無視できませんが、やはり本番同様の形式で演習を積んでおくことは、本番試験での得点力アップに直結するのではないでしょうか。
解く際に意識すべきこと
中小企業診断士の試験問題は、大きく分けて計算問題と暗記系の問題に分かれます。
ここでは、それぞれの問題に対してどのように取り組んでいけば良いかを説明していきます。
計算問題
計算問題を解く時に注意することは時間を意識するということです。
中小企業診断士の試験では、各科目の時間で1問3分程度の時間しかありません。
計算問題では問題の解き方に重点を置いて学習をすると思いますが、時間制約が厳しい以上、それだけでは合格は困難でしょう。
問題を見たら、この問題の公式は・・・手順は・・・といったようにすぐに解答への道が浮かんでくるレベルにまで達することができれば計算問題をマスターしていると言えます。
計算問題はとにかく時間を意識した勉強法をしましょう!
暗記系問題
中小企業診断士の試験で過去問と同じ問題は出ませんので、過去問や模試などをうまく併用しながら多角的に問題を見るように勉強してください。
中小企業診断士の試験本番でも対応できるように、いろいろな事柄を関連させながら暗記していく方法をオススメします!
単元別問題集と年度別問題集の使いわけが大事!
これまで中小企業診断士の試験で過去問が超重要であることをお伝えしてきましたが、ここではどのような過去問を使えば良いのかを紹介していきます。
この記事では過去問は2種類用意して解いていくことをオススメします。その種類は以下の2つです。
- 論点別問題集
- 年度別問題集
論点別問題集のいいところ
論点別問題集のいいところは、テキストで学んだ所をインプットしてすぐにアウトプットするための問題を解ける点です。
テキスト⇒問題集⇒テキスト確認のサイクルを何回も繰り返せることが論点別問題集の良い所です。
また出題頻度の高い問題から順に掲載されているので、頻出論点を重点的に学ぶことができます。
年度別問題集は本番を想定した練習
年度別問題集を用いて、中小企業診断士の試験直前期に本試験を意識して時間を計り問題を解いていきましょう。
中小企業診断士の試験で合格をする意識を高めたり、実際の試験の雰囲気を知るためにも、年度別問題集を使った直前期の演習は効果的です。
中小企業診断士過去問活用まとめ
中小企業診断士過去問活用まとめ
- 時間制約が厳しい試験に慣れるために過去問演習をすべし
- 計算問題は手順を覚えて活用できるように
- 暗記系問題は様々な問題集を併用して網羅する
この記事を読んで過去問が超重要であることが理解していただけたでしょうか?
過去問は自分に合ったものを選ぶのが一番ですが、今回紹介した過去問にも大変良いものがたくさんあります。
皆さんがこの記事を通じて、中小企業診断士合格へ向けての第一歩を踏み出してくれると幸いです。