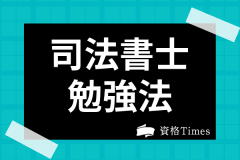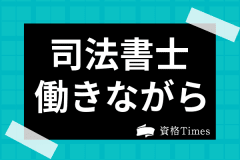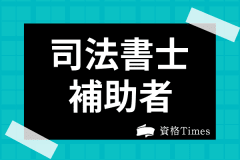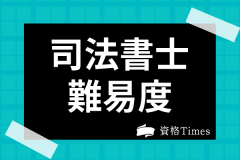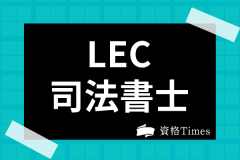ダイビングインストラクターから司法書士へと転身|佐伯知哉さんに直接取材しました!
難関資格として知られる司法書士。司法書士資格の取得を目指して勉強に励んでいる学生や社会人の方も多いことでしょう。
今回は、司法書士法人さえき事務所の代表である佐伯知哉(さえきともや)様にインタビューさせていただきました。
YouTubeやTwitterなどでもご活躍されている佐伯様の司法書士試験合格までの勉強法や独立・開業後の業務やこれからのビジョンについて語っていただきました。
司法書士を目指された経緯


本日はお忙しい中、インタビューに応じていただきありがとうございます。
資格Timesを運営しております、株式会社ベンドの北川と申します。
本日はどうぞよろしくお願いします。

司法書士法人さえき事務所で所長を務めております、司法書士の佐伯です。よろしくお願いします。

佐伯様のこれまでのご経歴を拝見したところ、法律畑とは無縁の世界から司法書士への挑戦を決断されております。
そこに至るまでの背景を教えていただきたいです。

私は日本の大学を卒業した後に、オーストラリアとパラオでダイビングのインストラクターとして働いておりました。
その後、パラオでの結婚を境に、今の仕事のままで子供をしっかりと養うことができるだろうか、という不安を抱えるようになり、同じタイミングでダイビングのお店を自分自身で開こうと考えていました。
しかし、人の命を預かるお仕事であること、初期投資が一定程度必要であることなど、開業自体にも少なくないリスクがあることを現地で働く中で体感し、結果的に現地で開業する道は断念することとなりました。

現地での開業を断念されて、日本に帰国後司法書士試験を受験しようと決意するまでの経緯について教えてください。

パラオから日本に帰国してからは、何かしら資格を取れば生活はできるだろうと安易に考えていました。
そこでどの資格を勉強しようか考えていたのですが、私の祖父が司法書士であった縁から、司法書士がまず初めに取得資格の候補として上がりました。
取得資格の検討段階では、税理士試験や司法試験など他の難関国家資格も併せて検討しましたが、税理士は受験資格を得る際に、一定の実務経験が必要なことから断念しました。
司法試験に関しても、受験資格を得るに際して必要であるロースクールに通う時間が膨大であることから、選択肢からは除外しました。
その点、司法書士は学歴要件やその他の受験資格が一切存在せず、最短で独立に向かうことができる点に大きな魅力を感じ、受験を決意するに至りました。
司法書士合格までの勉強法

働きながら司法書士を勉強するにあたり、苦労された点がございましたら教えていただきたいです。

忙しい合間を縫って一定程度の勉強時間を確保しようとした点は苦労したポイントです。
専業の受験生に比べて勉強にかけられる時間が、圧倒的に少ないので、冠婚葬祭以外の予定は全てシャットアウトして勉強時間に充てていました。
そのため、休日に家族の予定を極力入れないようにしていたので、その点は妻にも苦労をかけてしまいました。
朝の時間で勉強することを徹底

お忙しい日々の中でも、どの時間帯で勉強時間を確保されていたのか教えていただきたいです。

とにかく時間がなかったので、朝の時間に勉強することを徹底していました。
司法書士事務所に勤めながら勉強していましたが、夜は終わりの時間が仕事の内容によって変動するため、毎日決まった時間を学習に充てるのは困難でした。
一方朝であれば、就業がスタートする時間は決まっているため、一定の学習時間を捻出するための時間帯としては最適でした。
具体的には朝5時に起きて7時過ぎまで勉強する生活を毎日続けていました。
具体的には、5時に目覚ましをかけて朝食などは前日に用意を済ませておき、顔を洗ったら5時5分にはすぐに勉強を始められるようにしていました。

時間を一定程度確保できる朝のタイミングを活用して毎日コツコツ学習を積み重ねてこられたのですね!
多くの科目を同時に勉強する秘訣

司法書士試験の学習範囲は非常に広範なものとなりますが、このような広い学習範囲を学ぶ上で意識していたポイントを教えていただきたいです。

司法書士試験の科目の中には、民法など多くの出題がなされる科目もあれば、司法書士法のように試験全体で1問しか出題されない小さな科目もあります。
これらの科目の特性を踏まえた上で、負担の小さな科目は複数科目をひとまとまりにして学習を進め、負担の大きいメインの科目はそれ単体でそれぞれスケジューリングを行い、学習を進めるよう工夫しました。
具体的に見ていくと、司法書士試験での出題数が民法の場合当時は21問(現在は20問)、不動産登記法の場合も16問あるので、こららはそれぞれ一つの塊として捉え個別にしっかりと学習時間をとりました。
一方で、会社法・商業登記法に関してはテキストも一体化しており、2つ合わせて16問ぐらいの問題数ですので、こちらの2つを1つの塊と捉えました。
続いて、民事訴訟、民事執行、民事保全という民事系の3法と供託法は、これらがかなり似ているので4科目まとめて一塊と捉えて、12問になります。
余っているのが憲法刑法です。ただ、これらの問題は司法書士の問題はクイズみたいなものでしたので、これをまとめて一塊としました。
また、司法書士法は一問しか出題されなかったので、こちらは通常の学習期の学習セットには組み込まず、試験直前になってから、通勤電車の中で内容を眺めて内容を掴むようにしていました。
このように、11科目を5つの大きなブロックに分けて、学習を進めていました。

ありがとうございます。これらの5つのブロックに分けた科目について、どのようにインプット・問題演習されていたのでしょうか。

科目を5ブロックに分けて曜日ごとに勉強する科目を決めていました。例えば、月曜日はこのブロックとこのブロックを学習するというふうに決めていました。

勉強される曜日は各ブロックで固定されていましたか?

固定していましたね。
ブロックに分けて大体1週間から2週間ぐらいで全部のブロックを同じ時間で一周まわせるように勉強していました。
民法などボリュームの多いブロックは勉強の回数を多くすることで、触れる量を多くするよう工夫していました。

学習スケジュールは極力固定し、問題数に合わせてバランスよく学習時間を配置されていたのですね!
勉強する際に工夫したポイント

佐伯様自身が知識のインプット・アウトプットをする上で工夫されたポイントなどございましたら教えていただきたいです。

仕事を掛け持ちしながら受験をする場合、専業受験生と比較して勉強時間が圧倒的に足りないので、どうすれば最も効率が良く、試験で得点を最大化できるのかという点を意識していました。
そのため、得点の確保に直結する作業であるアウトプットの量をできるだけ増やすことを受験生時代は意識していました。
ですので、例えばテキストや条文をただ読み込み込んだりすることは、私自身はあまりしませんでしたね。
あとは、資格試験は過去問を使ったアウトプットがとても大切なので、過去問は自分なりに改造して有益に活用するようにしました。

過去問をご自身で改造されていたとのことですが、具体的にどのように改造されていたのでしょうか。

司法書士試験は5肢択一式の問題が出題されますが、そちらの過去問を正答できることは当たり前として、それらの択一式で問われた知識の派生系を問う問題を自分自身で考えました。
こちらの作業を通じて過去問を通じた知識の網羅的な補充を行うように努めました。
具体的には、過去問の裏の解説を用いて派生の選択肢を作成していきます。
解説には選択肢それぞれの正誤解説が掲載されており、そちらの正答の選択肢には但し書きが付いている場合があります。
例えば、「この条件では正しいが、但し、なお、などの接続詞がついて、条件が変わると正しくなくなる」という派生系の知識ですね。
私の経験上、この派生系の部分が本試験でも問われることが多いため、その派生の知識をアウトプットするためにアからオまでの選択肢の後にカ、キの問題を作成していました。
資格試験勉強のモチベーションを維持するためには

学習のモチベーションを維持する上で秘訣などございましたら教えていただきます。

実は私自身モチベーションに頼って司法書士試験学習に取り組んでいませんでした。
その理由として、司法書士試験に限定する場合、合格までに最短でも1年以上かかるケースが一般的であり、モチベーションに頼った学習を行うと学習を淡々と継続することは難しいと考えているからです。
勉強が習慣化してしまえば、モチベーションのアップダウンに縛られずに学習を続けることができます。
そのため、私自身はやるべきことを淡々とやり、学習を習慣化することこそが一番大切であると考えています。
人間なので、確かにやる気が起きない時は、多少あるんですけど、学習を始めたら時間の経過と共に気分が乗ってきますし、とにかく机に向かって毎日学習に励むことが大切だと考えています。
しかし、どうしても休みたい日とかは思い切り休んでしまうこともありだなと考えているため、そこら辺のメリハリをつけることも必要です。
仕組み化・習慣化してモチベーションに頼らずに学習を継続する。やるべきことをやるというだけだと思います。

ありがとうございます。物事を習慣化する際に一番気をつけていることなどがあればお伺いしたいです。

自分が何をやるにしても、一番習慣化しやすくてハードルが低い方法を見つけることが大切だと思います。
勉強する時間帯・場所なども自分が一番やりやすい時間、場所に当てこむと習慣化しやすいのではないかと思います。
資格取得後、独立・開業について

司法書士試験合格後から独立開業に至るまでの流れを教えていただきたいです。

合格した時は、司法書士事務所に勤めておりました。
司法書士資格の取得は、独立することを念頭に置いていたため、平成23年に試験に合格し、その後の一年ぐらいで現在の司法書士事務所を町田に開設しました。
司法書士事務所には補助者時代から含めて3年3ヶ月程度勤めておりました。

司法書士事務所を辞められる時期はどのように決断されたのでしょうか?

辞めた理由は2つございます。
1つ目の理由として、司法書士事務所に3年間勤めたことで、司法書士の業務にも慣れ、業務の全体像が掴めたこともありました。
2つ目の理由としては、自分自身が生意気になって、上長と衝突することもあったので、これが引き際である思い辞めました。
2012年の12月いっぱいで仕事を辞めてその翌一月に独立する運びとなりました。
そのため、独立開業するまでの時間というと辞めてすぐという感じですね。元々独立ありきで考えていたので、辞めてすぐに独立しました。

司法書士事務所に勤めておられる時から独立されるまでの期間の間に、準備などはされていたのでしょうか?

それが全然していなかったですね。司法書士の独立開業に関しては開業資金がそこまでかからないというのもあり、あまり準備はしていなかったです。
事務所とパソコンがあれば良かったので、開業までの費用は最小限に抑えることができました。
ただ、当時の自分の固定のお客さんなどはいなかったため、そういった意味では、独立後の将来に関してはとても楽観的でしたね。
顧客に関しては、それはもう開業すれば大丈夫だろと考えていました。

独立・開業する際に不安などはなかったのでしょうか。

独立をする際には、石橋叩いて渡るパターンの人も多いと思いますが、躊躇しているといつまでも先に進めないと私自身は考えています。
とにかく行動を起こしたら、あとは自分でどうにかするしかないので、「えいや」という感じでやってしまうのも大事かなと思います。
事務所でのメインのお仕事について


現在の事務所でメインに据えている業務内容を詳細に教えていただきたいです。

弊事務所では、相続と登記関係をメインの業務に据えています。
相続に関しては相続財産全部の手続きに最も注力しています。具体的には、相続の名義変更以外にも相続関係の預金とか有価証券などの相続財産全部の相続手続きをやることを注力しています。
相続の業務の中でも元々不動産関係に明るいので、相続登記に特に力を入れています。
加えて弊事務所の差別化ポイントとして、相続した不動産の売却代理まで一貫して手掛けている点が挙げられます。
一般的には、相続人が複数いる際の不動産の売却に関して、相続登記が終わった後には司法書士事務所の方では不動産屋さんを紹介してそちらで分割してくださいねという方法を採用しています。
しかし私たちの司法書士事務所では、事務所が相続人全員の代理となることで、売却手続きを代理して行い、遺産の割合に従って分配を行うことまで手掛けています。
こちらの業務を行うに際して、もちろん手数料などがかかるので、この業務を依頼するかどうかはお客様に一任していますが、弊事務所では依頼者様が不動産屋さんにお願いする場合とほとんど変わらない料金で不動産代理を行うことができます。

こちらの業務分野に特化されることによるメリットがあれば教えていただきたいです。

特定の分野に注力していくことで、当該分野に精通しやすい点、業務を効率化することができる点が大きなメリットとなります。
また、他の慣れない分野の業務には手を出さずに他の専門家の方々にご紹介することで、逆に自分の得意分野の仕事を次回以降これらの専門家の方々から逆にご依頼いただけるというメリットもございます。
例えば、訴訟代理のお仕事など弁護士さんの方に分のあるお仕事をお客様からいただいた際には、弁護士さんにそちらの仕事は依頼させていただき、一方で弁護士さんから登記のご相談を受けた際には、私の方にお仕事をお返しいただくことができます。
訴訟業務などの弊事務所の強み以外の分野は可能な限り他の専門家の方に任せ、自身の強みとなる分野にフォーカスして業務を進めていくことを意識しています。
お客様とのコミュニケーションについて

お客様とのコミュニケーションにおいて大切にされているポイントなどございましたら教えていただきたいです。

一般のお客様からご相談を受けることが多い事務所であるため、とにかくわかりやすく説明することはものすごく気を遣っている部分です。
難しいところを難しく話してしまうと、お客様は内容を全く理解できないので、なるべく平易な言葉を用いながらわかりやすく内容をお伝えするように注意しています。
初回の面談でお客様にわかりやすく説明した方が受託率も高くなっているので、受託率を上げるという意味でも、お客様の誤解を生まないようにわかりやすく説明するようにしています。
あとは愛想よく・感じよくお客様と接することというのはスタッフにもかなり気をつけるように常日頃言うようにしています。
地域との関係性について

最後に今後の佐伯様の事務所のビジョンを教えてください。

街の美味しいお寿司屋さん的な存在でありたいと思っています。
事務所を大きく展開していくというよりも手の届く範囲で、困っている方々の手助けできればと良いと考えています。
司法書士業務は何をやっているのかわかりづらいという側面もありますが、こんなふうに役に立っていることを知っていただきたいですね。
知らないからこそ、しかるべき専門家に相談せずに、経済的にも知識的にも不利益を被っている人もいると思うので、そう言った人たちを私の手の届く範囲内で助けたいなと考えています。

本日は貴重なお話をいただき誠にありがとうございました!
佐伯様の司法書士事務所はこちらをチェック!