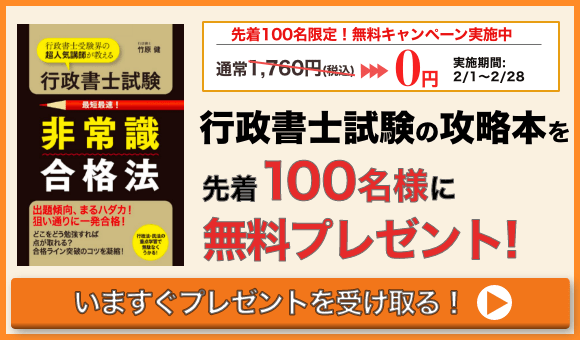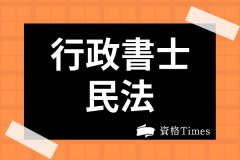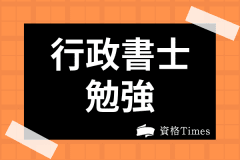行政書士の合格に近づく過去問の解き方|ポイントを抑えて効率良く勉強しよう!
「行政書士試験には過去問での勉強が重要って聞いたけど、理想の活用法や解き方ってあるの?」
「過去問って結局いつから使うのが正解なの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
過去問が重要と言われても、どれくらい解けば良いのか、いつからどのように活用すれば良いのか分からなくて困っている人も多いと思います。
そこでこの記事では過去問を使う重要性やメリット、正しく勉強するための活用法やスケジュールを詳しく解説していきます!
記事を読み終わる頃には、合格に近づくための過去問の活用法が具体的に分かるはずです!
行政書士の過去問の解き方についてざっくり説明すると
- 効率よく勉強するためには過去問は必須
- 過去問を使うことで頻出論点や出題傾向を把握できる
- 本番試験問題には過去問の類題も多い
- 暗記科目から取り組むことで効率よく勉強できる
このページにはプロモーションが含まれています
行政書士試験で過去問を軽視すると起こる失敗

「過去問が重要らしいから、とりあえず解けば良いかな?」
行政書士試験において過去問が重要なことは知っているのに活用法が分からなくて直前まで過去問に取り掛からなかったり、さらっと勉強しただけで試験に挑んでしまう人が意外と多いです。
以下では、過去問を軽視することで陥りやすい失敗例を紹介します。
過去問を使った間違った勉強法
行政書士の試験範囲はとても広いので、間違った勉強法で適当に勉強していると合格することは極めて難しいです。
-
過去問のポイントを意識せずに、とりあえず問題を解いていく
-
本番直前に過去問を一度だけ解いて試験に挑む
これではせっかく過去問に取り組んでも、よほど優秀な方でない限り合格はできないでしょう。
過去問の正しい活用法を知ることは学習効率を高める上でもとても重要です。
ポイントを意識せずなんとなく解く
過去問を解くときに重要なことは「問題を解いて正解すること」ではありません。
むしろ 「よし!正解したから次!」と次々に問題を解いていくと浅い学習になってしまって、初めて見る問題に対応できない・論点が変わるだけで回答できないという事態に繋がります。
例えば選択問題ではなぜその答えが正解なのか、逆になぜ他の選択肢では不正解なのかを突き詰めて考え、説明できるくらいまで理解を深めることが大切です。
多少表現を変えて出題されてもしっかり回答できるように、出題の意味や正誤の根拠を考えて問題を解き、答え合わせをするときも解説を読んだりテキストを振り返ったりしてポイントを意識しながら理解を深めることが重要です。
過去問を1度だけ本番直前に解く
「過去問は本番前の腕試しだ」と思って本番直前に過去問を解く人も多いですが、直前に一度解くだけでは過去問の良さはほとんど活かすことができません。
過去問を勉強すると出題傾向や頻出論点が分かります。とりあえず浅く広くテキストを勉強するよりポイントを絞ることができるので効率よく学習を進めることができます。
さらにテキスト学習と並行して過去問を解くことで知識をアウトプットすれば記憶を定着しやすくなります。
頻出論点を意識せず漫然と取り組む
過去問は漠然と勉強するだけでなく頻出論点を把握することが大切です。さらに難問・奇問を見分けられるようになる必要があります。
過去問を解いていくことで表現は違えど何度も出題されている問題に出会います。逆にある年にしか出題されていなくてテキストを読んでも全く分からないような対応のしようもない、悪問とも言えるような問題もあります。
めったに出題されない問題や重箱の隅をつついたような問題まですべて勉強しようとすると、とても時間が足りません。 勉強すべき項目を把握しつつ、解き方を学んで効率よく勉強を進めましょう。
行政書士試験で過去問重視の勉強法が大切な理由

行政書士試験において過去問は大変重要だということは多くの人が賛同するところです。
それは過去問が実際に試験に出た問題だからこそ、問題の中に合格に近づくヒントが隠れているからです。
他の多くの資格試験もそうであるように、行政書士試験でも過去問に多くの必須事項がちりばめられているため、過去問を解くことで効率よく勉強することができます。
逆に過去問の活用法が分からないまま勉強すると合格まで遠回りをすることになるとも言えます。
過去問は最も役立つ参考書
過去問を使う最大のメリットは解き進めることで行政書士試験の出題傾向や頻出される問題が分かることです。
行政書士試験は範囲がとても広い上に、仕事や育児など時間的な制約の大きい中で勉強を行わなければいけないため、的を絞って勉強することが大切になります。
過去問を解いていると出題方法は違っても何度も出題されている問題があることに気が付きます。こうした頻出問題は大事な得点源です。
それに加えて本番試験の出題傾向もよく分かるので、どの分野をどのように勉強すれば良いかも理解することができます。
過去問を丁寧にこなしていくことで、本試験の問題の中に「過去問で見たぞ」と思う問題を見つけることができるはずです。そうなれば、試験中でも心に余裕が生まれて本試験全体の成功にも繋がります。
過去問学習は苦手科目が効率よく見つけられる
過去問では各分野で似たような論点の問題が繰り返し出題されますが、その中で何度も間違えたり、なかなか答えられない問題に直面することがあります。
同じような問題を毎回間違えるということはその分野が苦手である可能性が高いです。
行政書士試験を受けるなら苦手科目を把握して克服することが必須になります。なぜなら行政書士試験は足切りのために各項目ごとに合格基準点が設定されていて、1科目でも基準以下の点数だった場合は不合格になってしまうからです。
そのため苦手な分野を明確にできることも過去問を利用するメリットになります。科目ごとのおおよその正解率を確認することで自分の苦手な分野を把握することができます。
科目によらずに満遍なく点数を獲得するためにも過去問を活用することで苦手分野を把握して克服していきましょう。
行政書士試験の過去問を解く際のポイント
 それでは行政書士の過去問を活用するにはどのようにするのが良いのか紹介します。過去問の活用法には3つのポイントがあります。
それでは行政書士の過去問を活用するにはどのようにするのが良いのか紹介します。過去問の活用法には3つのポイントがあります。
-
論点別の過去問を使う
-
一問一答形式の過去問がおすすめ
-
過去問は最低でも10年分解く
論点別の過去問を使うことで出題傾向と苦手分野が把握しやすくなりますし、一問一答形式の過去問は問題を解く時間が短くて正誤の論点が把握しやすいというメリットがあります。
また10年分の過去問を解くことで多種多様な問題に触れられる上に頻出問題を判別できます。
詳しい内容は後述しますが、これらのポイントを意識するかしないかで合格までに掛かる勉強時間が大幅に変わります。
一日でも早く行政書士として活躍するためにも、効率の良い解き方で過去問を活用して試験に合格できる力を身につけましょう。
論点別の過去問を使う
行政書士の過去問には年代別と論点別がありますが、資格Timesでは論点別の過去問題集をおすすめします。
年代別は出題された年ごとに並べられているのに対して、論点別は問題の種類ごとにまとめられているので、各分野ごとに集中して勉強することができる からです。
論点別になっていることで詳しく勉強したい分野をいっぺんにまとめて勉強することができますが、年代別を使用すると各年から問題を探さなければならずタイムロスになってしまいます。
さらに論点別には過去問には他にも次のようなメリットがあります。
・ある分野についていろいろな角度からの問題を解けるので知識を定着しやすい
・よく出題される分野はたくさんの問題が出題されているので出題傾向が掴みやすい
・自分の苦手分野の把握がしやすい
逆に年代別の過去問には「本番と同じ流れで試験問題を解くことができる」「時間配分の練習になる」というメリットがあります。
しかし一方で以下のような現象に陥りやすい危険性もあります。
・年ごとに難易度のばらつきがあり、出題傾向が掴みにくい
・苦手分野の克服など、目的を持った活用がしにくい
・自分の苦手分野の把握がしにくい
さらに年代別はすべての科目を終了してからでないと取り掛かることができませんし、問題形式や解き方に慣れたいのであれば公式HPなどで過去問をダウンロードすれば済みます。
各項目の学習を効率よく進めるためには、論点別の過去問題集を活用しましょう。
一問一答形式の過去問が勉強しやすい
さらに過去問には一問一答式と5肢択一式がありますが、一問一答形式のほうが学習が進めやすくておすすめです。
一問一答形式では5肢択一式を比べて消去法で解くことができないため、ひとつの問題に対して正誤をしっかりと考えなくてはいけません。
このため問題をより深く理解できる、法的思考力がつき知識を定着させやすい、というメリットがあります。
さらに一問一答形式の過去問には次のようなメリットもあります
-
一問を解く時間が短いので隙間時間も活用して勉強できる
-
問題に対して正誤の根拠や論点を把握しやすい
-
苦手分野が分かりやすいため知識の整理がしやすい
-
問題と向き合わないと解けないため記憶するべきところが明確になりやすい
過去問は10年分以上解く
さて、過去問は実際に何年分くらい解けば十分と言えるのでしょうか?
資格Timesでは10年分ほどの過去問を解くことをおすすめしています。 10年分の過去問を解くことで多種多様な問題に当たることができるからです。
10年分もの量の過去問を解けば、よく出る問題に繰り返し当たることで頻出問題を把握しやすく、自分で判断して頻出問題に優先順位をつけて勉強していくことが可能になります。
さらに必然的に頻出問題を繰り返し解くことが出来るというメリットもあります。
特に直近5年分の過去問は解くことで最近の行政書士試験の難易度や傾向を掴むことができます。さらに過去問を10年分解けば「こんなにたくさんの問題を解いてきた」という自信に繋がるはずです。
過去問の勉強は暗記が基本
 行政書士試験は記述式と択一式があります。
行政書士試験は記述式と択一式があります。
記述試験では40字程度の起承転結のある文章で解答しなければいけない上に問題文が複雑なため難しく感じますが、実は5肢択一式と変わらないことを聞いていることもあります。
記述式にしても択一式にしても過去問でしっかり勉強すれば対応できるようになります。
そのためにも過去問で出題された問題や関連する周辺知識をしっかりと暗記しながら、解き方を練習することがもっとも効率の良い方法だと言えます。
行政書士の試験には民法のように理解が大切な科目と行政法のように暗記が必要な科目がありますが、いずれにしてもまずは基礎知識を覚えていないと答えられません。
暗記重視の勉強と考える
行政書士試験に合格するには読解力と応用力が少なからず必要となってきます。しかしそれは基本がありきですので、結局暗記から初めて基礎知識を付けることから始めなければいけません。
行政書士試験には条文そのものを問う問題も出題され、そういう暗記系の問題は対策しやすいし、得点に繋げやすいです。
さらに暗記を中心に勉強を進めることで得点が徐々に上げていくことができるため、手ごたえを感じやすく自信に繋げることができます。
自信と基礎力を付けるためにはまず暗記中心の出題の多い科目から始めることをおすすめします。
以下に暗記が特に効果的な科目をまとめるので参考にしてみてください。
暗記が特に効果的な科目
暗記が必要な科目の中でも特に行政法は条文そのものを問われることが少なくないため、暗記で解ける問題が多くなっています。
さらに行政法は試験問題の中で出題数、配点ともにもっとも高い科目で、しっかり暗記することで合計点を伸ばしやすい科目でもあります。
特に過去問で頻出される重要な条文は必ず暗記するようにしましょう。
理解が大切な科目もある
行政書士試験には暗記だけでは対応できない科目もあります。中でも 「民法」と「一般知識の文章理解」は特に理解が重視され応用力を試される問題が目立ちます。
このような科目では条文や判例の知識を持った上で、その知識を使って答えを導き出さなければいけません。
このように行政書士の試験勉強には暗記が重要と言っても暗記するだけでは対応できない科目もあるので、科目に合わせて勉強を進めるようにしましょう。
以下に理解重視で勉強すべき科目をまとめるのでぜひ参考にしてください。
理解重視で勉強すべき科目
「民法」 は事例問題が中心となり、問題を解くときには読解力も必要になります。事案を読むときは図を描いたり分析しながら進めましょう。
しっかりと条文を理解した上で、問題文の事例に当てはめることが出来るようになることが重要です。
「一般知識の文章理解」 は比較的長い分を読ませて、文章の論理性を把握できるかが問われます。問題文を段落ごとに要約しながら読み、それぞれの関係性を把握して論理的に読み解く力をつけましょう。
毎年出題される上に出題パターンが少ないので解き方を身に付けることで得点しやすい科目です。
過去問を使うおすすめスケジュールは?

過去問の解答を始める最適なタイミングについて、多くの人がテキストの学習を一通り終えてから取り組むことが一般的ですが、実はそれはおすすめできる方法ではありません。特に行政書士のように試験範囲が広い場合、最初に重要項目を把握し、勉強に焦点を当てる方が効果的だからです。
テキストを全て勉強してから過去問に取り組んでも、解けないことが多いのは珍しいことではありません。この理由として、漠然とした勉強によって出題傾向が分からなかったり、一度に多くの内容を学ぶことで忘れてしまったりするケースがあるからです。
このため、過去問を早めに取り組むことで、実際の試験での出題傾向を掴み、重要な部分に焦点を当てて効率的に学習することができます。また、定期的に過去問を解くことで、学習の進捗を確認し、弱点を見つけて改善することも可能です。このような戦略的なアプローチにより、試験対策をより有効に進めることができるでしょう。
過去問はテキストと併用して解くのがおすすめ
そのため過去問を使うおすすめのスケジュールは「各項目の1章分の勉強をしたらすぐにその範囲の過去問を解く」ということを繰り返していくことです。
勉強した知識をすぐにアウトプットすることで知識を定着しやすくなりますし、勉強した項目の中で特に重要なポイントや出題傾向が分かるので必然的にメリハリをつけた勉強ができるようになるからです。
過去問の活用法についてさらに知りたい人は
ここまで過去問の活用法のエッセンスをお伝えしてきましたが、もっと具体的に知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
より詳細な過去問学習については、行政書士試験のプロである予備校講師の方の勉強法を参考にするのがおすすめです。
大手資格学校のクレアールでは、在籍する行政書士試験の講師が「非常識合格法」という過去問学習をベースにした勉強ノウハウを記した書籍を執筆しています。
クレアールでは現在、この行政書士試験の勉強法をまとめた書籍を無料プレゼントしています。行政書士の受験を控えている方であれば、是非とも手に入れておきたい1冊です。
無料プレゼントは先着100名様限定となっているので、この機会を逃さないようにしましょう!
行政書士の過去問活用法まとめ
行政書士の過去問の解き方まとめ
- 行政書士試験に合格するためには過去問の活用が必須
- 自分の苦手科目を把握して克服する
- 10年分の論点別、一問一答形式の過去問を使う
行政書士試験の勉強をするために過去問を活用すれば、出題傾向・頻出問題・自分の苦手分野が把握できるなどの多くのメリットがあります。
ぜひ過去問を活用して行政書士合格に向けての勉強を効率的に進めてください。