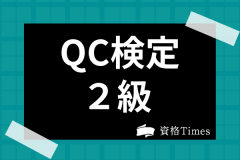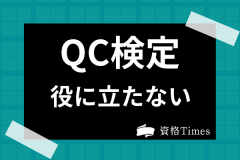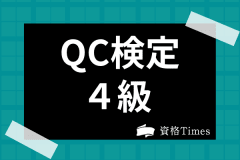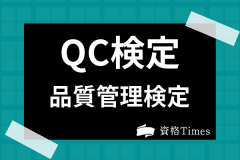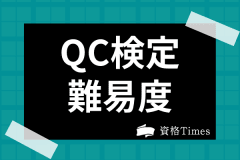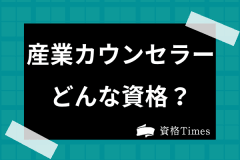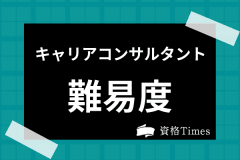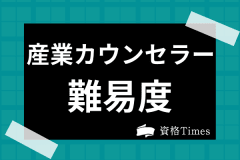QC検定1級の難易度は高い?合格率から勉強時間・論述式対策まで解説!
「QC検定1級の難易度ってどれくらい高いの?」
「QC検定1級の論述試験の対策方法が知りたいです!」
このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
QC検定1級は品質管理検定の最上級にあたるため、難易度は非常に高いです。
しかし、取得が難しい分、取得メリットは多くあるため、目指す価値はあります。
こちらの記事では、QC検定1級の難易度や論述試験の対策方法などについて解説していきます!
QC検定1級についてざっくり説明すると
- 難易度は非常に高く、合格率も低い
- 2級以上に専門的な知識が問われるため、しっかりと勉強計画を立てる必要がある
- 300時間の勉強をこなすのが一つの目安
- QC検定(品質管理検定)は多くの企業で役に立つ
QC検定1級は最難関

QC検定1級は求められる知識がハイレベル
QC検定1級は、品質管理検定とも呼ばれているQC検定の中でも最高峰の難易度を誇り、知識の要求レベルも非常に高くなります。
1級取得者の目指すレベルは非常に高く、組織内で起こる多くの問題に対して豊富な品質管理の知識を生かして解決策を考え、それを指導者の立場として実行することが求められます。
受験者は2022年9月の試験では705人でした。
非常に難易度が高い試験であるため、受験する人は少ない傾向にあります。
多くの人はいきなり1級を受けるのではなく、2級以下の下位試験にまずは合格して、知識を蓄えてから受験しています。
ステップを踏んだ方が合格に近付きやすいので、まずはこのように下位試験から受けることをオススメします。
想定される仕事
QC検定1級を生かした主な仕事内容は、部署のリーダーとしての組織内における全般的な品質管理作業です。
具体的には、組織に品質管理の問題が発生したときに、豊富な品質管理の知識を用いて直面している問題に対して自らリードする形で解決していくことが求められます。
また、自分のスキルを超えている専門領域の問題についても、解決手法を考えて筋道を立てられるようになる能力が期待されています。
リーダー職に就く人の受験が多い
QC検定1級は、主に品質管理の部署に所属して品質管理をリードしていく立場の人や、品質管理の部門を超えて品質についての問題解決を先導できる人の受験を想定しています。
そのため、企業である程度実務経験を積み、次の役職などにステップアップを目指している人が主に受験しています。
1級を受験するにはどうすればいい?
QC検定1級かなりの難関試験と言われていますが、受験資格は設けられていないため、他の級と同様に誰でも受験することが可能です。
なお、QC検定の申し込み期間は個人と団体によって異なっているため注意が必要です。
直近で開催される試験日は2024年3月17日(日)と2024年9月1日(日)とされています。それぞれの申込受付期間は2023年12月上旬と2024年6月下旬に予定されています。
受検料金に関しては、1級が11,000円、1・2級の併願が15,730円となっています。
なお、一般受験会場で受験を行う場合は5名以上であれば団体Aとして、自主会場で30人以上の団体で行う場合には団体Bとして申し込みを行います。 団体Bの場合には受験料の割引がなされます。 団体Bの1級の受検料は9,350円、1・2級の併願であれば13,420円となります。
1級の出題範囲・難易度
それではQC検定1級の出題内容や合格率など、具体的な試験情報から難易度を確認していきましょう。
出題形式・出題範囲とその内容
1級試験の出題形式はマークシートと論述形式で出題され、試験時間は13:30~15:30の2時間となっています。
出題範囲は主に品質管理の実践・手法の2つに分野に分かれていて、主な出題科目は以下の通りです
〈品質管理の実践の出題範囲〉
-
品質の概念
-
品質保証:新製品開発
-
品質保証:プロセス保障
-
品質経営の要素:方針管理
-
品質経営の要素:機能別管理(定義と基本的な考え方)
-
品質経営の要素:日常管理
-
品質経営の要素:標準化
-
品質経営の要素:人材育成
-
品質経営の要素:診断・監査
-
品質経営の要素:品質マネジメントシステム
-
倫理・社会的責任(定義と基本的な考え方)
-
品質管理周辺の実践活動
〈品質管理の手法の出題範囲〉
-
データの取り方とまとめ方
-
新 QC 七つ道具
-
統計的方法の基礎
-
計量値データに基づく検定と推定
-
計数値データに基づく検定と推定
-
管理図
-
工程能力指数
-
抜取検査
-
実験計画法
-
ノンパラメトリック法【定義と基本的な考え方】
-
感性品質と官能評価手法【定義と基本的な考え方】
-
相関分析
-
単回帰分析
-
重回帰分析
-
多変量解析法
-
信頼性工学
-
ロバストパラメータ設計
実践の対策においては、QC7つ道具などの基本知識に加えて実務においてしっかり実行することが求められます。
手法分野では、2級でも出題されていた統計分野について、さらに踏み込んだ重回帰分析や多変量解析法などの統計知識も求められるようになります。
2級と比べるとかなり難易度が上がっていることが分かります。
また、論述式試験では1級の出題範囲に沿って論述を行う必要があり、自分の知識をしっかりと整理した上で論理的に説明できるように練習しておかなければなりません。
論述式の詳細
論述式の問題は、4つのテーマの中から1つを選んで論述していきます。
出題テーマの傾向は、例年の出題実績から見ると実践分野から2~3問、手法分野から1~2問出題されています。
具体的な出題例だと、「品質クレームへの対処方法を記述せよ」という実践からの出題実績があります。
手法では、「主成分分析を使って品質問題を解決する際の注意すべきポイントを述べよ」という出題が過去にされています。
4つの中から選べるので、自分で書けそうなテーマを見極めて選ぶ必要があります。
QC検定1級の合格率・合格者数・合格ライン
QC検定1級の合格率は非常に低く 基本的には合格率1桁台~10数%で推移しているため、非常に難関試験であると言えるでしょう。
直近6回分の試験データは以下の通りです。
| 開催回数 | 合格率 |
|---|---|
| 第30回 | 8.10% |
| 第31回 | 9.18% |
| 第32回 | 12.69% |
| 第33回 | 8.18% |
| 第34回 | 10.35% |
| 第35回 | 2.48% |
ご覧のように、合格率は試験回によって異なるものの、かなり難関試験であることが分かります。
試験対策としては、基本的な知識を十分に身に着けるのに加えて、それを記述などで他人に分かりやすく説明できるレベルまで押し上げていく必要があります。
また、1級では合格ラインに3つの基準があります。以下で説明していきます。
-
一次試験の手法・実践分野の得点がそれぞれ50%以上である、かつ2つの総合得点が70%以上であること。
-
二次試験の論述の得点がおおむね50%以上であること。
-
一次・二次の得点が70%以上であること。
これらの足切り基準があることから、マークシートと論述で苦手を作らずに、どの論点が出題されても得点できるように満遍なく勉強を進める必要があるのです。
QC検定1級に適した勉強法

知識を1つずつ丁寧に習得
合格を目指すためには、基本的にはテキストと過去問を中心に勉強を進めていくと良いでしょう。
1級はかなり専門的で高度な知識が求められるため、時間をじっくりかけて1つ1つの論点を丁寧に理解していくことが大切です。
手法分野と実践分野を偏りなく勉強して、できるだけ苦手を作らないように意識し勉強していきましょう。以下で具体的に説明していきます。
実践分野に関しては、2級までに勉強した知識をさらに深い形で理解していくと良いでしょう。
手法分野に関しては、統計分野を中心に2級よりもハイレベルな知識が問われるため、一つ一つの統計手法の使い方と意味を理解しておく必要があります。
しっかりとインプットをこなして、知識がある程度身に着いてから過去問演習でアウトプットすると良いでしょう。
また、論述に関しては実践分野と手法分野の両科目の演習が必要となるため、論述問題をたくさん取り組んでとにかく出題に慣れておくことが必要です。
論述対策演習のポイントは、文字数の感覚や自分が上手く論述できそうな分野の見極めです。
過去問や問題集の演習を通じてこれらは慣れていくしかないため、数多くの問題演習をこなすようにしましょう。
また、本番が近くなってきたら本試験と同じ時間で実際に解いてみて、解き終わったら、間違いを復習してしっかりと知識を定着させるようにしましょう。
論述対策はどうする?
論述試験でよく出題されるのは、主に統計的分野について、生産現場での品質管理や保証について、品質マネジメントの考え方についての3つです。
日頃の演習でもこれら3つに絞って対策をしておくと、本番でも対応できるでしょう。
選んだ分野については予めどのような構成で書いていくか、どのような文章の流れで書いていくかをイメージしておくようにしましょう。
また、記述試験で高得点を狙うためには、過去問を中心に問題を解き、合格者や講師の添削を受けてどんどん論文の質を高めていくことが大事です。
余裕があれば合格レベルの解答例を読んでみて、論文の書き方のコツなどを感じておくと良いでしょう。
勉強時間は300時間程度
合格までに必要な勉強時間は人によって異なるものの、300時間が勉強時間の目安となります。
もちろん2級を取得して間もない人や品質管理部門で多くの予備知識を既に持っている人であれば、さらに短い勉強時間で合格を狙えます。
ちなみに、300時間こなす場合、1日3時間の勉強時間を確保できるとしたら3か月程度の勉強期間になる計算です。
社会人の人で1日3時間の勉強が難しい場合であれば、休日にまとめて勉強したり勉強期間を少し長めにとっておくなどの工夫をしましょう。
勉強期間としては3~6ヶ月程度見積もっておくと安心で、勉強スケジュールも組みやすくなります。
テキストは慎重に選ぶ
1級の勉強を進める際のオススメのテキストと問題集を紹介します。
まず、テキストは「QC検定受験テキスト1級」、問題集は「品質管理検定1級受験対策問題集」を使うのがおすすめです。
また、論述対策としては「QC検定1級模擬問題集」を使うのが非常に使いやすく分かりやすいと評判が高いのでおすすめです。
また、このテキストは論述のテーマが20テーマ程用意されており、幅広い出題範囲を網羅することができる点が特にオススメです。
テーマの傾向や書き方の例が載っており、論文を書き慣れていない人でも感覚を掴みやすい作りになっています。
なお、各オススメテキストの基本情報は以下の通りです。
- QC検定受験テキスト1級
5280円で出版社は日科技連出版社、著者は稲葉太一ら5名です。
- 品質管理検定1級受験対策問題集
2200円で出版社は日科技連出版社、著者はQC検定問題集編集委員会です。
- QC検定1級模擬問題集
4180円で出版社は日科技連出版社、著者は細谷克也ら5名です。
なお、過去問に関しては日本規格協会が公式で出版している過去問題集を用いること良いでしょう。
テキストや問題集を選ぶ際の注意点は、テキストは何冊も買わないことです。
何冊も使うよりも厳選して自分が最初に選んだ1冊を使い込んでいく方が知識の完成度も高まるため、結果的に効率的な勉強になるケースが圧倒的に多いのです。
電卓は使いやすいものを
1級の試験では電卓の持ち込みが認められているため、計算問題を電卓を使用して解くことができます。
電卓を使うことで計算ミスが減るので、自分の使いやすいものを選ぶと良いでしょう。
選び方の基準としては、大きくて数字が見やすい電卓かどうかを重視すると良いでしょう。
電卓をスムーズに使いこなすことで問題にかける時間を短縮することができるため、しっかりと使い込むようにしましょう。
電卓の注意点としては、四則演算に加えて三角関数などの計算が行える関数電卓の持ち込みは認められていないことです。
不安がある場合やはホームページや問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
QC検定1級の取得メリット
QC検定1級は品質管理部門の管理職クラス人が取得することを想定しているため、製造業などでに勤務している人であれば取得することでキャリアアップに直結します。
また、製造業以外でも品質管理と密接に関わってくる企業は多いため、収入アップを目指して転職などにも活用できるでしょう。
特に、近年は品質管理のミスがクレーム・ネット上の書き込みにつながり一つのミスで企業の信頼を損ねてしまうことがあります。
どの企業も口コミや評価には敏感になっているので、品質管理の高い知識と技能を持っているQC検定1級取得者は重宝されるでしょう。
特に、1級にもなると難易度が非常に高くなるため取得者も数もガクッと減ります。
つまり、取得している人があまりいない資格をアピールできることになるため、自分の市場価値も大きく上がるでしょう。
QC検定1級のまとめ
QC検定1級のまとめ
- 論述試験が課されるが、模範解答例などを見ながら書き慣れることが大切
- 100%の正解は求められないため、メリハリをつけて勉強しよう
- 試験範囲は広く専門的なので、しっかりと計画を立てて勉強しよう
- 難関資格である分、取得できたときのメリットは非常に大きい
QC検定1級は品質管理の最高ランクの資格なので、多くの企業で有効活用できるでしょう。
品質管理の現場に携わっていなくても、取得したことにより品質管理部門へ昇格したり昇級する可能性が高めることができます。
消費者の手元に安全な商品を届けるためにも、QC検定保有者が社会的に果たしている役割は非常に大きいと言えます。
QC検定1級は価値が高く、取得したことによるメリットも多くある魅力的な資格なので、興味がある人はぜひ取得を検討してみてください!