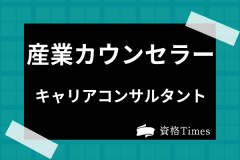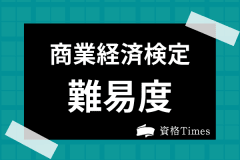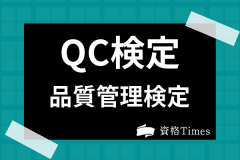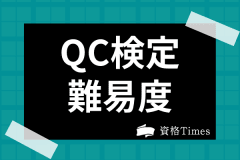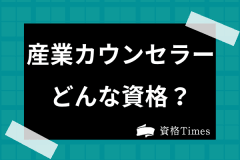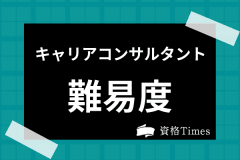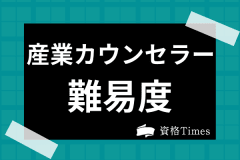経営学検定試験ってどんな資格?難易度・過去問・独学勉強法まで全て解説!
「経営学検定試験って興味はあるけど、どんな試験なのか分からない。」
そのように感じている人もいるのではないでしょうか。
経営学検定試験は、一般にそれほど難しくない試験だと言われています。中小企業診断士の練習台にもなります。
しかし、その知名度はあまり高くないため、「どんな資格なのか」「どれくらい難しいのか」「どういった勉強をすれば良いのか」など不明な点が多いはずです。
この記事では、経営学検定試験の概要から難易度、勉強法まで詳しく解説します。
これを読んで、経営学検定試験の受験を検討する際の参考にして下さい。
経営学検定試験をざっくり説明すると
- 経営学や経営管理に関する資格
- 初級・中級の難易度は低め
- 公式テキストと過去問で約1ヶ月勉強すれば合格できる
経営学検定試験ってどんな資格?
 経営学検定試験について、主催団体や取得をおすすめする人などを詳しく解説します。経営学についても説明するのでご参考にして下さい。
経営学検定試験について、主催団体や取得をおすすめする人などを詳しく解説します。経営学についても説明するのでご参考にして下さい。
経営学検定試験とは
経営学検定試験(マネジメント検定)とは、経営に関わる基礎的・専門的知識、またその応用能力としての経営管理能力や問題解決能力が一定レベルに達していることを全国レベルで資格認定する検定試験です。
特定非営利活動法人「経営能力開発センター」が平成15年にこの試験を始めました。
経営学を学ぶ大学生から企業や官公庁、NPOなどで活動する実務家たちに至るまで幅広い人間を対象としています。
平成27年からはマネジメント検定とも呼ばれています。
経営学検定試験の主催団体
経営学検定試験は、平成23年から一般社団法人日本経営協会の主催で行われるようになりました。
一般社団法人日本経営協会は1949年に設立された団体です。経営の近代化と事務の効率化を目指すために作られました。具体的には情報化の普及と推進事業および人材開発と育成事業の展開を目的とします。
中小企業診断士の試験と類似しており、腕試しの受験者も多数います。
そもそも経営学って何?
経営学とは、組織の運営について研究する学問で、その対象は企業となる場合が多いです。
企業は自社の利益追求のために存在しますが、上手くいく会社とそうでない会社があります。
両者の違いを分析し、「会社や組織の運営を上手くいかせるにはどうすれば良いのか」についてセオリーを打ち立てるのが経営学という学問です。
経営や組織マネジメントの現場で生きている社会人としては知っておくと良いのが経営学検定試験です。
経営学検定試験を取ることをおすすめする人
経営学検定試験は以下のような人におすすめです。
- 会社内や大学内での評価を高めたい人
経営学検定試験の資格は、企業内の研修・評価に活用されています。この資格は採用や昇格試験はもちろん、次代の経営幹部養成、社内ビジネススクールなど様々な場面で評価を受けます。
大学では学部やゼミの成果判定、大学院入学試験の要件などに活用されています。特に経営学を専攻する学生にとって、この検定は経営学「優」の価値があります。
- キャリアアップや転職・就職での武器が欲しい人
経営学検定試験の上級はMBSレベルの経営知識と経営幹部としての実践的経営能力が身につきます。そのためキャリアアップへの大きな武器になるでしょう。
また転職・就職活動の際にも活用できます。経営学検定試験を通じて、客観的な企業の見方や選び方を学ぶことができます。
経営学検定試験の難易度
 経営学検定試験の難易度はどのくらいなのでしょうか。
以下では経営学検定試験の難易度を中心に解説していきます。
経営学検定試験の難易度はどのくらいなのでしょうか。
以下では経営学検定試験の難易度を中心に解説していきます。
経営学検定試験の試験範囲と出題形式
経営学検定試験は、初級・中級・上級の3階級からなっています。
初級は学部学生や新入社員、若手社員向けです。中級になると中堅社員や経営学を専攻する大学院生が対象になります。上級は経営者や上級管理職向けの試験です。
試験範囲は、『経営学検定試験公式テキスト1 経営学の基本』が初級に対応しています。
中級は公式テキスト2〜5、『マネジメント』『人的資源管理/経営法務』『マーケティング/IT経営』『経営財務』が範囲です。中級ではテキスト以外に時事問題も数問出題されます。
上級に対応する公式テキストはなく、より実践的な内容が問われます。
初級の範囲と形式
初級は企業システム、経営戦略、経営組織、経営管理、経営課題の5科目からなります。マークシート方式(四肢択一)で問題数は50問あります。100点満点で、65%以上が合格の目安です。試験時間は90分となっています。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| 企業システム | ①会社と経営 ②企業の概要と諸形態 ③所有・経営・支配と経営目的 ④コーポレート・ガバナンス ⑤日本型企業システム など |
| 経営戦略 | ①経営戦略の体型と理論 ②全社戦略 ③事業戦略 ④機能別戦略 など |
| 経営組織 | ①組織に関する基礎理論 ②経営組織の基本形態 ③企業組織の諸形態 ④組織の制度・管理・文化 など |
| 経営管理 | ①経営管理の基礎理論 ②マネジメントの階層とプロセス ③経営計画 ④コントロール など |
| 経営課題 | ①M&Aと買収防衛策 ②経営のグローバリゼーション ③企業経営と情報化 ④企業の社会的責任(CSR)と企業倫理 ⑤環境経営 など |
中級の範囲と形式
中級は第1分野と第2分野に分かれます。第1分野は、「マネジメント」「人的資源管理」「経営法務」の3科目が課されています。第2分野は「マーケティング」「IT経営」「経営財務」の3科目です。
初級と同じくマークシート方式(四肢択一)ですが、第1分野と第2分野で各50問ずつ出題されます。そのため200点満点で、試験時間も各分野90分の計180分です。
尚、中級では不合格でも、各分野の得点が65点以上かつ各科目40%以上の正答率であれば分野別合格が認められます。不合格分野を再受験し、合格なら中級合格となります。
| 科目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 第1分野 | マネジメント | ①マネジメントの基本 ②経営戦略 ③組織デザインとマネジメント ④マネジメント・スキル ⑤内部統制 |
| 第1分野 | 人的資源管理 | ①人的資源管理の原則 ②人事制度と能力開発 ③労務管理と労使関係 など |
| 第1分野 | 経営法務 | ①企業経営と法務 ②企業組織と法務 ③企業取引と法 ④企業活動と法規制 ⑤企業をめぐる紛争と法 など |
| 第2分野 | マーケティング | ①マーケティングのコンセプト ②マーケティング・リサーチと標的市場 ③マーケティング・プログラム ④マーケティングのさらなる展開 など |
| 第2分野 | IT経営 | ①企業経営と経営情報システム ②情報処理とICTシステム ③ICTシステムの開発 ④経営情報システムに関する情報セキュリティ など |
| 第2分野 | 経営財務 | ①経営財務の意義 ②資本市場と投資 ③企業価値 ④業績評価と経営分析 ⑤資金調達と資本構成 ⑥管理会計 など |
さらにテキスト以外の時事問題が数問出題されています。
*2020年度からのCBT形式への変更については後述を参考にしてください。上記はパンフレットの内容を元に作成しております。
上級の範囲と形式
上級は記述式の1次試験と、レポート作成、プレゼンテーション、ディスカッションを含むの2次試験に分かれます。
1次試験の範囲は経営に関するケーススタディです。記述式で2題出題され、試験時間は180分です。200点満点で65%以上が合格の目安です。
2次試験の範囲は①マネジメント・プランの作成(経営課題に関するレポート)、②マネジメント・プランについてのプレゼンテーション、③グループ・ディスカッションの3つです。
①は自宅で作成し事前提出します。②はその課題のプレゼーションです。③では5〜7人の受験者とグループディスカッションを行います。詳しくは以下の表を参考にして下さい。
| 試験範囲 | 試験方法 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1次試験 | 経営に関するケーススタディ(ケースⅠ・Ⅱ 2題) | 記述式 | 試験時間:180分 |
| 2次試験 | ①マネジメント・プランの作成(経営課題に関するレポート) | 記述式・自宅で作成し、提出 | 作成期間:自宅で約2週間 |
| 2次試験 | ②マネジメント・プランについてプレゼンテーション | パワーポイントを使用したプレゼンテーション | 発表時間:1人10分程度 |
| 2次試験 | ③グループ・ディスカッション | 6人程度のグループでディスカッションを行う | 時間:40分 |
経営学検定試験の合格率・合格ライン
経営学検定試験の合格率と合格ラインについて、難易度や勉強時間の目安とともに解説します。
経営学検定試験の合格率
経営学検定試験の初級・中級・上級の平均合格率はそれぞれ以下の通りです。
| 級 | 合格率 |
|---|---|
| 初級 | 52.30% |
| 中級 | 42.90% |
| 上級 | 56.90% |
級によって波はあるものの、おおむね40~50%ほどのラインに落ち着いています。
また、最も難しい上級の合格率が最も高いですが、こちらは受験資格の厳しさが関係します。
具体的には、一次試験を受験する際に経営学検定中級を3年以内に取得していることが要件とされており、母集団の質が厳選されている中での56.90%となっているので、ミスリーディングには注意が必要です。
経営学検定試験の合格ライン
初級は100点満点中65点以上が合格ラインの目安となっています。
中級は各分野100点の200点満点となっていて、130点以上かつ6科目の正解率が40%以上を合格の目安としています。尚、上記でも説明したように各分野で分野別合格の制度もあります。
上級の合格は、1次試験が200点満点中65%以上、2次試験が300点満点中65%の得点を目安にしています。
経営学検定試験の難易度
マネジメント検定の難易度は、初級と中級に関しては易しめです。上級に関しては対応する公式テキストがなく、より実践的な知識が要求されるためやや難しめの設定になっています。
ちなみに試験勉強の時間は、約2ヶ月程度が目安になります。
経営学検定試験の勉強法
 経営学検定試験の勉強法は主に二つあります。
経営学検定試験の勉強法は主に二つあります。
経営学検定試験の勉強法は?独学は可能?
先述したようにマネジメント検定には、初級と中級でそれぞれ試験範囲に対応する公式テキストがあります。また過去問題集も公式から出ています。
そのためマネジメント検定の取得を目指す人の主な勉強法は、公式テキストの読み込みと過去問になります。
過去問題集の方が公式テキストよりも解説がしっかりしているため、取り組みやすいです。
範囲がそれほど広くないため、公式テキストと過去問題集の反復だけで十分合格を目指すことができるでしょう。
おすすめテキスト・問題集
経営学検定試験の独学には公式テキストと過去問題集がおすすめ。以下のようなバリエーションがあります。
| 商品情報 | |
|---|---|
| ① | 『経営学検定試験公式テキスト1 経営学の基本』2,600円(消費税別)・338ページ・中央経済社 |
| ② | 『経営学検定試験公式テキスト2 マネジメント』2,400円(消費税別)・242ページ・中央経済社 |
| ③ | 『経営学検定試験公式テキスト3 人的資源管理/経営法務』2,400円(消費税別)・240ページ・中央経済社 |
| ④ | 『経営学検定試験公式テキスト4 マーケティング/IT経営』2,400円(消費税別)・264ページ・中央経済社 |
| ⑤ | 『経営学検定試験公式テキスト5 経営財務』2,400円(消費税別)・253ページ・中央経済社 |
| ⑥ | 『初級過去問題・解答解説』各1,000円(消費税別) |
| ⑦ | 『中級過去問題・解答解説』各1,400円(消費税別) |
| ⑧ | 『上級過去問題・解答解説』各1,000円(消費税別) |
公式テキストは、初級・中級の出題範囲に対応しています。①は初級、②〜⑤が中級です。
テキストは経営学の学問的体系と経営の実践的な観点の両方を重視した構成になっています。経営学の理論的知識と企業経営における重要な実践的課題がバランスよく学べる内容です。
また⑥〜⑧の過去問題集は、1冊で6回分の問題と解説を収録しています。各年度毎の分冊になっており、マネジメント検定の年々のレベルと出題傾向が掴めるでしょう。
またマネジメント検定の公式HPでは、過去問のサンプルも公開されており、こちらも独学に役立ちます。
通信講座も存在
経営学検定試験(マネジメント検定)には公式の通信講座が存在します。
初級受験者向けのマネジメント力養成講座 (ベーシックコース/初級向け)と中級受験者向けのマネジメント力養成講座 (アドバンスコース/中級向け)の2つです。
マネジメント力養成講座 (ベーシックコース/初級向け)の受講期間は2ヶ月となっています。受講料は一般が16,000円(税別)で、日本経営協会の会員と学生が13,000円(税別)となっています。
一方、マネジメント力養成講座 (アドバンスコース/中級向け)の受講期間は4ヶ月です。受講料は一般が29,000円(税別)で、会員・学生が26,000円(税別)となっています。
初級講座にはテキスト1冊と補助教材4冊(全2回の添削)が、中級講座にはテキスト4冊と補助教材4冊(全4回の添削)がつきます。テキストに関しては公式テキストと同内容です。
経営学検定試験の試験日程・会場・申し込み方法
 ここからは手続きなど事務的な情報をお伝えします。
ここからは手続きなど事務的な情報をお伝えします。
経営学検定試験の基本情報
経営学検定試験は年2回で、6〜7月と11月〜12月頃に実施されます。
全国約260か所余りの試験会場で実施され、形式はCBT試験です。試験後は即時結果判定が行われ、合格証を各会場でプリントアウトされます。
受験料は以下の通りです。中級は分野別での受験になります。
| 等級 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初級 | 4950円 |
| 中級第1分野 | 4950円 |
| 中級第2分野 | 4950円 |
| 上級1次 | 8,800円 |
| 上級2次 | 28,600円 |
次の試験日は2021年6月15日(火)〜7月31日(土)です。こちらの日程では初級および中級の試験が実施されます。
一方上級は一次試験が7月18日(日)、二次試験が9月26日(日)の実施予定です。
経営学検定試験の受験資格
初級と中級は受験資格がなく、誰でも受験できます。
上級は中級合格者のみ受験が認められています。そのため中級合格の証書が必要です。
中級の分野別合格は1年間有効です。その期間内にもう一つの分野に合格すれば、中級合格となります。
上級の1次試験合格者は、合格後3年間は2次試験からの参加が認められています。
CBT方式への形式変更について
 経営学検定試験は2020年度より試験の形式が変更されました。受験を検討している方や試験を活用している方は注意して下さい。
経営学検定試験は2020年度より試験の形式が変更されました。受験を検討している方や試験を活用している方は注意して下さい。
マークシート形式からCBT試験へ
経営学検定試験は2019年まで全国8会場を中心にマークシート形式の公開試験が行われていましたが、2020年度からはCBT試験に変更されます。全国約270か所の試験会場で実施予定です。
ちなみにCBTとはComputer Based Testの略でコンピューターを使って行う形式のことです。オンライン上で処理を行うため様々な会場で実施が可能になっています。また即時結果判定ができるようにもなります。
実施期間が1ヶ月間に
以前は6月と12月の特定日に全国一斉で実施されていた経営学検定試験ですが、CBT方式の導入で上期、下期ともに約1ヶ月の期間で実施されます。
2021年の最新日程は初級・中級・上級それぞれで以下の通りです。
- 初級・中級
| 日程 | |
|---|---|
| 上期 | 2021年6月15日(火)〜7月31日(土) |
- 上級
| 日程 | |
|---|---|
| 一次 | 2021年7月18日(日) |
| 二次 | 2021年9月26日(日) |
中級分野別合格の有効期限が短縮される
2019年度まで、中級の分野別合格者は3年間資格が認められていました。しかし2020年度以降、分野別合格の有効期限は1年に短縮されます。
尚、第33回中級試験までの分野別合格者に関しては、従来の制度が適用されます。
また2020年度から中級は、初回からどちらか一方だけを受験することが可能になりました。そのため両方受験する場合は、それぞれ個別に申し込む必要があるので注意して下さい。
上級に関しては日程が指定されており注意が必要
2020年度から実施期間が1ヶ月となりましたが、上級に関しては上述したように日程が一次・二次試験それぞれで定められています。
よって、自分の都合の良い日程から受験日程を選択できるわけではないため、上級受験者は予め上記日程で都合をつけておく必要があります。
経営学検定試験と中小企業診断士
 経営学検定試験を受ける人が注目する資格として中小企業診断士があります。中小企業診断士の練習に経営学検定試験を受験する人もいます。
経営学検定試験を受ける人が注目する資格として中小企業診断士があります。中小企業診断士の練習に経営学検定試験を受験する人もいます。
中小企業診断士は、日経新聞が2016年に発表した「新たに取得したい資格ランキング」で1位に輝いています。難易度は経営学検定試験よりも高く、三段階の試験を突破しなければなりません。勉強時間も1〜2年と長いです。
中小企業診断士の腕試しに経営学検定試験を受験する場合、初級と中級は中小企業診断士の1次試験、上級の1次試験が中小企業診断士の2次試験のイメージです。
経営学検定試験の情報まとめ
経営学検定試験の情報まとめ
- 初級と中級の難易度は易しめ
- 公式テキストと過去問集で独学するか、通信講座もある
- 中小企業診断士の腕試しにも
- 2020年度以降の方式変更に注意
経営学検定試験の概要や難易度、勉強方法について解説しました!
一般的な勉強時間が約1ヶ月ほどとそこまで難易度は高くない試験です。腕試しに挑戦してみてはいかがでしょうか。受験の際は2020年度からの実施方法変更に注意して下さい!